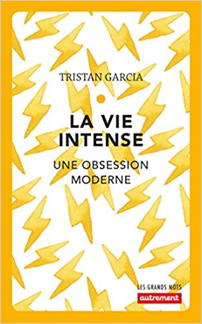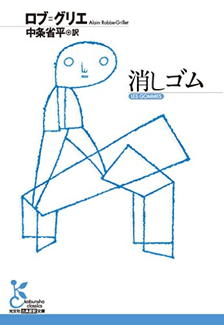噂に違わない短編の名手
イタリアの短編の名手として、名前だけ聞いたことがあったディーノ・ブッツァーティの作品を、邦訳本で読んでみました。『神を見た犬』(関口英子訳、光文社古典新訳文庫、2007)です。現時点ではkindle unlimitedに入ってはいないので、購入したものです。
https://amzn.to/3veTyef

どれも味わい深い、見事な幻想譚の数々が並んでいます。信仰を皮肉る独特な感覚、ちょっとした日常的な不安から紡ぎ出される奇譚、そして戦争への、やはり皮肉で批判的なまなざしなど。もともとジャーナリスト畑の著者ということで、そのあたりの絶妙な発想はなかなか刺激的です。いいですね、これ。短編の形式は、個人的に嗜好するある種のミニマリズムにもぴったり嵌まります。「戦の歌」「秘密兵器」「戦艦≪死(トート)≫」などの戦争ものなどは、読んでいて、ついつい今現在のウクライナの戦争を思わずにはいられない感じです。
タイトルよりもはるかに先鋭的・網羅的
最近は新刊の人文書とかも、あまり丁寧に追ってはいませんが、これは個人的にも、最近読んだうちのベストの一つでしょう。松村一志『エビデンスの社会学』(青土社、2021)。なにやら最近の世俗的な説明責任などの議論を思い起こさせるタイトルですが、同書が扱っているのはもっとずっと本格的な、科学の言説にまつわる「証拠」の理論とその変遷の歴史です。
https://amzn.to/3jASyL5

一言で言うなら、実に周到かつ幅広い目配せで深掘りされているように感じられました。科学というものをどう捉えるか考える場合、その対象や真理は実在すると素朴に考える実在論の立場もあれば、社会学で言う構築主義・相対主義の立場もあります。後者の場合は、えてして真理や対象が実態として存在しないといった「反実在論」になってしまいがちですが、同書はここで、相対主義的な疑念はそのままに、相対主義を徹底して貫くことは認識論的に不可能なのだ、という中庸的な立場に立ちます。これを反・反実在論として提唱しています。
これ、ルーマンの社会学やフーコーの議論を批判的に継承した俯瞰的な立場として、実によく練り込まれているように思われました。対象が虚構だとするのではなく、その対象がどのようにして現実性をもつのかという点を、問題にしようという姿勢です。わかりやすく、好感がもてます。
後半では、裁判のレトリックを受け継いだ「証言のゲーム」(人格の信頼)から、科学的証拠そのものを重視する立場である「命題のゲーム」(システムの信頼)へと、科学の論証の戦略が変わっていく様を、17世紀の第一次科学革命、19世紀の第二次科学革命とを通じ、両者の違いなども見届けながら、多様な側面を取り上げて詳述しています。科学と非科学の線引きとして、心霊現象の研究なども取り上げられています。言及される研究文献も実に多彩で、勉強になります。
読みどころが多く、それでいて書き慣れた感じの文章もいいですね。しなやかでありながら豪胆な知性、というところでしょうか。
躊躇を重ねるしなやかな知性
読みたかったのに、なぜか巡り合わせが悪くて未読・積ん読になっている本というのが、たまにあります。今回のもそうした一冊。橋本一径『指紋論』(青土社、2010)に、ようやく目を通すことができました。
https://amzn.to/35SukJ1

19世紀末から20世紀初めにかけて、西欧の警察が捜査目的で取り入れた人体測定、指紋の照合、足跡の参照などの近代的な方法論。同書はそれらがいずれも画期的と評価されながら、徐々に問題含みであることが明らかになっていく様を追っていくのですが、結局はそうした客観的なデータが、主観的な身元確認に貢献しているという、どこかねじれた感じの近代性を暴くことにもなります。これ、歴史的事象を丁寧に扱い、ときには躊躇や逡巡をも繰り返していくという、知的なしなやかさが導く到達点なのでしょう。拙速に決めつける本が多い昨今、一概に決めつけないという一貫した姿勢が、ある意味とても刺激的だという気がします。
トリスタン・ガルシアの野心作
すでに邦訳も出ているようですが、トリスタン・ガルシアの『激しい生』(Tristan Garcia, “La vie intense – une obsession moderne”, Autrement, 2016)を読んでみました。
https://amzn.to/3J3Kkpb
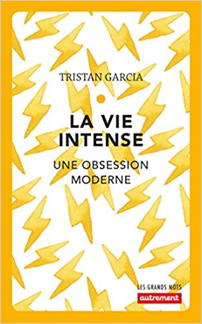
なかなか面白い論考です。「電気」が登場してからというもの、潜勢態・現勢態とか合理性とかいった概念に代わり、西欧社会を貫く概念として「強度」が台頭したというのがガルシアの着眼点です。強度はインフレ化し、社会全体がそれに巻き込まれていくようになる、と。ある種の競争、アピール、早い者勝ちの理論が席巻し、たとえば思想史なら、存在論がプロセス論に置き換わったり、分類という知が危うくなったり、あるいは科学なら、数値が幅を利かせるようになったり、芸術なら強烈な個性とか、独特な感性とかが重視されたり、というわけです。
でもいつしか人は「強度」ばかりを追い求めることに疲弊していきます。その結果、たとえば燃え尽き症候群が生じたりとか。あるいは反動的に、より恒常的・ルーチン的な平板なものを志向し、「思惟」や「賢慮」あるいは「信仰」などを求めるようになったりする……。ある種の保守化もそうですね。それと相まって、機械的な知の形象としての「電子」化も進んでいく、と。
この先はもはや、強度への志向と反動的な知や信仰との狭間・隘路での板挟み、行ったり来たりを続けていくしかないだろうと、ガルシアは見ているようです。全体として、すこし大まかすぎる見取り図のような気もしないわけではありませんが、楽観もしないが悲観もしないという、ある意味両義的で折衷論的なところに落ち着く感じが、どこかヘレニズム期のストア派的な思惟を想わせたりもします。それが単なる退廃ではなく、新しい知への準備期間となればよいのですけれどね。(ついでながら、個人的には、道徳(モラル)を形容詞的、倫理(エシックス)を副詞的だと述べている箇所など、随所に面白い言及がありました)。
ちなみに邦訳は栗脇永翔訳、人文書院刊(2021)です。→https://amzn.to/35lv1Ku
警察小説の枠組みを問う?
このところのkindle本、立て続けに「反警察小説」みたいなものを読んでみました。
まずはチェスタトン『木曜日だった男』(南条竹則訳、光文社古典新訳文庫、2008)。
https://amzn.to/358zlfY

チェスタトンといえば「ブラウン神父シリーズ」や「知りすぎた男」など、中短編で有名な作家ですが、いくつかある長編の一つが1905年の『木曜日だった男』なのだとか。これ、警察小説的な枠組みを借りてはいるものの、一種の冒険譚で、ある意味荒唐無稽な「バカ話」(良い意味でです)になっています。個人的にはにんまり笑ってしまいました。
続いて今度は久々にヌーボーロマン。アラン・ロブ=グリエ『消しゴム』(中条省平訳、光文社古典新訳文庫、2014)。
https://amzn.to/3LdfyLY
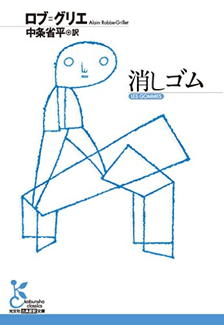
こちらは、1953年刊行のロブ=グリエの初期作品。昔結構好きだったヌーボーロマンの類も、最近はほとんど読んでいなかったのですが、推理小説的なやつがあったっけなあ、と思って、今回じっくり味わってみました。こちらは登場人物たちの様々な推測・憶測が、様々に事件を組み立ててしまう(読む側も、自分で組み立ててしまいますね)様子を、端正な文体で見事に描き出しています。いいですね、これ。
警察小説は枠組みとして、いろいろと「遊べる」ものだということを、どちらの作品も改めて認識させてくれます。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ