フランソワ・チェン『魂について: ある女性への七つの手紙 』(内山憲一訳、水声社、2018) 。チェン(1929 – )は中国出身の、フランス語で書く作家・詩人。アジア系初のアカデミー・フランセーズ会員でもある。そのチェンが2016年に刊行したのが、この『魂について』。哲学的な思考を書簡形式で小説風に、あるいは散文詩的に綴ったもの。ある女性からの問いかけを受けて、「魂」というものについて考察した軌跡をかたちにしたものという体裁だ。散文詩・小説的な形式が、哲学的な考察を記す理想的な形式の1つかもしれないことを改めて感じさせる。
思想の世界で「魂」が語られなくなって久しいが、それについてチェンは、精神と身体の二元論を学術的に固定するために魂についての議論は排除されていると捉える。けれども人の生と死をめぐる様々な問いかけを前にするとき、魂の復権はむしろ必須ではないかと訴えかけてくる。「魂は私たち各人の内に鳴り響く通奏低音である」(ジャック・ド・ブルボン=ビュッセ)なのだから、と。この魂の定義は、同書において何度も繰り返される。
(――やや些末な余談で恐縮だが、通奏低音(basse continue)はフランスでもよく誤って通低音(ドローン、仏語ではbourdon)と混同される。ここでも、どちらのことを言っているのか若干曖昧でもある。バロック音楽の通奏低音は、旋律の低音に和音を即興的につける伴奏のことを言うが、チェンは息吹を例に出していることなどから、どちらかというとドローンのことを意図している感じを受けないでもない。通奏低音という言い方がフランスも含めて世間的に独り歩きしているのは困った事態かもしれない……)
話をもどそう。魂をめぐる西欧の言説にはもちろん長い伝統があり、チェンは文献的に少しばかりそれを振り返ったりもする。けれども、主眼となるのは、「魂」というものを喚起する様々な事象、体験、記憶を掘り起こすこと、そこになんらかの実体を思い描くことにある。身体にも精神にも還元されない、あわい(間)に位置するものの一端が、感情・情動の起伏として顔をのぞかせる。そんな風景を、チェンは様々に綴っていく。文学作品や思想家の表現の端々に、あるいは中国語の言い回しの機微に、その「あわい」がほの見えるが、実はそれはとてつもなく深遠かつ広大だ、といわんばかりに。そのあたり、かつて河合隼雄が、魂と精神との位相を氷山の全体とその表面の一角に例えていたのを思い出した。
さらにチェンに言わせれば、魂は個人だけの問題ではない。それは世界に通じる根源的な「道」(儒教的・道教的な意味も含めて)でもあり、社会についての想像力をも開くものでもある。こうしてチェンは同書を構成する書簡の最後のものにおいて、シモーヌ・ヴェイユを取り上げている。ヴェイユは何度も繰り返し「魂」を引き合いに出している数少ない近現代の哲学者なのだという。しかもそれを貫いているのはある種のプラトン主義、そしてキリスト教的視座なのだ、と。なるほど、ヴェイユにおけるプラトン主義というのは、前に一度目にした ことはあるが、それきりになっていたっけ。改めて新たな課題をもらった気がする。
ユイスマンスを取り上げた が、それから一年(以上)越しで大野英士『ユイスマンスとオカルティズム 』(新評論、2010) を読了した(苦笑)。オカルト思想からカトリックへと「回心」したとされるユイスマンスだが、同書はそれがいかにしてなされたのかという問題に、時代背景から作家の実人生、精神分析的解釈、作品とその草稿を読み比べなどを通じて多面的にアプローチする、実直・堅実かつ重厚な一冊だ。ユイスマンスが接した「オカルト」と、その後のカトリックへの回心を貫く一つのキーワードとして、19世紀後半に流布した「流体」概念があった、と同書の著者は見る。「流体」は固有の形態をもたない物体とされる。ユイスマンスと親交のあったブーラン元神父という異端派の教祖が説教などで用いているというが、この概念には当時のパスツールによる微生物の発見などが絡み、ある種の独特な不可視の想像領域が形成されていたらしい。流体概念にはまた、メスマーが動物磁気などと呼んでいたものなどの系譜もあって、これも遡ればパラケルススやヘルモントなどから続いているし、著者によれば、ユイスマンス以降も、それは生気論などの一種の<変奏>などを経て、催眠術などの系譜へと受け継がれ、フロイトのリビドー概念、あるいはバタイユの「異質的な現実」概念などにも残響が刻まれていくという。
これと、ユイスマンス個人の「閉鎖された空間」への嗜好とが合わさって、小説内でのカトリックへの回心の記述は、流体的・神秘主義的なもの(どこか異端的な香りもするマリア信仰)として、ある種の一貫性をもつ動きとして記されていく。そこにはユイスマンスが多用する自作からの引用・転用の数々も絡み、また改宗後はブーラン的な異端を示すような記述が削除され(発表前に聖職者に見せて意見をもらったりしているのだとか)、と同時にいっそうのディテールへの拘りが前景化していくといった別筋の動きも絡み、重層的な文学空間が醸し出されていく……。もちろん、実人生での「回心」がどうだったのかはそれらから推測するしかないわけだろうけれど、テキストレベルでのそうした回心劇が、どのような文脈・概念・間テキスト性の上に構築されていたかを詳細にたどっていくのは、それだけでも実に読み応えがある。
一応、実人生での回心のキーのようなものもないわけではないようで、たとえばユイスマンスが衝撃を受け、回心に向けて大きな影響を受けたというグリューネヴァルト(16世紀の画家)の磔刑図があるという。有名なイッセンハイムの祭壇画ではなく、グリューネヴァルトの最後の磔刑図とされるもの。著者はこれをラカン的なキリスト受難の解釈に寄せて論じている。その解釈の是非は直ちには判断できないが、ともかくも、ユイスマンスがそこでもまた神秘主義的な嗜好からマリアのほうを向いていることは注目される。
Mathias Grünewald, Crucifixion, 1523–25
Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène , fayard, 2011 )。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
マラルメは共和国の制度、とりわけ政教分離に批判的で、宗教が担うような強い象徴的繋がりがなければ社会はありえないと考えていた、という。宗教とは私的なものなどではとうていなく、パブリックな事象だというわけだ。マラルメはまた、古い宗教に代わって芸術こそが近代に相応しい崇拝の対象にならなくてはならないと考えていたという。それは当時わりと人口に膾炙していた考え方のようなのだけれど、たとえばワーグナーの総合芸術が、あまりにギリシア風の演劇構成に依っている点にマラルメは批判的で、西欧の真の母体はむしろ中世ラテン文化にあると見なしていたという。近代の新たな芸術的崇拝が乗り越えなくてはならないのは、古代ギリシアの形式ではなく、中世以来のキリスト教の典礼にほかならない、というわけだ。マラルメは、詩作品はキリスト教の典礼にすら肩を並べる現実的な出来事をなさなくてはならないと考えていた。そしてメイヤスーによれば、それを作品化してみせているのがほかならぬ『骰子一擲』なのだ……という。そこで祭壇をなすのはほかならぬ「偶然」そのものであり、マラルメは不確定を永続化させる試みをそこで完遂しようとする。コード化はまさにそのための手段だとされる。コードはもしかすると永遠に発見されないかもしれない……。ある意味、犠牲として捧げられるのは生身のマラルメその人であり、そこから作者としてのマラルメが復活することが賭されている……と。
なるほど、マラルメの思想的な射程というのは考えたことがなかっただけに、これは瞠目させられる。マラルメのこうした構想(永続する不確定を軸とする作品構成なのだけれど、それが現実に観想されたのかどうか自体も不確定だ)は、実際の詩作の手法や作品世界などにも二重・三重に取り込まれている、とメイヤスーは見ているようだ。韻律こそが儀式的でパブリックな詩作の条件と考えるマラルメは、アレクサンドラン(12音節詩句)などの伝統的詩句を重視する立場を取っていたというが、当時は自由詩句の台頭とともに、たとえば語末のeの発音の有無が詩作上の論争となっていて(音節主義からアクセント主義への移行)、マラルメは語末のeを発音するかしないかを読み手に任せ、結果的に不確定要素を混入させて定型句を自由詩句に近づけているという。あからさまに詩句の自由化を説くのではなく、その自由詩句を不確定要素として反転させて定型句の側に取り込むという、ある意味狡猾なそのやり方は、描かれるテキストの中にも、一瞬だけ姿を現すセイレーンなどとして暗示されている……(とメイヤスーは論じる)。
同書を読むために、久々に秋山澄夫訳の『骰子一擲』(思潮社、1984)を引っ張り出してみたのだけれど、その解説部分に興味深い一節がある。「わたくしは『骰子一擲』をアンティ・スピノジズム、つまり、スピノザ主義への挑戦の書であると理解する。人間による創造はあり得るという、巨大な無神論の宣言だ。絶望の書ではない。確信の書であり、深淵から立ち上がった復活のドキュマンであり、マニフェストである」(p.76)。読みの方向性は違っていても、その強度において通底するかのような一節だ。
ジャン・グロンダン『宗教哲学 (文庫クセジュ) 』(越後圭一訳、白水社) に眼を通しているところ。ちょうど近代に入るところまで。基本的には整理という点で有意義な入門編という感じ。ただ、あまり事前情報を得ずに読み始めたせいか、個人的に期待していたものとは少しばかり違った(苦笑)。同書での「宗教哲学」の扱いは、一見広い意味のようでいて案外狭く設定されている気がする。たとえば冒頭近くの概論の章(第一章)に、宗教が科学によって駆逐されたわけではないという話の文脈で、アインシュタインの発言だとして「宇宙的な宗教感情が科学的探求の最も力強く最も高貴な動機であると断言する」という引用が紹介されている。その上で、アインシュタインの語りは科学者としてではなく、むしろ哲学者として語っていることを強調している。つまり彼ら科学者が形而上学的な帰結を導いたとすれば、それはもはや科学ではなく宗教哲学の領域に属する営為なのだというわけだ。ここからは同書が、宗教哲学を宗教感情を客観的に見据えるものと定義づけていることがわかる。ところでアインシュタインの発言の肝は、むしろ科学的探求にさえその深層には宗教感情が脈打っているということなのだけれど、そうなると個人的には、そうした深層の宗教感情そのものにアプローチするための方法論なり従来の試みなり、その評価なりを期待してしまうのだが、ここで同書はそういった方向へは向かわない。というか、多少は概論的に触れるけれども(機能主義を扱った第三章)、どちらかといえば宗教と哲学との関わりの変遷のような哲学史的な話題へとシフトしていく。そんなわけでちょっとはぐらかされた感じが残る(それはもちろんこちらの勝手な思い込みのせいなのだが)。もちろん同書のスタンスも、それはそれで哲学史的な整理という点では有意義だろう。たとえば個人的には、ラテン世界から中世についての章(第五、第六章)で出てきたreligioの語源をめぐる諸説の整理−−キケロの説(「再読」という意味だという説)、ラクタンティウスの説(「結び直し」という説)、アウグスティヌスの説(「選び直し」という説)、そしてトマスにおけるその統合など−−は、それだけでなんらかの肉付けができそうなテーマに思われる。同じく第六章でのアヴェロエスやマイモニデスなどとの関連で出てきた、啓示が本来的にもつ二重の真理(大衆にとっての真理と、哲学者の合理的分析のみが見抜ける真理)の話もしかりで、これまたとても広範なテーマのほんのささやかな端緒だと思われる。
前回のエントリで、トマスの実利主義をクローズアップした論考(というか発表用の原稿)を取り上げたけれど、今回も少し関連してトマスについてのより神学プロパーな論考を見てみた。ジョセフ・トラビック「アクィナスは『万人救済』を望むことができるか」(Joseph G. Trabbic, Can Aquinas Hope ‘That All Men Be Saved’? The Heythrop Journal, 2011 )というもの。まずスイスのハンス・ウルス・フォン・バルタザールという神学者による、トマスの万人救済への望みの解釈が示されている。それによれば、たとえばアウグスティヌスにおいては救済の望みはあくまで本人志向なのに対して、トマスは始めて他者の救済への望みを示し、キリスト教思想に重大なシフトを刻んだのだとされるという。これに対して同論考の著者は、トマスの諸テキストを再検討することによって、それとは違う結論を導こうとしている。つまり、トマスには確かに万人の救済の望みを抱きうると(さらにはそう望むことはキリスト者の義務であるとまで)解せる文章があるものの、一方で救済予定説・永罰説についての文章もあり、これが他者(つまりは万人)の救済の望みと齟齬をきたすことになるということ。救済予定説・永罰説については、ダマスクスのヨハンネスから継承したという「神の事前的意志と事後的意志」の区別(神はあらゆる者に事前に善への性向をもたしているが、特定個人は重罪者としての性向をもつことがあり、それを事後的意志として裁くことができるというもの)を持ち出したりもしているというが、それすら上の齟齬を解消するには十分ではないとし、むしろトマスが言うところの「万人」つまり「すべての者」の「すべて」が、永罰の対象者などを含まない非・一般概念であった可能性を示唆している。うーむ、確かにトマスの実利的なスタンスからすれば、そういった解釈もありうるかもしれないとは思えるけれど、それはテキストベースで検証されなくてはならないので、さしあたり判断を保留しておこう。同論考の著者はさらに、永罰論をめぐってもさらなる議論が必要だと末尾で述べている。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 秋読書の一環として手にとったが、これはなんとも渋みのある良書。フランソワ・チェン『魂について: ある女性への七つの手紙』(内山憲一訳、水声社、2018)。チェン(1929 – )は中国出身の、フランス語で書く作家・詩人。アジア系初のアカデミー・フランセーズ会員でもある。そのチェンが2016年に刊行したのが、この『魂について』。哲学的な思考を書簡形式で小説風に、あるいは散文詩的に綴ったもの。ある女性からの問いかけを受けて、「魂」というものについて考察した軌跡をかたちにしたものという体裁だ。散文詩・小説的な形式が、哲学的な考察を記す理想的な形式の1つかもしれないことを改めて感じさせる。
秋読書の一環として手にとったが、これはなんとも渋みのある良書。フランソワ・チェン『魂について: ある女性への七つの手紙』(内山憲一訳、水声社、2018)。チェン(1929 – )は中国出身の、フランス語で書く作家・詩人。アジア系初のアカデミー・フランセーズ会員でもある。そのチェンが2016年に刊行したのが、この『魂について』。哲学的な思考を書簡形式で小説風に、あるいは散文詩的に綴ったもの。ある女性からの問いかけを受けて、「魂」というものについて考察した軌跡をかたちにしたものという体裁だ。散文詩・小説的な形式が、哲学的な考察を記す理想的な形式の1つかもしれないことを改めて感じさせる。

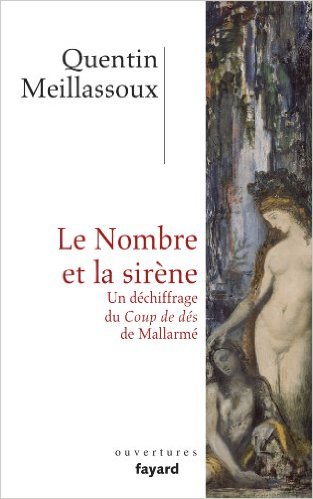
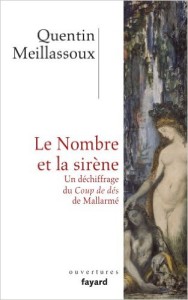 偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。