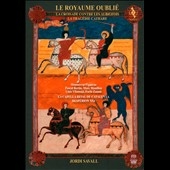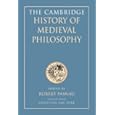 少し迷った後に、結局注文を出した『ケンブリッジ中世哲学史』(2巻本)(“The Cambridge History of Medieval Philosophy (2 Volume Boxed Set)”, ed. Robert Pasnau, Cambridge University Press, 2010)が届く。さっそくちらちらと見ているところ。テーマ別編集なので、引きやすそうな印象(辞書じゃないけれど)。問題を扱うときに初期段階で参照することを念頭に置いている感じの作り。とりあえず、第2巻の方にある形相と質料の話に目を通してみる。なるほど、すごく端的な記述なのだけれど、結構参考になるかも。第一質料を基底として質料・形相の複合体が一種の階層をなすという解釈(複合体がまた上位の形相にとっての質料をなす、みたいな感じで、オリヴィやドゥンス・スコトゥスに通じるものがある)は、古くはイブン・ガビロール(アヴィチェブロン)に見られるのだそうで(『生命の泉』は以前にを少しだけかじって積ん読になっているなあ……)、主にフランシスコ会系のスコラ学者がその立場を受け継いだものの、アルベルトゥス・マグヌスやトマス・アクィナスのころには、むしろ質料はあくまで物質界にのみ関わるという見識が席巻するようになったのだという。質料は純粋な可能態ではない、というスコトゥスの議論は、一方にはガビロールからの流れがあり、一方にはドミニコ会系の議論への反論という側面もあり……当たり前だが、結構背景は複雑かも。
少し迷った後に、結局注文を出した『ケンブリッジ中世哲学史』(2巻本)(“The Cambridge History of Medieval Philosophy (2 Volume Boxed Set)”, ed. Robert Pasnau, Cambridge University Press, 2010)が届く。さっそくちらちらと見ているところ。テーマ別編集なので、引きやすそうな印象(辞書じゃないけれど)。問題を扱うときに初期段階で参照することを念頭に置いている感じの作り。とりあえず、第2巻の方にある形相と質料の話に目を通してみる。なるほど、すごく端的な記述なのだけれど、結構参考になるかも。第一質料を基底として質料・形相の複合体が一種の階層をなすという解釈(複合体がまた上位の形相にとっての質料をなす、みたいな感じで、オリヴィやドゥンス・スコトゥスに通じるものがある)は、古くはイブン・ガビロール(アヴィチェブロン)に見られるのだそうで(『生命の泉』は以前にを少しだけかじって積ん読になっているなあ……)、主にフランシスコ会系のスコラ学者がその立場を受け継いだものの、アルベルトゥス・マグヌスやトマス・アクィナスのころには、むしろ質料はあくまで物質界にのみ関わるという見識が席巻するようになったのだという。質料は純粋な可能態ではない、というスコトゥスの議論は、一方にはガビロールからの流れがあり、一方にはドミニコ会系の議論への反論という側面もあり……当たり前だが、結構背景は複雑かも。
月別アーカイブ: 2010年3月
オクシタニア祭り
昨日の『異端者の群れ』を読むのに最高のBGMとなるのが、ジョルディ・サヴァールの新譜『忘れられた王国 – アルビジョア十字軍、カタリ派の悲劇』(Le Royaum oublié – La Croissade contre les albigeois, la tragédie Cathare)(The Forgotten Kingdom: The Cathar Tragedy – The Albigensian Crusade / Jordi Savall)。毎年出されるブック形式のテーマ別CDのシリーズ。今回のはまさにオクシタニアへの壮大なオマージュ。3枚組約60曲で奏でる、壮大な歴史絵巻という趣き。古いイスラム的な音楽から、いかにも悠久の大陸を思わせる哀感この上ない器楽曲、声楽曲まで、様々な楽曲が年代記に沿う形で次々に繰り出される。これはど迫力。演奏はもちろんサヴァール率いるエスペリオンXXI。アンドリュー・ローレンス=キングも参加している。ソリストはおなじみモンセラート・フィゲラスなど。さらにゲストとしてアルメニア、トルコ、ブルガリア、モロッコなどの奏者を入れている。曲の合間にいくつかテキストの朗読があって、これがまた雰囲気を一段と高めてくれる(ラテン語や古仏語のヒアリング練習にもなるかな)。たとえば1枚目では聖ベルナールへの書簡、2枚目ではカタリ派とシトー会との論争や、イノセンティウス3世の第一回十字軍の呼びかけなどなど。うーむ、もはやこれはオクシタニア祭り以外のなにものでもない(笑)。
「異端者の群れ」
 積ん読になっていた渡邊昌美『異端者の群れ – カタリ派とアルビジョア十字軍』(八坂書房、2008)を読み始める。これ、もとは1969年に刊行されたものだとか。ほぼ40年経っての再版とは、なんとも幸福な書籍だし、こちら読者にとっても僥倖。八坂書店のこうした再版シリーズ(とは銘打っていないが)はとてもありがたい企画だ。今後ともぜひ続けてほしいところ。副題にあるように、カタリ派やアルビジョア十字軍の概要を、幅広い文化的コンテキストから捉えようとする好著。とくに冒頭の三分の一くらいまでは、オクシタニア全般の文化的諸事情を俯瞰する内容で、見事な整理手腕。12世紀ごろの南仏というのも、文化的にも地政学的にもなかなか興味深い。一面では北仏に経済的に遅れた後進地域ではあったのかもしれないけれど、それにしてはトゥルバドゥールなどの宮廷恋愛詩とか、文化的にはある種の異文化混淆でもってとても豊かだったりし、そのあたりの溝というかギャップというかはどう整理されるのか、というあたりがやはり注目点か。まだ途中までしか読んでいないけれど、どうやらカタリ派や同時代の一連の異端派に、それらの溝を架橋する動きのようなものを見て取れるかもしれない、という印象を強く抱かせる。
積ん読になっていた渡邊昌美『異端者の群れ – カタリ派とアルビジョア十字軍』(八坂書房、2008)を読み始める。これ、もとは1969年に刊行されたものだとか。ほぼ40年経っての再版とは、なんとも幸福な書籍だし、こちら読者にとっても僥倖。八坂書店のこうした再版シリーズ(とは銘打っていないが)はとてもありがたい企画だ。今後ともぜひ続けてほしいところ。副題にあるように、カタリ派やアルビジョア十字軍の概要を、幅広い文化的コンテキストから捉えようとする好著。とくに冒頭の三分の一くらいまでは、オクシタニア全般の文化的諸事情を俯瞰する内容で、見事な整理手腕。12世紀ごろの南仏というのも、文化的にも地政学的にもなかなか興味深い。一面では北仏に経済的に遅れた後進地域ではあったのかもしれないけれど、それにしてはトゥルバドゥールなどの宮廷恋愛詩とか、文化的にはある種の異文化混淆でもってとても豊かだったりし、そのあたりの溝というかギャップというかはどう整理されるのか、というあたりがやはり注目点か。まだ途中までしか読んでいないけれど、どうやらカタリ派や同時代の一連の異端派に、それらの溝を架橋する動きのようなものを見て取れるかもしれない、という印象を強く抱かせる。
ダマスキオス
 プラトン主義の系譜を、飛び飛びに追っている形だけれど、ヌメニオス、アッティコスときて、今度はダマスキオスを読み始める。3巻本で出ている希仏対訳本『第一原理論』の一巻目(“Damascius – Traité des premiers principes 1 – de l’ineffable et de l’un”, L.-G. Westerink & J. Combès, Les Belles Lettres, 2002)。ダマスキオスは5世紀末から6世紀にかけて活躍した人物。同書の冒頭の解説によれば、他の例に漏れず、その生涯についても諸説入り交じっている模様だが、大筋は次のような感じ。ダマスキオスはシリア出身で、アレクサンドリアで学んだ後にアテネのマリノスのもとで学問を修める。そんなわけで新プラトン主義の一派に属し、とりわけイアンブリコスの影響を強く受け、プロクロスの見解をいろいろ再考しているという(ちなみにそれを証言しているシンプリキオスはダマスキオスの弟子だ)。ところが東ローマ皇帝ユスティニアヌスがキリスト教以外の異教の学問を禁じたためにアテネを追われ、シンプリキオスを含め仲間たちとペルシアに亡命。その後アテネに戻ったとか戻らないとか判然としていないという。
プラトン主義の系譜を、飛び飛びに追っている形だけれど、ヌメニオス、アッティコスときて、今度はダマスキオスを読み始める。3巻本で出ている希仏対訳本『第一原理論』の一巻目(“Damascius – Traité des premiers principes 1 – de l’ineffable et de l’un”, L.-G. Westerink & J. Combès, Les Belles Lettres, 2002)。ダマスキオスは5世紀末から6世紀にかけて活躍した人物。同書の冒頭の解説によれば、他の例に漏れず、その生涯についても諸説入り交じっている模様だが、大筋は次のような感じ。ダマスキオスはシリア出身で、アレクサンドリアで学んだ後にアテネのマリノスのもとで学問を修める。そんなわけで新プラトン主義の一派に属し、とりわけイアンブリコスの影響を強く受け、プロクロスの見解をいろいろ再考しているという(ちなみにそれを証言しているシンプリキオスはダマスキオスの弟子だ)。ところが東ローマ皇帝ユスティニアヌスがキリスト教以外の異教の学問を禁じたためにアテネを追われ、シンプリキオスを含め仲間たちとペルシアに亡命。その後アテネに戻ったとか戻らないとか判然としていないという。
著作はいろいろあり、哲学史的に重要とされる『イシドロスの生涯』、アリストテレスやプラトンの若干の著作への注解、そして『パルメニデス注解』とセットで語られるこの『第一原理論』。これは注解ではなく、第一原理(一者)と流出についてのかなり自由で思弁的な論述だという。まだ冒頭部分しか見ていないけれど、確かに一者の言語化できない特質などが淡々と(わりと平坦に)語られていく。でも細かく突き詰めていく異例な思考のスタイルだとされるだけに(シンプリキオスによると)、面白くなっていきそうな徴候も確かに感じられる(ような気がする)。
「神々の黄昏」
昨日だけれど、新国の『神々の黄昏』の再演を観る(このところ春休みっぽく遊んでいるなあ)。いわゆるトーキョーリングのツィクルス最終話(第3夜)。前回4年かけてツィクルス上演があったときには、この第3夜だけ見逃した。前年の『ジークフリート』がめちゃくちゃ良かったので、たぶんN響ファンとかが一気になだれこんだのだろう(かな?)、チケットがあっという間に売れてしまい取れなかった。というわけで、今回は個人的には6年越しのツィクルス完結(めでたしめでたし)。今回の演奏は東フィルで、前のツィクルスの除夜、1夜のときとはうって変わって(当時はさらさらと流れるようなワーグナーだったような)、結構厚みのあるずっしりとした音。すげーかっこいい(笑)。指揮はダン・エッティンガー。拍手。
一方、ソリストたちは、うーん、という感じも。特に歌唱にムラっ気を感じさせるジークフリート役とかね。個人的に『黄昏』は、ハーゲン役が重要な気がする。ハーゲンに存在感がないと、作品が締まらずバランスが悪くなっちゃうような。で、今回のハーゲン役はまずまず(もうちょっとアクがあってもいいかも)だけれど、あの「ハイホー」は、もうちょっと何とかして〜という感じだった(苦笑)。キース・ウォーナーの舞台演出は、相変わらずCGとか舞台装置とか駆使しまくる楽しいものだけれど、それほど意外性もなく、またそれほど邪魔でもない、という程合いか。キッチュさがほどよく殺がれて、結構舞台に溶け込んでいる感じもした。『黄昏』の場合には作品世界自体にぐいぐい押す力があるので、下手な小細工はいらないということかもしれないけど。ラストは大いに盛り上がった。いいねえ、これ。大拍手。