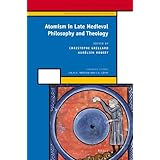Jacques Berlioz, Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age )は、主に中世盛期以降の各種災禍の記録をめぐる個人論集。その中の第四章として扱われているのが、1248年あたりに起きたとされるグラニエ山崩落で、これが同論集のうち最も長い論考(pp.57-139)になっている。これがなかなかの読み応え。グラニエ山というのは現在のフランス東部(ローヌ・アルプ地方)サヴォア県のシャンベリー(県庁所在地)近くにあった岩山だとされる。この山が大規模な土砂崩れを起こしたという話は、マシュー・パリス(ベネディクト会士)の複数の年代記のほか、エティエンヌ・ド・ブルボン(ドミニコ会士)の説教用の訓話(exemplum)、フラ・サリンベーネの年代記、マルタン・ル・ポロネ(ポーランドの聖職者)の年代記、エルフルト修道院(チューリンゲン、ドミニコ会)の編年史など、いろいろな史料に残されているというのだけれど、論文著者はこれらすべてを丹念に比較検証し、その「説話の構造」のようなものを描きだしている。
当然ながら、当時の災害記述においては聖書へのリファレンスが色濃く、この場合には山が動いたということで、ヨブ記一四章一八節「山は崩れてしまい、岩は場所を変える」が、説教用の訓話などではそのまま引き合いに出されたりする。一方でマシュー・パリスの年代記ではそうしたトーンはやや薄まっているようで、より「写実的」な面を強調した記述になっているともいう。面白いのは、原因の考察において、アリストテレス『気象論』での地震の説明(「地震は海流が激しい場所や、空洞が多々ある場所で起こる」)を取り込む形で(とくにパリスが)、グラニエ山の崩落前に高波があったことや、その山に多くの空洞があったことを記しているという話。『気象論』はヴァンサン・ド・ボーヴェ『大鏡(Speculum maius)』などを介して広く伝えられていたらしい。とはいえそれのあたりの自然学的な話は、原因としては副次的な扱いで、前面に出ているのはやはり神の罰という考え方。パリスの場合には、サヴォア人たちを快く思っていないこともあって(イングランド王妃エレノールの伯父にサヴォア伯がいて、そのあたりの絡みでサヴォアの人々がイングランドの封土を買い占めていたという現実があった)、「罰」という側面が記述に色濃く出ているのだとか。一方、訓話の場合には「祈りによって山を止める」話に力点が置かれているという。いずれにしても記録の書き手は伝聞にもとづいてその事象を記しているわけで、聖書その他の文献で伝わるもののほか、口承伝承の諸エレメントも、すでにして付与されている。代表例として悪魔と聖母との戦いのモチーフが挙げられているのだけれど、論文著者はこのあたりに当時の民衆の「期待の地平」(破壊とその救済)を見て取ることもできると指摘している。
(このところまた微妙に体調不良。以下は3日ほど前に記したアーティクル。あまり見直していないのだけれど、一応アップしておく)
前にも取り上げたヴェスコヴィーニ校注によるパルマのブラシウス『魂の諸問題』(Vescovini, Le Quaestiones de Anima , Leo S. Olschki Editore, 1974 ) から、本文の中身を大筋だけ断続的にまとめてメモしていくことにしよう。まずはパドヴァの1385年の写本のほうから、今回は1-8「知的魂は身体(コルプス)から分離できるか」。最初に、できるとする諸論と、できないとする諸論(アリストテレスにもとづく)のそれぞれの議論が列挙される。焦点となるのは「魂には固有の働きがあれば、肉体(物体)から分離しうる」かどうかをめぐる議論で、これを中心にブラシウス本人の論が続く。検討するのは主に次の三点。(1)魂に固有の働きがあるという前提は、コルプスからの分離の条件になっているかどうか、(2)魂にまったくコルプスに依存しない働きがあるというのは絶対的に正しいか、(3)魂は死後に肉体を離れるというのは自然の理に反しないか。
(1)についてブラシウスは、上の命題について条件節と主節の関連を否定している。天球を動かす魂は固有の働きがあるが、コルプス(天体のこと?)から分離することはない。神もまた創造などの固有の働きがあるが、コルプス(ん、神のコルプスって?)から分離することはないetc。ただし留保として、魂に固有の働きがあり、いかなる形でもコルプスに依存しないならば、その限りにおいて分離する可能性はある、としている。(2)についてはまず、魂の固有の働きというものを、みずからに内在し他の力に依らない働き(笑う可能性が人間に内在しているように)に限定する。次いで、「コルプスへの依存」の意味をいくつか分けて検討した後、知的魂は認識を形成していないなら固有の働きをもたないと断定する。ここで認識論が少しばかり展開する。知的ハビトゥス(スペキエスや認識に代わる、内的形成物(informata)をいう?)は事物の質料に属するものとされ、知(scientia)とは、みずからの潜在性から引き出されて質料に存するとされる「基体的な(subjective)性質」のことをいう、としている。しかしながら魂が実際に知解する場合の作用は魂に基体的に存する。したがって、あらゆる知的理解はコルプスに依存し、人間の魂に関する限り、固有の(非依存の)働きというものはない……。
(3)はというと、まず「知的魂は肉体から離れ、永劫的に離れたままになるのか」という命題に置き換え、この命題は「知られる」のか、「信じられる」のか、「臆見を抱かれる」のかと問うている。これら知・信・臆見の違いをめぐる議論が示され、さながらこの命題の不可知論が展開していく。臆見として示され、信の対象にはなりえても、確証として知られることはない……etc. そもそも魂が神の創造によるということも、明証的ではない、体験からも自明視などできないではないか、と。そしてそこから次に、知的魂は(創造されたか否かとは別に)、永続するようよりは費えるとするほうが蓋然性が高い、とブラシウスは論じる。分離した魂が永続するとするなら、それはより完全なものなるがゆえだが、今よりも後のほうが完全性が高い理由はない、そもそも、世界は無数の魂で溢れかえってしまうではないか、それが何の役に立つというのか、無用な多数が?さらにはノアの洪水による浄化をも引き合いに出して、浄化からの他の動物や人間の誕生を説き、それをもとに人間の知的魂もまた、質料の潜在性から引き出された(educta)、生成・消滅が可能なものではないかとまとめている。星辰の影響が唯一そこに関わってくる……。その後に続く、いくつかの疑念とそれらへの対応の部分で、善行によって欠陥を克服した魂を神がなんらかの永続的な身分へと高める、と信じることは可能だとして、教会側の教義への目配せをしているらしい点も面白い。
三たび『中世後期の哲学・神学における原子論』 より。論集の末尾を飾るのは、ジョエル・ビアールによる「原子論的推論に対峙するパルマのブラシウス」という論考。パルマのブラシウスは、基本的には不可分論者ではないようで、連続体は無限に分割可能だという立場を取る。たとえばこんな議論。線を等分に分割するという場合、不可分論(原子論)では厳密な等分が保証されない、なぜかというと、その場合、線は偶数の原子から成るのでなければならないが、それが偶数か奇数かなど、そもそも決定できないではないか……。これはあくまで数学的な話であるわけだけれど、一方で連続体が部分から構成されるという議論になると、議論の進め方に両論併記的なところがあってどこか曖昧さが残るという。また、話が自然学のほうにいたると、ミニマ・ナトゥラリアをめぐる議論など(質料は無限に分割できるにしても、形相が付与もしくは保持される上での上限・下限は必要になってくるという考え方)、不可分論的なトーンが出てこざるを得ない。このあたりは、14世紀のほかの論者たち(前にも挙げたけれど、ヴォデハムやビュリダンなど)とも共通する部分ではあるわけだけれど、ちょっと興味深いのは、線を構成する点とは別に、連続体に位置をもたない不可分なものの例として知的霊魂が挙げられていること。でもブラシウスは、自然学的観点から魂も無限に分割可能だとのスタンスなのだともいう(ヴェスコヴィーニの解釈)。このあたりもちょっと錯綜ぎみな感じで興味深いところ。
引き続き論集『中世後期の哲学・神学における原子論』 からメモ。不可分論は基本的にイングランド系の論者たちがメインという感じではあるけれども、一方で大陸側(というかフランス)でもそういう論を展開する人々はいた。というわけで、その代表的人物としてまず取り上げられているのがオドのジェラール(ゲラルドゥス・オドニス)(1285頃〜1349)。パリのフランシスコ会の学問所で『命題集』の講義を行っていた人物で、14世紀パリでの最初の原子論者とされている。ここでの論考(サンダー・デ・ボアー「オドのジェラールの哲学における原子論の重要性」)はその不可分論(原子論)の骨子を紹介しているのだけれど、それによると、オドの場合には、連続体を分割していって行き着く先に不可分の原子があるという議論(数学的)から出発しているのではなく、「全体よりも先にまずは部分が存在する」という基本スタンスがまずあって、現実に存在する実体を、不可分なものが相互に結びついて構成するという議論が中心になるという。そのため分割の議論にまつわる様々な難点(神の全能性との絡みなど)がまったく問題にならないのだ、と。
続いてクリストフ・グルヤールが取り上げるのはオートルクールのニコラ(「オートルクールのニコラの原子論的自然学」)。オートルクールのニコラ(1300頃〜1369)もなかなか数奇な運命を辿った人物。1347年には急進的なオッカム主義で異端と断じられ、その後はメスの大聖堂の参事会員となり、やがて参事会長になった。思想としては独特なものがあったようで、同論考によると、不可分なものに関する議論については数学的議論というより、自然学的な説明体系を志向しているらしい。上のオドとの絡みもあるし、このあたりが大陸的特徴なのかどうか……。ま、それはともかく、ニコラにおいては「ミニマ・ナトゥラリア」が「第一質料」の概念を不要にし、質料形相論が粒子論的な別の体系に置き換えられるのだという。そちらのほうがいっそう節約的な説明体系だというわけだ。で、同論考では、ニコラの原子論はデモクリトスの原子論が大元にあるらしいとされ、それにマイモニデス経由で伝わるムタカリムンの影響を受けて独自のものになっているとされる。原子はそれぞれ質的な属性をもち、ゆえに結合する力能を有しているとされるのだけれど、それを実際に結合させ実体を構成する(発生の原理)のは星辰の働き(!)なのだという。またそうした説明の文脈で真空の存在も認めている。デカルトにはるかに先んじての非アリストテレス的体系という意味でもまた面白そうな論者だ。
論集ではさらに、ビュリダンと論争したというモンテカレリオのミシェルなる人物も取り上げられている(ジャン・セレレット「1335年ごろのパリでの不可分論的議論」)。でもこれはさらにエキセントリックなもののように思えるので、とりあえず割愛しよう(苦笑)。
Grellard & Robert(ed), Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology )という論集を見始めている。とりあえず最初のマードック「アリストテレスを越えて;中世後期の不可分なもの、および無限の分割性」と、レガ・ウッド「不可分なものと無限:点に関するルフスの議論」の二章を読んだだけなのだけれど、なかなか面白い。まず、マードックのほうは主な不可分論者、アンチ不可分論者をチャートでまとめてくれているほか、いくつかの当時の論点を紹介し、論者たちのスタンスと何が問題だったのかを、アリストテレスからの距離という形で、著者本人言うところの「カタログ」として提示してくれている。ギリシアの原子論にはパルメニデスの一元論への対応や自然現象の説明といった動機があったといい、アラブ世界の原子論(ムタカリムンという学者たち)には連続的創造という教義を通じて、すべての因果関係を神の一手に委ねるという意図があったというが、中世後期の原子論(ないし不可分論)にはそのような大きな、確たる動機が見えてこないらしい。とまあ、いきなり肩すかしを食らう(苦笑)も、気分を取り直して見ていくと、やはり嚆矢とされるのはハークレイのヘンリー(1270 – 1317)だということで、その「無限の不等性」議論などはやはり注目に値するものらしい。これはつまり、連続した線が無限の不可分の点から成るものの、異なった長さの二つの線を比べること、つまり無限同士の比較が可能だという話。ヘンリーは点同士が隣接できるとし、点が互いに接し居並ぶことによって大きさが増えると考えていたという。このあたり、神学も絡んで結構複雑な話が展開しているようだ。
ウッドの論考は、一四世紀の議論の大元のひとつとなったコーンウォールのリチャード・ルフス(1260頃没)の議論を紹介しまとめている。著作から読み取れるその議論は、必ずしも一貫してはいないようで、詳細な説明がない場合もあるようなのだけれど、各著作の摺り合わせを通じて、最適解を作り上げようとしている。それによるとルフスは点を「位置を取る限りで実体のもとにある」と考えているといい(点はもちろん不可分なものとされる)、点が直線の「質料因」(つまり起点をなしているということ)だという言い方をしていることから、唯名論的な概念世界ではなく、外部世界の形而上学的説明を目してることが考えられるという。点は無限に繰り返されて直線をなすのではなく、質料の点的な位置取りが繰り返されて線ができるのであって、点そのものが線を作るのではないとしているという。また球と線が接する場合についても、接するとはそもそも運動であり、接する不可分なものは連続的に移っていくのであって、連続体として(線の流れで?)接するのだと考えているという。このあたりは相変わらず微妙にわかりにくいところではある……。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 ジャック・ベルリオーズ『中世の自然災害と災禍』(Jacques Berlioz, Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age, Sismel-Galluzzo, 1998)は、主に中世盛期以降の各種災禍の記録をめぐる個人論集。その中の第四章として扱われているのが、1248年あたりに起きたとされるグラニエ山崩落で、これが同論集のうち最も長い論考(pp.57-139)になっている。これがなかなかの読み応え。グラニエ山というのは現在のフランス東部(ローヌ・アルプ地方)サヴォア県のシャンベリー(県庁所在地)近くにあった岩山だとされる。この山が大規模な土砂崩れを起こしたという話は、マシュー・パリス(ベネディクト会士)の複数の年代記のほか、エティエンヌ・ド・ブルボン(ドミニコ会士)の説教用の訓話(exemplum)、フラ・サリンベーネの年代記、マルタン・ル・ポロネ(ポーランドの聖職者)の年代記、エルフルト修道院(チューリンゲン、ドミニコ会)の編年史など、いろいろな史料に残されているというのだけれど、論文著者はこれらすべてを丹念に比較検証し、その「説話の構造」のようなものを描きだしている。
ジャック・ベルリオーズ『中世の自然災害と災禍』(Jacques Berlioz, Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age, Sismel-Galluzzo, 1998)は、主に中世盛期以降の各種災禍の記録をめぐる個人論集。その中の第四章として扱われているのが、1248年あたりに起きたとされるグラニエ山崩落で、これが同論集のうち最も長い論考(pp.57-139)になっている。これがなかなかの読み応え。グラニエ山というのは現在のフランス東部(ローヌ・アルプ地方)サヴォア県のシャンベリー(県庁所在地)近くにあった岩山だとされる。この山が大規模な土砂崩れを起こしたという話は、マシュー・パリス(ベネディクト会士)の複数の年代記のほか、エティエンヌ・ド・ブルボン(ドミニコ会士)の説教用の訓話(exemplum)、フラ・サリンベーネの年代記、マルタン・ル・ポロネ(ポーランドの聖職者)の年代記、エルフルト修道院(チューリンゲン、ドミニコ会)の編年史など、いろいろな史料に残されているというのだけれど、論文著者はこれらすべてを丹念に比較検証し、その「説話の構造」のようなものを描きだしている。