前回のエントリーの末尾で触れた、「人間による創造」云々というあたりに、なにやら個人的にこだわってしかるべきポイントを強く感じている(苦笑)。「人間の創造性」についての系譜というのも、思想史的に追いかけ甲斐のあるテーマという気がする。この関連でまず思い出したのは、クザーヌスの『推測について』。前に触れたように 、これの仏訳版の解説によると、そこでのクザーヌスは、人間のある種の創造性・豊穣性を前面に押し出しているとのことだった。そういう側面からクザーヌスを読もうと思いつつ、今年はちょっと時間が取れなかった。これは来年の課題の一つ。
Richard De Mediavilla: Questions Disputées : Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique) , trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012
Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène , fayard, 2011 )。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
マラルメは共和国の制度、とりわけ政教分離に批判的で、宗教が担うような強い象徴的繋がりがなければ社会はありえないと考えていた、という。宗教とは私的なものなどではとうていなく、パブリックな事象だというわけだ。マラルメはまた、古い宗教に代わって芸術こそが近代に相応しい崇拝の対象にならなくてはならないと考えていたという。それは当時わりと人口に膾炙していた考え方のようなのだけれど、たとえばワーグナーの総合芸術が、あまりにギリシア風の演劇構成に依っている点にマラルメは批判的で、西欧の真の母体はむしろ中世ラテン文化にあると見なしていたという。近代の新たな芸術的崇拝が乗り越えなくてはならないのは、古代ギリシアの形式ではなく、中世以来のキリスト教の典礼にほかならない、というわけだ。マラルメは、詩作品はキリスト教の典礼にすら肩を並べる現実的な出来事をなさなくてはならないと考えていた。そしてメイヤスーによれば、それを作品化してみせているのがほかならぬ『骰子一擲』なのだ……という。そこで祭壇をなすのはほかならぬ「偶然」そのものであり、マラルメは不確定を永続化させる試みをそこで完遂しようとする。コード化はまさにそのための手段だとされる。コードはもしかすると永遠に発見されないかもしれない……。ある意味、犠牲として捧げられるのは生身のマラルメその人であり、そこから作者としてのマラルメが復活することが賭されている……と。
なるほど、マラルメの思想的な射程というのは考えたことがなかっただけに、これは瞠目させられる。マラルメのこうした構想(永続する不確定を軸とする作品構成なのだけれど、それが現実に観想されたのかどうか自体も不確定だ)は、実際の詩作の手法や作品世界などにも二重・三重に取り込まれている、とメイヤスーは見ているようだ。韻律こそが儀式的でパブリックな詩作の条件と考えるマラルメは、アレクサンドラン(12音節詩句)などの伝統的詩句を重視する立場を取っていたというが、当時は自由詩句の台頭とともに、たとえば語末のeの発音の有無が詩作上の論争となっていて(音節主義からアクセント主義への移行)、マラルメは語末のeを発音するかしないかを読み手に任せ、結果的に不確定要素を混入させて定型句を自由詩句に近づけているという。あからさまに詩句の自由化を説くのではなく、その自由詩句を不確定要素として反転させて定型句の側に取り込むという、ある意味狡猾なそのやり方は、描かれるテキストの中にも、一瞬だけ姿を現すセイレーンなどとして暗示されている……(とメイヤスーは論じる)。
同書を読むために、久々に秋山澄夫訳の『骰子一擲』(思潮社、1984)を引っ張り出してみたのだけれど、その解説部分に興味深い一節がある。「わたくしは『骰子一擲』をアンティ・スピノジズム、つまり、スピノザ主義への挑戦の書であると理解する。人間による創造はあり得るという、巨大な無神論の宣言だ。絶望の書ではない。確信の書であり、深淵から立ち上がった復活のドキュマンであり、マニフェストである」(p.76)。読みの方向性は違っていても、その強度において通底するかのような一節だ。
将基面貴巳『ヨーロッパ政治思想の誕生 』(名古屋大学出版会、2013) を読んでみた。12世紀から14世紀にかけてのヨーロッパ政治思想史の流れをまとめた一冊。扱われる比重の高い思想家とその内容を順に挙げておくと、人体と政体のアナロジーを語った嚆矢ではあっても「君主の鑑」の伝統を抜け出てはいないソールズベリーのジョン、同様の身体イメージをもとに、団体理論の発展に貢献した教会法学者のホスティエンシス、支配権概念を拡張して教皇絶対主義を唱えたエギディウス・ロマヌス、聖俗両権の二元論を唱えた反・教皇絶対主義者のパリのヨハネス、教会と国家の分離を押し進めようとしたダンテ、現世における教会の支配権を基本的に認めない医学畑出身のパドヴァのマルシリウス、聖俗両権の分離を認めつつも、危機管理の理論として、場合により一方への他方の介入を許すという立場を取ったオッカム、反教皇的立場を取りつつ、教会論のいっそうの神学化を図ったというウィクリフ、公会議主義を標榜しつつ教皇座の寡頭制を支持するザバレラ、公会議主義を徹底しようとするジャン・ジェルソン……。
いろいろな人物や流れが取り上げられているが、真に中心をなしているのはマルシリウスという感じ。たとえばウィクリフもオッカムも、マルシリウスとの対比で語られている。教会の強制力を認めず、教会を世俗の国家の側に取り込んでしまうという、ある意味画期的な議論をマルシリウスは展開しているのだけれど、オッカムは教会制度そのものを批判してはいないといい、ウィクリフは「改革」を志向しつつも、教会論はきわめて神学的なものだという。また、マルシリウスが人民の同意にもとづく国王の選出を訴えるのに対して、ウィクリフは国王の支配権を神の意志という不可知なものに帰し、暴君すら許容しようとするという。このあたりはなかなか面白そう。また、全体として、アウグスティヌスやアリストテレスに加えて、政治論的にはキケロの伝統というのもあるという話や、マルシリウス以前の伝統的な「同意」概念があくまで形式的なものにすぎなかった(同意は最初から与えられるのが前提だった)といった話、あるいは多数決の原理に関して、12世紀の教皇選出手続きにおいて出席者の三分の二を「多数」とし、これをもって全体を拘束する原則が広まったといった興味深い話もちりばめられている。そのあたりも含め、いろいろと確認・検証してみたくなってくる。
中世イスラムにおける心身問題(霊魂と身体の結びつき問題)に、ちょっと変わった角度からアプローチしている論考を見かけたので読んでみた。扱われているのはアヴィセンナ。ヤシン・R・バシャラン「アヴィセンナによる霊魂の物体操作力」(Yasin Ramazan Başaran, Avicenna on the Soul’s Power to Manipulate Material Objects , Eskiyeni , vol 30, 2015 )。「これって超能力話?」とか思ってしまうけれど(笑)、要は、霊魂が離在的に物質に働きかけることができるかという問題を、アヴィセンナがどう捉えていたか検証する論考。基本を押さえたストレートな論文という印象。前半は先行研究からの関連箇所をまとめていて、グタス、グッドマン、ドリュアールなどの研究から、そうした離在的な働きかけについて考えるアヴィセンナの諸前提を抽出している。
アヴィセンナの場合は流出論が基本で、上位のものは下位のものに原則働きかけることができる。したがって魂は物質(身体を含めて)に働きかけることができることになる(心身問題的に、魂が身体にどう結びついているかという点は不可知とされるものの、その結びつきは基本的にどうでもよくて(偶有的なことだとされる)、要は前者が後者を動かすことができればよい。身体が必要とされるのは、上位の知性界の上下関係の構造を物質世界に再現するためとされる)。魂にもとからある自由意志が行使される際には、上位の知性が参照され(それが魂に刻まれ)、自然の因果関係を踏み越えて物質に働きかけることができるとされる。ただ、魂のそうした自由意志力の強度、密度は人それぞれなので、物質への働きかけがもとよりできる人(預言者など)もいれば、なにがしかの訓練を経なければできない人(一般人)もいる……。いずれにせよ、魂と物質が存在論的に異なっているということと、コスモロジカルな構造が地上世界にも刻まれることが基本的な要件のようだ。
そうしたことを前提に、後半では、アヴィセンナ後期の書の一つとされる『所見と勧告』の第10巻(超自然な出来事について述べている部分)を取り上げて、超自然的な現象についての議論を紹介している。そこでは、超自然的な現象が可能になるケースは三つに分類されているという。一つめが主体に自然の能力としてそうした現象を起こす力が備わる場合(預言者の場合や、たとえばにらみつけるだけで呪いをかけられるという凶眼、魔術などがこれに分類される)、二つめが自然の産物の属性による場合(磁石の働きや、ある種の呪術的効果など)、三つめが天空の力、地上世界の物体、魂などの諸関係によって生じる場合(護符の作用など)。この後半部分の論述は物足りない気がするが、全体としては今後の研究を期待させる感触あり(かな)。
12. ヘシオドスが言うには、外側の人間とは紐帯であり、ゼウスはそれでプロメテウスを縛りつけた。次いでその紐帯の後に、ゼウスは別の紐帯であるパンドラを送り込んだ。ヘブライ人たちがエヴァと呼ぶものである。プロメテウスとエピメテウスは寓意の言葉では一人の人間、すなわち魂と身体を意味する。プロメテウスはときに魂の像、ときに知性の像をなし、またときに肉体の像をなすが、これはエピメテウスの無分別のせいである。エピメテウスはみずからの知性であるプロメテウスに対して注意を払わなかったのだ。というのも、私たちの知性は私たちにこう語るからである。「望めば、望む通りに、あらゆることができ、あらゆるものになりうる神の子は、各人のもとに立ち現れる」。
13. イエス・キリストはアダムに結びついていた。イエスは、「フォス」と呼ばれたものたちが以前にいた場所へと(アダムを?)連れていったのである。人間となり、苦しみを被り、打ちつけられたイエスは、まったく無力な人間のもとにも現れた。またイエスは、密かにみずからのフォスたちを救った。苦しむことのないその者は、死を踏みつけ、斥けることができることを示してみせた。しかるべき時まで、つまり世界の終わりが来るまで、イエスは密かに、あるいはあからさまに、みずからを慕う者たちを救い、密かに、それらの者たちの知性を通じて、彼らによって打ちつけられ殺害されたアダム、彼らを盲従させ、気息的で輝かしい人間に羨望を抱いたアダムを、交換するよう助言するのである。彼らはみずからのアダムを殺害するのである。
14. 偽造者のダイモンがやって来るまではそのような成り行きである。そのダイモンは彼らに羨望を抱き、先に迷わせてやろうとて、魂としても身体としてもみにくいにもかかわらず、自分が神の子であると言うのだ。だが、真の神の子がどのようなものであるか理解して以来、より聡明になっている彼らは、ダイモンにみずからのアダムを差し出し殺させて、輝かしい気息はみずからの場所、現世の前に彼らがいた場所へと救い置こうとする。だが、その偽造者、羨望者は、あえて(神の子との名乗りを)行う前に、まずはペルシアからの先発者を遣わすのだ。作り話を語って人を惑わせ、人々を運命の周囲に導く者である。その名の文字は九つで、「ヘイマルメネー」(運命)の拍に従い、二重母音をも温存している。七つ前後の時代区分を経て、その者はみずからの本性にもとづきやって来るであろう。
– プロメテウス神話が心身の結合の話になっているのが興味深い。「フォス」と「アダム」もこれとパラレルで、前者が魂、後者が身体・肉体に相当する。キリストはそのフォス(魂)を救い、それに対立するアダムを「交換」するよう諭すというわけだが、仏訳注では、この「交換する」は要するに「打ち捨てる」という意味だろうとされている。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。
けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。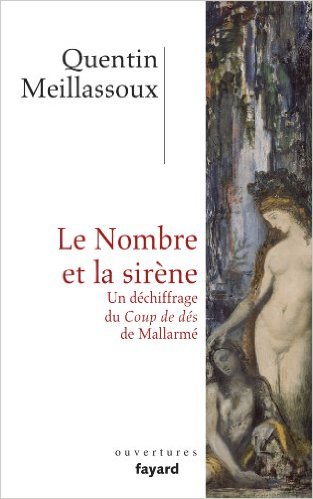
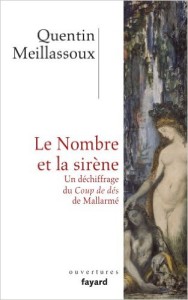 偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。