ヴァン・デル・ルクト本で取り上げられていたパルマのブラシウス(1345頃〜1416)は、とりわけ数学者として知られているということなのだけれど、当時の数学教育では自然学や医学なども一体化していたのだそうで、なるほど発生論を扱っているのも頷ける。で、この人物、変革期をしたたかに(?)生きた人物としてなにやら興味をそそるものがあり(笑)、少しこだわって眺めてみたいと思うのだけれど、あまり詳しそうな資料がない感じだ。でも、各種の文献に散らばっているらしい記述を拾っていくのも楽しそうではある。ネットで詳しいのはencyclopedia.comのアーティクル(エドワード・グラントによるもの)。フランスの出版社ヴランから、2000年代になって三冊ほど校注テキストが刊行されているので、いずれそれらも眺めていきたい。
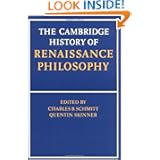 発生論のほうでもラディカルらしいブラシウスだけれど、魂の問題についてもやはりそうらしい。基本的なリファレンス本の一つ、シュミット&スキナー編『ケンブリッジ・ルネサンス哲学史』(Schmitt & Skinner, The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, 1988)の「知的霊魂」の章(15章)には、ブラシウスの「物質論的」霊魂論が紹介されている。知性は非物質的かつ身体から独立して存在しているのか、それとも身体との関係性においてのみ知性は存在しているのか(その場合、知性は身体の形相とされる)を決めるのは、身体から独立した形での魂の作用(操作)があるかどうかにかかっている。ところがそうした作用は観察ができない。そのため知解のプロセスを知覚とのアナロジーで考えるほかない。その場合、魂には対象が必要となるけれども、その対象にはなんらかの距離・外延がなくてはならない。そのためには質料が必須ということになる。とするなら、魂にとっての対象は物質的な対象(物質と結びついた形相)だということになる。外的対象のほか内的対象(想起されるものなど)の場合でも、知性が抱く概念はもともと質料のうちに表されるのでなくてはならない。外的世界での質料と形相の結びつきとパラレルな形で、知解もまた質料(この場合は身体)と形相が結びつく「自然」な作用にほかならないのだ、と。ここまで、ちょっと古い質料形相論に連なる感じだけれれど、この後、ブラシウスは一気にラディカルな方へと走り出す。認識対象と認識主体は同種でなくてはならないとされていたことから、ブラシウスは、知的霊魂もまた、質料(この場合は身体か)の潜在性から引き出される特殊な形相にすぎず、身体が滅べば消えてなくなると推論するのだ(!)。当然ながらこれは当時の哲学的な考え方にも、キリスト教の教義にも反する立場。ブラシウスは弁明を余儀なくされ、後に自説を引っ込めるらしい。でもその考え方、ヴェネツィアのパウルス(こちらもそのアヴェロエス主義的な考え方が面白そうだが)などがオッカム流の唯名論的に普遍を考え、外的世界の事物に根ざしてなどいないとするのに対し、改めて実在論を導いているような話になっていて興味深い。
発生論のほうでもラディカルらしいブラシウスだけれど、魂の問題についてもやはりそうらしい。基本的なリファレンス本の一つ、シュミット&スキナー編『ケンブリッジ・ルネサンス哲学史』(Schmitt & Skinner, The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, 1988)の「知的霊魂」の章(15章)には、ブラシウスの「物質論的」霊魂論が紹介されている。知性は非物質的かつ身体から独立して存在しているのか、それとも身体との関係性においてのみ知性は存在しているのか(その場合、知性は身体の形相とされる)を決めるのは、身体から独立した形での魂の作用(操作)があるかどうかにかかっている。ところがそうした作用は観察ができない。そのため知解のプロセスを知覚とのアナロジーで考えるほかない。その場合、魂には対象が必要となるけれども、その対象にはなんらかの距離・外延がなくてはならない。そのためには質料が必須ということになる。とするなら、魂にとっての対象は物質的な対象(物質と結びついた形相)だということになる。外的対象のほか内的対象(想起されるものなど)の場合でも、知性が抱く概念はもともと質料のうちに表されるのでなくてはならない。外的世界での質料と形相の結びつきとパラレルな形で、知解もまた質料(この場合は身体)と形相が結びつく「自然」な作用にほかならないのだ、と。ここまで、ちょっと古い質料形相論に連なる感じだけれれど、この後、ブラシウスは一気にラディカルな方へと走り出す。認識対象と認識主体は同種でなくてはならないとされていたことから、ブラシウスは、知的霊魂もまた、質料(この場合は身体か)の潜在性から引き出される特殊な形相にすぎず、身体が滅べば消えてなくなると推論するのだ(!)。当然ながらこれは当時の哲学的な考え方にも、キリスト教の教義にも反する立場。ブラシウスは弁明を余儀なくされ、後に自説を引っ込めるらしい。でもその考え方、ヴェネツィアのパウルス(こちらもそのアヴェロエス主義的な考え方が面白そうだが)などがオッカム流の唯名論的に普遍を考え、外的世界の事物に根ざしてなどいないとするのに対し、改めて実在論を導いているような話になっていて興味深い。