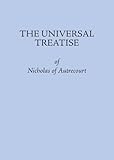 メルマガのほうでも出てきているオートレクールのニコラは、なかなかその議論の妙味が興味深い。で、その主著の一つ『秩序は求める(Exigit ordo)』の英訳『世界論』(The Universal Treatise of Nicholas of Autrecourt (Mediaeval Philosophical Texts in Translation), trad. Leonard A. Kennedy et al., Marquette University Press, 1971)を取り寄せてみた。この冒頭の解説部分では、ニコラはヒューム的な懐疑主義の先駆的な人物と位置づけられている。解説はやや複雑な本文内容の簡潔なまとめなのだけれど、同時にその思想的な広がりをも感じさせる紹介になっている。ニコラは粒子論者(原子論者)であり、また懐疑論者でもある。この後者の側面は別の文書、つまりアレッツオのベルナール(フランシスコ会士)宛の書簡のほうに顕著に見られるらしい(そちらも校注版が刊行されている(Nicholas of Autrecourt: His Correspondence With Master Giles and Bernard of Arezzo : A Critical Edition from the Two Parisian Manuscripts With an in (Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters))のだけれど、うーむ高額……)。とはいえ、こちらの『世界論』でも、アリストテレスやアヴェロエスなどの権威に異論を差し挟み、世間的に認められた教説に疑い目を向け、より一貫性のある教説を求めるという姿勢が貫かれている。同書の最も重要な教説はというと、本文の第一序文第二部にある「あらゆるものは不滅である」というテーゼなのだという。ニコラの教説の大枠はこんな感じ。世界は善であり、事物はすべてあるべき形で配置されている(当然、製作者としての神の意志による。さもなくばすべてはカオスでしかなくなる)。それらは相互に結びついており、全体としてつねに同じ善性を維持している。ここで何かが失われ減じるとすると、善性もまた減じてしまう。いちどそうなってしまえば歯止めも利かず、カオスへと落ちていってしまう。そうならないために、善性は常に不変でなくてはならず、したがってすべてのものは永遠に存在するのでなくてはならない……。
メルマガのほうでも出てきているオートレクールのニコラは、なかなかその議論の妙味が興味深い。で、その主著の一つ『秩序は求める(Exigit ordo)』の英訳『世界論』(The Universal Treatise of Nicholas of Autrecourt (Mediaeval Philosophical Texts in Translation), trad. Leonard A. Kennedy et al., Marquette University Press, 1971)を取り寄せてみた。この冒頭の解説部分では、ニコラはヒューム的な懐疑主義の先駆的な人物と位置づけられている。解説はやや複雑な本文内容の簡潔なまとめなのだけれど、同時にその思想的な広がりをも感じさせる紹介になっている。ニコラは粒子論者(原子論者)であり、また懐疑論者でもある。この後者の側面は別の文書、つまりアレッツオのベルナール(フランシスコ会士)宛の書簡のほうに顕著に見られるらしい(そちらも校注版が刊行されている(Nicholas of Autrecourt: His Correspondence With Master Giles and Bernard of Arezzo : A Critical Edition from the Two Parisian Manuscripts With an in (Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters))のだけれど、うーむ高額……)。とはいえ、こちらの『世界論』でも、アリストテレスやアヴェロエスなどの権威に異論を差し挟み、世間的に認められた教説に疑い目を向け、より一貫性のある教説を求めるという姿勢が貫かれている。同書の最も重要な教説はというと、本文の第一序文第二部にある「あらゆるものは不滅である」というテーゼなのだという。ニコラの教説の大枠はこんな感じ。世界は善であり、事物はすべてあるべき形で配置されている(当然、製作者としての神の意志による。さもなくばすべてはカオスでしかなくなる)。それらは相互に結びついており、全体としてつねに同じ善性を維持している。ここで何かが失われ減じるとすると、善性もまた減じてしまう。いちどそうなってしまえば歯止めも利かず、カオスへと落ちていってしまう。そうならないために、善性は常に不変でなくてはならず、したがってすべてのものは永遠に存在するのでなくてはならない……。
ニコラは、こうした教説のほうがアリストテレスのものより世界の正当性をよりよく擁護できると考えている。この永続性を支えているのが、目に見えない原子という考え方だ。事物が滅するように見えるのは感覚がそれらの存続を捉えきれないからだとされ、一方で知性は善の考察などからそうした不滅思想を導くことができるとされる。さらには輪廻的な考え方すら言及される。人間には感覚と知性という二つの精気が存在するといい、それらは身体の死後も存続して別の原子の集積に加わることができる、というのだ。ただしニコラは、これすら「蓋然的に」そう結論づけられるだけだとし、ここでも懐疑論を貫く。このような教説だけに、当時の教会関係者からは当然ながら問題視され、最終的に同書は焚書扱いとなったようだが、先にも触れたように、ニコラのその後の教会での立場にとって、その糾弾は比較的軽微な損害しか与えていないように見える。うーん、これはどういうことなのだろう……?