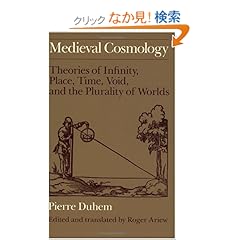 以前ドゥンス・スコトゥスの「場所」論がちょっと面白そうだったこともあって、少し前に場所論の系譜を調べようとしたら、デュエムがちゃんと整理していることをどこぞで知った。19世紀フランスの物理学者であり科学史家でもあるデュエム。その大作『世界の体系』10巻本は確かに、まずもって当たりたいリファレンスではあるのだけれど、量に圧倒されてさしあたり全部は読めそうにない(苦笑)。そうなると、縮約版とかがほしいところ。デュエム本人も晩年、そういう縮約版を構想していたという話もあるけれど、それは残念ながら実現していない……。と思っていたら、うかつだったけれど、中世に関しては英訳版でそれに類するものが出ているでないの。『中世のコスモロジー』(“Medieval Cosmology: Theories of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of Worlds”, tr. Roger Ariew, The Univ. of Chicago Press, 1985-87)というのがそれ。この序文などは、同著作のガイドとしても役に立ちそう。場所論は主に7巻に収録されていることがわかる。抄訳も収録されていて、大いに助かる。『世界の体系』は以前Gallicaでダウンロードできたのに、今はできなくなっているのだけれど、これって再版されたせいかしら?(amazon.frとかで各巻が買えるようだが……)
以前ドゥンス・スコトゥスの「場所」論がちょっと面白そうだったこともあって、少し前に場所論の系譜を調べようとしたら、デュエムがちゃんと整理していることをどこぞで知った。19世紀フランスの物理学者であり科学史家でもあるデュエム。その大作『世界の体系』10巻本は確かに、まずもって当たりたいリファレンスではあるのだけれど、量に圧倒されてさしあたり全部は読めそうにない(苦笑)。そうなると、縮約版とかがほしいところ。デュエム本人も晩年、そういう縮約版を構想していたという話もあるけれど、それは残念ながら実現していない……。と思っていたら、うかつだったけれど、中世に関しては英訳版でそれに類するものが出ているでないの。『中世のコスモロジー』(“Medieval Cosmology: Theories of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of Worlds”, tr. Roger Ariew, The Univ. of Chicago Press, 1985-87)というのがそれ。この序文などは、同著作のガイドとしても役に立ちそう。場所論は主に7巻に収録されていることがわかる。抄訳も収録されていて、大いに助かる。『世界の体系』は以前Gallicaでダウンロードできたのに、今はできなくなっているのだけれど、これって再版されたせいかしら?(amazon.frとかで各巻が買えるようだが……)
「象徴史・物質論など」カテゴリーアーカイブ
ペトルス・ロンバルドゥスと書物史
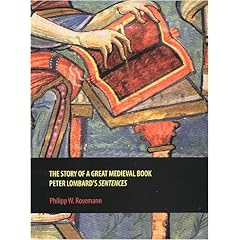 以前『フーコーで学ぶスコラ哲学』を取り上げたことのあるフィリップ・W・ローズマン。この人のフィールドはペトルス・ロンバルドゥスなのだそうで、その有名な『命題集』の内容を一般向けに解説した『ペトルス・ロンバルドゥス』(“Peter Lombard”, Oxford Univ. Press, 2004)なんてのも出しているのだけれど、今度はさらにその注解の歴史を大まかに辿るという一冊が出ていた。『ある偉大な中世の書の物語–ペトルス・ロンバルドゥスの「命題集」』(“The Story of a Great Medieval Book – Peter Lombard’s Sentences”, Broadview Press, 2007)。12世紀から15世紀までの「要約本」や「注解」などを書物史の観点からまとめている。とりあえず前半の12世紀と13世紀のところを読んでみたのだけれど、なるほど、『命題集』は書物史的にもとても重要なのだそうで、同書そのものが、欄外の「脚注」の嚆矢をなしているのだという。また目次が付されているのも画期的なことだったようだ。『命題集』そのものにも、最初の版のほかに増補版があるようで(ロンバルドゥス本人が記したもの)、さらに、直後から出ていたという要約本から、逐語注解を経て13世紀の自由討論風の注解(ボナヴェントゥラやトマス・アクィナス)へといたる経緯を追うと、神学が修道院や司牧の関心から遊離し、学として確立していく過程が追えるということにもなるらしい。うーん、書物史もやはり面白いねえ。13世紀に神学の講義に『命題集』を使うようになった嚆矢として、ヘイルズのアレクサンダーが重要だというのも、個人的にちょっと押さえておきたいポイントかも(笑)。
以前『フーコーで学ぶスコラ哲学』を取り上げたことのあるフィリップ・W・ローズマン。この人のフィールドはペトルス・ロンバルドゥスなのだそうで、その有名な『命題集』の内容を一般向けに解説した『ペトルス・ロンバルドゥス』(“Peter Lombard”, Oxford Univ. Press, 2004)なんてのも出しているのだけれど、今度はさらにその注解の歴史を大まかに辿るという一冊が出ていた。『ある偉大な中世の書の物語–ペトルス・ロンバルドゥスの「命題集」』(“The Story of a Great Medieval Book – Peter Lombard’s Sentences”, Broadview Press, 2007)。12世紀から15世紀までの「要約本」や「注解」などを書物史の観点からまとめている。とりあえず前半の12世紀と13世紀のところを読んでみたのだけれど、なるほど、『命題集』は書物史的にもとても重要なのだそうで、同書そのものが、欄外の「脚注」の嚆矢をなしているのだという。また目次が付されているのも画期的なことだったようだ。『命題集』そのものにも、最初の版のほかに増補版があるようで(ロンバルドゥス本人が記したもの)、さらに、直後から出ていたという要約本から、逐語注解を経て13世紀の自由討論風の注解(ボナヴェントゥラやトマス・アクィナス)へといたる経緯を追うと、神学が修道院や司牧の関心から遊離し、学として確立していく過程が追えるということにもなるらしい。うーん、書物史もやはり面白いねえ。13世紀に神学の講義に『命題集』を使うようになった嚆矢として、ヘイルズのアレクサンダーが重要だというのも、個人的にちょっと押さえておきたいポイントかも(笑)。
「舟と船人の比喩」の再考
またもアラン・ド・リベラ還暦記念論集『実体を補完するもの』の収録論文から。アレクサンドリーヌ・シュニーヴィントの「魂は舟の船人のようなものなのか」という小論。奇妙な変遷を辿ったことでも有名な「舟と船人の比喩」(身体と魂の関係を謳ったものとされる比喩)について、アリストテレスのもとのテキストと、アフロディシアスのアレクサンドロス、プロティノスの注解から要点をまとめている。この比喩は、むしろ「舟と操舵手」という比喩として人口に膾炙しているわけだれど、もとのアリストテレスは操舵手(κυβερνήτης)ではなく船員(πλωτήρ)を使っているといい、また両者を区別する一文が『政治学』にあることから、その語の選択は意図的になされたのだろうと推論する。そこにはしかるべき意味があったというわけだ。ところがアレクサンドロスになると、用語的にはすっかり「操舵手」になってしまい、その上で、その語が一人の操舵手を指すのか、それとも操舵の技術を指すのかを検討し(魂と身体の関係を譬えているわけで、前者ならばプラトン主義的に魂が身体から分離しうると解釈できるし、後者なら内在論と解することができる)、結局は両方とも魂と身体の関係の譬えに使うには不適切として斥ける。誤った語をさらに敷衍して考察しているのはちょっと悲惨だ、みたいな扱い。プロティノスになると、正しく「船員」「操舵手」両方の語の違いを考察し、やはりどちらも魂と身体の関係を表すには不当だとこれまた斥けているのだという。うーん。後世において「船員」が「操舵手」になった大元はアレクサンドロスの用語法のせいだというわけなのだけれど、そのあたりは結構微妙なのでは……?「操舵手」はプラトン『国家』にも見られる(488C)という話もあることだし(論文著者本人が指摘している)、第一、ギリシア語自体が時代によって多少意味のズレを含んでいたりもしないのかしら、などと素朴な疑問も浮かんでくるのだが……。

ノルウェーの中世美術
 近所の本屋でいつになく目についたのが『芸術新潮』の12月号。あまりに気にかけていない雑誌だけれど、いつもの月よりも置いている冊数が多いような気がする……。で、その特集が「ノルウェーの森へ–中世の美とオーロラの旅」。なんだか新幹線の車内誌『トランヴェール』の外国版という体裁だが……(笑)。でも、特集の中心をなす、美術史家の金沢百枝氏による木造教会探訪記は読み応え十分。写真も見事で、木造の教会の佇まいはとてもいい。細部の浮き彫りや板絵なども素晴らしい。ロマネスク建築の石造りの技法はノルウェーにも伝わっていたというけれど、素材の調達や資金の問題を超えて、地元の人々には木造への嗜好、こだわりがあったのではないか、という仮説が面白い。ノルウェーの中世美術史の大家だというホーラー氏を訪ねる件があるけれど、この方、異教の残滓を思わせる教会内の木彫りの彫刻などについて、「それは装飾だから意味はない」とにべもなく言い放つのが逆に印象的(笑)。実証を重んじる研究スタイルだというけれど、なるほど下手な解釈は恣意にすぎないのだからよしときなさいというのは、ある意味ごもっとも。
近所の本屋でいつになく目についたのが『芸術新潮』の12月号。あまりに気にかけていない雑誌だけれど、いつもの月よりも置いている冊数が多いような気がする……。で、その特集が「ノルウェーの森へ–中世の美とオーロラの旅」。なんだか新幹線の車内誌『トランヴェール』の外国版という体裁だが……(笑)。でも、特集の中心をなす、美術史家の金沢百枝氏による木造教会探訪記は読み応え十分。写真も見事で、木造の教会の佇まいはとてもいい。細部の浮き彫りや板絵なども素晴らしい。ロマネスク建築の石造りの技法はノルウェーにも伝わっていたというけれど、素材の調達や資金の問題を超えて、地元の人々には木造への嗜好、こだわりがあったのではないか、という仮説が面白い。ノルウェーの中世美術史の大家だというホーラー氏を訪ねる件があるけれど、この方、異教の残滓を思わせる教会内の木彫りの彫刻などについて、「それは装飾だから意味はない」とにべもなく言い放つのが逆に印象的(笑)。実証を重んじる研究スタイルだというけれど、なるほど下手な解釈は恣意にすぎないのだからよしときなさいというのは、ある意味ごもっとも。
アルベルトゥス論とか
 金森修編『エピステモロジーの現在』(慶應義塾大学出版会、2008)をぱらぱらと。エピステモロジーというと主にフランス系の科学哲学・認識論のことだけれど、これは国内のその分野(といってもかなり広いけれど)の若手研究者を中心とした論文集。デカルト、クールノー(19世紀の確率論者)、カヴァイエス(20世紀の数学史家)、ベルクソン、フランソワ・ダゴニェ(これは金森氏ならでは)などが取り上げられるかと思うと(第一部)、第二部ではフランスの心理学成立史、現代的な生命認識論、中世のアリストテレス主義の自然哲学、19世紀の地質学の誕生などの論考が続く。うーん、壮観だ。
金森修編『エピステモロジーの現在』(慶應義塾大学出版会、2008)をぱらぱらと。エピステモロジーというと主にフランス系の科学哲学・認識論のことだけれど、これは国内のその分野(といってもかなり広いけれど)の若手研究者を中心とした論文集。デカルト、クールノー(19世紀の確率論者)、カヴァイエス(20世紀の数学史家)、ベルクソン、フランソワ・ダゴニェ(これは金森氏ならでは)などが取り上げられるかと思うと(第一部)、第二部ではフランスの心理学成立史、現代的な生命認識論、中世のアリストテレス主義の自然哲学、19世紀の地質学の誕生などの論考が続く。うーん、壮観だ。
とりあえず個人的に食指をそそられるのは、なんといっても第二部の中世もの。高橋厚「自然の作品は知性の作品である」は、アルベルトゥス・マグヌスの「形成力」思想をまとめたなかなか贅沢な内容の論考。個人的にもアルベルトゥスには惹かれるものがあるだけに、こういう堅実な研究の登場は嬉しいところ。内容は、アルベルトゥスの『鉱物論』や『動物論』から無機物・有機物をつらぬく一貫した同じ生成原理が読み取れ、それがアリストテレスのプラトン主義的解釈から導出されるものだということを、テキストに即して論証しようというもの。個人的にはやはりナルディ的解釈とか思い出してしまう。そちらでは確か、天の第一動者(というか神ですね)は鉱物の生成に対して二度介入する形を取り、一度目で形相の胚芽を質料に注ぎ込み、可能態として内部に宿る形相の胚芽が本来の形相に対して決定的に欠損が刻印されるため、それを現実態にするには天の力(というか動者としての知性の力?これまた神?)の第二の介入が必要になる、という図式だった(生物の魂においても同じ図式が適用されていたようだったけれど、細部は微妙に異なっていたような気もする。アルベルトゥスはある時期、能動知性が魂に個別的に内在するみたいな話をしていて、能動知性と天の力とで少し話がぶれていたような印象も……)。で、その図式でみると、上の論文の「形成力」も、二つのどちらの介入に位置するものなのかが微妙にぶれるような気も……。でもこれは、解釈の格子をどう取るかの問題かしらね。いや〜、それにしても刺激も受けたことだし、個人的にも未読テキストが山のようにあるアルベルトゥス、また改めて読んでいきたいと思う。