Emmanuel Levinas, Entre nous – Essais sur le penser-à-l’autre , Livre de Poche, Grasset, 1991 邦訳(合田正人ほか訳、法政大学出版局)
冒頭の「存在論は根源的か」という短い論考は1951年初出のもの。当時の「現代的」存在論が、西欧の理論的伝統と断絶する形で実存に身を沈めているとの認識から、他者の問題についても知見の逆転を試みる。他者の理解というのはそもそもが存在の「開かれ」なのだといい、他者を独立した「モノ」のように扱わず、呼びかけ、祈り、語りかける宛先とすることこそが他者の理解なのだ、とレヴィナスは訴える。他者との関わりは突き詰めれば「祈り」に還元され、「理解」がそれに先立つことはない。これをレヴィナスはreligionであるとする。おそらくはreligionの原義である「強い(あらためての)結びつき」「再度の結びつき」ということなのだろうと思うけれど、いずれにしてもディスクールの本質はその「祈り」にある、とレヴィナスは断言する。
さらに他人との「遭遇」(接触)も逆転される。相手をモノのように扱うとは、要するに他人を「所有」するということになり、所有とはこの場合、存在する者としての相手を部分的に否認することになる。他人と「出会う」とは、そうした所有の拡がりの中にあって、相手を所有しないことだ、とレヴィナスは言う。相手を、たとえばレッテルを貼るなどして固定的に捉えることは、相手を抹消(抹殺)することでもあり、「私」は絶えずそういう抹消の望みとともにあるけれど、抹消が成就してしまえば、相手はこちらの手をすり抜けてしまう。このジレンマの中で相手と文字通り顔を突き合わせ対峙すること、それが遭遇(接触)のあからさまな姿にほかならない……ということなのかな(?)。この、境界線がどこかほつれるような、狭間の思考のような文面はたまらない魅力だ。まいど個人的な話で恐縮だが、認知症の親を相手に、理解しにくい奇行の闇と接していると、こうした文面はそこいらの安っぽい癒やしの言葉なんぞよりもよっぽど深い安らぎと残響をもたらしてくれるように思える。というわけで、いまさらながらだけれど、レヴィナスは新たな座右の書候補にすらなってきた(笑)。
村上靖彦『レヴィナスーー壊れものとしての人間』(河出ブックス、2012)
それにしても、他者と最初に切り結ばれる関係性が、言語以前・非言語的な「コンタクト」(レヴィナスの言うところの「愛撫」)であるということをレヴィナスが喝破し、ある種転倒した他者論を構築しているというところが個人的には興味深い。「死体」にすぎない他者が意味を有する他人として現れるようになるには、まずそのコンタクトが必要だというわけだ。たとえばうちの認知症の親は、ときおり記憶が曖昧になるのだけれど(同居している息子である私のことを、私が不在のときなど、たまに三人称的に「男たち」と称したりするようだ)、別のときには何かを確かめるように、不自然なまでにちらちらとこちらにアイコンタクトを送ってくるときがある。もしかすると、消えていきそうな記憶(つまりは無化である「ある」が襲ってくるということだろう)に、こちらにコンタクトを取ることで必死に抗っているのかもしれない……。
『ウィトゲンシュタインのパラドクス−−規則・私的言語・他人の心』(黒崎宏訳、産業図書)
補遺においては、それがさらに「他人の心」の問題にまで敷衍される。たとえば有名な痛みの問題。「他人の痛みを自分の痛みとして感じる」ということは物理的にありえず、他人の痛みを自分の痛みとして想像することさえ実は困難かもしれないという(つまり文字通りに取るなら、自分が感じない痛みをもとに、他人の痛みをどう感じうるのかというのは大きな問題になってしまう)。そもそも人が他人の心を覗くことは不可能である以上、人は外的に他人を見て、その他人の行動・発話から三人称的にその他人が痛みを有していることを判断するしかない。そしてその際の行動・発話は共同体的に共有されていなければならない。痛みについても、「他人が痛みを感じている」という状況の理解こそが重要であって(その状況に自分を置けることが、他人の痛みの判断となる)、痛みの想像は後から来ると(クリプキによれば)ウィトゲンシュタインは言う。なるほど、ウィトゲンシュタインが行動主義的だと言われる所以はこのあたりにあるのか。うーん、それにしても、認知症のような一種の私的言語化に踏み込んでいる人(親だけど)を家族にもっている身としては、上のような行動主義的なルール解釈・状況解釈からこぼれてしまうケースに、どう対応すればよいのかが切実な問題として立ちふさがるのだけれど……。
ジャレド・ダイアモンド『文庫 銃・病原菌・鉄 を読んでみた。で、以下少々乱暴な感想。同書の肝はなんといっても、技術的な事象(文字とか牧畜とかも含む)というものは同時多発的に複数の起源から出現するのではなく、ある特異点で登場し、そこから別の地域に伝播していくのだというモデルにある気がする。このモデルを採択すると、歴史上の西欧の圧倒的な物質的優位とかが比較的明快に整理できるというわけなのだけれど、個人的にはびみょ〜な違和感を感じたりもする。同モデルが、どこか偏った主体を前提にしているような気がするからだ。まったく未知だった文字や技術対象物が他所から伝えられると、受け入れる側の民族はごくわずかな時間でそれらを使いこなせるようになる。だから基本的能力は等しくもっているものの、ただ文字や技術対象物を生み出すほかの条件は整っていなかったせいで、当初は水を空けられているのだが、すぐにそれらを取り込んで追いつくことができる、というのが同書の基本線。なにやらこれ、だからグローバル化などは行き着くべき必然的な到達点なのだ、と言っているような気さえしてしまう(笑)。
同書では一貫して文字や技術対象物は「道具」として扱われているのだけれど、まがりなりにも仏系の現代思想とかを経てきた私たちは、別モデルの可能性を語れるんじゃなかったかなあ、と。たとえば文字は単なる道具じゃなく、もっと根源的なレベルをも構成している(しうる)可能性だってある、みたいな。言語が喚起する聴覚イメージと称されるものの分節は、もとよりきわめて文字的な何か(昔は痕跡とか言っていたが)だったのでは?技術対象物も同様で、そこにはどこか同化・異化の力学のようなものがあるんじゃなかったっけ?そういう議論から組み上げられるモデルがあるとすれば、西欧から持ち込まれた技術の類は、もとの民族がもっていたはずの豊かな創造性のようなものを駆逐し、均一化を押しつけてしまったという負の面のほうが強くなってしまうのだったはず。その意味での西欧文明は罪深いし、そのあたりを顧みず、同様の物質文化が他の地域で発生しなかったのは環境的条件のせいで、能力的な要因ではないとするのは、一見公正・平等な人間観のようでいて、実は西欧的な暴力行為を不問に付すという偽善的なスタンスなのではないか……なんて問うこともできる。道具立てでのみ見ないで、別様の可能性をさぐること。そこからすると基本的な問題は、なぜ西欧以外の地域は技術革新に至らなかったのかではなく、なぜ西欧はそういう暴力的な拡張性をあえてふりかざしたのか(あるいは、ふりかざすしかなかったのか)ではないかと……。
『イマーゴ』(斉藤環特集:東日本大震災と<こころ>のゆくえ)
「多くの老人たちは、治癒しないまま、この現実とは別のもうひとつの世界を創りあげる」(p.88)と同著者は記している。それはストレスやトラウマを遮断するシェルターのようなシステムなのだという。この場合の治癒とは、なんらかの社会的な行動ができるところまで症状を和らげることを言っているようだ。で、うちにいる認知症の老母はというと、確かにそういう徴候を示し、日増しにそれは深まっているようにも見える。相当崩れてしまっている記憶をもとに虚構を練り上げる一方、その認識がおりなすストーリーの一貫性だけは保とうとし、周りの人々の現実的な対応にほとんど嘘(?)でもって応答しようとする。たとえば、老母の頭の中では震災(というかその後の津波)が起きたのはつい先日(11月?)で、その前に予知夢のようなものを見ていたのだという(けれどもその夢の話は大昔に聞いた気もするのだが)。また、自分の生家は20年以上前に取り壊されているのに、その津波によってなくなったという話にすり替わっている。見方によってはこれは、記憶に残っている断片をつなぎ合わせて新しい主体構築をしようとしている……のだろうか。それにしても難しいのはこちら側の対応だ。その新しい世界をこちらが拒否すれば、それが傷になってさらにその世界に埋没していくのかもしれないが、それを仮に受け入れても、いわば図にのって、虚構世界をさらに拡大させていくという感じでもある。「傷つけられることはない。だがそれは共感することもない世界である。その世界は少しずつ荒廃せざるをえない」(同)と上の論考にも記されているが、そのきわめて異質な虚構世界をそのまま引き受けるというのは、身内であってみればよりいっそう難しい。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
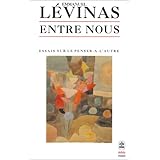 先月の村上本に触発されて(笑)このところ、少しずつでもレヴィナスの未読のものを読もうかと思っている。レヴィナスは個人的に、なぜか主著ではないものばかりをつまみ食いしてきた感じがあって(『タルムード四講話』とか『貨幣の哲学』とか)、改めて少し長くこだわってみたいという気がしている。そんなわけで、まずは『われわれのあいだに』(Emmanuel Levinas, Entre nous – Essais sur le penser-à-l’autre, Livre de Poche, Grasset, 1991)。年代順に講演や雑誌発表の論考などを集めた論文集。もちろん邦訳(合田正人ほか訳、法政大学出版局)も出ているが、個人的にはできればレヴィナスは(も?)原典で味わいたいところだ。語彙ひとつとってみても通常とは違う意味合いが込められていると言われるけれど、そうはいってもなにやら普通にも読めてしまい、こちらが受け取る文意がどこからか微妙にずれていく感覚があって、滑走するような心地よさと、宙づりになっているもどかしさを両方感じ取ることができたりして、なんとも複雑な気分になる(決して悪い意味ではないし、そもそもそういうのは嫌いではないのだけれど)。ある種の人がとても「ハマる」らしいというのも頷ける。
先月の村上本に触発されて(笑)このところ、少しずつでもレヴィナスの未読のものを読もうかと思っている。レヴィナスは個人的に、なぜか主著ではないものばかりをつまみ食いしてきた感じがあって(『タルムード四講話』とか『貨幣の哲学』とか)、改めて少し長くこだわってみたいという気がしている。そんなわけで、まずは『われわれのあいだに』(Emmanuel Levinas, Entre nous – Essais sur le penser-à-l’autre, Livre de Poche, Grasset, 1991)。年代順に講演や雑誌発表の論考などを集めた論文集。もちろん邦訳(合田正人ほか訳、法政大学出版局)も出ているが、個人的にはできればレヴィナスは(も?)原典で味わいたいところだ。語彙ひとつとってみても通常とは違う意味合いが込められていると言われるけれど、そうはいってもなにやら普通にも読めてしまい、こちらが受け取る文意がどこからか微妙にずれていく感覚があって、滑走するような心地よさと、宙づりになっているもどかしさを両方感じ取ることができたりして、なんとも複雑な気分になる(決して悪い意味ではないし、そもそもそういうのは嫌いではないのだけれど)。ある種の人がとても「ハマる」らしいというのも頷ける。


