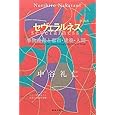ハイデガーの技術論ということで、『技術への問い』(関口浩訳、平凡社、2009)から表題の講演を読んでみる。技術の本質について考察したハイデガーの代表的技術論だ。ハイデガーは自然を伏蔵性(Verborgenheit)から不伏蔵性へといたらしめることを「開蔵」(entbergen)と称し、これを人間が自然に向ける基本姿勢と見なす。どうやらこれは、自然の諸側面になにがしかの有益性を見出すというプロセスのことらしい。そして人間は自然の側からの「挑発」でもって、そうした開蔵を促される。なるほど、ここには相互関係があるというわけだ。で、技術はその開蔵の「ひとつのしかた」なのだという。自然はかくして人間にとっては<使えるもの>(「用象」(Bestand)という用語が当てられている)としてアフォードされ、認識される。ややこしいのは、この場合の自然、つまり<使えるもの>には人間もまた含まれてしまうということ。つまり現実的なものはすべて「用象」になってしまう。この「挑発」の構造を支えるものは何か。それがあの有名な立て組み(Gestell:同書では集-立と訳出されている)という構造だということになる。人は外的な関係の構造上、立てて組まずにはいられない、集めて立てずにはいられない、と。
ハイデガーの技術論ということで、『技術への問い』(関口浩訳、平凡社、2009)から表題の講演を読んでみる。技術の本質について考察したハイデガーの代表的技術論だ。ハイデガーは自然を伏蔵性(Verborgenheit)から不伏蔵性へといたらしめることを「開蔵」(entbergen)と称し、これを人間が自然に向ける基本姿勢と見なす。どうやらこれは、自然の諸側面になにがしかの有益性を見出すというプロセスのことらしい。そして人間は自然の側からの「挑発」でもって、そうした開蔵を促される。なるほど、ここには相互関係があるというわけだ。で、技術はその開蔵の「ひとつのしかた」なのだという。自然はかくして人間にとっては<使えるもの>(「用象」(Bestand)という用語が当てられている)としてアフォードされ、認識される。ややこしいのは、この場合の自然、つまり<使えるもの>には人間もまた含まれてしまうということ。つまり現実的なものはすべて「用象」になってしまう。この「挑発」の構造を支えるものは何か。それがあの有名な立て組み(Gestell:同書では集-立と訳出されている)という構造だということになる。人は外的な関係の構造上、立てて組まずにはいられない、集めて立てずにはいられない、と。
ハイデガーはこの後、立て組みにもとづくこの技術という開蔵のしかたが、一つの命運として生きるしかなく、不伏蔵的なものの本質(たとえば、そのものとしての自然とか)にアクセスする可能性は閉ざされてしまうとし、人間には不伏蔵的なものを見誤る危険がつきまということを指摘する。別の開蔵のしかたはあらかじめ閉ざされているというわけか。ひとたび用象となってしまえば、対象として捉えること(つまりは本質的に理解する)はできなくなる、つまり人はもはやモノ(他の人も含めて)を使えるかどうか、どうすれば使えるようになるかでしか見なくなる……。なにやらすべてがエコノミーだ、エコノミーがすべてだとか乱暴なことをぬかすような経済学者を連想してしまう(笑)。人間を取り巻くすべてを用象にしてしまえば、結局はあらゆるものがインフレ的に一元化し脆弱にならざるをえない、ということなのだろう。
ではどうするのか。ハイデガーはここでいきなり反転的な楽観論を語り出す。危険のあるところには救うものもまた育つというのだ(出典はヘルダーリンだという)。集-立が技術を本質的に支える構造であるとするなら、そこに、本質が別の形で姿を現す可能性もあるのではないか、集-立そのものから「叶えるもの」(本質=真理の語源的解釈から出される用語だが……)という開蔵の固有性(本質)も出来するのではないか、というのだ。両者はちょうど表裏一体のような関係にあるとされているのだが、このモデルはどうなのか……。ハイデガーは、そうした裏側の本質的部分の出来を見据え、ささやかにその成長を見守るしかない、といったことを考えているようなのだが、その希望の道筋はあまりにもか弱い。この危険と希望のあまりの落差(とされを平然と語るハイデガーの淡々とした口調)にはちょっと面食らう。というか閉口してしまう。すべてが一元化し猛威を奮うような世界にあって、そのような希望もまた呑み込まれてしまわない保証はどこにもないのではないか。ハイデガー自身も「技術時代には危険は示されるのではなく、むしろなお伏蔵されるのであるが」と留保をつけているではないか。別様の開蔵の可能性は、ただlaisser-faireにまかせておいていいのか、そこにもまたなんらかのプログラムが必要なのではないか。そんなことを改めて強く思う週末読書だ……。
 ちょっと思うところもあって、岩波文庫で最近刊行された田辺元哲学選から『懺悔道としての哲学』(藤田正勝編)を読んでいるところ。うーん、これはある意味難儀な書だ。戦前に発表された『種の論理』では、個と類の中間にあるものとして国家を「類」に重ねて、まさしく近代国家称揚を説いているのだけれど、戦後すぐに出たこちらでは、戦争への流れを止めることができなかったという痛烈な思いをにじませ、「懺悔道」なる新機軸を提唱している。ある意味とても時代の空気に密着・連動している感じで、西田哲学の、どこまでも極北をめざすみたいな超然とした方向性とはやや赴きが異なっている。序には、個人的な体験に発するその反転の動きを体系化しようとする試みだといったことが記されている。懺悔道と言われるものは要するに、個人の無力を突き詰めていくと、それは絶対的な無への帰依という形で反転され、まさしく仏教的な他力本願の思想へと昇華させることができる……ということで、一種のニヒリズム克服のプログラムであるはずなのだけれど、なにやら反転へのプログラムというよりも、そうした反転を経た後でふりかえるところから逆に西欧の哲学を斬っていくことに主眼があるように見える(それはまだ読み終えていないから?)。プログラム的な側面からすれば、おそらく自力から他力へのシフトというところがとても重要になるのだろうけれど、そのあたりはあまり詳述されてはいない印象。一方、西欧の哲学的伝統を批判するという側面では、他力の側から自力を批判するという構図で、たとえばエックハルトについて、自己の否定を通じて絶対者への帰依へといたるという面が懺悔道に一致するとしながらも、それが自力ベースの実存哲学であるという側面では懺悔道の対極にあると批判したりしている。けれどもこの両義的なエックハルト像が、ルドルフ・オットーとケーテ・オルトマンスのそれぞれの書の解釈に依存しているというあたり、なんだかなあという気がしないでもない。そんなわけでこれは、存外に扱いに困る書という印象が強い(苦笑)。おそらくこの書の真価が問われるのは、プログラム部分をより普遍的・有意義的に取り出せるかどうか(それにはむしろ、これまた同書が依拠している親鸞を読むほうがよいような気もする)、そういう読み方ができるかどうかにあるのだろうが……。
ちょっと思うところもあって、岩波文庫で最近刊行された田辺元哲学選から『懺悔道としての哲学』(藤田正勝編)を読んでいるところ。うーん、これはある意味難儀な書だ。戦前に発表された『種の論理』では、個と類の中間にあるものとして国家を「類」に重ねて、まさしく近代国家称揚を説いているのだけれど、戦後すぐに出たこちらでは、戦争への流れを止めることができなかったという痛烈な思いをにじませ、「懺悔道」なる新機軸を提唱している。ある意味とても時代の空気に密着・連動している感じで、西田哲学の、どこまでも極北をめざすみたいな超然とした方向性とはやや赴きが異なっている。序には、個人的な体験に発するその反転の動きを体系化しようとする試みだといったことが記されている。懺悔道と言われるものは要するに、個人の無力を突き詰めていくと、それは絶対的な無への帰依という形で反転され、まさしく仏教的な他力本願の思想へと昇華させることができる……ということで、一種のニヒリズム克服のプログラムであるはずなのだけれど、なにやら反転へのプログラムというよりも、そうした反転を経た後でふりかえるところから逆に西欧の哲学を斬っていくことに主眼があるように見える(それはまだ読み終えていないから?)。プログラム的な側面からすれば、おそらく自力から他力へのシフトというところがとても重要になるのだろうけれど、そのあたりはあまり詳述されてはいない印象。一方、西欧の哲学的伝統を批判するという側面では、他力の側から自力を批判するという構図で、たとえばエックハルトについて、自己の否定を通じて絶対者への帰依へといたるという面が懺悔道に一致するとしながらも、それが自力ベースの実存哲学であるという側面では懺悔道の対極にあると批判したりしている。けれどもこの両義的なエックハルト像が、ルドルフ・オットーとケーテ・オルトマンスのそれぞれの書の解釈に依存しているというあたり、なんだかなあという気がしないでもない。そんなわけでこれは、存外に扱いに困る書という印象が強い(苦笑)。おそらくこの書の真価が問われるのは、プログラム部分をより普遍的・有意義的に取り出せるかどうか(それにはむしろ、これまた同書が依拠している親鸞を読むほうがよいような気もする)、そういう読み方ができるかどうかにあるのだろうが……。
 このところ、アーサー・クローカー『技術への意志とニヒリズムの文化』(伊藤茂訳、NTT出版)を読んでいる。基本的にはIT技術というか、サイバースペース的な話なのだけれど、原発などの近代技術全般を絡めて考えてみるともっと息の長い議論になりそうな気がする。というのも、これが扱っているのはハイデガーの立て組み概念の読み直しということだから。この著者によると、立て組みという概念は、外的なものを人間が「常備在庫」に仕立てるよう、存在そのものが呼びかける衝動だという。常備在庫(この用語が興味深い)化は、つまりは外的な対象物を「開発・変形・蓄積・配分・転換」するということであり、その(半ば自動的な?)サイクルに、人間の身体・自然(本性?)がそのエネルギーも含めてすべて注がれることになり、その結果何が起きるかというと、マルクスが半ばスルーしニーチェが別様に問題化したような人間主体の虚無化が促される、と。著者はこれをITっぽく「ヴァーチャル化」としているけれど、それは自動的なサイクルに巻き込まれることで主体そのものの関わりが希薄化・希釈化していくプロセスということになる。技術的な存在としての人間は、最終的に「純粋空間の中に姿を消してしまう」(p.86)ということになるらしい。著者いわく、それを予言したことがハイデガーの功績なのだ、と。外的対象を常備在庫に変えるという力学を支えているのは意志であり、上の半ば自動的なサイクルの中で、ひたすら意志を志向する「意志への意志」となってしまい、やがては対象すらともなわない意志が空虚に回りつづけるだけになってしまう……。
このところ、アーサー・クローカー『技術への意志とニヒリズムの文化』(伊藤茂訳、NTT出版)を読んでいる。基本的にはIT技術というか、サイバースペース的な話なのだけれど、原発などの近代技術全般を絡めて考えてみるともっと息の長い議論になりそうな気がする。というのも、これが扱っているのはハイデガーの立て組み概念の読み直しということだから。この著者によると、立て組みという概念は、外的なものを人間が「常備在庫」に仕立てるよう、存在そのものが呼びかける衝動だという。常備在庫(この用語が興味深い)化は、つまりは外的な対象物を「開発・変形・蓄積・配分・転換」するということであり、その(半ば自動的な?)サイクルに、人間の身体・自然(本性?)がそのエネルギーも含めてすべて注がれることになり、その結果何が起きるかというと、マルクスが半ばスルーしニーチェが別様に問題化したような人間主体の虚無化が促される、と。著者はこれをITっぽく「ヴァーチャル化」としているけれど、それは自動的なサイクルに巻き込まれることで主体そのものの関わりが希薄化・希釈化していくプロセスということになる。技術的な存在としての人間は、最終的に「純粋空間の中に姿を消してしまう」(p.86)ということになるらしい。著者いわく、それを予言したことがハイデガーの功績なのだ、と。外的対象を常備在庫に変えるという力学を支えているのは意志であり、上の半ば自動的なサイクルの中で、ひたすら意志を志向する「意志への意志」となってしまい、やがては対象すらともなわない意志が空虚に回りつづけるだけになってしまう……。
著者はこれをネットワークの時代の主体問題と見、現代がその新たな転換点を迎えているという形で肯定的な捉え直しを模索しようとしているようだけれど、事態はそれほど軽やかには進みそうにもない気がする。サイバー文化(デジタルアートなど)がどうこう言う前に、ハイデガーの問題系のもっと重苦しい部分に注目しなくてはならないのではないか、つまり、ハイデガーはその立て組みを人間の本質的な部分に絡めて論じているのではなかったかという点あたりから、再検証しなくてはならないのではないか、と。アリストテレス的な知のあり方が、人間にとってきわめて本質的なものであるのかどうか、主体の希薄化は果たして不可避的なものなのか、それともなんらかの方法で迂回できるものなのか。そうした問題を再考するために召喚できる思想がほかにないのかどうか(先の八木氏の本にあったような、パルメニデスの可能性も含めて)。「人ごとのようだ」とネットで揶揄される東電の会見の、どこか主体的虚無を部分的にせよ体現したような話し手の淡々とした表情を見るにつけ、技術と主体の問題がなにやらとても根深そうだということが改めて想起されてくる。
震災と原発事故で改めて明らかになったことの一つに、避難を余儀なくされた人々が郷里から遠く離れようとはしないという全体的な動向がある。震災後に、被災地から遠い各県がいろいろな施設を用意したと聞くが、中にはほとんど入所希望が出なかったようなところもあったらしいし、退避勧告が出た原発近くの住民には、それでもなお地元で暮らし続けようとしている人もいるという。もちろん直接的理由は様々だろうけれど(世話をしている家畜を見捨てていけない、よそに行っては仕事がない、などなど)、大きな括りとしてはどこか漠然とした「離郷に対する抵抗感」があるように見える。これは一体どういうものなのか。これを郷里への執着として理解しようとすると、なにやら感情論や審美的判断のように見えてしまうのだが、そう考えることにどこか違和感を伴うのもまた事実だ。疎開論もどこか違うという感覚を覚える。これはどういうことなのか。
なにも罹災者に限ったことではない。田舎に暮らす老親を都会に住む子ども世代が引き取ろうとするような場合でも、同じような抵抗に遭う場合がある。たいていは一般論として、老人特有の頑固さのせいで地元への執着が高まる、みたいな話に帰着させてしまうのだろうが、これもそれだけではないような気もする。問題はもっと細やかな理にあるようにも思われる。つまり、土地勘という名称で呼ばれているある種の認識形態・認識プロセスが、そこに大きく影響している可能性があるのではないか、と。それはおそらく情動的なものと、なにがしかの記憶、隠微な合理性などが入り組んだプロセスで(ある種のアフォーダンス?)、だからこそ見知らぬ土地に放り込まれてしまうと、そうしたプロセスの不全が反動的な不安となって襲ってくるのではないか……。この「土地勘」みたいなものは、詳細に分析する必要がありそうだ。震災後の復興において、それは一つの鍵になるかもしれないからだ。首相が提唱しているらしい沿岸都市のあり方とかエコタウン構想などが、どこか机上の空論に終わりそうな、微妙な「よるべなさ」を醸し出しているのも、そのあたりに理由を見いだせそうな気がするのだが……。
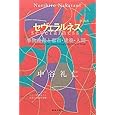 復興ということで言えば、中谷礼仁『セヴェラルネスPLUS – 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)所収の「先行形態論」という論考は示唆的だ。これは、都市の発展がそれ以前の形を無意識的に踏襲するというどこか「無意識的」な動きについて議論を展開したもので、具体例として原爆投下後の広島を取り上げており、一種の復興論としても読める。それによると、戦後の広島の街路計画に一見すると新設根拠が不明瞭な道路があるのだという。ところが時間を遡ってみると、これが計画者ら自身も自覚していなかった近世の市街地と新開地との境界にほぼ一致していたという。同じく区画整理においても、それまでの市街地の無計画性を取り除くことで、近世期の町割りと親和性のある形態ができあがったりしているのだとか。これらはもしかすると、上のような「土地勘」のような合理性を示す一種の事例かもしれない。一方でヤミ市がその時々の交通の要所に誕生し、都市の転用としてシステム全体の再定義を促したともいう。こうした回帰と再定義の動的なプロセスが、おそらく今回の各被災地でも見られていくことだろう。一方で、もし原発事故で完全に郷里を追われる人々が出てくるならば、新たな都市の創成プロジェクトは回帰しなぞるべき参照系がないだけに、いっそう多くの困難を強いられるのではないだろうか。
復興ということで言えば、中谷礼仁『セヴェラルネスPLUS – 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)所収の「先行形態論」という論考は示唆的だ。これは、都市の発展がそれ以前の形を無意識的に踏襲するというどこか「無意識的」な動きについて議論を展開したもので、具体例として原爆投下後の広島を取り上げており、一種の復興論としても読める。それによると、戦後の広島の街路計画に一見すると新設根拠が不明瞭な道路があるのだという。ところが時間を遡ってみると、これが計画者ら自身も自覚していなかった近世の市街地と新開地との境界にほぼ一致していたという。同じく区画整理においても、それまでの市街地の無計画性を取り除くことで、近世期の町割りと親和性のある形態ができあがったりしているのだとか。これらはもしかすると、上のような「土地勘」のような合理性を示す一種の事例かもしれない。一方でヤミ市がその時々の交通の要所に誕生し、都市の転用としてシステム全体の再定義を促したともいう。こうした回帰と再定義の動的なプロセスが、おそらく今回の各被災地でも見られていくことだろう。一方で、もし原発事故で完全に郷里を追われる人々が出てくるならば、新たな都市の創成プロジェクトは回帰しなぞるべき参照系がないだけに、いっそう多くの困難を強いられるのではないだろうか。
フランスのサルコジ大統領は3月末の来日会見で、「原発は地震は耐えたが津波にやられた。津波が問題だったのだ」と述べていた。おそらく日本側からの説明がそういうものだったのだろう。けれども、先日7日の夜の大きな余震後、この余震の影響を受けた福島以外の原発が軒並み綱渡り的な状況になったことで、問題が津波だったとは断定できなくなった。少なくとも疑問符が付いた……そう、原発はそもそも地震に耐えたのかという問いが浮上した。
原発には耐震処理がなされているという話は以前からあったように思う。問題なのは「耐震」が何を意味するかだ。なるほど、確かに建物自体が崩壊するような事態はなかった。単に家屋ならばそれで「耐震」ということで問題はないだろう。けれども、原発などなんらかの生産設備は、そもそも地震によって機能が損なわれてしまわないことを「耐震」と呼んでしかるべきなのではないか、と思われる。電源が簡単に落ちてしまうような設備を「耐震」とは言えない。そういう意味での「耐震」を基準にするなら、現時点での原発は必ずしも合格点とは言えない。構造体としてのみ捉えてしまい、機能面を加味した全体的な生産設備(それもクリティカルな)として「耐震」を考えていなかった可能性は否定できない。少し前のポストとも重なるけれど、構造体として捉えるとは、いわば一面(一点)だけをピックアップして考慮するということであり、生産設備を全体として捉えることができていないということ。リスク管理としては、もはやそうした点的な対応では不十分で、全体的・包括的な捉え方が求められる……。今の場合でいえば、「電源込み」で耐震設計をするとか、電源の取り込み口を複数化しておくとか、システム全体で「耐震」ないし「免震」を実現する……。
 ではなぜ、そうした全体的思考はなかなか育まれないのか。この問題に関連についてはアンドリュー・フィーンバーグ『技術への問い』(直江清隆訳、岩波書店)が様々に示唆的だ。目的に奉仕するという意味で技術は「中立」だとする通念に対して、著者はそれが実は「自分たちの自律性を守ろうとする専門家や組織の側の一般的な防衛反応」(p.130)にすぎないと喝破する。技術が「中立」に見えてしまうのは、当該技術をめぐる以前の利害関心がデザインに内在化していくように、社会・組織と技術の体制が変化していくからだと指摘している(同)。その特殊な一例としてあげられているのが、まさに原子力の事例だ。アメリカでは、大衆が抱く不安・反発によって、原発が1960年代のデザインで80年代ごろまで固定されたままという事態を引き起こしたという。しかしこの場合、非合理だったのは大衆の側でもなければ、事業を推進した側でもなかった、と著者はいう。両者の再帰的な関係がそういう膠着状態を招いたというのだ。環境運動は技術の副作用を減少させようとするが、往々にして「技術プロセスから製品や人に、事前の防止から事後的な後始末に、批判の目をそらせようとする傾向が見られる」(p.137)という(なぜそうなるのかは触れていないようだが……)。一方の運営する側はこれを受けて「トレードオフを含むコストとして認識」(この技術を使わないと、その先に待ち構えているのは貧困だぞ、と)し、相手を追い詰めていく。
ではなぜ、そうした全体的思考はなかなか育まれないのか。この問題に関連についてはアンドリュー・フィーンバーグ『技術への問い』(直江清隆訳、岩波書店)が様々に示唆的だ。目的に奉仕するという意味で技術は「中立」だとする通念に対して、著者はそれが実は「自分たちの自律性を守ろうとする専門家や組織の側の一般的な防衛反応」(p.130)にすぎないと喝破する。技術が「中立」に見えてしまうのは、当該技術をめぐる以前の利害関心がデザインに内在化していくように、社会・組織と技術の体制が変化していくからだと指摘している(同)。その特殊な一例としてあげられているのが、まさに原子力の事例だ。アメリカでは、大衆が抱く不安・反発によって、原発が1960年代のデザインで80年代ごろまで固定されたままという事態を引き起こしたという。しかしこの場合、非合理だったのは大衆の側でもなければ、事業を推進した側でもなかった、と著者はいう。両者の再帰的な関係がそういう膠着状態を招いたというのだ。環境運動は技術の副作用を減少させようとするが、往々にして「技術プロセスから製品や人に、事前の防止から事後的な後始末に、批判の目をそらせようとする傾向が見られる」(p.137)という(なぜそうなるのかは触れていないようだが……)。一方の運営する側はこれを受けて「トレードオフを含むコストとして認識」(この技術を使わないと、その先に待ち構えているのは貧困だぞ、と)し、相手を追い詰めていく。
著者によれば、このトレードオフモデルは一種の偏向(バイアス)であり、そこで突きつけられるジレンマ(「環境的に健全な技術VS繁栄」など)の統合こそが重要だという。それが政治的なイデオロギーの対立に見えるというのは本質的問題ではなく、技術の本質からすると(シモンドンが引き合いに出されているが)、そもそも技術的発展の目標とはそうしたジレンマを避けることにあるはず、と。その上で、こうしたトレードオフではない別の価値観へのシフトを模索することが求められる、ということを著者は論じている。一例として、アメリカ政府が汽船のボイラーに課した安全規則が挙げられている。それは「人間の生命の価値と政府の責任についての非経済的な決定」(p.143)だったという。話を目下の問題に戻すならば、おそらくはもう一度、上の技術プロセスと事前の防止の方へ立ち戻ることが肝心だということになるだろう。この著者が示すようなバイアスを生む土壌すらをも見据えて……。それは当該技術を全体(関連技術や組織論も含めたまさにマクロな体制)から捉え直すというスタンスと切り離すことはできないはずだ。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 ハイデガーの技術論ということで、『技術への問い』(関口浩訳、平凡社、2009)から表題の講演を読んでみる。技術の本質について考察したハイデガーの代表的技術論だ。ハイデガーは自然を伏蔵性(Verborgenheit)から不伏蔵性へといたらしめることを「開蔵」(entbergen)と称し、これを人間が自然に向ける基本姿勢と見なす。どうやらこれは、自然の諸側面になにがしかの有益性を見出すというプロセスのことらしい。そして人間は自然の側からの「挑発」でもって、そうした開蔵を促される。なるほど、ここには相互関係があるというわけだ。で、技術はその開蔵の「ひとつのしかた」なのだという。自然はかくして人間にとっては<使えるもの>(「用象」(Bestand)という用語が当てられている)としてアフォードされ、認識される。ややこしいのは、この場合の自然、つまり<使えるもの>には人間もまた含まれてしまうということ。つまり現実的なものはすべて「用象」になってしまう。この「挑発」の構造を支えるものは何か。それがあの有名な立て組み(Gestell:同書では集-立と訳出されている)という構造だということになる。人は外的な関係の構造上、立てて組まずにはいられない、集めて立てずにはいられない、と。
ハイデガーの技術論ということで、『技術への問い』(関口浩訳、平凡社、2009)から表題の講演を読んでみる。技術の本質について考察したハイデガーの代表的技術論だ。ハイデガーは自然を伏蔵性(Verborgenheit)から不伏蔵性へといたらしめることを「開蔵」(entbergen)と称し、これを人間が自然に向ける基本姿勢と見なす。どうやらこれは、自然の諸側面になにがしかの有益性を見出すというプロセスのことらしい。そして人間は自然の側からの「挑発」でもって、そうした開蔵を促される。なるほど、ここには相互関係があるというわけだ。で、技術はその開蔵の「ひとつのしかた」なのだという。自然はかくして人間にとっては<使えるもの>(「用象」(Bestand)という用語が当てられている)としてアフォードされ、認識される。ややこしいのは、この場合の自然、つまり<使えるもの>には人間もまた含まれてしまうということ。つまり現実的なものはすべて「用象」になってしまう。この「挑発」の構造を支えるものは何か。それがあの有名な立て組み(Gestell:同書では集-立と訳出されている)という構造だということになる。人は外的な関係の構造上、立てて組まずにはいられない、集めて立てずにはいられない、と。