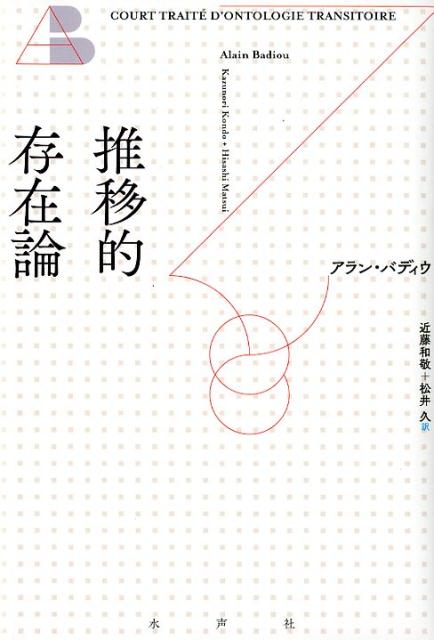パズルゲームの「数独」では、上級問題になってくると、ある数が2つのマスに入る可能性があってほかの手がかりがなく、論理的推論だけでは判断できないような場面が出てきたりする。そんなときの対処法は、やはりトライ&エラーに限る。とりあえず入れてみて、ほかのマスがうまく埋まるかどうかを見てみる、というやり方。うまくはまれば、それでほかのマスが一挙に埋まったりする。当てずっぽう、あるいは決め打ちという感じではあるけれど(苦笑)、作業効率は悪くない。で、こうしたやり方は案外広く用いられている印象もある。機械学習・深層学習の教科書などでよく眼にする「ベイズ推定」「ベイズ定理」なども、ごく基本的なところの発想はそういうトライ&エラーにあるらしい。
 なんでこんな話をしているかというと、次の本を読んでいるところだから。シャロン・バーチュ・マグレイン『異端の統計学 ベイズ (草思社文庫 マ 3-1)』(冨永星訳、草思社、2018)。まだ冒頭150ページ弱の第一部を見ただけだけれど、これがなかなか面白くて引き込まれる。トーマス・ベイズが1740年代に発見し、その後ラプラスが精緻化したというこのトライ&エラー型の確率論(「事後確率は事前確率と尤度の積に比例する」という定理)の盛衰を、時代に沿って順に詳述していくというもので、ノンフィクションの群像劇的な面白さを味わうことができる。盛衰というが、第一部に関しては、その悲劇的ともいえる毀損の数々が描かれていく。主要登場人物で著名な数学者だったラプラスの存在にもかかわらず、ベイズ推定はおもにその主観的な推測と、初期設定となる等確率の無根拠さによって散々な攻撃に曝され、文字通り粉砕されてしまう。けれどもその理論の発想は、一部の人々、とくに他領域の研究者らによって徴用・温存されて、やがて日の目を見ていくことになる……と、なかなか情感に訴えるストーリー展開が待っていることは予想がつくが、いずれにしてもこれは実に骨太のサイエンスライティング。
なんでこんな話をしているかというと、次の本を読んでいるところだから。シャロン・バーチュ・マグレイン『異端の統計学 ベイズ (草思社文庫 マ 3-1)』(冨永星訳、草思社、2018)。まだ冒頭150ページ弱の第一部を見ただけだけれど、これがなかなか面白くて引き込まれる。トーマス・ベイズが1740年代に発見し、その後ラプラスが精緻化したというこのトライ&エラー型の確率論(「事後確率は事前確率と尤度の積に比例する」という定理)の盛衰を、時代に沿って順に詳述していくというもので、ノンフィクションの群像劇的な面白さを味わうことができる。盛衰というが、第一部に関しては、その悲劇的ともいえる毀損の数々が描かれていく。主要登場人物で著名な数学者だったラプラスの存在にもかかわらず、ベイズ推定はおもにその主観的な推測と、初期設定となる等確率の無根拠さによって散々な攻撃に曝され、文字通り粉砕されてしまう。けれどもその理論の発想は、一部の人々、とくに他領域の研究者らによって徴用・温存されて、やがて日の目を見ていくことになる……と、なかなか情感に訴えるストーリー展開が待っていることは予想がつくが、いずれにしてもこれは実に骨太のサイエンスライティング。
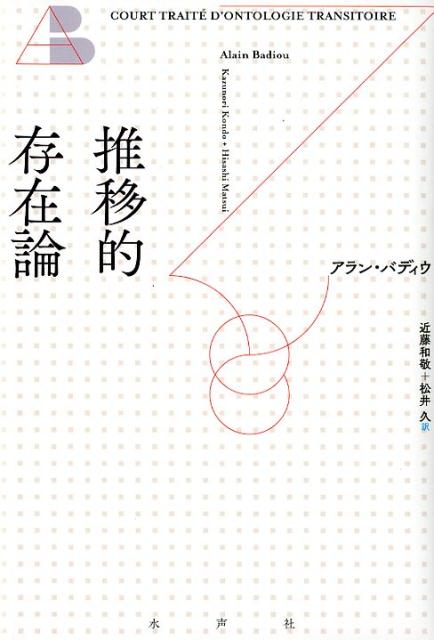 今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
このような立場を擁護すべく、同書では主要な哲学史上の議論の流れが再整理されることになる。その整理は、ある意味刺激的な読み直しをともないつつ、ドゥルーズ、スピノザなどをめぐりながら、少しずつ着実に進んでいく。中でもとりわけ刺激的なのは、プラトン思想やカント思想の「読み直し方」。前者においては、アリストテレスが「一」の論理に存在論を落とし込もうとする(記述を通じて)のに対し、プラトンは「多」の絶対的な決定不可能性のほうへと向かっていく、とされる。決定不可能性とは、たとえば認識主体と認識対象との区別になんの妥当性もないということだ。バディウは、思考が包蔵する存在と、思考が調整する運動との共外延性こそが、プラトンの言う「イデア」なのだと喝破してみせる。つまり思考の能力と思考の対象とは同じものであって分離できないということ。するとそれは多数性へと向かう契機こそを重視する立場を導き、選択公理(集合の生成力に制限を設けない)に好意的で、連続体仮説(限定を加えそうな)には慎重だということになる。
後者についても、たとえばカントの議論を、現象の側に純粋な多を、主体の側に「一として数えること」(統一)を置くように解釈してしまうのは誤りだとし、統一もまた、現象の多性の側の問題へと送り返していると読むべきだとしている。そのような統一をなす「統覚」の能力は、多の事象をたがいに結びつけるようなカテゴリーの体系とは別物で、むしろ連結の側から接近されるようなものなのだという。純粋な多がなんらかの状況に置かれて、「一として数えられる」ようになるのが実在するものだといい、一方の対象とは、連結(結びつきの錯覚)からのみ表象可能となったものだとされる。ここでもまた、統覚(主体)と対象とに、それらを表象可能にするような源・主体と源・対象があるならば、それらはいっさい現前することがなく、存在から引き離された「空」であるという意味において、不可分のものなのだとされる。
総じて、細やかで難解でありながらも、見かけ以上に価値転覆的な戦略を伴った議論という印象。消化しきれないところも多々あるし、これがどのような展開を遂げていくのかも気になるところではある。今回の翻訳は少し読みにくい印象もあるけれど、いずれにしてもバディウは少しこだわって見てみたい著者である。
 スピノザの後世への影響についての諸論文を集めたものだろう、という軽い気持ちで手にとった論集『主体の論理・概念の倫理 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』(上野修、米虫正巳、近藤和敬編、以文社、2017)。読み始めてみると、どんどん別世界のほうに引き込まれるかのようで、なんとも心地よいドライヴ感(笑)。冒頭はいきなり数学者ジャン・カヴァイエスが主役級の扱い。カヴァイエス(1903 – 44)は先のブラウワーよりもやや遅れてやって来た世代の人物。ブラウワーの直観主義の影響も受けているらしいのだが、もちろんそのまま継承しているわけではないようで、その直観論がどのようなものだったのか気になるところでもある。まず同書の第一章にあたる中村大介「一つの哲学的生成ーーブランシュヴィックからカヴァイエスへ」では、カヴァイエスの数学的エピステモロジーの基本として、数学の展開(多数の方法や操作のうちどれを拡張すれば問題が解けるか)は予見不可能ながら、その拡張すべき方法を捉えるところに、数学的直観が働くとされることが記されている。そうした展開には三つのプロセスがあるとされ(理念化、形式化、主題化)、いずれのプロセスも本質は概念を創り出すことにあるのだという。それは数学以外に依存しないという意味で、自律的であるとも言われる。こうした一連の考え方の下支えとなっているのが、スピノザが言うところの「思惟内容の必然性」なのだという。スピノザ的な主体と客体とがどこか混成的であるかのような論理が、カヴァイエスにあってはある意味刷新されているということか。
スピノザの後世への影響についての諸論文を集めたものだろう、という軽い気持ちで手にとった論集『主体の論理・概念の倫理 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義』(上野修、米虫正巳、近藤和敬編、以文社、2017)。読み始めてみると、どんどん別世界のほうに引き込まれるかのようで、なんとも心地よいドライヴ感(笑)。冒頭はいきなり数学者ジャン・カヴァイエスが主役級の扱い。カヴァイエス(1903 – 44)は先のブラウワーよりもやや遅れてやって来た世代の人物。ブラウワーの直観主義の影響も受けているらしいのだが、もちろんそのまま継承しているわけではないようで、その直観論がどのようなものだったのか気になるところでもある。まず同書の第一章にあたる中村大介「一つの哲学的生成ーーブランシュヴィックからカヴァイエスへ」では、カヴァイエスの数学的エピステモロジーの基本として、数学の展開(多数の方法や操作のうちどれを拡張すれば問題が解けるか)は予見不可能ながら、その拡張すべき方法を捉えるところに、数学的直観が働くとされることが記されている。そうした展開には三つのプロセスがあるとされ(理念化、形式化、主題化)、いずれのプロセスも本質は概念を創り出すことにあるのだという。それは数学以外に依存しないという意味で、自律的であるとも言われる。こうした一連の考え方の下支えとなっているのが、スピノザが言うところの「思惟内容の必然性」なのだという。スピノザ的な主体と客体とがどこか混成的であるかのような論理が、カヴァイエスにあってはある意味刷新されているということか。
第二章にあたるウーリア・ベニス=シナスール「ジャン・カヴァイエスーー概念の哲学 その下部構造の諸要素」(近藤和敬訳)では、カヴァイエスが直観主義に賛同していたことが示されている。数学的理性にはある論理が備わっていて、それが厳密な形式主義を乗り越える、とカヴァイエスは考えていた、と。しかしながらそこでの直観は「主観性から切り離」されていて(論文著者によれば、これは哲学的な意味での革命的観念だとされる)、結果的にカントやフッサール、ブラウワーからも遠ざかっているのだという。「直観は対象の性質なのであって、主体の能力ではない」というのだ。概念は対象本来の自己だとされる。主体はいわば後景へと引っ込み、対象がもつ内容の運動を構築するだけのものとなる。そんなわけでカヴァイエスは、概念が現実的過程であるとするヘーゲルに近いというのだが、一方では、対象の主体化や実体の意識化をも斥け、対象そのものが主体とのつながりから独立して考察されるという点で、カヴァイエスはヘーゲルに対しても距離を置くのだという。そこで援用されるのはスピノザ的な「観念:なのではないか、というのがどうやらこの論考の肝の部分らしい。そのあたりの吟味はすぐにはできないし、多少とも読み込みにくい論考ではあるけれど、カヴァイエスが唱えるのは、結果的にヘーゲルよりもさらに厳格な客観主義なのだというあたり、とても惹かれるものがあるのも確か。
 ずいぶん間が開いてしまったが、アンソロジー『数学の哲学』からデトレフセン「ブラウワーの直観主義」を眺めてみる。まずブラウワーの場合、推論(inference)の考え方が当時としては斬新だったようだ。それによると命題の真理が論証されるには、それが「経験」の対象になっていなければならないとされ、翻って論証における論理的推論の役割は著しく制限されることになる。いきおい、ブラウワーの数学的直観主義は、意味論というよりも基本的に認識論(エピステモロジー)的なものとなる。直観主義においては、数学の命題を論理的に操作できることが、それらの命題を(派生命題も含めて)知ることにはならないというのが基本(ポアンカレ)で、数学的知識と論理学的知識とが異なるものとして扱われるのだが、ブラウワーの場合には、それがなんらかの「経験」にもとづいていることが区別の鍵となっているらしい。たとえば命題pの知識を類推的に命題qに拡張する場合、推論は形式的なだけではダメで、その推論に命題pを成立させている条件についての知識が保持されていなければならない。それこそが実践的な操作をなすのであって、ゆえに単なる論理的操作とは異なるのだ、とされる。ブラウワーにおいては(古典的な認識論におけるような)推論そのものの正当化の重視以上に、認識の様態の保持が重視されるという次第だ。
ずいぶん間が開いてしまったが、アンソロジー『数学の哲学』からデトレフセン「ブラウワーの直観主義」を眺めてみる。まずブラウワーの場合、推論(inference)の考え方が当時としては斬新だったようだ。それによると命題の真理が論証されるには、それが「経験」の対象になっていなければならないとされ、翻って論証における論理的推論の役割は著しく制限されることになる。いきおい、ブラウワーの数学的直観主義は、意味論というよりも基本的に認識論(エピステモロジー)的なものとなる。直観主義においては、数学の命題を論理的に操作できることが、それらの命題を(派生命題も含めて)知ることにはならないというのが基本(ポアンカレ)で、数学的知識と論理学的知識とが異なるものとして扱われるのだが、ブラウワーの場合には、それがなんらかの「経験」にもとづいていることが区別の鍵となっているらしい。たとえば命題pの知識を類推的に命題qに拡張する場合、推論は形式的なだけではダメで、その推論に命題pを成立させている条件についての知識が保持されていなければならない。それこそが実践的な操作をなすのであって、ゆえに単なる論理的操作とは異なるのだ、とされる。ブラウワーにおいては(古典的な認識論におけるような)推論そのものの正当化の重視以上に、認識の様態の保持が重視されるという次第だ。
直観主義は総じて構成主義的であり、数学的知識というものは基本的に構築・構成という活動(心的活動)の一形態であるとされるわけだけれど、ブラウワーの場合はこのように、論理的推論だけでそれは拡張できず、内容を伴ってそういう活動そのものが拡張されるのではなくてはならないと考える。Aという構築された命題と、Bという構築された命題があったとき、推論的連結だけでは、AかつBという命題は構築されない。そこには形式的推論を越えた何かが必要になる。それが「経験」で示される構築の枠組みの連続性・一貫性ということになるようなのだが、著者のデトレフセンによれば、その後の直観主義はそうした構築過程の形式化(ハイティング)を通じて、形式的推論を大幅に認める立場へと移行したといい、上の「AかつB」の命題構築が導かれる過程についても、「シンタクス」的な連結をもってよしとするようになり、ブラウワー的な議論からは大きく逸れてしまっているようだ。ただこのテキストからは、ブラウワーの言う「経験」の内実という部分がもう一つはっきりしないようにも思われる。そのあたりを求めて、この探索はさらに続くことになりそうだ……。
 空き時間を利用して、『現代思想2018年1月号 特集=現代思想の総展望2018』(青土社、2017)を一通り眺めてみた。ハーマンやガブリエルなどの新しい実在論はそれぞれの著書の一部分のまとめなので、とりたてて新しい感じはしないが、オブジェクト指向存在論を詩作に結びつけた文芸潮流(オブジェクト指向詩)があるという話(ゴルィンコ=ヴォルフソン)などは少し面白い。また、急進左派系の加速主義(スルニチェク&ウィリアムズ)というのにも、ある意味とんがったトピックとして眼を惹くものもある。けれども、いずれにせよどこか脱人間的なコンテキストを強く匂わせていて、なにやら一種の逃避感(?)のようなものが浮かび上がってくるのは気のせいだろうか、と思ったりもする。
空き時間を利用して、『現代思想2018年1月号 特集=現代思想の総展望2018』(青土社、2017)を一通り眺めてみた。ハーマンやガブリエルなどの新しい実在論はそれぞれの著書の一部分のまとめなので、とりたてて新しい感じはしないが、オブジェクト指向存在論を詩作に結びつけた文芸潮流(オブジェクト指向詩)があるという話(ゴルィンコ=ヴォルフソン)などは少し面白い。また、急進左派系の加速主義(スルニチェク&ウィリアムズ)というのにも、ある意味とんがったトピックとして眼を惹くものもある。けれども、いずれにせよどこか脱人間的なコンテキストを強く匂わせていて、なにやら一種の逃避感(?)のようなものが浮かび上がってくるのは気のせいだろうか、と思ったりもする。
個人的にとくに面白かったのは、数学に絡んだ二つの論考。一つは中沢新一「レンマ的算術の基礎」。映画『メッセージ』の原作『あなたの人生の物語』をもとに、全体思考を一挙に行うという非線形的・非因果律的を人間から「取り出す」ことは可能かと問い(それを著者はレンマ的知性と称している)、また厳密な学は算術で基礎付けられなくてはならないとして、レンマ的算術なるものを考察している。けれども(やはりというべきか)ここからは仏教思想に範を取った話になっていき、直観的認識でしか捉えられないようなもの、虚数であったり、実無限であったりするものが引き合いに出されて、通常の論理的思考とは別様の数学が示唆される。その数学的構造というのは、超実数(hyperreal number)の構造にほかならない……と。数というのは「生成される一つ一つがすぐ前のものから定義されていくという、正の整数の無限列の逐次的な創造」とされるものの、通常はいったん生成した数が前の数との関係を失ってしまう。それに対して「縁起的思考による数論」では、生成された数は他の数とのつながり(縁(!)によるつながりとされる)を絶たないとされる。そうした数の計算(行列としての計算となる)、とくに積の問題から、交換法則が成り立たない空間が導かれるとされる。仏教思想との絡みはともかく、数論的な部分自体はとても興味を惹く。個人的にももう少しちゃんと押さえておきたいところだ。
一方、ルーベン・ハーシュ「書評 アラン・バディウ『数と数たち』」は、バディウが超現実数(こちらはsuperreal number)(こちらにその導入的な記述があってわかりやすい)からインスパイアされ、それを形而上学的な水準にまで、つまりは存在論の基礎にまで上昇させた点を問題として取り上げている。もともと構成的・ボトムアップ的に実数などを得るための操作的概念だった超現実数は、バディウにおいては多様性(それが存在の実例だという)をもたらす大元の基盤と見なされ、超現実数と順序数によって多様性が記述しつくされるという主張にまでいたるというのだ。著者ハーシュはこれに、順序数の構成を強制するものがないこと、さらに数体系はいかなるものであれ、存在やリアリティをモデル化したり記述したりするには不十分だということを反論としてあげている。リアリティ(現実)を整列集合に一次元的に還元することは単純化しすぎだというわけで、著者は現実の状況というのは多次元的、さらには無次元的でさえあると指摘している。上で述べた、個人的に感じるどこかしら逃避感のようなものとは、もしかするとそうした一種過剰な還元と、それによってかえって現実から位相的な遠ざってしまうことについて覚えるものなのかもしれない。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 なんでこんな話をしているかというと、次の本を読んでいるところだから。シャロン・バーチュ・マグレイン『異端の統計学 ベイズ (草思社文庫 マ 3-1)』(冨永星訳、草思社、2018)。まだ冒頭150ページ弱の第一部を見ただけだけれど、これがなかなか面白くて引き込まれる。トーマス・ベイズが1740年代に発見し、その後ラプラスが精緻化したというこのトライ&エラー型の確率論(「事後確率は事前確率と尤度の積に比例する」という定理)の盛衰を、時代に沿って順に詳述していくというもので、ノンフィクションの群像劇的な面白さを味わうことができる。盛衰というが、第一部に関しては、その悲劇的ともいえる毀損の数々が描かれていく。主要登場人物で著名な数学者だったラプラスの存在にもかかわらず、ベイズ推定はおもにその主観的な推測と、初期設定となる等確率の無根拠さによって散々な攻撃に曝され、文字通り粉砕されてしまう。けれどもその理論の発想は、一部の人々、とくに他領域の研究者らによって徴用・温存されて、やがて日の目を見ていくことになる……と、なかなか情感に訴えるストーリー展開が待っていることは予想がつくが、いずれにしてもこれは実に骨太のサイエンスライティング。
なんでこんな話をしているかというと、次の本を読んでいるところだから。シャロン・バーチュ・マグレイン『異端の統計学 ベイズ (草思社文庫 マ 3-1)』(冨永星訳、草思社、2018)。まだ冒頭150ページ弱の第一部を見ただけだけれど、これがなかなか面白くて引き込まれる。トーマス・ベイズが1740年代に発見し、その後ラプラスが精緻化したというこのトライ&エラー型の確率論(「事後確率は事前確率と尤度の積に比例する」という定理)の盛衰を、時代に沿って順に詳述していくというもので、ノンフィクションの群像劇的な面白さを味わうことができる。盛衰というが、第一部に関しては、その悲劇的ともいえる毀損の数々が描かれていく。主要登場人物で著名な数学者だったラプラスの存在にもかかわらず、ベイズ推定はおもにその主観的な推測と、初期設定となる等確率の無根拠さによって散々な攻撃に曝され、文字通り粉砕されてしまう。けれどもその理論の発想は、一部の人々、とくに他領域の研究者らによって徴用・温存されて、やがて日の目を見ていくことになる……と、なかなか情感に訴えるストーリー展開が待っていることは予想がつくが、いずれにしてもこれは実に骨太のサイエンスライティング。