またもE. ファルクの『神、肉体、他者』 からのメモ。ほとんど末尾の方だけれど、第8章はトマスによる天使論(とりわけ『神学大全』の議論)。「天使」の認識その他の問題を取り上げ、フッサールの『デカルト的省察』に絡めて現象学的に見直すという趣旨。トマスが展開する議論がまさしく形を変えた現象学として読めることを示しているわけで、これがなかなか面白い(主眼は「他者」とのコムニオンがどう織りなされるかを探っていくということなのだけれど……)。質料をもたないとされる天使は、一方で知性的存在とされるわけだけれど、トマスはそこで「では天使の認識とは一体どういうものなのか」と問うことになる。それはまさにデカルト以前のデカルト的「我」のようなものということになる。けれどもそこでトマスは「では天使は他の天使をどう認識するか」と問い、そこから間主観性(フッサール)ならぬ「間天使論」が導かれ、独我論を脱するのだという。さらに天使は質料をもたないといいながら聖書では人々の前に姿を現すとされる。トマスはこの「現れ」をも問い直し、まさに天使についての現象学のようなものを展開するという。存在論を宙吊りにした「現れ」だけに特化した身体性……。
Tiziana Suarez-nani, “Connaissance et langage des anges”, Vrin, 2002
(Lamberz版:21、Creuzer & Moser版:22)
Τὰ πάθη περὶ τοῦτο [πάντα], περὶ ὃ καὶ ἡ φθορὰ· ὁδὸς γὰρ ἐστιν εἰς φθορὰν ἡ παραδοχὴ τοῦ πάθους, καὶ τούτου τὸ φθείρεσθαι, οὗ καὶ τὸ πάσχειν· φθείρεται δὲ οὐδὲν ἀσώματον, τινὰ δὲ αὐτῶν ἤ ἔστιν ἤ οὐκ ἔστιν, ὣστε πάσχειν οὐδὲν· τὸ γὰρ πάσχον οὐ τοιοῦτον εἶναι δεῖ, ἀλλ᾿ οἷον ἀλλοιοῦσθαι καὶ φθείρεσθαι ταῖς ποιότησι τῶν ἐπεισιόντων καὶ τὸ πάσχειν ἐμποιούντων· τῷ γὰρ ἐνόντι ἀλλοίωσις <οὐ> παρὰ τοῦ τυχόντος· <τῷ γὰρ ἐνόντι θερμῷ ἡ ἀλλοίωσις παρὰ τοῦ ψύχοντος καὶ τῷ ἐνόντι ὑγρῷ ἡ ἀλλοίωσις παρά τοῦ ξηραίνοντος, καὶ ἠλλοιῶσθαι λέγομεν τὸ ὑποκείμενον, ὅταν ἐκ θερμοῦ ψυχρὸν ἤ ἐκ ξηροῦ ὑγρὸν γένηται>.
(外部からの何らかの)被りは、[すべからく]消滅もまた属するところに属する。というのも、被りの受け入れは消滅へといたる道であり、被ることがあるところに滅することもあるからだ。一方、非物体は滅することがない。そのうちのあるものは存在し、あるものは存在せず、そのためなんら被ることはまったくない。というのも、ひとたび被ったものは同じではいられず、介入して被りを導き入れる性質によって変化・消滅するものとしてあらねばならないからだ。内的な変化は、偶然のもとで生じる<のではない>からである。<内的な熱における変化は冷いもののもとで生じ、内的な湿度の変化は乾いたもののもとで生じる。熱いものから冷たいものが生じたり、乾いたものから湿ったものが生じるとき、われわれは基体が変化したと言うのである>。
ὥστε οὔτε ἡ ὕλη πάσχει – ἄποιος γὰρ καθ᾿ ἑαυτήν – οὔτε τὰ ἐπ᾿ αὐτῆς εἴδη εἱσιόντα και ἐξιόντα, ἀλλὰ τὸ πάθος περὶ τὸ συναμφότερον καὶ ᾧ τὸ εἶναι ἐν τῷ συναμφότερον· τουτὶ γὰρ ἐν ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσι καὶ ποιότησι τῶν ἐπεισιόντων θεωρεῖται. διὸ καὶ οἷς τὸ ζῆν ἔξωθεν καὶ οὐ παρ᾿ ἑαυτῶν, ταῦτα τὸ ζῆν καὶ τὸ μὴ ζῆν παθεῖν οἷά τε· οἷς δὲ τὸ εἶναι ἐν ζωῇ ἀπαθεῖ, κατὰ ζωὴν μένειν ἀνάγκη, ὥσπερ τῇ ἀζωίᾳ τὸ μὴ παθεῖν καθ᾿ ὅσον ἀζωία. ὡς οὐν τὸ τρέπεσθαι καὶ πάσχειν ἐν τῷ συνθέτῳ τῷ ἐξ ὕλης τε καὶ εἴδους, ὅπερ ἦν τὸ σώμα – οὐ μὴν τῇ ὕλῃ τοῦτο προσῆν – οὕτω καὶ τὸ ζῆν καὶ ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν κατὰ τοῦτο ἐν τῷ συνθέτῳ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος θεωρεῖται· οὐ μὴν [καὶ] τῇ ψυχῇ κατὰ τοῦτο συμβαίνει· ὅτι οὐκ ἦν ἐξ ἀζωίας καὶ ζωῆς συγκείμενον πρᾶγμα, ἀλλὰ ζωὴ μόνον· καὶ τοῦτο ἦν τῷ Πλάτωνι τὸ ουσίαν εἶναι καὶ λόγον τῆς ψυχῆς τὸ αὐτοκίνητον.
したがって質料も被ることはないし–というのもそれ自身では性質をもたないからだ–、その内部に入ったり外部に出たりする形相も被ることはない。しかしながら被りは複合物に関与し、複合物において存在するものに生じる。なぜならそれは、介入するものに反する潜在力や性質に見出されるからである。おのれ自身のもとではなく外部から生命をもたらされるものは、かかる生命もしくは非生命を被ることができる。被ることなく生命のうちに存在するものは、必然的に生命のもとにあり続け、生命のないものは、生命がない限りにおいて、必然的に(生命を)被ることもない。変化や被りは質料と形相から成るもの、つまり物体に見られる–このことは明らかに質料には当てはまらない–が、同様に、生きること、死ぬこと、被ることは、魂と身体から成るものに見出される。確かにそれは魂そのものには生じない。なぜなら、それは非生命と生命から成る実体ではなく、生命のみから成る実体(プラグマ)であるからだ。このことはプラトンにとって、魂の本質(ウーシア)と定義はみずから動くことにあるということを意味していた。
ラ・フォル・ジュルネでファビオ・ビオンディらが弾いたテレマンの組曲「ドン・キホーテ」が気になって、どんな録音があるだろうかと思って探したら、なんとバーバラ・ヘンドリクスを支えていたドロットニングホルム・バロック・アンサンブルによる2001年の盤がiTunesに出ていた(こちら→
わぉ。この団体、個人的には知らなかったのだけれど、かなりのCDを出している老舗だったのね(71年の結成だとか)。なるほど、どうりで落ち着いた風情を感じさせる演奏だったわけだ(今さら言うか(笑))。このドン・キホーテ組曲もビオンディ的な激しさはないけれど、実にいい感じ。
また、ラ・フォル・ジュルネで聞きそびれたリュート奏者のエドゥアルド・エグエスも、会場に出ていたショップに新譜があったので購入。こちら→
一応の連休明け。連休中はさしあたり急ぎの仕事とかもなく、ラ・フォル・ジュルネに行った以外はちらちらと読んだりDVDとか見たり。そんなわけでとりあえず短評メモという感じで落ち穂拾いでもしておこう。
まず、石野はるみ『チョーサーの自然–四月の雨が降れば–』(松籟社、2009)
西山雄二編『哲学と大学』(未来社、2009)
ニーチェといえば、6月に出る次号でニヒリズム特集をやるらしい雑誌『大航海』 。3月に出ていたNo.70は「[現代芸術]徹底批判」という特集。現代美術、現代音楽などがバッサバッサとなぎ倒されている(笑)。ちょっと身も蓋もないか……。たとえば片山杜秀は無調音楽などは(調性音楽もそうだというが)キメの重要な音型がどこに現れているか判別できるのが鑑賞法の基本なのだけれど、もはや楽譜の分析をソフトウエアなどで一般向けにする以外に、一部の選民思想的リスナーを超えて鑑賞させる方法はないみたいなことを示唆している。で、きわめつけは編集長の三浦雅士と安芸光男の対談。特に三浦氏は現代芸術はことごとくカスのようだみたいなことをいい、若手作曲家が留学するIRCAM(ポンピドゥセンター横の現代音楽研究所みたいなところ)なんか単なる箔付け機関でしかなくて不毛だとにべもない。で、評価もなにも抜きに一律50万円出すというような企業メセナのあり方に、ニーチェ的なニヒリズムの問いを重ねているところがケッサク(「要するにニーチェは、『音楽や美術に対して一律五十万ずつ配給する以外に正しさはないということに、君は耐えられるか』と問うているわけですよ」(p.103))。うむ、次号のニヒリズム特集も期待していよう(笑)。
有楽町の東京国際フォーラムで5日までやっている「ラ・フォル・ジュルネ–熱狂の日音楽祭」。フォーマットに飽きたと言いつつ今年も出かけた。しかも二日連続(苦笑)。なにせ今年はテーマがバッハで、もの凄く濃いバロック音楽祭になっているもんだから、こちらも気合いを入れて出かけたというわけ。各日三公演づつを堪能。以下メモっておこう。
一日目、最初は来日中止になったサンフォニー・マラン・マレに代わる若手グループ「ラ・レヴーズ」。テオルボ奏者(バンジャマン・ペロー)が指揮をするというのが珍しい。技術はともかくどこかまだ「荒削りっぽくない?」みたいな、でも結構今後に期待できそうなグループ。曲目は変更があって、BWV1027(ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ1番)、BWV912(トッカータ・ニ長調)、ラインケンのパルティータ4番ニ短調。続く二つめの公演はリチェルカール・コンソート(フィリップ・ピエルロ指揮)によるBWV235ミサ曲ト短調、BWV243マニフィカト・ニ長調。ベルギーのグループ。最近の流れという感じだけれど、古楽系というのを感じさせないオーソドックスで重厚感のある演奏だ。もちろん宗教曲はこれくらいがいいのだけれど。それと対照的なのが、三つめのエウローパ・ガランテ。ファビオ・ビオンティ率いるこのグループはもうすぐ20周年になるそうで。一世を風靡した爆走系(失礼)だけれど、期待通り疾風のような圧倒的ヴィヴァルディ(シンフォニア・ト長調と、「ラ・ストラヴァガンツァ」から)。けれども単に爆走というわけでもなく、パーセルなど、このグループにかかると、なんだか緩急取り合わせて妙な色つやに彩られる(笑)。コレッリの合奏協奏曲作品6もそう。自在な音のさばき方はまさに名人芸。というわけで、これは名演でしょうね。アンコールはテレマンの組曲「ドン・キホーテ」から。これも見事な対比具合。このグループのテオルボ奏者はジャンジャコモ・ピナルディという人らしいのだけれど、これがやけにクリアな音を出していた(ほかのリュート属と違い、テオルボは爪で弾くのもアリなんだそうで、この人などはもろ爪でもって弦をバシバシ言わせている(苦笑))。
二日目はまずピエール・アンタイ指揮でル・コンセール・スピリチュエルによるバッハのコラール・カンタータ2曲(BWV178と93)から。うーん、午後のけだるいときにこの手のカンタータは禁物か。ついつい舟をこいでしまう(笑)。続いてバーバラ・ヘンドリクスほかのペルゴレージ「スターバト・マーテル」。伴奏はドロットニングホルム・バロック・アンサンブルというグループなのだけれど、メンバーなどの情報は不明(パンフに未記載……ってどういうことよ?)。ヘンドリクスはさすがに大物の貫禄というか、お手のものという感じの「スターバト・マーテル」。ものすごいビブラートのかけっぷりに、最初は個人的にちょっと引いた(笑)。でも全体としては迫力勝ち。さかんにブラヴォーが出ていた(えーと、本当はブラヴァですけどね)。締めとなったのはラ・ヴェネクシアーナ(クラウディオ・カヴィーナ指揮)によるブクステフーデ「われらがイエスの御体」。これもすばらしい。もともと隠れた名曲という感じで、生で演奏される機会というのはほとんどないと思う本作。個人的にも生演奏で聴くのは初めて。CDで聴くと結構反復部分などが耳に残ったり、半ば過ぎくらいには弛緩して聞き流すみたいになってしまうことも多いのだけれど(苦笑)、生演奏だとぐいぐい引き込まれるから不思議だ。というか、それくらいの演奏だったということかな。ラ・ヴェネクシアーナというと、モンテヴェルディもののCDくらいでしか知らなかったけれど、ブクステフーデもとても良い。これまた収穫。
明日は行かないので今年はこれで打ち止めだけれど、全体としてバロック系のスター奏者らがこれだけ一堂に会する機会というのはあまりないわけで、このイベントが今後も続くようなら、何年かに一度はバロックものでやってほしいところ。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
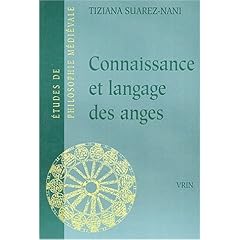 トマスによる天使の認識という面についてもっと長く検討しているものとして、ティシアナ・スアレス=ナニの『天使の認識と言語』(Tiziana Suarez-nani, “Connaissance et langage des anges”, Vrin, 2002)があるけれど、これも積ん読を解除して読み始める(笑)。この著者の前作では5人の神学者の天使論を大まかにまとめていたが、これはより範囲をせばめ、トマスと弟子筋のローマのジル(エギディウス・ロマヌス)に絞り、内容的にも認識と言語に特化したもののよう。トマスに関しては『神学大全』での天使論からとりわけ認識と言語に関する部分を詳細に検討しているようで、こちらも興味深い点があればメモしていきたいところ。
トマスによる天使の認識という面についてもっと長く検討しているものとして、ティシアナ・スアレス=ナニの『天使の認識と言語』(Tiziana Suarez-nani, “Connaissance et langage des anges”, Vrin, 2002)があるけれど、これも積ん読を解除して読み始める(笑)。この著者の前作では5人の神学者の天使論を大まかにまとめていたが、これはより範囲をせばめ、トマスと弟子筋のローマのジル(エギディウス・ロマヌス)に絞り、内容的にも認識と言語に特化したもののよう。トマスに関しては『神学大全』での天使論からとりわけ認識と言語に関する部分を詳細に検討しているようで、こちらも興味深い点があればメモしていきたいところ。