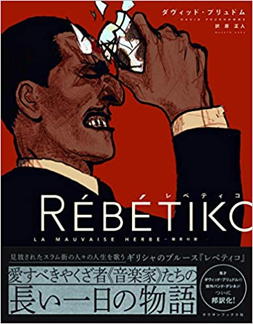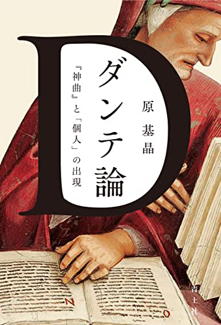見ることの禁忌/血の禁忌
まだ半分くらいですが、このところマリ=ジョゼ・モンザンの『まなざしの交換』(Le commerce des regards, Seuil, 2003)を読んでいます。モンザンは美学系の研究者で、宗教の問題からイメージ論を説き起こしているところが特徴的です。この著書でも、旧約と新約のイメージへのアプローチを、それぞれの聖書の記述から掘り下げて比較しています。なかなか面白いです。
https://amzn.to/3q7Vna1

第1章では、父親ノアの裸を見てしまったハムの逸話をテーマとして、イメージにとっての覆いの意味や、逸話に潜む近親相姦の禁忌、さらには血と汚れの近畿などを論じています。これを読むと、ホラー映画などでの流血がなぜに忌み嫌われるのかの一端が、そうした文化的な禁忌に根ざしているのかもしれない、と思ったりします。
第2章になると、キリスト教での転換点として、パウロの書簡などが検討され、不純から純粋さへの昇華の問題が扱われています。キーとなっているのは、死せる身体から犠牲の肉体へ、肉体から聖体としての教会への変容の問題です。ギリシア語のソーマからサルクスを介してラテン語のコルプスへ。意味論的に必ずしも重ならない言葉をつなぐべく、イメージはそれらの仲介役を担った、という次第なのですね。このあたりは、モンザンの主著『イメージ、イコン、エコノミー(救済体系)——現代イメージャリーのビザンツ起源』(1996)に詳しい話です。
モンザンの割と最近の著書が今年の始め、邦訳で出ています。『イメージは殺すことができるか』(澤田直、黒木秀房訳、法政大学出版局)。初の単著での邦訳ということです。状況に対して書かれた著書ではありますが、当然ながらモンザンの主要な主張がちりばめられています。たとえば次のような箇所ですね。
イメージは非類似性、つまり目に見えるものとまなざしの主体との隔たりのなかでのみ成立する(…)(p.24)
(…)媒介をコミュニケーション戦略や技術に矮小化する(中略)このような態度は、イメージの根本的な性質が非媒介性(中略)であること、媒介に対する原初的な抵抗であることを忘れている。(p.50)
https://amzn.to/3CHzXpj

プラトンの対話編で押しはこれ
数年ぶり、何度目かになりますが、プラトンの対話編から『ティマイオス』を再読しました。対話編からどれか1編押すとしたら、個人的にはやっぱり『ティマイオス』ですね。これ、対話編というかほとんどモノローグですが、読むたびにいろいろな発見もあって妙に刺激を受けます。今回はレクラム文庫のギリシア語版。
https://amzn.to/3q12YHq

なぜそんなに良いのかというと、一つには、そこに世界というものを全体として掌握したいという人間の性<さが>のようなものが見受けられるからでしょうか。書かれた当時の思想的伝統と、制限的な知識のなかで、ひたすら推論とイマジネーションを積み重ねて万物の移りゆきを説明しようとする、人間のひたむきさ、饒舌さ、放漫さ(ある意味での)などなど……。ああ、人間ってこういうものだな、昔から変わっていないのだな、という感慨。それはまた未来への希望でもあると思うのです。
そんなわけで、個人的におすすめの『ティマイオス』です。
虚軸となったスピノザ
積ん読から、岩波『思想』の2014年4月号を見ているところです。「スピノザというトラウマ」という特集で、上野修氏が中心となってスピノザ受容史の二つの大きなフェーズを検討しなおすという号になっています。
https://amzn.to/3hRsiey

二つのフェーズのうちの一つは、ドイツ観念論の隆盛期でのスピノザもしくはスピノザ主義の役割です。当時の思想界においては、スピノザの思想は忌避すべき対象(無神論的・決定論的)とされ、それと対立する形で観念論が定立された側面がある、ということのようです。なぜそれほどまでに忌み嫌われたのかとか、それはスピノザ本来の思想だったのかとか、あるいはカントなどの哲学は本当にそれを対立軸として成立していたのかとか、いろいろな面が問題含みで、とても刺激的なテーマになっているのですね。
もう一つのフェーズは、いわゆるドゥルーズなどフランスの1960年代ごろの思想です。そこではスピノザはむしろ好意的に受け入れられていたということなのですが、これも、同じように哲学史的には様々な問題点をはらんでいるようで、これもまたとても面白そうです。
愛すべきやさぐれ者たち
もはやバンド・デシネというより、まるで映画を観ているかのようです。この叙情性、展開、見せ場の数々……。そのすべてが見事に一本のストーリーを織りなし、やさぐれ歌手たちの寄る辺なさ、それでいて小粋な愛らしさを浮き彫りにしていきます。ダヴィッド・プリュドム『レベティコ——雑草の歌』(原正人訳、サウザンコミックス、2020)。
https://amzn.to/34kGBoN
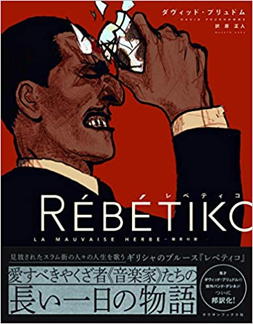
バンド・デシネの底力を味わわせてくれます。これは文句なしに傑作ですね。原書は2009年刊。よくぞ見事な翻訳で日本でも世に出てくれました。
新しいダンテ像
原基晶『ダンテ論——『神曲』と「個人」の出現』(青土社、2021)を読んでみました。既成のダンテ像を打ち崩す、なんとも痛快な論考です。
https://amzn.to/3gIfqH4
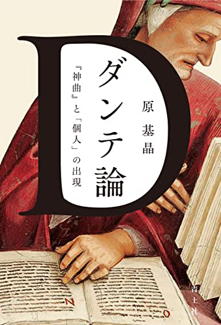
ダンテの出自、当時の政治状況、作中のダンテやベアトリーチェの位置づけ、ダンテとその諸作品の歴史的評価の移り変わり、日本での受容、『新生』『神曲』『帝政論』のそれぞれの再解釈など、内容は網羅的です。取り上げるテーマ1つ1つで、従来の解釈が退けられ、新しい視点が盛り込まれており、またそれをどこか醒めたような筆致が支えている、という感じです。
個人的には、やはり『帝政論』がらみの部分が一番面白く感じられました。全体的に、ダンテの執筆当時の社会的変化についての、著者の鋭い感性が底流になっている印象です。作品解釈の軸に予型論をもち出してくる、大御所アウエルバッハすらも俎上に乗っているのにはびっくりしました。著者によれば、そうではなく、封建制社会から商業活動中心の都市社会への時代的変化こそが、解釈の軸になるはずだ、というのですね。なかなか見事です。
ダンテとは直接関係はないのですが、最近文庫化された幻視SF、オラフ・ステープルドン『スター・メイカー』(浜口稔訳、ちくま文庫、2021)をちょうど読んでいるところで、なにやらこれが、ダンテの『新曲』と通底するような気もしていました。「ノリが似てる?」みたいな。『新曲』がなにがしかの作品のモデルのようになっているような部分も、当然あるのかもしれませんね。
https://amzn.to/3sFrPRE

δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ