この間取り上げた根津由喜夫『夢想のなかのビザンティウム – 中世西欧の「他者」認識』。2章に入ったところでいろいろ用事などがあったりして中断していたけれど、晴れて読書再開(笑)。この第2章は「シャルルマーニュ巡礼記」を取り上げている。著者によれば、これにはルイ7世の東方遠征の記録や、サン・ドニへの聖遺物の「由来記」が色濃く反映されているといい、そもそもの成立がそのサン・ドニ周辺だろいうということで、カペー朝との絡みなど、政治的な要素も読み込むことができるテキストということらしい。で、全体的な話は、東方にもっとすごい王がいると奥方に言われたシャルルマーニュが、その王を探す旅に出かけ、途中で聖地に立ち寄り(聖地が目的地でないのがすごい)聖遺物の数々を得て、それからコンスタンティノープルで「ユーグ」というそのすごい王に会い、ホラ話の実現(神の加護による)という試練を経て、そのユーグを超えた王となって帰国するという、立場逆転物語。この話の構成やモチーフなどの解釈が一番の読みどころ。ユーグの宮殿が風力で動いたり、黄金の犂を繰っていたりするディテールの解釈は、諸説の紹介と相まってとても面白い。そもそもなぜ「ユーグ」というフランス名なのか、という問題の解釈も興味深いし。著者は総括的に、ビザンツに対する西欧人のコンプレックスや、勇猛さでは勝っているという自負が随所に読み取れるとしているけれど、全体としてどちらかといえば口承的なテキストだけに(たぶん)、浮かび上がるのはむしろ民衆寄りの(?)、あくまで類型化されたビザンツのイメージのような気もするのだけれど……。うーん、個人的にももう少し考えてみよう。
「言葉の学」カテゴリーアーカイブ
ビュリダンの「推論」論
14世紀に活躍したジャン・ビュリダンとその周辺(先に挙げたザクセンのアルベルトとか)について、個人的に少し詳しく知りたいと思っている。どちらかといえば自然学方面での著作を検討したいわけなのだけれど、ビュリダンのもう一つの軸になっていると思われる論理学方面も見ないわけにはいかない……。ビュリダンの『ソフィスマータ(謬論)』の仏語訳(“Buridan – Sophismes”, trad. J. Biard, Vrin, 1993)の序文によると、ビュリダンの論理学は当然ながらその自然学の基盤をなしていて、無限、原因の種別、量、運動、真空など、いずれの問題についてもビュリダンはその言語的な解明、命題の分析、概念の意味の明確化をつねに念頭に置いているのだという。なるほどね。というわけで、まずはとっかかりとして、比較的短いテキスト『帰結論(推論論)』の校注版(Hubert Hubien, “Iohannis Buridani Tractatus de consequentiis”, Publicaitons Universitaires, Louvain, 1976)を読んでいるところ。まあ、推論の各種パターン(条件命題など)を整理・分類しているものなので、「むちゃくちゃ面白い」というわけにはいかないのだけれど(苦笑)、それでも三段論法(syllogismus)をきっちり推論の特殊形態として、かなり厳密に定義しているところなどは面白い。上の『ソフィスマータ』も同じようなスタンスの著書のようだけど、そちらもまた見ていかないと。
ストラスブールの誓約書
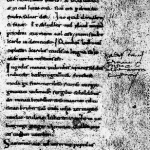 2月14日といえば世間的にはヴァレンタインデーだけれど、古仏語などをやっている人にとってはまた別の意味合いがある日かもしれない。つまり最古の文献「ストラスブールの誓約書」の日だ。842年の2月14日に、ルイ善良王の息子ルイとシャルルが、長兄のロテールを敵に回して立てた誓いで、ルイの側がロマン語(古仏語)で、シャルルの側がゲルマン語で記している(それぞれの領土はちょうど逆)。中身は「神の愛と、キリスト教の民と我々の民の共通の救いのため、この日より、神が知と力をわれに与える限り、兄弟がそうすべきであるよう、われは弟シャルルをあらゆる援助で支える。ただし、弟もわれを等しく支えることを条件とする。また、われはロタールとは、弟のシャルルに不利になると思われるようないかなる取り決めも行わない」というもの。ちょっと古い本だけれど、山田秀男『フランス語史』(駿河台出版、1994)から重訳(ちょっと正確さには欠けているかしら)。うーん、あえてラテン語ではなく二つの世俗語が併記されているというのがなんとも象徴的。そういえばベルギーの分裂状態はその後どうなっているのかしら……。また、古仏語研究の最先端とかはどうなっているのかも気になるところ。久々に研究動向とかアップグレードしたいところだなあ。
2月14日といえば世間的にはヴァレンタインデーだけれど、古仏語などをやっている人にとってはまた別の意味合いがある日かもしれない。つまり最古の文献「ストラスブールの誓約書」の日だ。842年の2月14日に、ルイ善良王の息子ルイとシャルルが、長兄のロテールを敵に回して立てた誓いで、ルイの側がロマン語(古仏語)で、シャルルの側がゲルマン語で記している(それぞれの領土はちょうど逆)。中身は「神の愛と、キリスト教の民と我々の民の共通の救いのため、この日より、神が知と力をわれに与える限り、兄弟がそうすべきであるよう、われは弟シャルルをあらゆる援助で支える。ただし、弟もわれを等しく支えることを条件とする。また、われはロタールとは、弟のシャルルに不利になると思われるようないかなる取り決めも行わない」というもの。ちょっと古い本だけれど、山田秀男『フランス語史』(駿河台出版、1994)から重訳(ちょっと正確さには欠けているかしら)。うーん、あえてラテン語ではなく二つの世俗語が併記されているというのがなんとも象徴的。そういえばベルギーの分裂状態はその後どうなっているのかしら……。また、古仏語研究の最先端とかはどうなっているのかも気になるところ。久々に研究動向とかアップグレードしたいところだなあ。
……まったくの余談だが、せっかくヴァレンタインデーなので、世間の恋人たちには、Zガンダム(またその話か……ま、30周年だからな(笑))劇場版3作目のラストに流れる、Gaktの曲Love Letter
を捧げよう(今さらだが)。本編全体はともかく、このラストは悪くなかったし。
キマイラ問題
相変わらず読んでいるド・リベラの『虚無への参照–命題の理論』。分析哲学系・論理学系のターム(Sachverhalte(事態)、Truthmaker、tropesなど)の中世的考古学を展開するわけだけれど、当初、頭から読んでいかなかったせいか、なんだか今ひとつ議論に乗れないというか……。中身の議論もちょっといわゆる「スパゲッティコード」のような代物なので……。でも中盤を貫く中心的トピックをなすのは、中世で大きな問題だったとされる「キマイラ」の扱い。キマイラのような存在しないにもかかわらず言表で表せるものは、論理学的にどう扱えばよいのか、ということで、上のトゥルースメーカー(真をなす根拠)にも関わってくる問題。特に取り上げられているのが、14世紀のウッドハムのアダムが提唱したとされるsignificable complexe(複合的な意味可能体とか訳せるかしら?)という議論。これは真偽の判断の対象(つまり語の意味内容)というのは複合的なものであるとする立場で、判断の対象となるのは前提と結論からなる命題全体か、あるいは結論のみかという問題について、命題全体だとするウッドハムのアダムによって、初めて「意味内容」という概念が導入されたのだという。で、同時代のリミニのグレゴリオは、その枠組みを保持しながらも「神学的事情から」「結論のみ」の方へとシフトさせるらしいのだけれど、このあたりは議論もよく見えないし、当時の神学状況も絡んでなにやらとても煩雑(苦笑)。で、今度はそれをニコラ・オレームやジャン・ビュリダンなどが批判し、命題内の項は命題そのものの意味内容であって、命題自体が真偽の判断などを課すのではない、みたいな議論を展開するという。うーん、14世紀の論争はまたなかなかに複雑そうだ(笑)。
翻訳論の今
 ミカエル・ウスティノフ『翻訳–その歴史・理論・展望』(服部雄一郎訳、白水社文庫クセジュ)(画像)を読む。これはまたコンパクトな翻訳論入門書。よくぞまとめてくれました、という感じでもある。起点言語から目標言語への変換みたいなことを述べるのにわざわざ「TS→TC」とかって無意味に記号を使うのは、一時期の言語論みたいでゲンナリするけれど、ま、最小限なのでよしとしよう(笑)。基本的に技法重視の理想論でもなく、アウトプットの現状について実証的に捉えようとする立場はなかなか新鮮。というか、本来そういう論がきちんと出なくてはねえ(笑)。とくに通訳と翻訳の対比を考える第5章などは実例も含めて興味深い(学生とプロ通訳の差とか)。同じように第4章「翻訳の作用」も、たとえば仏語と英語の表現的特徴の差などを指摘していて好ましい(そういう部分って、誰もがなんとなく感じていても、なかなか明示されないし、逆に安易に定式化されるとひどくつまんなくなってしまうからねえ)。
ミカエル・ウスティノフ『翻訳–その歴史・理論・展望』(服部雄一郎訳、白水社文庫クセジュ)(画像)を読む。これはまたコンパクトな翻訳論入門書。よくぞまとめてくれました、という感じでもある。起点言語から目標言語への変換みたいなことを述べるのにわざわざ「TS→TC」とかって無意味に記号を使うのは、一時期の言語論みたいでゲンナリするけれど、ま、最小限なのでよしとしよう(笑)。基本的に技法重視の理想論でもなく、アウトプットの現状について実証的に捉えようとする立場はなかなか新鮮。というか、本来そういう論がきちんと出なくてはねえ(笑)。とくに通訳と翻訳の対比を考える第5章などは実例も含めて興味深い(学生とプロ通訳の差とか)。同じように第4章「翻訳の作用」も、たとえば仏語と英語の表現的特徴の差などを指摘していて好ましい(そういう部分って、誰もがなんとなく感じていても、なかなか明示されないし、逆に安易に定式化されるとひどくつまんなくなってしまうからねえ)。
翻訳論の歴史を、逐語訳を批判したとされるキケロや聖ヒエロニムスから説き始めているのもなかなかよいのだけれど(そのあたりのもとのテキストを読んでみたくなった)、中世やルネサンスについてはかなりあっさり駆け抜けてしまうのが、相変わらずでちょっと脱力(苦笑)。そのあたりの豊かな翻訳の所作は、もっと吟味されてしかるべきでしょうにね。というわけで、そこいらがやはり空隙になっていそうだな、と。