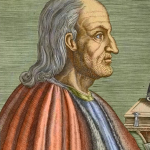
「情念・倫理学・主意主義」カテゴリーアーカイブ
ビュリダンの認識論を復習する
学知論・認識論がらみで、久々にビュリダンについての論考を読んでみた。クリストフ・グルヤール「誤信はいかにして可能か:ジャン・ビュリダン、初老女性、および誤謬の心理学」(Christophe Grellard, How Is it Possible to Believe Falsely? John Buridan, the Vetula, and the Psychology of Error, Uncertain Knowledge: Scepticism, Relativism and Doubt in the Middle Ages, ed. D. G. Denery and al, Brepols, 2014)というもの。収録されている論集そのものも面白そうだが、とりあえずオンライン公開されているこの一論考を見てみた。ビュリダンの学知論・認識論において、とりわけ誤謬がどう生じるかについての議論を取り上げてまとめているもの。ビュリダンの場合、認識論の基本的な図式はオッカムなどが示すものとそれほど違う印象は受けないのだけれど、同論考によれば、とりわけ重視されるのが、感覚器官を通じて心的に処理される対象の像を知性が「それと認める」プロセス。いわば概念的な「判断」(悟性的な)の介在だ。オッカムよりもその判断プロセスが強調される点にビュリダンの特徴が表れているということらしい。で、これは最初の意志の介在プロセスでもあり、ここに誤りの可能性も生じてくるとされる。たとえば教育、習慣(ハビトゥス)などの影響で、学知の受け入れ拒否が生じたりする、という具合だ。論考では、ビュリダンが「初老の女性」を例にそうした誤信について説明している文章を取り上げている。初老の女性が例とされるのは、ビュリダンの説教などの実践から、信じ込みやすい人々として性格づけられているからのようだ(もちろん、中世に特有の蔑視がなかったわけでもないだろうけれど)。そこからビュリダンは推測する。認識機能自体が自然にもつ「真理へと向かう性向」が、獲得された習慣(反復によって固着する)によっていかにして疎外されるか、あるいは意志によっていかにして非・自然的な形で妨げられるかが、そうした事例をもとに説明できるのだ、と。同論考で見る限り、ビュリダンはある意味、民族学・人類学を先取りするかのようでさえある。で、そうした人々が陥る誤信を、合理的説明にもとづいて払拭するのが学問に携わる者の職務の一つであると位置づけていたのだという。なるほど、そのあたりの使命感(?)も、あるいは説教の経験が大きくものを言っているのかもしれない。
アウグスティヌスの意志論再び
 アウグスティヌスがらみで気になっていた一冊を見てみた。アラン・ド・リベラ編『形而上学の後に−−アウグスティヌス?』(Après La Métaphysique: Augustin? (Publications De L’institut D’études Médiévales De L’institut Catholique De Paris), éd. Alain de Libera, Vrin, 2013)という論集。アウグスティヌスが通常の形而上学的な枠組みに収まりきらない、その収まりきらなさを取り上げようという趣旨の論考が居並ぶ小著。リベラは巻頭でアウグスティヌスにおける主体の不在の問題を取り上げ、続くジャン=リュック・ナンシーは、信仰と思考との対立軸の乗り越えの可能性をアウグスティヌスに見るなどなど……。けれども個人的な目下の関心からすると、一番の注目はやはりオリヴィエ・ブールノアによるアウグスティヌスの意志についての論考。「アウグスティヌス:弱さと意志」(Olivier Boulnois, Augustin, La Faiblesse et la Volonté, pp.51-77)というそれは、善を指向しつつ悪を行ってしまうという人間の性<さが>、すなわち意志の弱さというテーマを通して、アウグスティヌスの意志論の全体像をまとめようというもので、とても参考になる一篇だ。
アウグスティヌスがらみで気になっていた一冊を見てみた。アラン・ド・リベラ編『形而上学の後に−−アウグスティヌス?』(Après La Métaphysique: Augustin? (Publications De L’institut D’études Médiévales De L’institut Catholique De Paris), éd. Alain de Libera, Vrin, 2013)という論集。アウグスティヌスが通常の形而上学的な枠組みに収まりきらない、その収まりきらなさを取り上げようという趣旨の論考が居並ぶ小著。リベラは巻頭でアウグスティヌスにおける主体の不在の問題を取り上げ、続くジャン=リュック・ナンシーは、信仰と思考との対立軸の乗り越えの可能性をアウグスティヌスに見るなどなど……。けれども個人的な目下の関心からすると、一番の注目はやはりオリヴィエ・ブールノアによるアウグスティヌスの意志についての論考。「アウグスティヌス:弱さと意志」(Olivier Boulnois, Augustin, La Faiblesse et la Volonté, pp.51-77)というそれは、善を指向しつつ悪を行ってしまうという人間の性<さが>、すなわち意志の弱さというテーマを通して、アウグスティヌスの意志論の全体像をまとめようというもので、とても参考になる一篇だ。
ブールノアによれば、たとえばアリストテレスの意志論では、欲望による駆動と逸脱が問題になるのだけれど、それに対しアウグスティヌスにおいては、自由意志は自律的だとされ、それは善に向かうという性向を備えているものの、(原罪による)人間の不完全性ゆえに必ずしも善を実現するとは限らない。その意志は選択的な自由を与えられてはいても、それが善を選ぶときにこそ真に自由であるとされ、善悪の選択は事実上なく、ただ善への意志があるのみだとされる。自由意志と言うときの「自由」は、善への意志という意味において、名詞での「自由」とは意味が異なるのだという。ところがここに、習慣(ハビトゥス)が立ちふさがる。習慣とはいわば固着化のことであり、人間が身体的な快楽などを求めるなど、自由意志からすれば避けるべき事柄の数々が、そうした固着化としてある。固着化した力は並大抵ではない。人間の自由意志は、選択という面から見れば大きな非対称になっているし、習慣の強固さという面から見ても逆方向での大きな非対称になっている。アウグスティヌスは確かに悪の選択を、元来の自由の欠落(選択ゆえの)と見なしているが、人間のすべての行動にはそうした「弱さ」が刻まれている、とされる。その根源的な悪への傾斜は、もともとのアダムの「意志」による選択の結果でもあった。原罪にまで遡るといわれる人間の意志の弱さは、やはり人間の意志に依存しているのであり、ゆえに人間の責任に帰されるしかない……。
かように引き裂かれた状態の解消のためには、神の恩寵の介在が必要とされる……というのが一応の筋書きなのだけれど(ペラギウス派への反論として)、しかしながらその恩寵は「万能の切り札」なのではない。解消にいたるには人間の側からの鍛錬もまた求められるのだ。その点にこそ、アウグスティヌスが単に神学の問題としてのみ意志論を扱うようなことをせず、哲学的的議論をも援用していることの意味がある、とブールノアは指摘する。なるほど、アウグスティヌスの意志論が、倫理的性向と固着化した習慣との分裂という、深いところに設定された不均衡の問題として掲げられているという見立ては、単なる欲望の力学などよりもはるかに重層的で異義深いものかもしれない、と思わせずにはいない。
自由意志論−−古代と近世での断絶?
 またまた中間報告だけれど、大西克智『意志と自由―一つの系譜学 アウグスティヌス‐モリナ&スアレス‐デカルト』(知泉書館、2014)を読み始めた。まだ全体の三分の一、アウグスティヌスを扱った第一章から第二章冒頭にかけての箇所まで。全体としては「自由意志論の思想史」といった内容で、自由意志論に大きく外挿的思考と内在的思考との二つの流れを見出し、それらを思想史的な議論を踏まえつつ考察するというもののようで、すでにしてとても面白い。序章の見取り図によれば、前者は自由意志の在りようを外部からの非決定に委ねて考察するという立場のようで、代表的なものとして近世のイエズス会系(同書ではジェズイットと表記される)の自由意志論がそれにあたるとされる。後者はそうした外部によるのではない、意志そのものが内的に自律し自由に判断できるという議論を言うようで、近世ではデカルトがその代表格とされている。また、これらに被さるかのように、意志について個人がもつ実感と、そこから離れた(哲学的)概念形成という対立軸も浮かび上がり、実感寄りがジェズイット、実感との乖離論がデカルトと重ね合わされている。この対立軸は(同書が目標とする)哲学史研究と哲学的営為そのものとの接合を果たす上で重要な軸線にもなっていくようだ。
またまた中間報告だけれど、大西克智『意志と自由―一つの系譜学 アウグスティヌス‐モリナ&スアレス‐デカルト』(知泉書館、2014)を読み始めた。まだ全体の三分の一、アウグスティヌスを扱った第一章から第二章冒頭にかけての箇所まで。全体としては「自由意志論の思想史」といった内容で、自由意志論に大きく外挿的思考と内在的思考との二つの流れを見出し、それらを思想史的な議論を踏まえつつ考察するというもののようで、すでにしてとても面白い。序章の見取り図によれば、前者は自由意志の在りようを外部からの非決定に委ねて考察するという立場のようで、代表的なものとして近世のイエズス会系(同書ではジェズイットと表記される)の自由意志論がそれにあたるとされる。後者はそうした外部によるのではない、意志そのものが内的に自律し自由に判断できるという議論を言うようで、近世ではデカルトがその代表格とされている。また、これらに被さるかのように、意志について個人がもつ実感と、そこから離れた(哲学的)概念形成という対立軸も浮かび上がり、実感寄りがジェズイット、実感との乖離論がデカルトと重ね合わされている。この対立軸は(同書が目標とする)哲学史研究と哲学的営為そのものとの接合を果たす上で重要な軸線にもなっていくようだ。
こうしていよいよ本論へ。第一章では、上の内在的思考の流れを遡及するという観点からアウグスティヌスが中心に論じられる。アウグスティヌスにあっては、意志の自由は、たとえば善悪のいずれかを選ぶといった形では提起されない。悪は「欠損」ないしは無であると解釈されるので、悪を選ぶという選択肢がそもそも想定されていない。善をなす限りにおいて人間の意志は自由なのだとされるわけだ。けれども実際に人は悪をなしうる。その原因はどこにあるのか、意志のどこに悪が内包されているというのか……。これはアポリアだ。アウグスティヌスはこうして、有と無の中間体のような「冥さ」(と同書は称している)へと沈み込むのだというが、それはとりもなおさず、自由意志の自律性と神による先知との板挟みということでもある。アウグスティヌスはそこで一種の反転を見せ、意志と神的先知のいずれをもそっくりそのまま肯定するしかないとする(らしい)。純然たる肯定へ?それは、ストア派による運命と意志との肯定(あらゆるものに原因を見る決定論的なスタンスであるがゆえに、運命による決定と意志とに本質的な齟齬が生じることはないというスタンス)よりも高い強度と緊張を伴っている、とされる。対照的に、後のジェズイット(モリナに代表されている)、あるいはパスカルなどは、決定を被らない(非・被決定)ということを自由の説明原理として立てるが、それでもなお悪の原因が定まらないという事態を招く(非決定の自由の中でなぜ悪を選んだのかが問われないというわけだ)。ではデカルトはどうなのか……というところで近世を本格的に扱う次章以降へと話が進んでいくわけなのだけれど、それにしてもこのあたりのアウグスティヌス解釈、あるいはストア派についての解釈については、個人的にどこか違和感を覚える。その違和感の正体というか、それが具体的にどこの何の部分への違和感なのかは、すぐには答えられない感じだ(苦笑)。うーむ、なんとも歯がゆいのだけれど、要はそうした記述をこちらなりに検証し消化せよということか……。このあたりはまた、追って報告したい。また、それとは別に、非決定による自由論が確立されるには一六世紀のジェズイットを待たなくてはならない、といったあたりも実のところどうなのか、なんて疑問もあったりする。それは第二章以降……ということなのかしら?なるほど、第二章の冒頭部分では、先駆者としてロジャー・ベーコンやブルージュのヴァルターへの言及があるし、もう少し先でドゥンス・スコトゥスへのモリナの評価なども取り上げられているようだ。けれどもそれらの自由意志論は、置かれている力点が異なっていて、非・被決定性の徹底にはいたらない、として一蹴される運命にあるようなのだが……。
一四世紀の情念論
先に見た清水真木『感情とは何か』によると、デカルトまでの情念論は情念の分類に始終していたという話だった。しかしながら、多少とも実際のテキストから受ける印象は、「分類に始終」というのとは微妙にズレるような気がする。おそらくは「分類」の様態なり動機なりが独特なものだったからではないかと思うのだけれど、そのあたり、きちんと言語化するのは難しい。かつてのそれをどういう分類と位置づければいいのか……なんてことを念頭に置きつつ、さしあたり一四世紀の情念論を扱った論考を眺めておくことにした。ドミニク・ペルラー「感情と認識−−魂の情念に関する一四世紀の論説」(Dominik Perler, Emotions and Cognitions – Fourteenth-Century Discussions on the Passions of the Soul, Vivarium, vol. 43, No.2, 2005)というもの。必ずしも全体像が明確なわけではないオッカムとその後のヴォデハムによる情念論を、体系的に再構築しようという試みだ。
まずオッカムは、情念はあくまで感覚的な知覚によって生じるものと位置づけ、知性はそこにいっさい関与しないという立場を取る。直観的認識(知覚の場合)でも抽象的認識(記憶などの場合)でもいいが、対象を感覚が捉えることによってなにがしかの感情が直接的にせり上がる以上、知性(つまりは概念化)はそこに関係していない、と見るわけだ。つまりは対象が情念をもたらすのではなく、世界についての人間の感覚的認識が情念をもたらすのだということだ。情念は感覚に帰結するのであり、オッカムはそこに認識内容がなくともよいとすら考えているという。その一方でオッカムは、そうした感覚的認識に際して意志が介在することで、情念をある程度制御することもできると考えている。そしてまた、意志は人間の高次の行為をもたらすものであることから、意志がもたらす情念というものもある、と想定しているという。例として挙げられているのが(いかにも中世的なものだが)「享楽(fruitio)」についての議論。その最たるものは死後の離在的な魂が神を観想する際の至福とされるわけだが、その場合、感覚器官のない魂がどうやって享楽を得るのかが問われることになる。そこから、非感覚的な情念の構造や原因が議論されることにもなる。で、その場合でもオッカムは、享楽を「知性によって概念化された情念」と見なす当時の他の論者たちとは異なり、意志のみから生じる働きだとしているという。なかなか徹底している。けれどもその場合、それは厳密な知的作用とはどう違うのかといった問題が生じてくる。
オッカムが明確な回答を寄せていないそうした問題に、徹底的に拘ることになるのがヴォデハムだ。ヴォデハムは「意志的な情念」にまつわる構造を細かく検討してみせる。まず、享楽対象の最初の認識は、その対象による享楽とは異なるとし、その情念の生成に知的作用が必要であることを認める。知性は部分的な原因をなしているというのだ。けれども情念は認識とイコールではない。ヴォデハムは一種の折衷案を提示する。情念は、知性による認識と、意志そのものとの両方を原因とする、認識対象を伴った意志の状態だとされる。情念とはいわば事物のある種の概念化の方途であるというのだ。ただしそれは必ずしも判断を伴うものではない。一方でそれは必ずや理解を伴っている。こうして最終的に、ヴォデハムは認識を再分割し、感覚的認識、知的認識、さらに単に理解のみを伴う意志的認識、判断をも伴う意志的認識などを分けて考えることになる。オッカムの議論を補足するものとしてもともとは構想された、この高次の認識の分類ではあるけれど、その煩雑さにはリミニのグレゴリウスやアイイーのペトルスなどによって、オッカム的な批判が浴びせられたのだそうだ。主知主義か主意主義かという文脈において、ヴォデハムは知性寄りの譲歩を行うも、主意主義を保つために苦労して認識の分類を練り上げていることがわかる。でもそれならば、最初から知性が認識を一手に引き受けるとすればよいではないか、意志はただ情動的なものを付け加えるだけだとすればよいではないか(リミニのグレゴリウス)という話が出てくるのも頷ける。なるほど、オッカムがいくぶん単純に分割してみせるところに、ウォデハムはもっと曖昧で混沌としたものを見てとっているように見える。それをあえて明確化しようとして、細かい分割に行き着くしかなくなっているように……。