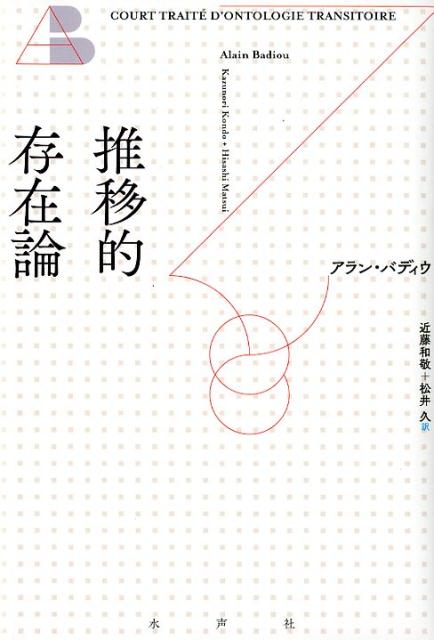『植物原因論』は第三巻まで読み進んだところでいったん休止中。その代わりというわけでもないのだけれど、同じテオフラストスから、『形而上学』(の抜粋とされるテキスト)を、いつものレ・ベル・レットル版の希仏対訳本(Théophraste, Métaphysique (Collection des Universités de France), trad. A. Laks et G. W. Most, Les Belles Lettres, 1993-2002)で見てみた。植物論のような具体的な事象に取り組んでいるわけではないが、当然ながらそのスタンスには通底する部分が多々ある。基本的には学問的な対象や方法論をめぐる考察なのだが、冒頭からすでにして、感覚的対象(自然学の対象)と知的対象(形而上学の対象)とがどう結びつくのか、一般が個物の原因、とりわけ後者の運動の原因であるのなら、なぜ個物は休止ではなく運動を求めようとするのか云々といった、難問の数々が提示される。
『植物原因論』は第三巻まで読み進んだところでいったん休止中。その代わりというわけでもないのだけれど、同じテオフラストスから、『形而上学』(の抜粋とされるテキスト)を、いつものレ・ベル・レットル版の希仏対訳本(Théophraste, Métaphysique (Collection des Universités de France), trad. A. Laks et G. W. Most, Les Belles Lettres, 1993-2002)で見てみた。植物論のような具体的な事象に取り組んでいるわけではないが、当然ながらそのスタンスには通底する部分が多々ある。基本的には学問的な対象や方法論をめぐる考察なのだが、冒頭からすでにして、感覚的対象(自然学の対象)と知的対象(形而上学の対象)とがどう結びつくのか、一般が個物の原因、とりわけ後者の運動の原因であるのなら、なぜ個物は休止ではなく運動を求めようとするのか云々といった、難問の数々が提示される。
そうした問いに、必ずしも答えが示されるわけでもない。総じてこれは、いくつもの差異から成るような多様な事象・現象を前にして、そこから共通項をどう導きだし、一般的な問題へとどう遡っていくか、どう接近していくかについて、ある種の困難を吐露した文章という印象だ。多様なものに理由を探ろうとすれば、いつしか理由そのものを見失い、知をも失いかねない。では、そうしたリスクがある以上、たとえば動物について探求する場合でも、生命そのものの考察に踏み込んではならないのだろうか、気象現象や天体の探求でも同様だろうか……。どこに制限を設ければよいのか。もちろん明確な答えはないが、このどこか震えるようなアポリアの感覚こそが、哲学的な問いかけの醍醐味であることを改めて感じさせもする。
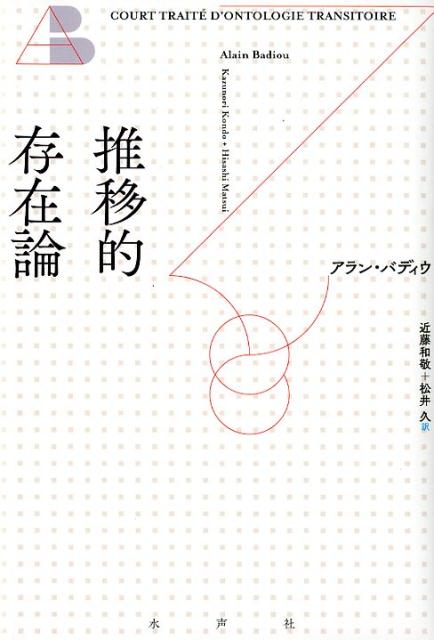 今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
このような立場を擁護すべく、同書では主要な哲学史上の議論の流れが再整理されることになる。その整理は、ある意味刺激的な読み直しをともないつつ、ドゥルーズ、スピノザなどをめぐりながら、少しずつ着実に進んでいく。中でもとりわけ刺激的なのは、プラトン思想やカント思想の「読み直し方」。前者においては、アリストテレスが「一」の論理に存在論を落とし込もうとする(記述を通じて)のに対し、プラトンは「多」の絶対的な決定不可能性のほうへと向かっていく、とされる。決定不可能性とは、たとえば認識主体と認識対象との区別になんの妥当性もないということだ。バディウは、思考が包蔵する存在と、思考が調整する運動との共外延性こそが、プラトンの言う「イデア」なのだと喝破してみせる。つまり思考の能力と思考の対象とは同じものであって分離できないということ。するとそれは多数性へと向かう契機こそを重視する立場を導き、選択公理(集合の生成力に制限を設けない)に好意的で、連続体仮説(限定を加えそうな)には慎重だということになる。
後者についても、たとえばカントの議論を、現象の側に純粋な多を、主体の側に「一として数えること」(統一)を置くように解釈してしまうのは誤りだとし、統一もまた、現象の多性の側の問題へと送り返していると読むべきだとしている。そのような統一をなす「統覚」の能力は、多の事象をたがいに結びつけるようなカテゴリーの体系とは別物で、むしろ連結の側から接近されるようなものなのだという。純粋な多がなんらかの状況に置かれて、「一として数えられる」ようになるのが実在するものだといい、一方の対象とは、連結(結びつきの錯覚)からのみ表象可能となったものだとされる。ここでもまた、統覚(主体)と対象とに、それらを表象可能にするような源・主体と源・対象があるならば、それらはいっさい現前することがなく、存在から引き離された「空」であるという意味において、不可分のものなのだとされる。
総じて、細やかで難解でありながらも、見かけ以上に価値転覆的な戦略を伴った議論という印象。消化しきれないところも多々あるし、これがどのような展開を遂げていくのかも気になるところではある。今回の翻訳は少し読みにくい印象もあるけれど、いずれにしてもバディウは少しこだわって見てみたい著者である。
 レ・ベル・レットル社から出ている擬アリストテレスのシリーズから、『世界について・風の位置と名前・植物について』(Pseudo-aristote, Du Monde: Positions et Dénominations des Vents; Des Plantes (La Roue à Livres), trad. Michel Federspiel et al., Les Belles Lettres, 2018)を見ている。このところの流れで、個人的な注目テキストはやはり『植物について』。この書はギリシア語原典が失われ、シリア語版が残り、そこからアラビア語版、ラテン語版、ギリシア語版などが派生しているもの。今回のテキストはラテン語版からの仏訳。アリストテレスの真正のテキストではないというのが一般的な見解で、おそらくは逍遙学派の誰かが著したのだろうという。同書の解説序文によれば、テオフラストスの植物論にも一部呼応しているという。
レ・ベル・レットル社から出ている擬アリストテレスのシリーズから、『世界について・風の位置と名前・植物について』(Pseudo-aristote, Du Monde: Positions et Dénominations des Vents; Des Plantes (La Roue à Livres), trad. Michel Federspiel et al., Les Belles Lettres, 2018)を見ている。このところの流れで、個人的な注目テキストはやはり『植物について』。この書はギリシア語原典が失われ、シリア語版が残り、そこからアラビア語版、ラテン語版、ギリシア語版などが派生しているもの。今回のテキストはラテン語版からの仏訳。アリストテレスの真正のテキストではないというのが一般的な見解で、おそらくは逍遙学派の誰かが著したのだろうという。同書の解説序文によれば、テオフラストスの植物論にも一部呼応しているという。
で、この擬アリストテレス『植物論』だが、解説序文でもまとめられているが、全体は第一書と第二書にわかれ、第一書はさらに前半と後半にわかれる。つまり全体で3つの部分から成り、最初が植物における感覚の有無の問題や存在論的位置づけなど、二つめの部分が植物の分類、三つめは環境などを含む植物の生成に関する議論、という感じになっている。このうち、とりわけ注目されるのは第一の部分。逍遙学派の立場では、植物には感覚などはなく、呼吸や睡眠もなく、きわめて静的な生命であるとされていて、こうした議論それ自体はさほど面白くないのだけれど、そこで示され反駁されている異論のドクソグラフィ的な言及には大いに興味がわく。とくに言及されているのはアナクサゴラスやエンペドクレスの説。両者は植物にも快不快などの感覚があると考えていたという。アナクサゴラスは、植物も呼吸をすると考えたようだし、エンペドクレスはまた、植物は雄雌が一体化していると説明していたらしい。ちなみにこの『植物論』の逸名著者は、その性別の一体化を認めると、植物を動物以上に完全な存在になってしまうとして、この説を斥けている。いずれにしても、アナクサゴラスやエンペドクレスのほうに、植物についての現代的な知見は再接近しているように思われる。
 今年の年越し本は、このところ普段あまり読んでいないフィクションものから円城塔『文字渦』(新潮社、2018)。文字、とくに漢字にまつわる短編集なのだけれど、これが良い意味で人を食ったような、外連味たっぷりの異色短編の連作になっている。古代中国とSF的な未来世界とを行きつ戻りつしながら、生命になぞらえた漢字たちの諸相が描かれるという寸法。どこか小気味よい、壮大な法螺話(失礼)。
今年の年越し本は、このところ普段あまり読んでいないフィクションものから円城塔『文字渦』(新潮社、2018)。文字、とくに漢字にまつわる短編集なのだけれど、これが良い意味で人を食ったような、外連味たっぷりの異色短編の連作になっている。古代中国とSF的な未来世界とを行きつ戻りつしながら、生命になぞらえた漢字たちの諸相が描かれるという寸法。どこか小気味よい、壮大な法螺話(失礼)。
作品全体を貫いているのは、その「文字と生きもの」のアナロジー的な重ね合わせ。これはなかなか興味深い問題系でもある。そのアナロジーはいつ頃からあるのか、どのようにして成立してきたのか、などなど。書画を見るときに、どこかゲシュタルト崩壊的な操作を意図的に適用して、描かれた字の止めや跳ねのダイナミズムを見るというのはよく言われることだけれど、漢字というものがそもそも本来的にそうしたダイナミズムを内に含んでいるものだと捉えるなら、そのまま書字は生命の躍動へと直接的に接合できるかもしれない……というあたりが、おそらくはそのアイデアの基幹になっているのだろう。したがってそれは決して新しいものではなさそうだ。ただ、それをなんらかの物語に落とし込むのはなかなか容易ではないように思われる。この作品では、古代中国の書字の成立史や、より現代的・未来的な情報処理の話などが複合的に絡み合い、かなり錯綜感のあるアウトプットになっている。書字を扱うフィクションだけに、音読できないような字や、意味すらも連想できないような字が出てくるのも当然か。ページの字面は漢字で黒っぽくなり(現代の出版の世界では結構嫌われる作りだが、反面それはとても贅沢と言えるかもしれない)、ときおり可読性の限界のようなところにまで突き進んでもいく……。というわけで、これは刺激的な仕掛けに満ちた、読み手に挑みかける巧妙なフィクション、というところ。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 『植物原因論』は第三巻まで読み進んだところでいったん休止中。その代わりというわけでもないのだけれど、同じテオフラストスから、『形而上学』(の抜粋とされるテキスト)を、いつものレ・ベル・レットル版の希仏対訳本(Théophraste, Métaphysique (Collection des Universités de France), trad. A. Laks et G. W. Most, Les Belles Lettres, 1993-2002)で見てみた。植物論のような具体的な事象に取り組んでいるわけではないが、当然ながらそのスタンスには通底する部分が多々ある。基本的には学問的な対象や方法論をめぐる考察なのだが、冒頭からすでにして、感覚的対象(自然学の対象)と知的対象(形而上学の対象)とがどう結びつくのか、一般が個物の原因、とりわけ後者の運動の原因であるのなら、なぜ個物は休止ではなく運動を求めようとするのか云々といった、難問の数々が提示される。
『植物原因論』は第三巻まで読み進んだところでいったん休止中。その代わりというわけでもないのだけれど、同じテオフラストスから、『形而上学』(の抜粋とされるテキスト)を、いつものレ・ベル・レットル版の希仏対訳本(Théophraste, Métaphysique (Collection des Universités de France), trad. A. Laks et G. W. Most, Les Belles Lettres, 1993-2002)で見てみた。植物論のような具体的な事象に取り組んでいるわけではないが、当然ながらそのスタンスには通底する部分が多々ある。基本的には学問的な対象や方法論をめぐる考察なのだが、冒頭からすでにして、感覚的対象(自然学の対象)と知的対象(形而上学の対象)とがどう結びつくのか、一般が個物の原因、とりわけ後者の運動の原因であるのなら、なぜ個物は休止ではなく運動を求めようとするのか云々といった、難問の数々が提示される。