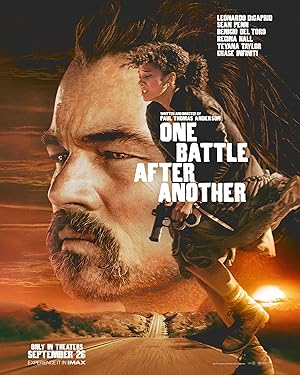以前『なぜフィクションか』(1999)が良かったジャン=マリー・シェフェール。同著書の10年前に刊行された『文学ジャンルとは何か』(”Qu’est-ce qu’un genre litteraire?”, Le Seuil, 1989)を読んでみました。
https://amzn.to/4qXJf84
前者が学際的なアプローチだったのに対し、後者はいわば剛直な文学論でした。まだ認知科学や心理学などへの言及もないのですが、文学作品の研究にコミュニケーションという観点を入れているところに、少し野心的な感じを受けたりもします。基本的に文学ジャンルをどう規定し、どう理解すべきかについて論じた本なのですが、「ジャンル」を導く論理というのは実に多彩で、簡単なものに還元できないのではないかという、ちょっと身も蓋もない結論を導いていて、個人的には思わず苦笑してしまいました。
でも、ちょっとおもしろかったのが、歴史的な文脈について考える章。ボルヘスの『伝奇集』に入っている短編「『ドン・キホーテ』の作者、ピエール・メナール」を引き合いに出していました。これ、ある種のボルヘスの思考実験(?)みたいなものでしょうか。20世紀の作家(とされる)、ピエール・メナールなる人物が、セルバンテスになりきるという方法で、セルバンテスのものと一語一句変わらない『ドン・キホーテ』を書こうとしたという想定(さらにその断片が残っているという想定)のもと、両者の比較を文芸批評的に行ったというフィクションなのです。
たとえ文面はまったく同じだとはいっても、セルバンテスよりメナールのほうが多義的だという意味で豊穣である、とボルヘスは記しています。シェフェールはこれについて、歴史的なコンテキストがもはや同じではないことの示唆として受け止めています。騎士物語のパロディだったセルバンテスのテキストは、メナールにおいては心理小説・形而上学的小説のジャンルに入れられるべきものになっているというわけです。また、スペイン語を学ぶことから入っているメナールの文体はどこか擬古的、セルバンテスのものは自分の時代のナチュラルな口語になっている、とボルヘスは記しています。シェフェールはここに、ジャンルの問題が、少なくともテキストの創造と受容の2つの問題として示されることを見てとっています。
それにしてもこのボルヘスの作品は、今読むとあまり面白みもないのですが(失敬)、むしろこの、ピエール・メナールの姿勢の極端さらしきものに、ちょっと惹かれるところがないわけでもありません。これ、ある意味でのファンダム的なスタンスの現れにも思えてきますね。ボルヘスはセルバンテスの、そしてシェフェールももしかしたらボルヘスの、なんらかのファンダムを生きている、みたいな?妄想ですけど……。
昔ここで書いたことがあったかもしれませんが、私個人も(ちょっと方向性は違いますが)、もうちょっと古典ギリシア語ができたなら、ヴァレリーの『エウパリノス』とかのギリシア語訳を、偽書として作りたいなあ、なんて思っていました(今でもかすかに思っています(苦笑))。まあ、でもそこまで古典ギリシア語できないからなあ……(遠い目?)。