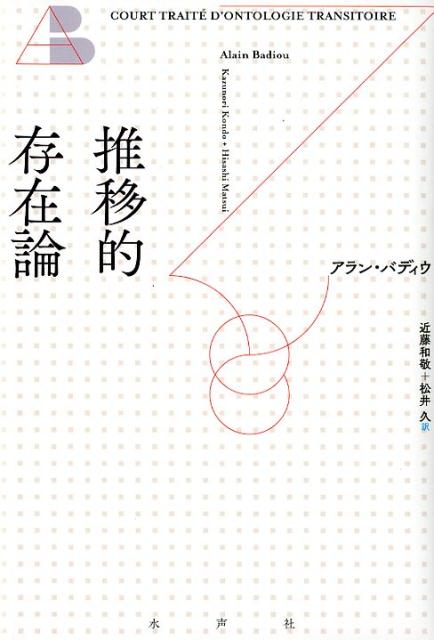 今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
今週はずっとアラン・バディウ『推移的存在論』(近藤和敬・松井久訳、水声社、2018)を眺めている。中心的な考え方はもちろん存在論の捉え直し。歴史的に存在論は「一」(一者、一性)の統一する力、その潜在力に従属してきた。けれども思想史には別筋の流れももちろんあって、そこでは存在論はそうした従属から解放され、いかなる一貫性にも還元されないような「多」についての理論となっているのではないか、そしてそれを今再び練り上げなくてはならないのではないか、というわけだ。で、そうした多を扱う理論は、結果的・必然的に「数学」、しかも論理記述的なものではなく、直観主義が言うような形での「数学」(そこでの数学的事象は、疑似的存在であり、存在論的な「決意」に属するものだとされる)でなくてはならないという。
このような立場を擁護すべく、同書では主要な哲学史上の議論の流れが再整理されることになる。その整理は、ある意味刺激的な読み直しをともないつつ、ドゥルーズ、スピノザなどをめぐりながら、少しずつ着実に進んでいく。中でもとりわけ刺激的なのは、プラトン思想やカント思想の「読み直し方」。前者においては、アリストテレスが「一」の論理に存在論を落とし込もうとする(記述を通じて)のに対し、プラトンは「多」の絶対的な決定不可能性のほうへと向かっていく、とされる。決定不可能性とは、たとえば認識主体と認識対象との区別になんの妥当性もないということだ。バディウは、思考が包蔵する存在と、思考が調整する運動との共外延性こそが、プラトンの言う「イデア」なのだと喝破してみせる。つまり思考の能力と思考の対象とは同じものであって分離できないということ。するとそれは多数性へと向かう契機こそを重視する立場を導き、選択公理(集合の生成力に制限を設けない)に好意的で、連続体仮説(限定を加えそうな)には慎重だということになる。
後者についても、たとえばカントの議論を、現象の側に純粋な多を、主体の側に「一として数えること」(統一)を置くように解釈してしまうのは誤りだとし、統一もまた、現象の多性の側の問題へと送り返していると読むべきだとしている。そのような統一をなす「統覚」の能力は、多の事象をたがいに結びつけるようなカテゴリーの体系とは別物で、むしろ連結の側から接近されるようなものなのだという。純粋な多がなんらかの状況に置かれて、「一として数えられる」ようになるのが実在するものだといい、一方の対象とは、連結(結びつきの錯覚)からのみ表象可能となったものだとされる。ここでもまた、統覚(主体)と対象とに、それらを表象可能にするような源・主体と源・対象があるならば、それらはいっさい現前することがなく、存在から引き離された「空」であるという意味において、不可分のものなのだとされる。
総じて、細やかで難解でありながらも、見かけ以上に価値転覆的な戦略を伴った議論という印象。消化しきれないところも多々あるし、これがどのような展開を遂げていくのかも気になるところではある。今回の翻訳は少し読みにくい印象もあるけれど、いずれにしてもバディウは少しこだわって見てみたい著者である。