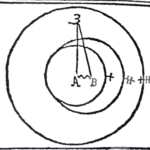フレデリック・ネフの著書に、相変わらず流し読み的に目を通している。今回のは、前に挙げた『なにがしかの対象』『事物の属性』に続く、それらと合わせて三部作をなすという『アンチ・ヒューム』(Frédéric Nef, L’anti-hume : De la logique des relations à la métaphysique des connexions (Problemes & Controverses), J. Vrin, 2017)。これは三冊のうちではとくに面白く、これ単独で読むというのも十分アリだと感じられた。副題(関係の論理学からコネクションの形而上学へ)に示されている通り、今回のテーマは「コネクション」、つまりモノや事象の間のつながり・連関を存在論的に再考しようというもの。結果、そのつながりこそを従来とは別様の存在論的対象として認めようという話になっている。従来の存在論では、実体的か偶有的かはともなく、各々の個物にこそ存在が認められ、個物は多かれ少なかれ他に従属せず(独立して)存在するとされてきた(これをアトミズムと称している)。しかしながらそれを突き詰めると、個物同士の関係性は損なわれていくことになる。ヒュームなどは因果関係を知覚する者の内的なものにまで矮小化した(とはいえヒュームは、因果関係そのものの実在には可能性を残しているようなのだが)し、さらにその後継とされるルイスなどは、因果性など端から認めないというところにまで行っているというのだが、これに対して、因果関係をもう一度救済できないかというのが著者の試み。そこで着目されるのが、複合体を一つにまとめている関係性、とりわけその連関の在り方とはどういうものかという問題。そこから著者は、このコネクションの存在論をつかみ出そうとする。
フレデリック・ネフの著書に、相変わらず流し読み的に目を通している。今回のは、前に挙げた『なにがしかの対象』『事物の属性』に続く、それらと合わせて三部作をなすという『アンチ・ヒューム』(Frédéric Nef, L’anti-hume : De la logique des relations à la métaphysique des connexions (Problemes & Controverses), J. Vrin, 2017)。これは三冊のうちではとくに面白く、これ単独で読むというのも十分アリだと感じられた。副題(関係の論理学からコネクションの形而上学へ)に示されている通り、今回のテーマは「コネクション」、つまりモノや事象の間のつながり・連関を存在論的に再考しようというもの。結果、そのつながりこそを従来とは別様の存在論的対象として認めようという話になっている。従来の存在論では、実体的か偶有的かはともなく、各々の個物にこそ存在が認められ、個物は多かれ少なかれ他に従属せず(独立して)存在するとされてきた(これをアトミズムと称している)。しかしながらそれを突き詰めると、個物同士の関係性は損なわれていくことになる。ヒュームなどは因果関係を知覚する者の内的なものにまで矮小化した(とはいえヒュームは、因果関係そのものの実在には可能性を残しているようなのだが)し、さらにその後継とされるルイスなどは、因果性など端から認めないというところにまで行っているというのだが、これに対して、因果関係をもう一度救済できないかというのが著者の試み。そこで着目されるのが、複合体を一つにまとめている関係性、とりわけその連関の在り方とはどういうものかという問題。そこから著者は、このコネクションの存在論をつかみ出そうとする。
存在論的アトミズムは歴史的には中世からあるといい、ドゥンス・スコトゥスやトマスの穏健な実在論の後、オッカムの「関係そのものは存在しない」というテーゼをもって最初の極北をなす、とされている。一方で中世思想のある種の集大成としてのライプニッツは、関係性を認識論的なものと見なしつつも、それを事物の基盤として捉えてみせる。ここに、連関(コネクション)の関係性の議論が胚胎する。ネクサス(コネクションが操作・作用を言うのに対して、ネクサスはその産出物としてのつながりを言う)をめぐる思想はその後18世紀に、ウォルフ、バウムガルテン、カントなどによって洗練され、さらに後にはウィトゲンシュタイン(アトミズムの系譜にも入れられるが)、そしてホワイトヘッドにまでいたる……。著者ネフは、新しい存在論の可能性を論じながら、それをきっちり哲学史上に位置付けようとし、実に手際よく整理しながら話を進めていく。もちろん分析哲学的なアプローチが主となるのだけれど、哲学史のあまり表面に出ない系譜をまとめ上げている手法も見逃せない。というか、そういう堅実な部分が、どこか重厚な筆致と合わせて、魅力を醸しているように個人的には思える……。