この数か月何度も耳にした「専門家会議」という名称。報道その他を見ている限り、同会議が出してくる提言(?)は、思ったほど厳密に数値や客観的基準に依っていないのではないかという印象だ。けれども、そのような通俗的なイメージが、実は案外、今現在において専門知と称されるものの本質を見据えているのかもしれない、ということを思わせる一冊に目を通してみた。セオドア・M・ポーター『数値と客観性:科学と社会における信頼の獲得』(藤垣裕子訳、みすず書房、2013-20)。
これによると、専門的知識は本来、暗黙知のようなものをも含む広い概念なのだが、これに社会的な意味での客観化の要請が結びつくことで限定化され、とりわけ数字の使用(定量化)に重きが置かれることになったという。このプロセスは18世紀以降に加速的に進んだようだ。ここでの客観化の要請とは、おもに近代の欧米各国において、官僚機構が外部からの攻撃や批判をかわすために必要とした権威付けのことだったとされる。数字が重視されるようになったことそれ自体には、もちろん当時の実験科学の拡大とか、商業や行政での会計学や保険技術の進展とかの要因もあった。けれども重要なのは、それが客観性を担保するものとして、「政治的に」利用されていったということ。かくして定量化は物事の管理手段として重視されることになる。数字が客観性の指標として重視されていく背景には、行政・統治機構の政治的思惑が当初から含まれていたというのだ(!)。
衝撃的ともいえるそうした事象を、同書は実例としてフランス、イギリス、アメリカなどの技術官僚その他を取り上げ、丹念に描き出していく。「信頼できる数字」というのは、信頼できるとされる機関、すなわち官庁だったり、大学や研究機関だったりのメンバーが出す数字でなければならない。階層性や制度に裏打ちされていなければならない、というわけだ。それが信頼の構図であり、著者によれば数字への信頼は、原書刊行の1995年当時に、「個人の判断に対する圧倒的な不信の文脈」が形成されていたことの裏返しでもあるとされている。では今また、その数字自体が、あるいは専門家の判断が不信をもって受け止められているとしたらどうなるのか?個人の判断への妄信にはもちろん戻れない。けれども、機関が出してくる数字もいい加減、すなわち統治機構もいい加減では、となったなら、もはや管理も統治もできない。残るはカオスしかない、ということになってしまうのだろうか……??



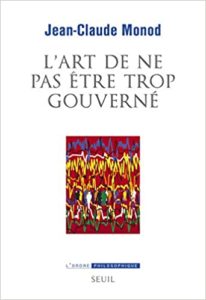 このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “
このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “