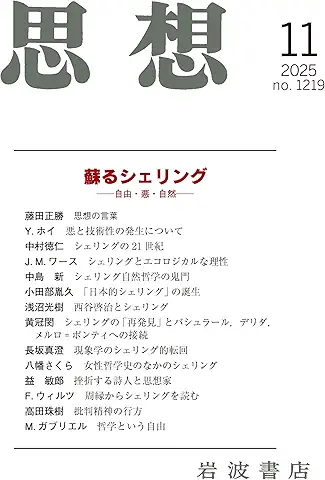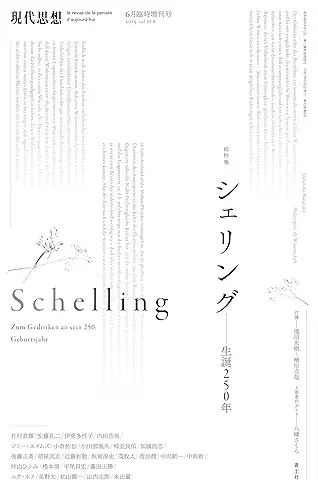明けて2026、おめでとうございます。今年もいろいろな書籍や映画、音楽などに出会いたいと期待しています。というわけで、まずはこの年末年始の「年越し本」から。
まず、去年の夏ぐらいから、一元論のアプローチについて、いろいろ考えてみたりしていた、というのがあって、その流れで大森荘蔵『物と心』(ちくま学芸文庫、2015年)を見てみました。もとは1976年刊行の本。
https://amzn.to/3YGI3ul
自己の意識と外の世界の物質について、両者を区別するものは何もなく、両者ともに「立ち現れ」があるだけなのだとするラディカルな立場が示されます。でもこの「立ち現れ」そのもの(観念などを介さずに、直接的に触れること(?))が、なにやら釈然としない感じもありますね。
思うに一元論的記述は、たとえばなんらかの対象について、その対象に当事者として関わる人が抱く、情感や実感、細やかな現実認識といった、数字など客観的なデータでは捉えきれない部分を汲み上げるためには有効なのでしょうけれど(現象学などがそうだったりします)、あらゆるものが本質的にそのような構図で捉えられる、それがすべてだと言い切ってしまうとき、なにかまた別の問題を導き入れてしまうように思えます。なんらかの対象が想起されるなどのときの、その対象となるものは、いったい何だということになるのか(対象という言い方がすでにして二元論的ですが)、とか。
ちなみに文庫版の巻末の解説で、哲学者の青山拓央氏は、物に対する心を考える限り、立ち現れ論は観念論ではないが、他我に対して二義的に心を考えるとき、独我論的なものとして、観念論になってしまう、みたいなことを書いていますね。他我の関係まで一元化しようとするとき、はたしてその一元論は、論述としてそもそも成立しうるのでしょうか?ある種の詩にしかならないのでは?いずれにせよ、それはとても困難なものになりそうです。