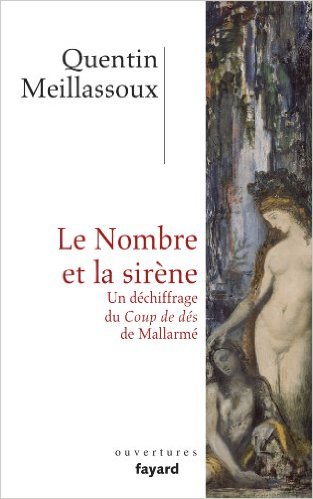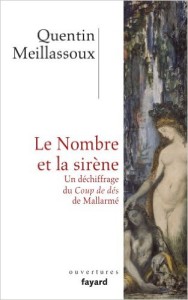 偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
マラルメは共和国の制度、とりわけ政教分離に批判的で、宗教が担うような強い象徴的繋がりがなければ社会はありえないと考えていた、という。宗教とは私的なものなどではとうていなく、パブリックな事象だというわけだ。マラルメはまた、古い宗教に代わって芸術こそが近代に相応しい崇拝の対象にならなくてはならないと考えていたという。それは当時わりと人口に膾炙していた考え方のようなのだけれど、たとえばワーグナーの総合芸術が、あまりにギリシア風の演劇構成に依っている点にマラルメは批判的で、西欧の真の母体はむしろ中世ラテン文化にあると見なしていたという。近代の新たな芸術的崇拝が乗り越えなくてはならないのは、古代ギリシアの形式ではなく、中世以来のキリスト教の典礼にほかならない、というわけだ。マラルメは、詩作品はキリスト教の典礼にすら肩を並べる現実的な出来事をなさなくてはならないと考えていた。そしてメイヤスーによれば、それを作品化してみせているのがほかならぬ『骰子一擲』なのだ……という。そこで祭壇をなすのはほかならぬ「偶然」そのものであり、マラルメは不確定を永続化させる試みをそこで完遂しようとする。コード化はまさにそのための手段だとされる。コードはもしかすると永遠に発見されないかもしれない……。ある意味、犠牲として捧げられるのは生身のマラルメその人であり、そこから作者としてのマラルメが復活することが賭されている……と。
なるほど、マラルメの思想的な射程というのは考えたことがなかっただけに、これは瞠目させられる。マラルメのこうした構想(永続する不確定を軸とする作品構成なのだけれど、それが現実に観想されたのかどうか自体も不確定だ)は、実際の詩作の手法や作品世界などにも二重・三重に取り込まれている、とメイヤスーは見ているようだ。韻律こそが儀式的でパブリックな詩作の条件と考えるマラルメは、アレクサンドラン(12音節詩句)などの伝統的詩句を重視する立場を取っていたというが、当時は自由詩句の台頭とともに、たとえば語末のeの発音の有無が詩作上の論争となっていて(音節主義からアクセント主義への移行)、マラルメは語末のeを発音するかしないかを読み手に任せ、結果的に不確定要素を混入させて定型句を自由詩句に近づけているという。あからさまに詩句の自由化を説くのではなく、その自由詩句を不確定要素として反転させて定型句の側に取り込むという、ある意味狡猾なそのやり方は、描かれるテキストの中にも、一瞬だけ姿を現すセイレーンなどとして暗示されている……(とメイヤスーは論じる)。
同書を読むために、久々に秋山澄夫訳の『骰子一擲』(思潮社、1984)を引っ張り出してみたのだけれど、その解説部分に興味深い一節がある。「わたくしは『骰子一擲』をアンティ・スピノジズム、つまり、スピノザ主義への挑戦の書であると理解する。人間による創造はあり得るという、巨大な無神論の宣言だ。絶望の書ではない。確信の書であり、深淵から立ち上がった復活のドキュマンであり、マニフェストである」(p.76)。読みの方向性は違っていても、その強度において通底するかのような一節だ。