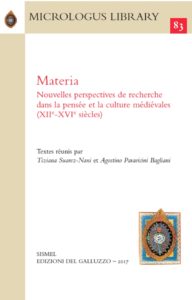夏読書という感じでジェームズ・フランクリン『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』(南條郁子訳、みすず書房、2018)を読み始めた。原書は2001年刊。数理的な意味での確率論の前史として、法学などで使われる蓋然性概念を追った力作。まだ総論的な最初の三章を見ただけだけれども、古代から中世、ルネサンスへと至る西欧の法体系・法理論の概略についてまとめられていて、個人的にはかなり惹かれるものがある。古代エジプト、メソポタミアのハンムラビ法典、ユダヤ教のタルムード、ローマ法、グレゴリウス改革とグラティアヌス法令集、そしてインノケンティウス3世の治世などなど……。同書でとくに問題とされているのが、今でいう証拠能力。古代の法から、証拠の強さといった概念は漠然と盛り込まれていたようなのだけれど、それが明確に問題として取り上げられる過程にはいくつかのメルクマールがあるらしい。
夏読書という感じでジェームズ・フランクリン『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』(南條郁子訳、みすず書房、2018)を読み始めた。原書は2001年刊。数理的な意味での確率論の前史として、法学などで使われる蓋然性概念を追った力作。まだ総論的な最初の三章を見ただけだけれども、古代から中世、ルネサンスへと至る西欧の法体系・法理論の概略についてまとめられていて、個人的にはかなり惹かれるものがある。古代エジプト、メソポタミアのハンムラビ法典、ユダヤ教のタルムード、ローマ法、グレゴリウス改革とグラティアヌス法令集、そしてインノケンティウス3世の治世などなど……。同書でとくに問題とされているのが、今でいう証拠能力。古代の法から、証拠の強さといった概念は漠然と盛り込まれていたようなのだけれど、それが明確に問題として取り上げられる過程にはいくつかのメルクマールがあるらしい。
たとえばヘレニズム期のアレクサンドリアのフィロンは法の根拠を問題にしていて、2人証人則の合理性を論じたりしているという(p.15)。グレゴリウス改革期には、2人証人が完全な証拠であるなら1人証人は「半証拠」である、という考え方も出てくる(p. 36)。推定の強さをもとにした等級づけの発想も、グラティアヌス法令集の初期の段階で現れるのだという(p.39)。拷問に関しては大陸にはその習慣がなく、ローマ法の流れを汲んで、すでに有罪の証拠が強いとされる場合の補完として使われるべきだとされていたという(p.49)。拷問がそれなりに有用とされるのはルネサンス期以降の魔女裁判などでのことのようだが、それでも基本的に補完的手段であるのは変わらないようだ(p.87)。また大陸では証拠の等級は13世紀の『グレゴリウス9世教令集』などでさらに精緻化するものの、イングランドの法はそうした点でだいぶ遅れをとっていたともいう(pp.50-52)。……とまあ、最初の数章だけでもいろいろとメモすべき記述が満載。続く各章は諸学のテーマ別となるようで、そちらもまたメモしていくことにしよう。
前回取り上げた論集『マテリアーー中世思想文化研究の新展望』(T. Suarez-Nani et A.P. Bagliani, Materia. Nouvelles perspectives de recherche dans la pensée et la culture médiévales (XIIe-XVIe siècles), Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2017)から追加的にもう一つ。アントニオ・ペタジネ「質料は実定的存在か?ーージャン・ル・シャノワンの応答」(pp.173 – 190)は、タイトルにある「参事会員ジャン(ジャン・ル・シャノワンヌ)」なる人物がいきなり本文で名前が変わってしまうという意外な一篇。作品の途中で主人公が変わる小説かなにかのよう(笑)。なぜそうなったのか。実は1330年ごろの逸名著者による『自然学の諸問題』という書物(初期の印刷でもって16世紀初頭まで命脈を保った一冊)が、最初はアントワーヌ・アンドレに、次いで「シャノワンヌ(参事会員)」との肩書きをもつ人物だとされて、ジャン・マルブルなる人物に帰属させられることになった。このジャン・マルブルとはフランシスコ会士ピエール・ケネルではないかとされたのが1981年。そして2015年、どうやらその逸名著者は、フランシスコ会派の人物ではなく、アウグスティヌス会のフランセスク・マルブル(トゥールーズ大学の自由学科教師、トルトサ大聖堂の参事会員でもあった)である可能性が高いということでどうやら落ち着いた、という経緯らしい。
マルブルはフランシスコ会系の学校で哲学や神学を修めたらしく、そのせいか質料論などを論じる内容がドゥンス・スコトゥスの立場に近いとされ、質料に実定的なもの(形相によるものから独立した最小限の現実態)を認めているほか、同じくフランシスコ会系のジェラール・オドン(ゲラルドゥス・オドニス:1285 – 1349、どうやらスコトゥス派らしい)の議論などをも援用しているという。マルブルが借り入れているオドンという人物の議論には、たとえば次のようなものがあるという。(1)形相は質料を必要としているという意味で、質料に依存しているが、依存するものは現実態でなければならない、(2)質料はあらゆる実体に先行して存在しているのであるから、現実態でなければならない、(3)質料は本質において「無を超えたもの」である以上、それは固有の現実態をもっていなければならない……。これらはいずれもスコトゥスには見られない議論だといい、どれもオドンがペトルス・アウレリウスの批判に対する反論として提示したものだという。この論文でもなにやらそのジェラール・オドンが、もう一人の主役のようになっている(気がする)。これまた思想史的な重要人物?
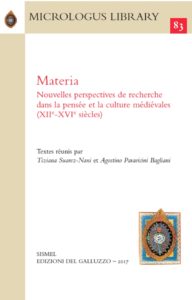 刺激的なテーマの著作がラインナップに居並ぶミクロログス・ライブラリから、昨年刊行されたスアレス=ナニ&バリアーニ編『マテリアーー中世思想文化研究の新展望』(T. Suarez-Nani et A.P. Bagliani, Materia. Nouvelles perspectives de recherche dans la pensée et la culture médiévales (XIIe-XVIe siècles), Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2017)を見ているところ。現代思想的な唯物論もこのところちょっとした展開があるなか、中世の質料論(あるいは物質論)も少しずつ変化・進展を見せているらしいことを窺わせる論集になっている。お馴染みの論者や研究対象に混じって、少しずつまた新たな見識が寄せられていることは大変喜ばしいところ。個人的に興味をそそられるのは、スコトゥス派(スコトゥスの難解で曖昧なテキストに注釈を施そうとしていたフランシスコ会系の内部的な一派で、14世紀初めごろにはすでに確立されていたという)のマテリア論を扱った論考が数本ある点。注釈者たちの常で、元のテキストにはない問題系などが新たに創発されていくらしいのだけれど、そいういうのを見ていると、まだまだ光を当てるべき対象が多々あるのだなあと改めて感慨深い。
刺激的なテーマの著作がラインナップに居並ぶミクロログス・ライブラリから、昨年刊行されたスアレス=ナニ&バリアーニ編『マテリアーー中世思想文化研究の新展望』(T. Suarez-Nani et A.P. Bagliani, Materia. Nouvelles perspectives de recherche dans la pensée et la culture médiévales (XIIe-XVIe siècles), Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2017)を見ているところ。現代思想的な唯物論もこのところちょっとした展開があるなか、中世の質料論(あるいは物質論)も少しずつ変化・進展を見せているらしいことを窺わせる論集になっている。お馴染みの論者や研究対象に混じって、少しずつまた新たな見識が寄せられていることは大変喜ばしいところ。個人的に興味をそそられるのは、スコトゥス派(スコトゥスの難解で曖昧なテキストに注釈を施そうとしていたフランシスコ会系の内部的な一派で、14世紀初めごろにはすでに確立されていたという)のマテリア論を扱った論考が数本ある点。注釈者たちの常で、元のテキストにはない問題系などが新たに創発されていくらしいのだけれど、そいういうのを見ていると、まだまだ光を当てるべき対象が多々あるのだなあと改めて感慨深い。
たとえば、アスコリのヤコブス(ジャック・ダスコリ)についての一篇(pp. 151 – 171)。アスコリは1310年から11年ごろにパリ大学神学部の教授になった人物で、そうしたスコトゥス派の初期を代表する一人だという。論文著者のロベルタ・パドリーナという人は、スコトゥスの質料論のエッセンスをまとめ、さらにこのアスコリがそれをどう展開したかを論じている。13世紀ごろの議論では、第一質料は純粋に潜在的なものだとされていたが、それでは第一質料があらゆる事物の基礎をなしているというもう一つの議論と整合しないとスコトゥスは考え、形相によるものとは違うなんらかの現実態が第一質料になければならないとした。そのためにスコトゥスは、変化の原理としての潜在態と、存在様式としての潜在態とを区別する。そしてこの後者の潜在態はさらに分析され、形而上学的な潜在態として、客観的潜在態(内的な固有の存在の潜在性?)と主観的潜在態(外的な存在者の本質の潜在性?)が区別される。論文著者は、質料に当てはめられるこの区別の曖昧さをめぐって、アスコリがもとのスコトゥスとは多少とも別様の区分・説明を配してその曖昧さと格闘している様子を浮かび上がらせる。
元素の混合の問題を扱った論考もそういった一篇(pp.123 – 149)。混合に際して元素はもとの性質を失うのかどうかという問題について、かつてアンネリーゼ・マイヤーは、もとの元素の性質が実質残るという説と、もとの元素は消滅し新たな性質が獲得されるという説との対立を、前者をアヴィセンナに、後者(およびそれをさらに先鋭化した同時代の「近代派」)をアヴェロエスの系譜に位置付けるかたちで整理したことがあった。けれどもウィリアム・ドゥーバという人の論文では、その見方自体が14世紀のペトルス・アウレオルス(後者のアヴェロエスの系譜に属している)に準拠しているのではないかといい、論文著者はこれに、アウレオルス(やマルキアのフランシス)が批判的だったスコトゥス思想を継承する一人としてブリエンヌのギヨーム(ウィリアム)を対置して、スコトゥス派の反論を描きだそうと試みる。アヴェロエスの系譜とされた説は、もとの元素の消滅を唱えながらも、その一部が残るとか、消滅は漸進的になされるとかといった、どこか中間派・折衷派という感じ。これに対して近代派は、混合は一種の生成であるとするスコトゥスの説をかざして中間派を一蹴してみせる。こうしてブリエンヌは「余計な概念や分析を持ち込まない」というオッカムの剃刀的なスタンスで、アウレオルスやマルキアの折衷的議論をばっさりと斬っていく。
 新しい実在論が多少ともかまびすしく持ち上げられているようだけれど、一方でそれもまったく一枚岩ではなく、そのあたりを整理し、それぞれの論を批判的に捉えるという動きもやはり出てきているようで、これなどはまさにそういう一冊。このところ読み始めているジョスラン・ブノワ『リアルの在処』(Jocelyn Benoist, L’adresse du réel (Moments philosophiques), J, Vrin, 2017)。まだ前半部分だけだけれど、そこではとくにマルクス・ガブリエル(日本でも『なぜ世界は存在しないのか』で一気に表舞台に躍り出た感がある)への批判的対応がメインに置かれている。その最も中心的な批判が展開されるのは第三章。ガブリエルの説く「意味の場」の存在論(存在するものはすべて、その時々の意味の場のうちに現象する・現れる、という議論)について、その「意味」にあたるSinnに注目し、ガブリエルはフレーゲ的な「意味」と「存在」との対立を解消しようとしているせいで、かえって「現実」の概念を脆弱なものにしているのではないか、その現実の「現れ」(apparaître)の概念は「現実」の概念の一部をなしていないのではないか、その議論はカテゴリーミステイクに立脚してはいないか、と論難する。現れを中立化させて意味と存在をつなぐのは、人が思うほど容易ではない……と。
新しい実在論が多少ともかまびすしく持ち上げられているようだけれど、一方でそれもまったく一枚岩ではなく、そのあたりを整理し、それぞれの論を批判的に捉えるという動きもやはり出てきているようで、これなどはまさにそういう一冊。このところ読み始めているジョスラン・ブノワ『リアルの在処』(Jocelyn Benoist, L’adresse du réel (Moments philosophiques), J, Vrin, 2017)。まだ前半部分だけだけれど、そこではとくにマルクス・ガブリエル(日本でも『なぜ世界は存在しないのか』で一気に表舞台に躍り出た感がある)への批判的対応がメインに置かれている。その最も中心的な批判が展開されるのは第三章。ガブリエルの説く「意味の場」の存在論(存在するものはすべて、その時々の意味の場のうちに現象する・現れる、という議論)について、その「意味」にあたるSinnに注目し、ガブリエルはフレーゲ的な「意味」と「存在」との対立を解消しようとしているせいで、かえって「現実」の概念を脆弱なものにしているのではないか、その現実の「現れ」(apparaître)の概念は「現実」の概念の一部をなしていないのではないか、その議論はカテゴリーミステイクに立脚してはいないか、と論難する。現れを中立化させて意味と存在をつなぐのは、人が思うほど容易ではない……と。
同著者は「意味」と「存在」は対置しないものの、区別はすべきだとの立場を示す。意味の場が一種の悪しきメタファー(カテゴリーミステイクに立脚した)であるならーーと著者は提案するーー、むしろそこに、規範をともなった(規範が組み込まれた)構造を見るほうがよいのではないか。そのほうが、ガブリエルのような志向的存在論(「規範」が適用される手前、あるいはその外部で、存在する事物がいわば「背景」から「せり上がる」がごとくに意味の場に現象する、と考える存在論だ)には相応しいのではないか、というわけだ。このあたりは考えどころで、同著者のいう「構造」や「規範」にはもう少し厳密な定義が必要な気もする。後半部分でより明らかになることを期待しつつ、もう少し議論を追うこととする。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 夏読書という感じでジェームズ・フランクリン『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』(南條郁子訳、みすず書房、2018)を読み始めた。原書は2001年刊。数理的な意味での確率論の前史として、法学などで使われる蓋然性概念を追った力作。まだ総論的な最初の三章を見ただけだけれども、古代から中世、ルネサンスへと至る西欧の法体系・法理論の概略についてまとめられていて、個人的にはかなり惹かれるものがある。古代エジプト、メソポタミアのハンムラビ法典、ユダヤ教のタルムード、ローマ法、グレゴリウス改革とグラティアヌス法令集、そしてインノケンティウス3世の治世などなど……。同書でとくに問題とされているのが、今でいう証拠能力。古代の法から、証拠の強さといった概念は漠然と盛り込まれていたようなのだけれど、それが明確に問題として取り上げられる過程にはいくつかのメルクマールがあるらしい。
夏読書という感じでジェームズ・フランクリン『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』(南條郁子訳、みすず書房、2018)を読み始めた。原書は2001年刊。数理的な意味での確率論の前史として、法学などで使われる蓋然性概念を追った力作。まだ総論的な最初の三章を見ただけだけれども、古代から中世、ルネサンスへと至る西欧の法体系・法理論の概略についてまとめられていて、個人的にはかなり惹かれるものがある。古代エジプト、メソポタミアのハンムラビ法典、ユダヤ教のタルムード、ローマ法、グレゴリウス改革とグラティアヌス法令集、そしてインノケンティウス3世の治世などなど……。同書でとくに問題とされているのが、今でいう証拠能力。古代の法から、証拠の強さといった概念は漠然と盛り込まれていたようなのだけれど、それが明確に問題として取り上げられる過程にはいくつかのメルクマールがあるらしい。