少し前に触れたモミリアーノの『蛮族の知恵』。同書の最後の章をメモっておくつもりが、まだやっていなかったので、改めて。これによると古代ギリシアの人々は、蛮族と称された他国の人々の文化・伝統に、言語の問題などで、事実上これといった関心を寄せたふうがないとのことだった。同章では東方のペルシア(現イラン)との接触について取り上げているが、ソクラテス以前の初期の哲学者たちが東方ペルシアの思想的(宗教的)影響を受けていたのでは、あるいはギリシアに哲学をもたらしたのは東方のマギたちだ、という話は昔(紀元前)からあったらしい。そのくせ、そうしたコンタクトがなんらかの政治状況によるものだったことが理解されたためしはなく、また他国への関心が向くというようなこともなかったようなのだ。
一方で、マギとかザラツストラ(ゾロアスター)などのイメージは、真偽に関係なく増殖していったという。前3世紀には、プラトンの創設のアカデメイア内部において、セム系のエル神やザラツストラ、さらにはカルデアの神託などに関する議論が巻き起こっていた(プロクロスによる記述)。ヘルメス・トリスメギストスと並んで、ザラツストラの名は、占星術や彼岸の生、自然の神秘などについての思弁を引き寄せる極となり、モミリアーノ言うところの幾多もの愚論を生み出すことになる。偽造・変造の数々は紀元後にまで延々と続いていく。
ヘロドトスが伝えるペルシア戦争(前5世紀)での勝利の後には、ギリシアの軍事的な優位性をめぐる考察(自国をほめそやす民族主義的なもの?)に絡んで、ギリシアにおける新たな民族誌の擁立が導かれたというが、ギリシア人がペルシアの行政機構を対象とした考察をめぐらすことは、前4世紀にいたってもほとんどなかったようだ。ペルシアについて記したクテシアスを敬意をもって引用するクセノフォンですら、ペルシアの社会についてはまったく関心を寄せていないという。同時代のプラトンやアリストテレスにしても同様だったと、モミリアーノは述べている。
メルマガで見ているフェスチュジエールは、アレクサンドロス大王のコスモポリタン的な思想が、教師役だったアリストテレスによるものではないとしているが、モミリアーノによれば、アリストテレスがアレクサンドロスに宛てた、真贋が定まっていない書簡(アラビア語訳)が残っているそうで、そこではギリシアの民族主義とともに、(それと相矛盾するかのような)普遍的国家の構想が謳われているという。モミリアーノはそれが帝政ローマ期に書かれた贋作との見方を強めている。重要なのは、帝政ローマでコスモポリタン的な思想が広がると同時に、その前モデルとしてのペルシアが再浮上したという構図だ。コスモポリタン思想の起源が、ギリシアそのものというよりペルシアあたりにあったかもしれない、という見立てだが、これは果たして正鵠を射ているのだろうか?
ギリシアは他文化に関心を寄せる度合いが少なかったが、逆に他の民族はヘレニズム文化にそれなりの関心を寄せている場合が多く、マケドニア系のセレウコス朝や、それに続く前3世紀のパルティア帝国(前3世紀の古代イラン王朝)などでそのことは顕著だったという。とくにこの後者は、ギリシアのものを模した貨幣を作ったり、ギリシア的な知的活動に力を注いだりしていたという。ギリシア人を積極的に国家の要職に登用していたとか。けれどもそうした在パルティアのギリシア人らは、パルティアの歴史や地理について記すことはなく、パルティアについての研究が出てくるのはローマ時代のストラボンやトログス(前1世紀)を待たなくてはならない。繰り返されるこの一方通行感……。それでいて、上でも触れたように、ギリシア文化が蛮族の知恵に全面的に依存していたという印象もまた、ギリシアの内外で様々な偽造を通じて膨らんでいく。そういうところに、なにやら文明の退潮が重ね合わせられるかのようだ。
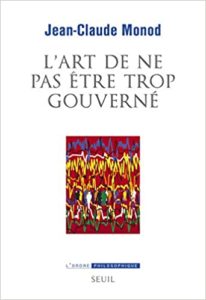 このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “L’Art de ne pas être trop gouverné“, Seuil, 2019)などか。でも、フーコー的な権力への対峙の仕方を、現代的文脈に置き換えて論じるといった姿勢が、すでにどこか既視感にあふれた、手垢のついたスタンスでしかないように見えて、あまり読書に奮い立たされる感じがしない。現代における統治の問題は、統治機構そのものが市場経済(というか市場というよりは企業ということだが)に従属してしまい、統治者もまた少数の特権的なエリート集団と化してしまっていること。そのために、近年の各種の対抗運動も、「このように統治されるのを自分たちは望まない」という叫びに変質していることを見てとっている。この見立ては正鵠を射ているだろうけれど、それにしても危機的状況に際して生じている反動として列挙される対抗運動の数々は、いずれもおのれの立脚点とすべき概念なり理念なりを、まだ十分に手にしていないとされる。もちろん前回に触れたドンズロのように、そうした概念・理念がまた新たな分裂や争議を呼ぶようなこともあるだろうし、そもそも概念化はある種の制度化を伴うわけであるし、カオスとなった運動の熱が冷めていくときに生じる事柄については、より精緻な分析が必要かもしれない(ただしそれは、ある意味とても退屈な作業かもしれないのだけれど)。
このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “L’Art de ne pas être trop gouverné“, Seuil, 2019)などか。でも、フーコー的な権力への対峙の仕方を、現代的文脈に置き換えて論じるといった姿勢が、すでにどこか既視感にあふれた、手垢のついたスタンスでしかないように見えて、あまり読書に奮い立たされる感じがしない。現代における統治の問題は、統治機構そのものが市場経済(というか市場というよりは企業ということだが)に従属してしまい、統治者もまた少数の特権的なエリート集団と化してしまっていること。そのために、近年の各種の対抗運動も、「このように統治されるのを自分たちは望まない」という叫びに変質していることを見てとっている。この見立ては正鵠を射ているだろうけれど、それにしても危機的状況に際して生じている反動として列挙される対抗運動の数々は、いずれもおのれの立脚点とすべき概念なり理念なりを、まだ十分に手にしていないとされる。もちろん前回に触れたドンズロのように、そうした概念・理念がまた新たな分裂や争議を呼ぶようなこともあるだろうし、そもそも概念化はある種の制度化を伴うわけであるし、カオスとなった運動の熱が冷めていくときに生じる事柄については、より精緻な分析が必要かもしれない(ただしそれは、ある意味とても退屈な作業かもしれないのだけれど)。

 すっかり形骸化してはいるものの、5月1日はメーデー。これに向けて(というわけでもなかったのだけれど)、少しばかりフランスの社会史・政治史に絡んだものに目を通しているところ。さしたあり見ているのは、ジャック・ドンズロ『社会的なものの発明』(真島一郎訳、インスクリプト、2020)。まだざっと3分の2ほど。原書は最初の版が84年刊、底本になっているものが94年刊。
すっかり形骸化してはいるものの、5月1日はメーデー。これに向けて(というわけでもなかったのだけれど)、少しばかりフランスの社会史・政治史に絡んだものに目を通しているところ。さしたあり見ているのは、ジャック・ドンズロ『社会的なものの発明』(真島一郎訳、インスクリプト、2020)。まだざっと3分の2ほど。原書は最初の版が84年刊、底本になっているものが94年刊。
これが面白いのは、一つの概念の導入が、ほどなく両義的な意味合いに分裂し、相互にせめぎ合うようになるという視点を一貫して保ちながら、そうした概念の歴史的な展開を分析していくところ。メソッド的に一貫している、ということか。まず最初の章では、「社会的なもの」の成立をめぐる分析が展開するが、そこでは、社会的なものの合意の内部に分裂をもたらすことが問題とされる。「社会的なもの」というのはそもそも本来的に欠損しているのだが、そこになんらかの概念を打ち立てて社会の体制の説明付けを行おうとするがゆえに、それは共有されもするが、同時に対立の芽をはぐくむことにもなる……。たとえばルソーの社会契約のモデルは、ルソー本人への評価とは別に、共和主義、社会主義の双方の拠り所となっていたという。しかしながら1848年に国家そのものが問題になると、その契約モデルのほころび(国家や経済への考察の不備)が露呈し、中央集権的な立場と無政府主義との衝突が激化する事態を招いてしまう、と。
続いて今度は、そうした衝突を背景に出てくる連帯の観念が取り上げられる。中心となるのはデュルケムの社会分業論。デュルケムは契約の発展のそもそもの由来を、相互依存の社会的事象、社会の有機的連帯に見て取るが、個人と社会との関係性の問題はその後も熾烈な対立をもたらしていく。国家の役割を拡張するかどうかについての賛否をめぐる論争は、どちらも連帯の観念に依拠したがために、止揚への道を逆に絶たれてしまったのだ、と。「連帯の観念さえあれば終止符を打てるとみなされてきた論争を、当の連帯観念がこうして再燃させていく」。反復されるこの構図。
さらに続いて出てくるのは、社会法をめぐる議論。とくに労災問題の解決策として出てきた保険技術だ。デュルケムの分業論やそこから導かれる連帯論を実現するとされた保険技術は、社会法によって規範化されることで、企業主と労働者の関係を賃金交渉にのみ位置づけることを可能にし、一方で労働組合も社会的合理性を持ち出して要求を拡充することが可能になったという(1920年代)。しかし一方でそれは、社会的なものと経済的なもののいずれか一方の合理性のみを押し通そうとする勢力をいっそうはぐくみ、再び国家問題を中心に、介入の役割についての対立をあおることにもなる……。
この後、さらに60年代、70年代の新左翼、改良主義運動、の話などが続く。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
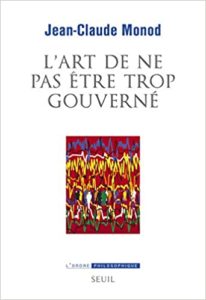 このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “
このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “