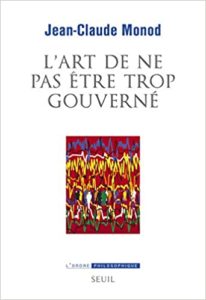 このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “L’Art de ne pas être trop gouverné“, Seuil, 2019)などか。でも、フーコー的な権力への対峙の仕方を、現代的文脈に置き換えて論じるといった姿勢が、すでにどこか既視感にあふれた、手垢のついたスタンスでしかないように見えて、あまり読書に奮い立たされる感じがしない。現代における統治の問題は、統治機構そのものが市場経済(というか市場というよりは企業ということだが)に従属してしまい、統治者もまた少数の特権的なエリート集団と化してしまっていること。そのために、近年の各種の対抗運動も、「このように統治されるのを自分たちは望まない」という叫びに変質していることを見てとっている。この見立ては正鵠を射ているだろうけれど、それにしても危機的状況に際して生じている反動として列挙される対抗運動の数々は、いずれもおのれの立脚点とすべき概念なり理念なりを、まだ十分に手にしていないとされる。もちろん前回に触れたドンズロのように、そうした概念・理念がまた新たな分裂や争議を呼ぶようなこともあるだろうし、そもそも概念化はある種の制度化を伴うわけであるし、カオスとなった運動の熱が冷めていくときに生じる事柄については、より精緻な分析が必要かもしれない(ただしそれは、ある意味とても退屈な作業かもしれないのだけれど)。
このところ、読む本にもこれといって注目できるものがなくて、少し悶々とした日々を過ごしている。それでもあえて挙げるなら、ジャン=クロード・モノ『統治されすぎない技法』(Jean-Claude Monod, “L’Art de ne pas être trop gouverné“, Seuil, 2019)などか。でも、フーコー的な権力への対峙の仕方を、現代的文脈に置き換えて論じるといった姿勢が、すでにどこか既視感にあふれた、手垢のついたスタンスでしかないように見えて、あまり読書に奮い立たされる感じがしない。現代における統治の問題は、統治機構そのものが市場経済(というか市場というよりは企業ということだが)に従属してしまい、統治者もまた少数の特権的なエリート集団と化してしまっていること。そのために、近年の各種の対抗運動も、「このように統治されるのを自分たちは望まない」という叫びに変質していることを見てとっている。この見立ては正鵠を射ているだろうけれど、それにしても危機的状況に際して生じている反動として列挙される対抗運動の数々は、いずれもおのれの立脚点とすべき概念なり理念なりを、まだ十分に手にしていないとされる。もちろん前回に触れたドンズロのように、そうした概念・理念がまた新たな分裂や争議を呼ぶようなこともあるだろうし、そもそも概念化はある種の制度化を伴うわけであるし、カオスとなった運動の熱が冷めていくときに生じる事柄については、より精緻な分析が必要かもしれない(ただしそれは、ある意味とても退屈な作業かもしれないのだけれど)。
「見・聞・読・食」カテゴリーアーカイブ
概念は分裂を呼ぶ……
すっかり形骸化してはいるものの、5月1日はメーデー。これに向けて(というわけでもなかったのだけれど)、少しばかりフランスの社会史・政治史に絡んだものに目を通しているところ。さしたあり見ているのは、ジャック・ドンズロ『社会的なものの発明』(真島一郎訳、インスクリプト、2020)。まだざっと3分の2ほど。原書は最初の版が84年刊、底本になっているものが94年刊。
これが面白いのは、一つの概念の導入が、ほどなく両義的な意味合いに分裂し、相互にせめぎ合うようになるという視点を一貫して保ちながら、そうした概念の歴史的な展開を分析していくところ。メソッド的に一貫している、ということか。まず最初の章では、「社会的なもの」の成立をめぐる分析が展開するが、そこでは、社会的なものの合意の内部に分裂をもたらすことが問題とされる。「社会的なもの」というのはそもそも本来的に欠損しているのだが、そこになんらかの概念を打ち立てて社会の体制の説明付けを行おうとするがゆえに、それは共有されもするが、同時に対立の芽をはぐくむことにもなる……。たとえばルソーの社会契約のモデルは、ルソー本人への評価とは別に、共和主義、社会主義の双方の拠り所となっていたという。しかしながら1848年に国家そのものが問題になると、その契約モデルのほころび(国家や経済への考察の不備)が露呈し、中央集権的な立場と無政府主義との衝突が激化する事態を招いてしまう、と。
続いて今度は、そうした衝突を背景に出てくる連帯の観念が取り上げられる。中心となるのはデュルケムの社会分業論。デュルケムは契約の発展のそもそもの由来を、相互依存の社会的事象、社会の有機的連帯に見て取るが、個人と社会との関係性の問題はその後も熾烈な対立をもたらしていく。国家の役割を拡張するかどうかについての賛否をめぐる論争は、どちらも連帯の観念に依拠したがために、止揚への道を逆に絶たれてしまったのだ、と。「連帯の観念さえあれば終止符を打てるとみなされてきた論争を、当の連帯観念がこうして再燃させていく」。反復されるこの構図。
さらに続いて出てくるのは、社会法をめぐる議論。とくに労災問題の解決策として出てきた保険技術だ。デュルケムの分業論やそこから導かれる連帯論を実現するとされた保険技術は、社会法によって規範化されることで、企業主と労働者の関係を賃金交渉にのみ位置づけることを可能にし、一方で労働組合も社会的合理性を持ち出して要求を拡充することが可能になったという(1920年代)。しかし一方でそれは、社会的なものと経済的なもののいずれか一方の合理性のみを押し通そうとする勢力をいっそうはぐくみ、再び国家問題を中心に、介入の役割についての対立をあおることにもなる……。
この後、さらに60年代、70年代の新左翼、改良主義運動、の話などが続く。
批評の捉え方
今週はこれを読んでいた。ノエル・キャロル『批評について――芸術批評の哲学』(森功次訳、勁草書房、2017)。キャロルは分析美学の泰斗にして、芸術・映画の批評も手掛ける研究者とのこと。その大御所が同書で示すのは、自身の批評観であり、批評というものの一般的な「構え方」。それはとてもシンプルかつオーソドックスな(ある意味古風でもある)立場で、「批評とは作品の価値づけのためになされるもの」というものだ。さらにそのためには、価値づけに際して批評家はその理由を示せるのでなくてはならない、とされる。さらにまた、そこでいう価値づけとは、作品を通じて作者が何をなそうとしていたのかという、人工物における意図を問題にして評価されるのでなくてはならない、と。
なるほどこれは、ポストモダンな「作者の死」や受容価値の理論(とキャロルは述べている)などの対極にあるスタンスだ。それだけにキャロルに対する批判もいろいろ出てくることが予想される。訳者があとがきに記しているけれど、実際に批評活動をしている人たちから、一種の拒否反応が示されることもあるという。思うにそうした反応が出るのは、意図主義的なスタンスが強調されてしまうことで、作品をめぐる解釈の多義性、枠組みにとらわれない豊かさなどを、つかみ損ねてしまうかもしれないからだろう。実際同書の中でも、たとえばカルトムービーとして先ごろ再上映されたエド・ウッド『プラン9・フロム・アウター・スペース』への好意的な評価(「SFジャンルのお約束を暴露している、時代反抗的な策略」)に、キャロルは真っ向から批判を加えている。そのような評価は、キャロルからすると、その手の作品(キャロルはこれを激怒に値する茶番であると評している)を観客はどうしたら楽しめるのか、という一点張りの評価にすぎず、批評家が本来的に関心を向けるべきこと、つまり、しかるべき情報や知識をもっている観客が、そうした知識を前提として味わう経験、すなわち「芸術的卓越の追跡」とはなんの関係ももたない、と断じている。なるほど知的達成には、それなりの手順と認識が必要だというわけだ。
けれども、すると複線的な価値観、多重的な構成、別様の可能性など、「多」に開かれる道が、部分的にふさがれることになってしまわないのだろうか、という疑問も沸く。一定の規範から逸脱したものを、下らないと断じてしまう傾向や身振りを、たやすく醸成することにはならないのだろうか。そのあたり、同書がどのような対応を見せてくれるのかが気になるところだが、どうやら末尾のあたりに、その回答めいたものが示されている。批評の判断基準となる原理を、あまり一般性の高くないものに設定する(たとえば対象範囲を芸術一般ではなく、一部の形式やジャンルごとに限定するなど)ことで、そういった固着的な事態をも回避できるということらしい。キャロルはみずからの立場を、「多元カテゴリーアプローチである」と高らかに宣言している。でもそれって、なんだかすごく肩透かしを食わされたような気分……??
ソール・ライター
今日は雑記。コロナ禍の影響で当初の開催予定よりも少し早く終了してしまい、行きそびれてしまった東急文化村でのソール・ライター展。せめてもの埋め合わせにと、一応公式の図録も兼ねているという作品集を入手してみた。『永遠のソール・ライター』(小学館、2020)がそれ。ソール・ライター(Saul Leiter)は20世紀の写真家・画家。写真は、とりわけガラスなどを通じた被写体へのアプローチなどが有名だ。ピントがそのガラスのほうに合っていたりして、絶妙なぼかしの表現が味わい深い。被写体を直接撮るというような場合でも、どこかに近景の何かをかませて、ぼかしを巧みに取り込んでいる。見る側の視点がどこかはぐらかされるようでもあるが、それでいて視覚のある種の名状しがたい真実(文字通り「写」真である)を切り取っているかのようで、個人的にはとても惹かれるものがある。近景と遠景のはざまをさまよう視線、余白・奥行き・手前の果てしないせめぎ合い(?)。そのせいか、ライターの作品群はときに不安的ながら、ときに躍動的・リズミカル・動的なものを感じさせもする。図録は実に多くの作品を掲載していて圧巻でもある。
今年の年越し本から
明けて2020年。今年もぼちぼちと本ブログを記していこう。年末年始に読む本を個人的に「年越し本」と称しているが、今年も何冊かに目を通している。まず、これはなかなか痛快な一冊。小川さやか『チョンキンマンションのボスは知っている』(春秋社、2019)。アングラ経済のフィールドワークを手掛ける人類学者が、香港のタンザニア人移民コミュニティの実態を豊かなエピソードを交えて活写するというエッセイ。どこか飄々として、いい加減にも見えるゆるい行動の背後から、普通の売買などとは別様のシステムが浮かび上がってくる。
互酬制というと、どうしても贈与の相手との直接的な相互のやりとりを連想してしまいがちだけれど、そこでの「ついで」としての助け合いや贈与は、その相手からの直接的な対価を期待したりはしない。報酬は別の筋から、回りまわってもたらされるのだ。誰かが「負い目」を感じることのないように、「負い目」は広く共有され拡散されている。そうした相互扶助の上に、彼らは市場交換の仕組みを築いているというのだ。そのための基本的な条件となる買い付けの情報などはオープンにされていなくてはならない。かといって相互の競争を制限することがあってもならない。誰もが仲間としてゆるく連携しながら、個々の利益のためにしのぎを削る、というわけだ。「金は天下の回りもの」を地でいくこのゆるやかなシステムは、硬直し歪んだ寡占的な商業関係へのオルタナティブとして、批判力に満ちているように見える。決して発展途上国的な限定的体制ではない。
*
 もう一冊の年越し本は、アルナルド・モミリアーノ『古代ギリシアにおける伝記の起源』(71年刊)の仏訳本(Arnaldo Momigliano, “Les origines de la biographie en Grèce ancienne”, Circé, 1991)。モミリアーノ(1908 – 1987)は古代史、とくに史料編纂の研究を手掛けた歴史学者で、同書は邦訳もあったはず(『伝記文学の誕生』)。昨年の夏くらいに朝日の記事か何かがきっかけで、ツィッター界隈でやたらと言及されていたのが印象的だった。今回は仏訳版の古本を最近入手したので、これをざっと読んでみているところ。
もう一冊の年越し本は、アルナルド・モミリアーノ『古代ギリシアにおける伝記の起源』(71年刊)の仏訳本(Arnaldo Momigliano, “Les origines de la biographie en Grèce ancienne”, Circé, 1991)。モミリアーノ(1908 – 1987)は古代史、とくに史料編纂の研究を手掛けた歴史学者で、同書は邦訳もあったはず(『伝記文学の誕生』)。昨年の夏くらいに朝日の記事か何かがきっかけで、ツィッター界隈でやたらと言及されていたのが印象的だった。今回は仏訳版の古本を最近入手したので、これをざっと読んでみているところ。
ギリシア世界で「伝記」といえば、たとえばプラトンやクセノフォンによるソクラテス伝が思い浮かぶが、当然ながらそうした伝記文学の起源はソクラテスではない。で、それが成立したのかを、史的な流れから紐解こうというのが同書。話は前5世紀に遡り、どうやら古代ギリシアの貴族階級が家系図の作成に拘っていたことや、神話の英雄たちや、いわゆる「ギリシア七賢人」(前6、7世紀の知恵者たち)へのコンスタントな関心などが源流となっていたようだ。ただこの流れはいったん終息し、前4世紀になると、新たに哲学や雄弁術の諸学派が人物についての語りの技法をゼロから発展させていくのだという。プラトンやクセノフォンを含むソクラテスの弟子筋もそうした流れの中にあった。クセノフォンのモデルを提供したのは、ソフィストとして糾弾されたイソクラテスだったりもした。ほかに伝記文学の成立に重要な貢献を果たした人物として、アンティステネスやテオポンポスが挙げられている。
もちろん彼らは、現実と虚構とをごちゃまぜにして記述を進めていくのだが、それでもそこには確かに伝記文学、さらには自伝の萌芽があった。けれども、人物の生涯について真正の事実を集めることを重視したのはアリストテレスとその一派になってからだった。ヘレニズム期の伝記文学を考案した人物として重要視されているのは、アリストテレスの弟子筋の一人、アリストクセネスだったとされる。一方、同じくヘレニズム期の自伝の伝統を担ったのは、ほぼ政治家に限られ、プロパガンダや自己弁護のための手段として用いていた……。要約してしまうと平坦な印象になるかもしれないけれど、なるほどモミリアーノは、方法論的にも、学知への真摯な姿勢でも、また博学ぶりでもなかなか興味深い。ほかの著書も探してみたい。
……そういえば年末に、同じくギリシア関連で、ピエール・アドの初の邦訳が出たようだ。これは嬉しいかも。そのうち見てみることにしよう。



