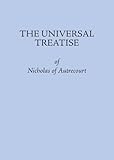こちらも間が空いてしまったが、同じく粗訳(今回はπάσχωに当てる訳を変えてみた)。イアンブリコスが説く天の秩序は、下から魂、半神、ダイモン、と続いていることがこの箇所からも分かる。その上に神々が君臨する。
* * *
(3.3 続き)
上位の存在のうち末端の種族、すなわち魂については、パトスへの参与はありえないことを私たちは示したが、そうなると、なにゆえにダイモンや半神にそれを結びつけなければならないというのか?それらは永続するし、すべてにおいて神々に付き従い、神々の秩序づけのイメージをなし、その維持に努め、神々の階級を温存し決してそれを離れることがないというのに?というのも、おそらく私たちは知っているからだ。パトスとは無秩序、不協和、不安定のことであり、まったく自立しておらず、それを支配するものに従属し、生成のためにその奴隷となるのだということを。パトスは、永続し神々の階級に属して神々とともに周回運動を果たすものたちよりも、それ以外の種族にいっそう相応しい。したがってダイモンも、また上位の存在のうちそれらに続くものたちもパトスの影響を受けることはない。
また間が空いてしまったが、とりあえず粗訳。形相的概念と対象的概念のペアにはいろいろなヴァリアントがあるようで、今回の箇所はフランチェスコ・シルヴェストリ・ダ・フェラーラ(1474-528)による区分が取り上げられている。シルヴェストリはイタリアのドミニコ会士で、トマスの『対異教徒大全』の注解書で知られる人物とのこと。
* * *
3. 第二の見解はむしろ前述の見解の説明になっているが、それはフェラーラ(フランチェスコ・シルヴェストリ)の『対異教徒大全注解』第一巻三四章のもので、二つの概念を区別している。フェラーラは一つを名称的概念と称し、もう一つを事物的概念と称している。彼は前者を、存在するものの概念の一つでありうると述べ、一方の後者は少しもそうではないとし、両者とも存在の類比にもとづくものとしている。また、そのような在り方を、共通する類比の考え方から説明づけている。類比は二つの意味で理解されうる。一つは、名称によって意味づけられる実際の固有な概念の場合である。この場合、類比とされる限りにおいて、実際の概念を一つではなく複数有している。そのことは類比的な比例関係でも、比例関係もしくは帰属関係の場合と同様に明らかである。たとえば今、「笑っている」という言葉を聞いて、意味される事物の固有の概念が形成されるとするなら、それは一つではなく二つの概念となる。一つは固有性および形として笑っている人物の概念である。もう一つはなんらかの比例関係のみによってそのように称された、野獣の概念である。仮にこれらの概念の両方ではなく、一方のみが形成されるとするなら、類比の全体にもとづいてその言葉が理解されることにもならないし、事物を指す共通の意味にもとづいて理解されることにもならず、単に人間を一義的に表すだけか、あるいは単に意味を移しかえただけで、隠喩的に野獣を意味するかのいずれかでしかない。帰属関係の類比の場合も同様である。「健康な」を例に取ろう。意味される事物に固有の概念が形成されるのであるなら、それは単一ではなく複数となる。一つは、形および固有性において健康であるような動物の概念である。もう一つは、様々な慣例もしくは呼称によって動物の健全さについて外的に健康と称する場合の、他の事物の概念である。だがいずれの場合でも、その類比からは、事物よりもむしろ言葉の意味を表す一つのきわめて不明瞭な概念が形成されうる。「健康な」という言葉を聞いて、健全さへの秩序を理解するような場合である。目下示している場合でなら、「存在するもの」という言葉を聞くことで、なんらかの存在があること、あるいは存在への習性があることを表す、不明瞭な概念が形成されうるのだ。だがこれは名称的概念であるにすぎない。一方、実際にその名で意味される事物が概念化されるのであれば、形成されるのは一つではなく複数の概念ということになる。
Olivier Boulnois, Le refoulement de la liberté d’indifference et les polémiques anti-scotistes de la métaphysique moderne )というもので、少し前に取り上げた『レ・ゼチュード・フィロゾフィック』のスコトゥス主義特集の続きにあたる巻(Etudes philosophiques 2002 no.2 Duns Scot au dix septième siècle
そもそも、意志があからじめ決定されているか、それとも中立的に自由であるかという議論は、トマス対スコトゥス、さらには後のトマス主義対スコトゥス主義(17世紀)の対立に引き継がれていくものでもあった。両者の論争の発端は、14世紀にトマス・ブラッドワーディンが「神は、人間の意志が自由な行動を生み出せるようそれを強いる」というテーゼを打ち出した(反ペラギウス主義的な議論の文脈で)ことにあるという。けれども、そこで再燃した論争はトマス&スコトゥス本来の論争とはズレていて、主知主義か主意主義かという枠ではなく、意志は神による恩寵に導かれる(決定づけられる)のか、それとも中立的な自由を内包しているのかという議論にシフトしてしまっている。イエズス会、とりわけモリナ主義は、神による人間への協力が人間の意志の本来的な中立性を損なうことはないとして、中立的自由を重んじる。対するトマス主義者たちはというと、たとえば代表的なところとしてギヨーム・ジブーフ(デカルトの友人だ)が挙げられているが、自由というのは幅(amplitude)として定義されるとし、中立的自由などというのは偽の議論であるとして、意志が神(=善)による決定に従属しているとの立場を前面に押し出す。ジャンセニズム(の始祖ヤンセン)ともなると、ジブーフをさらに急進的に捉え先鋭化する……。
こうした背景のもとでデカルトが論じられる。1630年ごろのデカルトはジブーフの自由の理論に賛同していたといい(メルセンヌに書簡でそう告げているのだとか)、後の『省察』でも、自由とは外部からの決定づけがないことを言うが、だからといって至高の存在である神、あるいは真や善といったものの明白な理解(それは至高の内的な傾向だとされる)によって決定づけられないわけではない、としている。ところが1645年頃のメラン宛の書簡では、むしろ意志の中立的自由のほうを重んじたような記述があるという。また1644年の『哲学原理』では、原因の必然性(神が収める世界の)と人間の自由の感情とをどう折り合いをつけるかというアポリアで身動きがとれないかのようだ。デカルトの後継者たちの立場も、そのあたりの曖昧さへの反応から、たとえばジャンセニズムやカルヴァン派のデカルト主義者たちは決定論に傾き、アルミニウス派やジャンセニズム以外のカトリック系デカルト主義者たちは中立論を重んじと、各者各様に異なっていく……。この錯綜感はなにやらとても刺激的だ(笑)。
ジョイス・ソールズベリー「動物は天国に行くか−−天上の人間例外主義を観想する中世の哲学者たち」(Joyce E. Salisbury, Do Animals Go to Heaven? Medieval Philosophers Contemplate Heavenly Human Exceptionalism , Athens Journal of Humanities & Arts , 2014 )という小論を読む。キリスト教は長い間、動物には理性がないとして救済の対象から外してきたわけだけれど、その考え方自体は実は一枚岩ではなく、意外に豊かなニュアンスに富んでいるらしい。その多様な議論について大まかな見取り図を示してくれているのが同論考だ。救済を人間のみとするとする立場は、アウグスティヌスをはじめとし、きわめて長く継承されてきた。けれども、たとえば中世盛期などには、そのためにいろいろな考察が巡らされることにもなった。たとえば羊が狼を見て逃げるという現象について、羊の反応が理性的な思考ではないことを示すべく、「推測(estimativa)」という第六感を仮定したり、内的感覚の議論が追加されたりもしたという(このあたりはアヴィセンナなどがもとになっているらしい)。動物に魂を認めつつも理性を欠いているとするよりも、端的に動物には魂がないとするほうが、たとえば幼児や狂人の救済との矛盾が少ないとされたりもした。天上世界には理性的魂をもった人間しかいない、というわけだ。
けれども、と論文著者は言う。初期のキリスト教においては事情は少し違っていて、天国には、地上世界の肉体とは違う精神的な肉体を纏ってもっといろいろなものが住んでいるとされていたのだという。かくしてそれは復活後の肉体がどのようなものかという議論を促した(代表的なところとして、オリゲネス、キュリロスのほか、ヒエロニムス、テルトゥリアヌスなどのそれぞれの論が簡単に挙げられている)。13世紀になると、地上世界の動物と人間との関わりが問題とされ、人間が動物の肉を食することが、動物が天上世界に赴く方途であるという考えすら生まれてくるのだとか。さらには、動物が分解し消費した人間の肉が、復活の日に再び集められてもとの肉体を再構成するという説もあったといい、11世紀のトルチェッロの聖堂には、動物たちがかつて食べた人間の身体部分を、復活の日に吐きもどす場面の絵があるのだという。
天に動物が住まうかどうかは、さらに天上世界をどのようなものとして描くかにも関係してくる問題だという。初期キリスト教では天上世界は都市国家として思い描かれていた。一方でより世俗的なイメージでは楽園として描かれたりもし、そうなるとそこに住まう木々や動物たちが必要となってくる。かくして「動物に魂はない」とする支配的な知識階級の見識と、世俗的な享楽を欠いた天国を思い浮かべることができない大衆的な曖昧な見識との間の溝が広がっていく。かくして中世においては、天上世界を地上の完成形と見、あらゆる生き物が変容を遂げて相互に連関し、改めて住まうといったヴィジョンが登場する。つまりは初期キリスト教の見方が形を変えて再浮上したということだ。なるほど、確かに動物をめぐる諸説、あるいはイメージャリーはいろいろありそうで興味は尽きない。
トルチェッロ聖堂のモザイク画。わかりにくいが、おそらく上から二段目の右端が動物が吐いている描写(たぶん)
The Universal Treatise of Nicholas of Autrecourt (Mediaeval Philosophical Texts in Translation) Nicholas of Autrecourt: His Correspondence With Master Giles and Bernard of Arezzo : A Critical Edition from the Two Parisian Manuscripts With an in (Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters) )のだけれど、うーむ高額……)。とはいえ、こちらの『世界論』でも、アリストテレスやアヴェロエスなどの権威に異論を差し挟み、世間的に認められた教説に疑い目を向け、より一貫性のある教説を求めるという姿勢が貫かれている。同書の最も重要な教説はというと、本文の第一序文第二部にある「あらゆるものは不滅である」というテーゼなのだという。ニコラの教説の大枠はこんな感じ。世界は善であり、事物はすべてあるべき形で配置されている(当然、製作者としての神の意志による。さもなくばすべてはカオスでしかなくなる)。それらは相互に結びついており、全体としてつねに同じ善性を維持している。ここで何かが失われ減じるとすると、善性もまた減じてしまう。いちどそうなってしまえば歯止めも利かず、カオスへと落ちていってしまう。そうならないために、善性は常に不変でなくてはならず、したがってすべてのものは永遠に存在するのでなくてはならない……。
ニコラは、こうした教説のほうがアリストテレスのものより世界の正当性をよりよく擁護できると考えている。この永続性を支えているのが、目に見えない原子という考え方だ。事物が滅するように見えるのは感覚がそれらの存続を捉えきれないからだとされ、一方で知性は善の考察などからそうした不滅思想を導くことができるとされる。さらには輪廻的な考え方すら言及される。人間には感覚と知性という二つの精気が存在するといい、それらは身体の死後も存続して別の原子の集積に加わることができる、というのだ。ただしニコラは、これすら「蓋然的に」そう結論づけられるだけだとし、ここでも懐疑論を貫く。このような教説だけに、当時の教会関係者からは当然ながら問題視され、最終的に同書は焚書扱いとなったようだが、先にも触れたように、ニコラのその後の教会での立場にとって、その糾弾は比較的軽微な損害しか与えていないように見える。うーん、これはどういうことなのだろう……?
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ