警察小説の枠組みを問う?
このところのkindle本、立て続けに「反警察小説」みたいなものを読んでみました。
まずはチェスタトン『木曜日だった男』(南条竹則訳、光文社古典新訳文庫、2008)。

チェスタトンといえば「ブラウン神父シリーズ」や「知りすぎた男」など、中短編で有名な作家ですが、いくつかある長編の一つが1905年の『木曜日だった男』なのだとか。これ、警察小説的な枠組みを借りてはいるものの、一種の冒険譚で、ある意味荒唐無稽な「バカ話」(良い意味でです)になっています。個人的にはにんまり笑ってしまいました。
続いて今度は久々にヌーボーロマン。アラン・ロブ=グリエ『消しゴム』(中条省平訳、光文社古典新訳文庫、2014)。
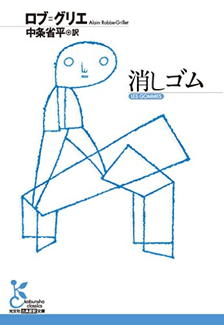
こちらは、1953年刊行のロブ=グリエの初期作品。昔結構好きだったヌーボーロマンの類も、最近はほとんど読んでいなかったのですが、推理小説的なやつがあったっけなあ、と思って、今回じっくり味わってみました。こちらは登場人物たちの様々な推測・憶測が、様々に事件を組み立ててしまう(読む側も、自分で組み立ててしまいますね)様子を、端正な文体で見事に描き出しています。いいですね、これ。
警察小説は枠組みとして、いろいろと「遊べる」ものだということを、どちらの作品も改めて認識させてくれます。