ジャケット絵はパリのルーヴルにあるシャルル・ポエルソンなる画家の『キリストの降誕』とのこと。こちらのルーヴルのページ をどうぞ。シャルパンティエのほぼ同時代人らしいけれど、詳しいことがよくわからない。そういえば、シャルパンティエもその生涯は微妙にわかっていないとかいう話だったっけ?うーむ、謎が多いねえ。
“Peter Lombard”, Oxford Univ. Press, 2004 )なんてのも出しているのだけれど、今度はさらにその注解の歴史を大まかに辿るという一冊が出ていた。『ある偉大な中世の書の物語–ペトルス・ロンバルドゥスの「命題集」』(“The Story of a Great Medieval Book – Peter Lombard’s Sentences”, Broadview Press, 2007 )。12世紀から15世紀までの「要約本」や「注解」などを書物史の観点からまとめている。とりあえず前半の12世紀と13世紀のところを読んでみたのだけれど、なるほど、『命題集』は書物史的にもとても重要なのだそうで、同書そのものが、欄外の「脚注」の嚆矢をなしているのだという。また目次が付されているのも画期的なことだったようだ。『命題集』そのものにも、最初の版のほかに増補版があるようで(ロンバルドゥス本人が記したもの)、さらに、直後から出ていたという要約本から、逐語注解を経て13世紀の自由討論風の注解(ボナヴェントゥラやトマス・アクィナス)へといたる経緯を追うと、神学が修道院や司牧の関心から遊離し、学として確立していく過程が追えるということにもなるらしい。うーん、書物史もやはり面白いねえ。13世紀に神学の講義に『命題集』を使うようになった嚆矢として、ヘイルズのアレクサンダーが重要だというのも、個人的にちょっと押さえておきたいポイントかも(笑)。
Πᾶν τὸ γεννῶν τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ χεῖρον ἑαυτοῦ γεννᾷ, καὶ πᾶν τὸ γεννηθὲν φύσει πρὸς τὸ γεννῆσαν ἐπιστρέφει· τῶν δὲ γεννώντων τὰ μὲν οὐδ᾿ ὅλως ἐπιτρέφει πρὸς τὰ γεννηθέντα, τὰ δὲ καὶ πρὸς ἐκεῖνα ἐπιστρέφει καὶ πρὸς ἑαυτὰ, τὰ δὲ μὸνον ἐπεστραπται πρὸς τὰ γεννήματα εἰς ἑαυτὰ μὴ ἐπιστρέφοντα.
みずからの本質によって生み出すものはすべて、おのれに劣るものを生み出し、生み出されたものはすべて、その本性により、生み出したものへと向き直る。生み出すものには、生み出されたものへといっさい向き直らないものもあれば、そちらに向き直ったりみずからに向き直ったりするものもあり、生み出されたものにのみ向き直り、みずからには向き直らないものもある。
『クーリエジャポン』の2月号 を見ていたら、森巣博「越境者的ニッポン」という連載で、枕部分に、ネオコンに通底する考え方としてサッチャーの言葉だという一句が引かれていた。「社会なんてものは、ない。あるのは個人と家族だけだ」というのがそれ。うーん、びっくり(笑)。そんなことをノタまっていたとは知らなかったなあ。なるほどこれは通俗的な意味での「唯名論」だ。これがネオコン思想に結びつくというのは合点がいく。自己だけがすべてであとは存在しないというわけか。まあ、もちろん唯名論的には、ごくごく大雑把なもので(だから通俗的というわけなのだが)、「オッカムの剃刀」をご都合主義的に適用し、恣意的なサイズでふるってみせているわけだけれど、やはりこういうのは同じ唯名論的な視座からも批判されなくてはならないだろうなあと改めて思う。そう、もう一段ギアチェンジをして、「個人なんてものすらもしかしたらないかもしれない、あるのはある種のプロセスだけかも」とするとかね。ここで通俗は通俗なりに、実在論的な反転(ドゥルーズの通俗版のような)が生じうるというわけで(笑)。
……とそういうふうに記してハタと気がつくのは、昨日の『イカの哲学』にあった「エロティシズム態」なる用語で語られていたものが、その通俗的な実在論的反転に重なってくるということ。他の生命をモノとか商品とかに還元しない方便というのは、声高に「生命の尊重」みたいなことを唱えるという平常態的対応もあるだろうけれど、もう一つ、案外そういう通俗的唯名論の反転の方途もあるかもしれないあなあ、なんて。あらゆるものをモノ・商品と捉えると、さしあたり自分までもがその範疇に入ってしまい、あらゆるものが売り買いのトランザクションでしかなくなり、さらにその売り買いを見据えるなら、不思議とそこに流転する流動体のようなプロセスが見えてきたりして、すべてが流れの中にあることがわかり、まるで同じ一つの生命現象のように重なって見えてくる……とかならないもんだろうか。いやいや、これはいわば「エロティシズム態」的妄想ですけどね。うーむ、さてそろそろ平常態に戻るとしようか……(笑)。
『イカの哲学』(集英社新書) を読む。波多野一郎という若くして没した哲学者の哲学的寓話『イカの哲学』を、中沢新一が「解説」するという一風変わった作りの体裁。そのもとの哲学的寓話は著者(波多野)の体験記にもとづくもので、特攻経験を経てアメリカに留学していた日本人学生が、バイト先の水産加工場で陸揚げされたイカの群れを目にしたのをきっかけに、ある種の平和思想に目覚めるというもの。「解説」(?)部分はこれにある種の現代思想風なリファレンスを絡めることによって、そこから大きな「平和学」を取りだそうとするのだが、これがまた注釈・注解を超えて、もとの『イカの哲学』に触発された別様の哲学的寓話になっている感じ(笑)。とりわけ鍵となるのが、援用されるバタイユのエロティシズム論。生き物に内在する、個体を超えようとする連続性の原理を「エロティシズム態」として、個体の維持にのみ奔走する「平常態」と対立させ、両者のせめぎ合い・相克から新しい平和への視座を見つけようとする。なるほど多少論理の飛躍もなきにしもあらずだけれども、「実存の相互理解」といった単純・素朴ながらとても難しい問題を突きつけるというスタンスはちょっと情感に訴えるものもある。それになにより、こうした「埋もれたテキスト」を現代思想風の語りで掘り起こすというのは、企画としてもっと色々あっていいような気がする(笑)。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 ちょっと季節的に一ヶ月ほどずれてしまうけれど(笑)、マルク・アントワーヌ・シャルパンティエのクリスマス・カンタータ集を購入し、このところ聴いている。
ちょっと季節的に一ヶ月ほどずれてしまうけれど(笑)、マルク・アントワーヌ・シャルパンティエのクリスマス・カンタータ集を購入し、このところ聴いている。”Noel” – M.A.Charpentier: Christmas Cantatas / Kay Johannsen, Ensemble 94, Solistenensemble Stimmkunstという一枚。なかなか端正で落ち着いたパフォーマンス。シャルパンティエはイタリアでカリッシミに師事したといい、その功績としてはイタリアで盛んだったオラトリオ形式をフランスに紹介したことにあるというのだけれど(ライナー)、17世紀のフランスでこれを受け継いだ者はいなかったのだそうで。曲そのものもいいけれど、なにやらそういう孤高な境遇とかにも惹かれるものがあるかも(苦笑)。
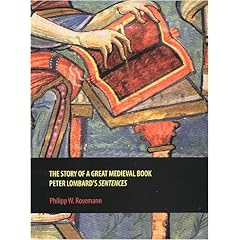 以前『フーコーで学ぶスコラ哲学』を取り上げたことのあるフィリップ・W・ローズマン。この人のフィールドはペトルス・ロンバルドゥスなのだそうで、その有名な『命題集』の内容を一般向けに解説した『ペトルス・ロンバルドゥス』(
以前『フーコーで学ぶスコラ哲学』を取り上げたことのあるフィリップ・W・ローズマン。この人のフィールドはペトルス・ロンバルドゥスなのだそうで、その有名な『命題集』の内容を一般向けに解説した『ペトルス・ロンバルドゥス』(
