前回のエントリーの末尾で触れた、「人間による創造」云々というあたりに、なにやら個人的にこだわってしかるべきポイントを強く感じている(苦笑)。「人間の創造性」についての系譜というのも、思想史的に追いかけ甲斐のあるテーマという気がする。この関連でまず思い出したのは、クザーヌスの『推測について』。前に触れたように、これの仏訳版の解説によると、そこでのクザーヌスは、人間のある種の創造性・豊穣性を前面に押し出しているとのことだった。そういう側面からクザーヌスを読もうと思いつつ、今年はちょっと時間が取れなかった。これは来年の課題の一つ。
 けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。
けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。
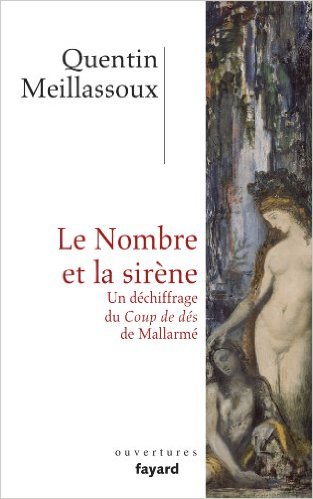
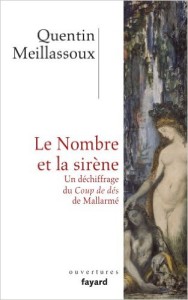 偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。
偶然世界を極限にまで突き詰めるメイヤスーが2011年に問うた『数とセイレーン』(Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, fayard, 2011)。以前の『現代思想』誌で、メイヤスーが神論のほうに向かっているといった話があったけれども、ここではマラルメの『骰子一擲』を題材に、かなり独創的な解釈を通じて、おそらくはそうした新たな神論の一端を垣間見せている。前半はマラルメのその詩が、数をコード化したものであるとしてそのコードを明らかに(?)し、後半は、同時にそのコードには不確定さ・偶然が永続的に刻印されていることを論じていく。前半はなんというか、メソッド的に「トンデモ」感があって、おそらく文学研究的にはかなりの異論があるところと思われ、その強引さにちょっと引いてしまうかも(苦笑)。ここで投げ出してしまう人も少なからずいるだろうなという案配。けれども、同書が面白くなるのは実は後半だったりする。もちろんそのコード解釈は前提をなしているのだけれど、マラルメのそのコード設定(があったとして、それは)は何を目的としているのかという推論が展開していき、結構読ませる。