 オリヴィエ・ブールノア『イメージを超えて – 中世5〜16世紀の視覚の考古学』(Olivier Boulnois, “Au-delà de l’image – Une archéologie du visuel au Moyen Âge Ve – XVIe siècle”, Seuil, 2008)を読み始める。仏語で言うところの「イメージ(イマージュ)」は内面的な想像力から外部の絵画まで様々な事象を言う多義的な言葉だけれど、これはその多義性をそのままに、中世のイメージの諸側面を広くほ渉猟しようという一冊らしい。まだ二章目に入ったところ。一章目はアウグスティヌスのイメージ論を手堅くまとめていてとても参考になる。ここでの「イメージ論」は「神の似姿としての人間」という聖書の解釈を中心としたもの。そこから「像とは何か」といった問題が切り出されるという次第。で、アウグスティヌスの場合4つほどの点で、先行する教父たちの伝統から隔たった革新的な議論になっているのだという。人間は子(キリスト)にではなく三位に共通するエッセンスに似せられている、とした点が第一点。「像であること」と「似ていること」の区別を廃した点が第二点。「似姿」と「像」を切り離さずに考察していることのが第三点。神の似像とは魂であって、魂と身体の結合体ではないとしたことが第四点なのだという。それぞれの詳しい議論とか、参照されているテキストとか、なかなか興味深いのだけれど、いずれにしてもこうしたアウグスティヌスの革新性というのが、どうやら同書を貫く縦糸をなしていくような気配だ。というわけで、これも読み進めながら面白い点があればメモっていこうっと。
オリヴィエ・ブールノア『イメージを超えて – 中世5〜16世紀の視覚の考古学』(Olivier Boulnois, “Au-delà de l’image – Une archéologie du visuel au Moyen Âge Ve – XVIe siècle”, Seuil, 2008)を読み始める。仏語で言うところの「イメージ(イマージュ)」は内面的な想像力から外部の絵画まで様々な事象を言う多義的な言葉だけれど、これはその多義性をそのままに、中世のイメージの諸側面を広くほ渉猟しようという一冊らしい。まだ二章目に入ったところ。一章目はアウグスティヌスのイメージ論を手堅くまとめていてとても参考になる。ここでの「イメージ論」は「神の似姿としての人間」という聖書の解釈を中心としたもの。そこから「像とは何か」といった問題が切り出されるという次第。で、アウグスティヌスの場合4つほどの点で、先行する教父たちの伝統から隔たった革新的な議論になっているのだという。人間は子(キリスト)にではなく三位に共通するエッセンスに似せられている、とした点が第一点。「像であること」と「似ていること」の区別を廃した点が第二点。「似姿」と「像」を切り離さずに考察していることのが第三点。神の似像とは魂であって、魂と身体の結合体ではないとしたことが第四点なのだという。それぞれの詳しい議論とか、参照されているテキストとか、なかなか興味深いのだけれど、いずれにしてもこうしたアウグスティヌスの革新性というのが、どうやら同書を貫く縦糸をなしていくような気配だ。というわけで、これも読み進めながら面白い点があればメモっていこうっと。
「象徴史・物質論など」カテゴリーアーカイブ
巨匠逝く
うーむ、やはり触れないわけにはいかない、レヴィ=ストロースの死去。その著書には個人的にいろいろ勇気づけられることしかりだった……。深く感謝しなくては。とはいえ、一方ではとりたててすごくfidèleな読者ではなかったかもなあ、という反省も……。最近はとくにそんな感じで、新しい邦訳とかが出ても購入は後回しという状態が続いていた。せっかくなのでbk1で『パロール・ドネ』を購入してみる。bk1はいきなり追悼ページを掲載している。ベルトレの評伝の邦訳や、新書らしい研究書が予約扱いになっているっすね。フランスの方でもたぶんいろいろレトロスペクティブがあるだろうし。ちなみに、フィガロ紙のページに在りし日の氏の映像などが(ブラウザで再生するのはちょっと重たい……フルダウンロードは有料)。
古代における「胚」
 メルマガのほうで見ているインペトゥス理論がらみかどうかと思い、フランスのVrinから去年出た、リュック・ブリソンほか編の論集『胚:形成と生命活動』(“L’embryon – Formation et animation”, éd. Luc Brisson et al., Vrin, 2008)を読み始める。古代から中世にかけて、思想史的に胚(胎児)の形成や活動がどう考えられていたかをめぐる論集。まだ3分の1ほどだけれど、なるほどいろいろと整理されていてためになる。そもそも胚は生命体と考えられていたのかどうか、という点については、プラトンがそれを生命体と考えていたのに対して、ストア派は腹部の一部で生物ではないと(木になる果実のようなものと)見なし、エンペドクレスは呼吸をしていないから生命体ではないとし、セレウコスのディオゲネスはまだ魂を欠いていると考えていたという。ガレノスは種子からして生命体という立場だそうだ(ブドン=ミヨーの論文)。個人的に面白いのはグルニエの論文で、ストア派が魂の形成をどう考えていたかをまとめたもの。それによると胎内の胚はまだ生命体とは考えられていないものの、誕生とともに、ちょうど熱い鉄が冷やされることによって固まる「焼き入れ」のようにして、息吹が性質を変え、かくして魂が形成されるのだという。なるほど、そういえばストア派の魂ってば、物質と一続きだったっけね。それにしても「焼き入れ」の比喩を出してくるとは……(笑)。なにかこの、金属と生命の類比というのは気になるところ。
メルマガのほうで見ているインペトゥス理論がらみかどうかと思い、フランスのVrinから去年出た、リュック・ブリソンほか編の論集『胚:形成と生命活動』(“L’embryon – Formation et animation”, éd. Luc Brisson et al., Vrin, 2008)を読み始める。古代から中世にかけて、思想史的に胚(胎児)の形成や活動がどう考えられていたかをめぐる論集。まだ3分の1ほどだけれど、なるほどいろいろと整理されていてためになる。そもそも胚は生命体と考えられていたのかどうか、という点については、プラトンがそれを生命体と考えていたのに対して、ストア派は腹部の一部で生物ではないと(木になる果実のようなものと)見なし、エンペドクレスは呼吸をしていないから生命体ではないとし、セレウコスのディオゲネスはまだ魂を欠いていると考えていたという。ガレノスは種子からして生命体という立場だそうだ(ブドン=ミヨーの論文)。個人的に面白いのはグルニエの論文で、ストア派が魂の形成をどう考えていたかをまとめたもの。それによると胎内の胚はまだ生命体とは考えられていないものの、誕生とともに、ちょうど熱い鉄が冷やされることによって固まる「焼き入れ」のようにして、息吹が性質を変え、かくして魂が形成されるのだという。なるほど、そういえばストア派の魂ってば、物質と一続きだったっけね。それにしても「焼き入れ」の比喩を出してくるとは……(笑)。なにかこの、金属と生命の類比というのは気になるところ。
インペトゥスがらみでも、アリストテレスの『動物生成論』にちょっと興味深い箇所があることが判明(モレル論文)。また、この後も双子の場合の問題とか、重要著作とされるAd Gaurum(ポルピュリオス?)についてとか、期待値の高い論考が並んでいるようで、なかなか楽しみ。
モノに宿る力とは……
 秋山聰『聖遺物崇敬の心性史』(講談社選書メチエ、2009)を読み始める。とりあえず前半。教会の拡張政策と相まって拡がり、中世の民衆の信仰にまで根を下ろした聖遺物崇拝について多面的にまとめた好著。聖遺物崇拝の起源、史的展開、演出・造形的変遷などが章ごとにつづられている。第二章でアインハルトの奉遷記の内容が細かくまとめられているのが個人的には興味深かった。なるほどすでにシャルル・マーニュの時代に、聖遺物ブローカーのような存在が教会関係者を相手に商売を始めているわけか。アインハルトが、隠棲のために建立していた教会も、思わぬ聖遺物の数々の入手によって大幅に計画修正させられたという話も。時代が下って12世紀ごろの聖遺物容器が人前に出されて、華麗な装飾を施されるようになると、学識者たちが賛否両論の見解を示すというくだりも興味深い。「ほとんど唯一の神学的論考」とされるエヒテルナッハのテオフリートの論というのも紹介されている。天上世界での栄誉にあずかる聖人には、地上でも相応の栄誉をもって扱わなくてはならないという、そうした華美の礼賛論らしいけれど、これなどは原文を読んでみたい気もする(笑)。
秋山聰『聖遺物崇敬の心性史』(講談社選書メチエ、2009)を読み始める。とりあえず前半。教会の拡張政策と相まって拡がり、中世の民衆の信仰にまで根を下ろした聖遺物崇拝について多面的にまとめた好著。聖遺物崇拝の起源、史的展開、演出・造形的変遷などが章ごとにつづられている。第二章でアインハルトの奉遷記の内容が細かくまとめられているのが個人的には興味深かった。なるほどすでにシャルル・マーニュの時代に、聖遺物ブローカーのような存在が教会関係者を相手に商売を始めているわけか。アインハルトが、隠棲のために建立していた教会も、思わぬ聖遺物の数々の入手によって大幅に計画修正させられたという話も。時代が下って12世紀ごろの聖遺物容器が人前に出されて、華麗な装飾を施されるようになると、学識者たちが賛否両論の見解を示すというくだりも興味深い。「ほとんど唯一の神学的論考」とされるエヒテルナッハのテオフリートの論というのも紹介されている。天上世界での栄誉にあずかる聖人には、地上でも相応の栄誉をもって扱わなくてはならないという、そうした華美の礼賛論らしいけれど、これなどは原文を読んでみたい気もする(笑)。
とにかく、聖遺物崇敬が聖職者も民衆も巻き込んだ大きな社会動向となっていたことが様々な具体例から窺える。見た目には時に貧相だったりする聖遺物に、神の力が働く媒体を見るという民衆的想像力。古代からの伝統的な信仰が起源とか言われるけれど、いずれにしても、それってもしかして時代が下ってからのインペトゥス理論のような、ごく自然の力もまた媒体に宿る・温存されるといった考え方の、はるか源流の一つになっているのかもしれないという気もしてきた。うーむ、このあたり、ちょっと検討してみるのも悪くないかもしれない……。
イスラム系の天使論……
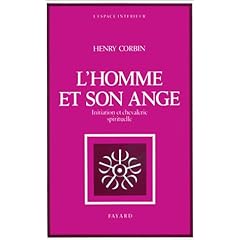 スアレス=ナニの『天使の認識と言語』も少しづつ読んでいるけれど、これまた積ん読になっていたアンリ・コルバン『人間のその天使–霊的イニシエーションと騎士道』(Henry Corbin, “L’Homme et son Ange – Initiation et chevalerie spirituelle”, Fayard, 1983)も引っ張り出して読み始める。うん、コルバンも久しぶり。前に大著『アヴィセンナと幻想譚』を読んで以来か。本書は基本的にコルバンの講演3つ(それぞれ1949、70、71年のもの)を収録したもの。とりあえず最初の1949年の講演は、イスラム教シーア派のイスマエル派に伝わるイニシエーション物語(14世紀以降)を取り上げ、そこに記された西欧のものとは大きく異なる天使像をヘルメス主義の伝統と合わせて論じるというもの。うーん、ここに描かれる天使は、宇宙開闢論なども絡んでスケールが大きい。なにせそれは一種の原・人間であり(アダムよりも先に生まれたとか)、人間がイニシエーションを通じてやがて到達すべき目標としての「完全体」でもあるということらしいので。コルバンはいつもながら西欧の神秘主義にも目配せしつつ論を進めるのだけれど、それにしても西欧の天使は、視覚的な表象は膨大な数に上るものの、シンボリズム(というか意味論というか)の豊かさ・広大さという意味でははるかに見劣りするのでは?逆にイスラム教神秘主義でのこの厚みは、視覚的な表象が乏しいことの裏返しなのかしら(その分、こうしたイニシエーション物語のようなものが隆盛する?)、なんてことも思いつつ、しばらく読み進めることにしよう。
スアレス=ナニの『天使の認識と言語』も少しづつ読んでいるけれど、これまた積ん読になっていたアンリ・コルバン『人間のその天使–霊的イニシエーションと騎士道』(Henry Corbin, “L’Homme et son Ange – Initiation et chevalerie spirituelle”, Fayard, 1983)も引っ張り出して読み始める。うん、コルバンも久しぶり。前に大著『アヴィセンナと幻想譚』を読んで以来か。本書は基本的にコルバンの講演3つ(それぞれ1949、70、71年のもの)を収録したもの。とりあえず最初の1949年の講演は、イスラム教シーア派のイスマエル派に伝わるイニシエーション物語(14世紀以降)を取り上げ、そこに記された西欧のものとは大きく異なる天使像をヘルメス主義の伝統と合わせて論じるというもの。うーん、ここに描かれる天使は、宇宙開闢論なども絡んでスケールが大きい。なにせそれは一種の原・人間であり(アダムよりも先に生まれたとか)、人間がイニシエーションを通じてやがて到達すべき目標としての「完全体」でもあるということらしいので。コルバンはいつもながら西欧の神秘主義にも目配せしつつ論を進めるのだけれど、それにしても西欧の天使は、視覚的な表象は膨大な数に上るものの、シンボリズム(というか意味論というか)の豊かさ・広大さという意味でははるかに見劣りするのでは?逆にイスラム教神秘主義でのこの厚みは、視覚的な表象が乏しいことの裏返しなのかしら(その分、こうしたイニシエーション物語のようなものが隆盛する?)、なんてことも思いつつ、しばらく読み進めることにしよう。