震災と原発事故で改めて明らかになったことの一つに、避難を余儀なくされた人々が郷里から遠く離れようとはしないという全体的な動向がある。震災後に、被災地から遠い各県がいろいろな施設を用意したと聞くが、中にはほとんど入所希望が出なかったようなところもあったらしいし、退避勧告が出た原発近くの住民には、それでもなお地元で暮らし続けようとしている人もいるという。もちろん直接的理由は様々だろうけれど(世話をしている家畜を見捨てていけない、よそに行っては仕事がない、などなど)、大きな括りとしてはどこか漠然とした「離郷に対する抵抗感」があるように見える。これは一体どういうものなのか。これを郷里への執着として理解しようとすると、なにやら感情論や審美的判断のように見えてしまうのだが、そう考えることにどこか違和感を伴うのもまた事実だ。疎開論もどこか違うという感覚を覚える。これはどういうことなのか。
なにも罹災者に限ったことではない。田舎に暮らす老親を都会に住む子ども世代が引き取ろうとするような場合でも、同じような抵抗に遭う場合がある。たいていは一般論として、老人特有の頑固さのせいで地元への執着が高まる、みたいな話に帰着させてしまうのだろうが、これもそれだけではないような気もする。問題はもっと細やかな理にあるようにも思われる。つまり、土地勘という名称で呼ばれているある種の認識形態・認識プロセスが、そこに大きく影響している可能性があるのではないか、と。それはおそらく情動的なものと、なにがしかの記憶、隠微な合理性などが入り組んだプロセスで(ある種のアフォーダンス?)、だからこそ見知らぬ土地に放り込まれてしまうと、そうしたプロセスの不全が反動的な不安となって襲ってくるのではないか……。この「土地勘」みたいなものは、詳細に分析する必要がありそうだ。震災後の復興において、それは一つの鍵になるかもしれないからだ。首相が提唱しているらしい沿岸都市のあり方とかエコタウン構想などが、どこか机上の空論に終わりそうな、微妙な「よるべなさ」を醸し出しているのも、そのあたりに理由を見いだせそうな気がするのだが……。
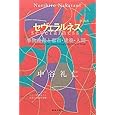 復興ということで言えば、中谷礼仁『セヴェラルネスPLUS – 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)所収の「先行形態論」という論考は示唆的だ。これは、都市の発展がそれ以前の形を無意識的に踏襲するというどこか「無意識的」な動きについて議論を展開したもので、具体例として原爆投下後の広島を取り上げており、一種の復興論としても読める。それによると、戦後の広島の街路計画に一見すると新設根拠が不明瞭な道路があるのだという。ところが時間を遡ってみると、これが計画者ら自身も自覚していなかった近世の市街地と新開地との境界にほぼ一致していたという。同じく区画整理においても、それまでの市街地の無計画性を取り除くことで、近世期の町割りと親和性のある形態ができあがったりしているのだとか。これらはもしかすると、上のような「土地勘」のような合理性を示す一種の事例かもしれない。一方でヤミ市がその時々の交通の要所に誕生し、都市の転用としてシステム全体の再定義を促したともいう。こうした回帰と再定義の動的なプロセスが、おそらく今回の各被災地でも見られていくことだろう。一方で、もし原発事故で完全に郷里を追われる人々が出てくるならば、新たな都市の創成プロジェクトは回帰しなぞるべき参照系がないだけに、いっそう多くの困難を強いられるのではないだろうか。
復興ということで言えば、中谷礼仁『セヴェラルネスPLUS – 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)所収の「先行形態論」という論考は示唆的だ。これは、都市の発展がそれ以前の形を無意識的に踏襲するというどこか「無意識的」な動きについて議論を展開したもので、具体例として原爆投下後の広島を取り上げており、一種の復興論としても読める。それによると、戦後の広島の街路計画に一見すると新設根拠が不明瞭な道路があるのだという。ところが時間を遡ってみると、これが計画者ら自身も自覚していなかった近世の市街地と新開地との境界にほぼ一致していたという。同じく区画整理においても、それまでの市街地の無計画性を取り除くことで、近世期の町割りと親和性のある形態ができあがったりしているのだとか。これらはもしかすると、上のような「土地勘」のような合理性を示す一種の事例かもしれない。一方でヤミ市がその時々の交通の要所に誕生し、都市の転用としてシステム全体の再定義を促したともいう。こうした回帰と再定義の動的なプロセスが、おそらく今回の各被災地でも見られていくことだろう。一方で、もし原発事故で完全に郷里を追われる人々が出てくるならば、新たな都市の創成プロジェクトは回帰しなぞるべき参照系がないだけに、いっそう多くの困難を強いられるのではないだろうか。