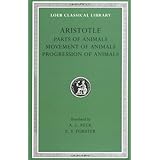先日のヴァン・デル・ルクト『虫、悪魔・処女−−中世の異常発生論』
この情勢が大きく変わるのは1240年を中心とする10年間(1235〜45)。神学者たちはキリストの誕生について新たな身体的・生理学的議論をするようになる。これはちょうどアラブ経由での学知の流入を受けてのことだったらしい。とくに議論の対象となったのはマリアが果たした役割について。アリストテレス思想に準拠するドミニコ会と、ガレノス主義を採択するフランシスコ会が、マリアの役割をめぐって対立する。発生に関して女性が受動的に質料をもたらすだけだとする前者に対して、後者は女性も種子を放出するとしてより積極的な関与があると主張する。もちろん実際には、それぞれの陣営の中でも見解に幅があり、ときにはオーバーラップしたりして(フランシスコ会派内のアリストテレス寄りの論客など)、各論者のスタンスはもっと錯綜している。とはいえ、いずれにせよキリストの受胎はこうしてより「発生学的に」論じられるようになる。当然その背景には、神学におけるアリストテレス思想の一般化や、世俗的なものも含めたマリア崇拝の隆盛などがある。自然観も変質し、それまで(12世紀)世界は神の所業ということで自然と非自然(奇跡など)が地続きの関係にあったのに対し、13世紀中盤には両者の間にはっきりとした区別ができるようになる……。
こういう大局的なまとめにしてしまうと、同書で最も面白い個々の細部の議論は割愛するしかないのが残念なのだけれど、とにかく興味深いのは、キリストの誕生を部分的にせよ自然の事例として捉えようとする(異常発生の範疇で扱われる)中世的なディスクールにおいて、キリストが虫(腐肉にわくウジなどの)に喩えられたり、マリアがミツバチ(同様に雌馬、ハゲワシ、真珠などにも)に喩えられりしていたこと(同書のタイトルもそのあたりから来ている)。いずれも単為生殖の例(虫もミツバチもそのような例とされた)でのアナロジーなのだけれど、そのように語られる伝統が一部にあった、ということのようだ。キリストのその喩えは詩編22
一般に、国民(ネイション)というのは近代的概念だとされ、中世などに当てはめるとたんに微妙な感じ、どこか落ち着かない感じがしてしまう。けれどもルネサンス期あたりでも、たとえばイタリアのナショナリズムは人文主義と密接に結びついていたとされ、そうしたナショナリズムの強化という時代の流れに乗じて、教皇たちはみずからをイタリア精神を体現する君主と捉えるようになり、都市国家側の野心と衝突することになる……なんて記述が、少し前に挙げたバラクロウ『中世教皇史』 に見られたりもする。うーむ、では中世においてはどうだったのか。実際のところ、13世紀当時の大学において、学生が出身地別の「国民団」に属していたことはよく知られている。ブラバンのシゲルスなど、その団長として大暴れした話などが伝わっているくらいだ。総じて「国民」という意識はどの程度、あるいはどのように共有されていたのか。そのあたりがとても気になってくる……というわけで、リーズ・デーヴィス「中世世界における国民と国民的アイデンティティ:一つの擁護論」(Rees Davies, Nations and National Identities in the Medieval World: An Apologia , Revue belge d’histoire contemporaine , Vol.34, 2004 )という論考に目を通してみた。近代以降についてのネイションの定義(アントニー・スミスによる定義など)には確かにそぐわないものの、中世においても人々は自分たちがなんらかの民族・国民に属していると信じていただろうという立場から、論文著者は中世研究においてもしかるべき「国民」概念を用いてよい、あるいは用いてしかるべきだと主張する。
その理由は、まずもってそもそも民族を指す意味でのnacio(natio)という言葉、あるいはgentes(民族・氏族)という言葉が中世の文書によく見られるからだとされる。ウェールズのルーワリン・アプ・グリフィズ(Llywelyn ap Gruffudd)の書状が例として挙げられているほか、ウェールズで初のノルマン人司教となったベルナルドゥスの教皇宛ての書状(1140年ごろ)や、シチリアのフリードリヒ二世が民族同化の危険を警告する文書(1233年)など、いろいろな史料に見いだせるようだ。著者は、そもそも中世人の民族意識は私たちが考えるよりもっと生々しいものだったろうとしている。民族自体が神が創ったものとされ、血縁関係こそがその所属を規定していたというわけだ。それは現代人に負けず劣らず現実的なものだったはずだ、と。
論文の後半では、イングランドを例に、ネイション・ステートの成立プロセスを描いている(イングランドは12世紀ごろのきわめて早い段階から一種のネイション・ステートだった、という話)。それは基本的に、外敵に対する集団の自己規定、民族名の付与、過去の共有(ルナンが言うところの歴史的神話の創設)という形でのアイデンティティの確立というステップを踏んでいる。とくにこの第三の点は、もとはベーダの『イングランド教会史』があり、11世紀のノルマン・コンクエストを経てもなお、イングランドの歴史的神話は改編を経てその出来事に適応しそれを吸収していったとされる(反ティントンのヘンリーが1120〜30年代に著した『イングランド史』)。このあたりはちょっと図式的すぎる感触もないわけではないけれど、議論の入り口としては悪くない気がする。
ノルマン・コンクエストを描いた「バイユー・タペストリー」から、ヘイスティングの戦いの場面
Loeb版
ジョン・マクギニス訳の対訳本 『魂について』(木下雄介訳、知泉書館)
さらに以前やっていたプセロスの『カルデア神託註解』の訳出作業も、震災の後にいろいろな事情で止めてしまっていたけれど、そろそろぼちぼちと再開しようかと思っている。これをとりあえず一通り訳了したら、『ティマイオス』がらみで何か見ていくのもよいかなあ、とも考えている。一昨年の春ごろだったかにフランスで刊行されたカルキディウスの『ティマイオス註解』(Vrin, 2011)
Maaike van der Lugt, Le Ver, Le Démon et La Vierge – Les Théories médiévales de la génération extraordinaire )。ちょっとエキセントリックな題名で、なんとなく敬遠していたのだけれど、読んでみると中身はしっかりした研究だった。12〜13世紀の中世の動物発生論、とりわけ「異常発生」(つまり通常の生殖によらない発生)の問題圏めぐって、当時の議論を手堅く整理している感じだ。人口に膾炙した伝承の類や聖書にもとづくエピソードなどについて、当時の識者たち(主として神学者たち)がどのように解釈していたかをまとめ、わかりやすく紹介している。この、説話と学識層の議論とを行き来する様がとてもいい。というか、対象の選定としても論考の展開としても、ある種理想的な研究に思える。こういうのがやれれば本当にいいよねえ、と思う(笑)。
第一部は中世盛期の発生論のまとめ。ガレノス流に女性にも種子を認める立場と、アリストテレス流の男性のみに種子や形成力を認める立場との対立として各論者たちの布置を描き出しているのだけれど、個人的にエギディウス・ロマヌスのテキストなどはもっと錯綜感があったような印象があり、そんなにきれいに分かれるんだっけかなあと思ってしまった(笑)。いずれにしてもこれは序の口。本論は第二部から。まず紹介されるのは、アヴェロエスの『医学集成(Colliget)』にある話。近隣の女性の証言としてアヴェロエスは、悪意ある男性が射精した湯に浸かったら妊娠したという話を記しているというのだけれど、これに関連した様々な論者の説がまとめられていく。もともとその話はユダヤ起源のものとされ、反ユダヤ的な姿勢に結びつけられて(たとえば尊者ペトルスなど)一蹴されていたものの、やがて、性交がなくても女性の妊娠があり得るかという議論に移り変わり、多くの論者たちがその可能性を認めるにいたったという。続いて、動物の場合(たとえば雌馬)の「風による妊娠」話など、単為生殖にまつわる伝説とそれらをめぐる識者たちの議論が紹介される(サレルノのウルススやアルベルトゥス・マグヌスによる反論など)。生物の自然発生の伝説も俎上に乗る。たとえばエボシガイ(barnacle:貝)からコクガン(barnacle:野生の雁の一種)が生まれるという中世起源らしいとされる伝承。サレルノのウルスス(ウルソ)がその話に合理的説明を付けようとしたりするものの、13世紀になるとアリストテレス説に基づきそうした伝承は否定されていく。
そうした伝承についての議論で問われるのは、どこまでそうした自然発生を認めるかという限度の問題だ。一部の動物に自然発生を認めるという考え方(アリストテレス)は、アヴィセンナなども継承しているわけなのだけれど、西欧においてはそのコスモロジー思想の最下層に位置する「形相付与者」(dator formarum)の考え方が問題視される。それを認めてしまうと天使や悪魔にも創造の力があることになってしまうとして、後に糾弾されることになる(タンピエの禁令など)。とはいえ、やはり急進的な考えをもつ人もいないわけではなく、なかなか事態は複雑だ。ちょっと個人的に面白そうだと思ったのは、14世紀末ごろのパルマのビアッジョという人物。ラディカルな合理主義・自然主義を貫き、魂の不死を否定し、知的魂すら質料の中から引き出されると考えていたという。発生論的には、一部の動物は空気の中間領域から生じるとしていたらしい(!)。
続く第三部は悪魔がらみの発生について。ここでまず問題になっているのは、中世の説話に登場する魔術師マーリンの出生譚。母親が悪魔(夢魔:incubus)によって受胎したとする説話だ。さらに聖書に出てくる巨人族の出自が悪魔にあるとする教説もある。これらはいずれも神学者たちからは否定されていくのだけれど、その際に悪魔の身体性が問題とされるようになる。悪魔が人前に姿を現すときの身体は雲の形成に喩えられるような仮の身体(corpus assumptus)とされ(トマス・アクィナス、ボナヴェントゥラ、ドゥンス・スコトゥスなど)、実質的には人間への影響を及ぼせないという説が一般化するのだけれど、それ以前からもすでに、そうした仮の身体での咀嚼や生殖は議論の的になっていた。悪魔が生殖に及ぶ場合に擬似的な種子を作るといった説(ヘイルズのアレクサンドルス、オーベルニュのギヨーム)も出るものの、これは後に斥けられ(サン・シェールのフーゴー)、かくして仮の身体や擬似的な種子では人間を形成する力が得られないという議論が大勢を占める(形成力は親の魂に由来するとされる)。代わりに出てくるのが、悪魔が人間の精子を盗み、一種の「人工授精」を行うという考え方で(トマス・アクィナス)、中世末ごろまでそれは定説として一般化する……。こうした諸説はペトルス・ロンバルドゥスの『命題集』の注釈という形で議論されているのだけれど、著者によれば14世紀になると、発生論に関連した注釈はほとんど姿を消してしまう。特にフランシスコ会派がそうだといい、一因は命題集への註解の仕方がそもそも変容してしまうからだというが、とにかく発生論の議論全体が下火になるらしい。15世紀になって悪魔学が天使論から切り離され、魔術の言説と結びつくようになって、オーベルニュのギヨームなどの説がまた引き合いに出されるようになり、発生論がらみの議論も一種のリバイバルが起きるのだとか。
いや〜、実に面白い。キリストの受胎を扱う第四部についてはいずれまた。
マージョリー・G・ジョーンズ『フランシス・イェイツとヘルメス的伝統』(正岡和恵ほか訳、作品社)
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ