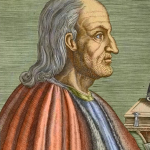
月別アーカイブ: 2014年11月
分断と再生
先週のことだけれど、ポレポレ東中野で舩橋淳監督作品『フタバから遠く離れて−−第二部』を観た。原発事故で避難を強いられた双葉町の住民を丹念に追ったドキュメンタリーの第二弾。いまさらながらだが、一言でいうならこれは分断・断絶を描いた作品。今回は事故後二年目から三年目を描いているせいか、その二重三重の分断状況がいやというほど目につき、静かな悲痛さがじわじわと伝わってくる感じだ。大きいものとしては、町長と町議会の分断、埼玉の旧高校校舎に避難した人々といわき市など他地域の仮設住宅に暮らす人々との断絶感、双葉町と他の原発誘致市町村との断絶などなど……。ほかにも画面の様々なところに、もっとミクロな分断・断絶が見てとれるような気がした。住民はそうした複合的な分断に、身をもって抗おうとしているようにも思える。一番印象的だったのは、避難所の大広間のテレビが首相の演説を映し出す中、その手前で、端がささくれ立ってけが人まで出たという畳を、住民の男性が紙テープで必死に修理しようとしている場面。応急措置でしかないわけだけれど、それでもなにかそれは、分断された状況そのものをなんとか塞ごうとしている姿のようにも見えて、なにやらとても痛々しい。
 これにも関連するが、併せ読んだものがあるのでそちらも取り上げておこう。原発事故の現場を訪ねるという趣旨のバンド・デシネ、エマニュエル・ルパージュ『チェルノブイリの春』(大西愛子訳、明石書店)。荒廃した無色の廃墟を訪ねる悲愴な覚悟で事故現場に赴いた作者は、そこで近隣に暮らす人々の豊かな暮らし見出す……、というルポなのだけれど、こちらはなんというか、分断された人々の暮らしが少しずつ再生し始めている様を描いていて、また別の意味で圧巻。時折差し込まれるカラフルな絵が情感を誘う。バンド・デシネが日本のマンガよりもはるかに「絵」的だということを(一冊一冊を「アルバム」って呼び方をするし)あらためて感じさせる、まさにイラスト・エセーという感じの一冊。末尾に、フクシマを取材した短編が収録されているのだけれど、そちらはまだモノトーンが似合う混迷のただ中にある。チェルノブイリのルポのように、いつかは再生の物語が綴られることを強く願わずにはいられない。
これにも関連するが、併せ読んだものがあるのでそちらも取り上げておこう。原発事故の現場を訪ねるという趣旨のバンド・デシネ、エマニュエル・ルパージュ『チェルノブイリの春』(大西愛子訳、明石書店)。荒廃した無色の廃墟を訪ねる悲愴な覚悟で事故現場に赴いた作者は、そこで近隣に暮らす人々の豊かな暮らし見出す……、というルポなのだけれど、こちらはなんというか、分断された人々の暮らしが少しずつ再生し始めている様を描いていて、また別の意味で圧巻。時折差し込まれるカラフルな絵が情感を誘う。バンド・デシネが日本のマンガよりもはるかに「絵」的だということを(一冊一冊を「アルバム」って呼び方をするし)あらためて感じさせる、まさにイラスト・エセーという感じの一冊。末尾に、フクシマを取材した短編が収録されているのだけれど、そちらはまだモノトーンが似合う混迷のただ中にある。チェルノブイリのルポのように、いつかは再生の物語が綴られることを強く願わずにはいられない。
無矛盾律から選択的自由へ
間が空いてしまったけれど大西克智『意志と自由』の続きをゆっくりと堪能中。少しばかりメモ。前回取り上げたグルヤール論文には、初老の女性による反応の事例としてこんな話が出てくる。まずビュリダンは「食べることと食べないことは同時に可能か」と相手の女性たちに尋ねる。当然「可能ではない」という答えが返ってくる。すると今度は「神は全能で世界を無に帰すこともできる。ならば食べることと食べないことが同時に可能であるようにすることもできると思うか」と問う。女性たちは一様に「わからない」と答える。実際には、当時の神学的な考え方からすると、神の全能性といえど無矛盾律の制約だけは受けるとされていたわけだけれど、一般信徒はさすがにそこまで知ることはなく、判断が保留にされてしまう。そんなわけで、謬論により認知・同意が弱められる例としてビュリダンはこれを挙げているのだけれど、改めて重要なのは、その無矛盾律の尊重が一四世紀当時においてきわめて一般的だったという点。

反対の行為を選ぶ潜勢的力能、あるいは潜在的な選択性は、続くスアレス(第三章)においてはさらに汎用的に拡張されるらしい。知性がもたらす判断に対して意志の同意を先行させることにより、意志の自由が担保されるという図式が、スアレスにあってはいっそう精緻化されるらしいのだけれど、その場合の意志の同意は、基本的に潜勢的な選択肢を<潜在的に比較する>ことから成り立っている。しかもそれは、あくまで回顧的に、後から「そういえば、これこれはあれとの比較で選んだのだな」とわかるような、というか再構成されるような比較であり、そうした比較があればこそ、別の選択もあったという意味で「事前に決定されてはいなかった、自由だった」ということが確信できるという類のプロセスなのだという。なるほどスアレスにおいて自由は、常に回顧的に見出されるものでしかないというわけだ。けれども実際の行動に際しては、比較の意識などまるでないような場面も多々ある。で、スアレスはそのような場合があることも認めつつも、そうした方向には議論を進めてはいかないのだという。それがスアレス、ひいてはイエズス会全体のある種の思想的限界(?)なのかもしれない、と。彼らにおいて抑圧されるもの(同書ではそれを選択という外挿によらない、内在的な「自己決定」だとされる)を救い出すには、どうやらデカルトを待たなくてはならないらしい。
ビュリダンの認識論を復習する
学知論・認識論がらみで、久々にビュリダンについての論考を読んでみた。クリストフ・グルヤール「誤信はいかにして可能か:ジャン・ビュリダン、初老女性、および誤謬の心理学」(Christophe Grellard, How Is it Possible to Believe Falsely? John Buridan, the Vetula, and the Psychology of Error, Uncertain Knowledge: Scepticism, Relativism and Doubt in the Middle Ages, ed. D. G. Denery and al, Brepols, 2014)というもの。収録されている論集そのものも面白そうだが、とりあえずオンライン公開されているこの一論考を見てみた。ビュリダンの学知論・認識論において、とりわけ誤謬がどう生じるかについての議論を取り上げてまとめているもの。ビュリダンの場合、認識論の基本的な図式はオッカムなどが示すものとそれほど違う印象は受けないのだけれど、同論考によれば、とりわけ重視されるのが、感覚器官を通じて心的に処理される対象の像を知性が「それと認める」プロセス。いわば概念的な「判断」(悟性的な)の介在だ。オッカムよりもその判断プロセスが強調される点にビュリダンの特徴が表れているということらしい。で、これは最初の意志の介在プロセスでもあり、ここに誤りの可能性も生じてくるとされる。たとえば教育、習慣(ハビトゥス)などの影響で、学知の受け入れ拒否が生じたりする、という具合だ。論考では、ビュリダンが「初老の女性」を例にそうした誤信について説明している文章を取り上げている。初老の女性が例とされるのは、ビュリダンの説教などの実践から、信じ込みやすい人々として性格づけられているからのようだ(もちろん、中世に特有の蔑視がなかったわけでもないだろうけれど)。そこからビュリダンは推測する。認識機能自体が自然にもつ「真理へと向かう性向」が、獲得された習慣(反復によって固着する)によっていかにして疎外されるか、あるいは意志によっていかにして非・自然的な形で妨げられるかが、そうした事例をもとに説明できるのだ、と。同論考で見る限り、ビュリダンはある意味、民族学・人類学を先取りするかのようでさえある。で、そうした人々が陥る誤信を、合理的説明にもとづいて払拭するのが学問に携わる者の職務の一つであると位置づけていたのだという。なるほど、そのあたりの使命感(?)も、あるいは説教の経験が大きくものを言っているのかもしれない。
アウグスティヌスの意志論再び
 アウグスティヌスがらみで気になっていた一冊を見てみた。アラン・ド・リベラ編『形而上学の後に−−アウグスティヌス?』(Après La Métaphysique: Augustin? (Publications De L’institut D’études Médiévales De L’institut Catholique De Paris), éd. Alain de Libera, Vrin, 2013)という論集。アウグスティヌスが通常の形而上学的な枠組みに収まりきらない、その収まりきらなさを取り上げようという趣旨の論考が居並ぶ小著。リベラは巻頭でアウグスティヌスにおける主体の不在の問題を取り上げ、続くジャン=リュック・ナンシーは、信仰と思考との対立軸の乗り越えの可能性をアウグスティヌスに見るなどなど……。けれども個人的な目下の関心からすると、一番の注目はやはりオリヴィエ・ブールノアによるアウグスティヌスの意志についての論考。「アウグスティヌス:弱さと意志」(Olivier Boulnois, Augustin, La Faiblesse et la Volonté, pp.51-77)というそれは、善を指向しつつ悪を行ってしまうという人間の性<さが>、すなわち意志の弱さというテーマを通して、アウグスティヌスの意志論の全体像をまとめようというもので、とても参考になる一篇だ。
アウグスティヌスがらみで気になっていた一冊を見てみた。アラン・ド・リベラ編『形而上学の後に−−アウグスティヌス?』(Après La Métaphysique: Augustin? (Publications De L’institut D’études Médiévales De L’institut Catholique De Paris), éd. Alain de Libera, Vrin, 2013)という論集。アウグスティヌスが通常の形而上学的な枠組みに収まりきらない、その収まりきらなさを取り上げようという趣旨の論考が居並ぶ小著。リベラは巻頭でアウグスティヌスにおける主体の不在の問題を取り上げ、続くジャン=リュック・ナンシーは、信仰と思考との対立軸の乗り越えの可能性をアウグスティヌスに見るなどなど……。けれども個人的な目下の関心からすると、一番の注目はやはりオリヴィエ・ブールノアによるアウグスティヌスの意志についての論考。「アウグスティヌス:弱さと意志」(Olivier Boulnois, Augustin, La Faiblesse et la Volonté, pp.51-77)というそれは、善を指向しつつ悪を行ってしまうという人間の性<さが>、すなわち意志の弱さというテーマを通して、アウグスティヌスの意志論の全体像をまとめようというもので、とても参考になる一篇だ。
ブールノアによれば、たとえばアリストテレスの意志論では、欲望による駆動と逸脱が問題になるのだけれど、それに対しアウグスティヌスにおいては、自由意志は自律的だとされ、それは善に向かうという性向を備えているものの、(原罪による)人間の不完全性ゆえに必ずしも善を実現するとは限らない。その意志は選択的な自由を与えられてはいても、それが善を選ぶときにこそ真に自由であるとされ、善悪の選択は事実上なく、ただ善への意志があるのみだとされる。自由意志と言うときの「自由」は、善への意志という意味において、名詞での「自由」とは意味が異なるのだという。ところがここに、習慣(ハビトゥス)が立ちふさがる。習慣とはいわば固着化のことであり、人間が身体的な快楽などを求めるなど、自由意志からすれば避けるべき事柄の数々が、そうした固着化としてある。固着化した力は並大抵ではない。人間の自由意志は、選択という面から見れば大きな非対称になっているし、習慣の強固さという面から見ても逆方向での大きな非対称になっている。アウグスティヌスは確かに悪の選択を、元来の自由の欠落(選択ゆえの)と見なしているが、人間のすべての行動にはそうした「弱さ」が刻まれている、とされる。その根源的な悪への傾斜は、もともとのアダムの「意志」による選択の結果でもあった。原罪にまで遡るといわれる人間の意志の弱さは、やはり人間の意志に依存しているのであり、ゆえに人間の責任に帰されるしかない……。
かように引き裂かれた状態の解消のためには、神の恩寵の介在が必要とされる……というのが一応の筋書きなのだけれど(ペラギウス派への反論として)、しかしながらその恩寵は「万能の切り札」なのではない。解消にいたるには人間の側からの鍛錬もまた求められるのだ。その点にこそ、アウグスティヌスが単に神学の問題としてのみ意志論を扱うようなことをせず、哲学的的議論をも援用していることの意味がある、とブールノアは指摘する。なるほど、アウグスティヌスの意志論が、倫理的性向と固着化した習慣との分裂という、深いところに設定された不均衡の問題として掲げられているという見立ては、単なる欲望の力学などよりもはるかに重層的で異義深いものかもしれない、と思わせずにはいない。