久々にリュートtube……ていうか、今回はリュートではなく厳密にはビウエラtube(笑)。アロンソ・ムダーラの名曲、ファンタシア10番を、英国のギター奏者・リュート奏者のジュリアン・ブリームの演奏で。冒頭、クラッシクギターの製作の映像が流れるけれど、いやいやだまされてはいけない。音はビウエラのもの。途中からブリームの演奏の映像になる。右手の斜め上からのアップがいいねえ。それにしてもこの使用しているビウエラ、なにやらやけにデカイんでないの?
悪の問題
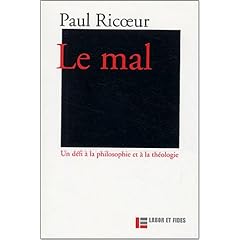 ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
結局リクールによれば、後の時代の弁神論においても、悪についての問いの緊張状態は解かれないという。カントやヘーゲルに至っても、また他のリソース(理性といった)がつぎ込まれて、悪の問題が投げかける問いは再生されていく、と。「凡悲劇論が凡論理主義に回収される世界観にあって、被害者の苦しみにはどんな運命が残されているのか」(p.48)というわけだ。悪というものの現実が神の善性と相反することを認める立場に立ち、従来の弁神論とは「別の仕方で」悪を考えるカール・バルトの神学すら、シェリングがルネサンスの思想家たちに見出したという「神性のダークサイド」を開くことになる可能性を見てとっている。振り出しに戻るかのように……。その上でなお、悪の問題への思考によるアプローチを降伏させてはならない、より緻密な論理をもって臨み、さらに行動と感性をも動員せよ、とリクールは唱える。悪への実践的抵抗、喪の仕事をモデルとした愁訴の変容など、ヒントも示唆しているが、それを受け止めるような議論はその後のフランス思想界(でなくてもよいのだけれど)とかでもなされているのかしら、とちょっと気になる。
断章24 & 25
(Lamberz : 10 & 22、Creuzer=Moser : 10 & 23)
Πάντα μὲν ἐν πᾶσιν, ἀλλὰ οἰκείως τῇ ἑκάστου οὐσίᾳ· ἐν νῷ μὲν γὰρ νοερῶς, ἐν ψυχῇ δὲ λογικῶς, ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς σπερματικῶς, ἐν δὲ σώμασιν εἰδωλικῶς, ἐν δὲ τῷ ἐπέκεινα ἀνεννοήτως τε καὶ ὑπερουσίως.
すべてのものはすべてのものの中に在るが、それぞれの本質に適切な形で在る。すなわち、知性には(すべては)知解可能なものとして在るし、魂には理性的なものとして、植物には種子的なものとして、物体には像的なものとして、超越するものには不可知的なものかつ本質を超えたものとして在る。
Ἡ νοερὰ οὐσία ὁμοιομερής ἐστιν, ὡς καὶ ἐν τῷ μερικῷ νῷ εἶναι τὰ ὄντα καὶ ἐν τῷ παντελείῳ· ἀλλ᾿ ἐν μὲν τῷ καθόλου καὶ τὰ μερικὰ καθολικῶς, ἐν δὲ τῷ μερικῷ καὶ τὰ καθόλου μερικῶς.
知性的な本質は類似する部分から成るものである。ちょうど存在するものが個別の知性ならびにその完成形に在るように。しかしながら、普遍的な知性においては、個別のものも普遍的に在り、また個別の知性にあっては普遍的なものも個別的に在る。
気候条件と中世
 文庫化を期に読んでみた、ブライアン・フェイガン『歴史を変えた気候大変動』(東郷えりか他訳、河出文庫)。主に13世紀から19世紀にかけての欧州の気候変動を概説しつつ、それが歴史に及ぼした影響を語っていくというもの。こりゃなかなか面白い。中世盛期が温暖で、その後寒冷化する欧州は、その変化の影響をかなり直接的に受けていたらしい。温暖だった中世には、北方系の人々がスカンジナビアから船でグリーンランドに渡るようになり、北アメリカもどうやら発見していたらしいという。それはひとえに温暖な気候の賜物。カトリックが四旬節中も食べて良いとしたタラやニシンの市場は8世紀頃からあるというけれど、これもまた水温の関係で生息域が変わり(中世にはノルウェー沖からその先まで南下)、12世紀にはスペイン北部のバスク地方の人々が捕鯨と合わせ、タラも捕って塩漬けを作っていたのだという。これはちょっと意外だった(苦笑)。海と同様、山も気候変化の直撃を受ける。寒冷化によって食料難になり、飢饉や疾病の蔓延は、人々の恐怖や不満を煽って、たとえば魔女狩りなどの遠因にもなった……。慢性的な食糧不足は、後にはフランス革命すらも導く要因の一つに……。
文庫化を期に読んでみた、ブライアン・フェイガン『歴史を変えた気候大変動』(東郷えりか他訳、河出文庫)。主に13世紀から19世紀にかけての欧州の気候変動を概説しつつ、それが歴史に及ぼした影響を語っていくというもの。こりゃなかなか面白い。中世盛期が温暖で、その後寒冷化する欧州は、その変化の影響をかなり直接的に受けていたらしい。温暖だった中世には、北方系の人々がスカンジナビアから船でグリーンランドに渡るようになり、北アメリカもどうやら発見していたらしいという。それはひとえに温暖な気候の賜物。カトリックが四旬節中も食べて良いとしたタラやニシンの市場は8世紀頃からあるというけれど、これもまた水温の関係で生息域が変わり(中世にはノルウェー沖からその先まで南下)、12世紀にはスペイン北部のバスク地方の人々が捕鯨と合わせ、タラも捕って塩漬けを作っていたのだという。これはちょっと意外だった(苦笑)。海と同様、山も気候変化の直撃を受ける。寒冷化によって食料難になり、飢饉や疾病の蔓延は、人々の恐怖や不満を煽って、たとえば魔女狩りなどの遠因にもなった……。慢性的な食糧不足は、後にはフランス革命すらも導く要因の一つに……。
著者は結構慎重な筆さばきを見せ、気候を決定論的にではなく、歴史的要因のあるいは一番外側の枠組みを作るものというような視点から描いている。でも、読後感としては、気候が一定の影響力を持っているという強い印象が刻まれる。うーむ、このあたりが実に巧みなところだ。こうした記述方法は、一定の枠組みをもたらしているのではないかと仮定できるような要因を論じるには効果的かも。技術環境論なども、こういう論述方法に範を仰ぐのがよいかもなあ、と思ってしまう。
……そういえば去年から今年にかけて太陽の黒点が約100年ぶりにゼロになったとかいう話だったけれど、また気温が急激に下がるなんてことが起きるのかしら?
イングランド系舞曲
英国ものは大陸ものとどこか感覚というか感性というかが違う気がするのだけれど、大陸系の人が弾く英国ものはやはり大陸系に引っ張られる……のだろうか?そんなことを久々に思わせるのが、ラ・ベアータ・オランダ(La Beata Olanda)というドイツ系のグループによる『ジョン、来て、すぐキスして(”John come kiss me now”)』という一枚。表題は伝統的な旋律の曲(たぶん)。リュート界隈では逸名著者のアレンジ譜があり、ポール・オデットとかが弾いていて、よく知られている(と思う)。今回収録されているのは、おそらくはその伝承の旋律を用いたデーヴィッド・メル(17世紀のヴァイオリニスト)の曲。リュート用のものみたいにいろいろ変化していくような面白味はなく、なんだか平坦な印象。というか、このCD、全体になにかこう、やけにまったりゆったりしている印象が強い。決して演奏が悪いというのではないのだけれど、あえて言えば、踊れる舞曲のテンポをわざと落とし、あえて微妙な陰影を付けているという感じ(?)。うーん、こういうアプローチはちょっと久しぶりな気がする。個人的には少しばかりフラストレーションも……(苦笑)。でもこういうのが落ち着いていて良いという向きも絶対あるはず。
ちなみにジャケット写真はリュートのリブ(背中の丸みを帯びた部分)。
John Come Kiss Me Now – Suites, Divisions and Dances for Diverse Instruments / La Beata Olanda
