本格的な寓意的解釈の嚆矢とも言われるポルピュリオスの『ニンフの洞窟』。これの希伊対訳本(“L’antro delle Ninfe”, a cura di Laura Simonini, Adelphi Edizioni, 1986)を、積ん読解除で読み始める。テキスト自体はそれほど長いものではない。まだ3分の1くらいだけれど、すでにしてなかなか面白い。ホメロスの『オデュッセイア』に出てくる一節をめぐり、洞窟やニンフの寓意、そこに古来より込められた多義的な意味をめぐる話が展開していく。ポルピュリオスの、これはコスモロジー系のテキストということになるのかしら。いずれにしても、洞窟はまずもって人間と神を繋ぐものであり、ヒューレー(第一質料でしょうね)の寓意であったり、質料から生成するコスモスの寓意であったりするという。その際の理屈が、洞窟は「自発的に形成される(αὐτοφυής)」からというのだけれど、考えようによってはこれはとても興味深いところ。原初的な形成(形相との混成?)がまずもって穿たれた「穴」として生じるというところに、ある種の形而上学的な可能性が感じられる(笑)。穴の形而上学というと分析哲学系の話題になってしまうけれど、「自発的」という部分も含めて「穿ち」の形而上学ということを考えることもできたりするんじゃないかしら、なんてね(笑)。とりあえずゆっくりとテキストの先に進むことにしよう。
物体としての本
 今福龍太『身体としての書物』(東京外国語大学出版会、2009)を読んでいるところ。まずこの出版元。ついに外語にも出版会ができたようで(笑)、今後のラインアップも楽しみではある。大学の出版会も全般に懐事情は厳しい、みたいな話も聞こえてくるけれど、頑張ってほしいところ。で、この本。内容は、ボルヘス、ジャベス、ベンヤミンの書物論をきっかけとして、書物の受容というか知的営為との関わりというかを、書物のマテリアルな面との関係性で論じた一連の講義録。活版印刷以後を主に扱っているのだけれど、個人的にとりわけ引き寄せられた(笑)のは「口誦から文字へ」と題された第4章。ボルヘスの講演集を読み進める形で、プラトン以前となる古代の知の伝達の様が取り上げられている。ボルヘスは、口承文化の時代において「師の言葉は弟子を拘束しない、弟子は師の思想を自由に発展させることができた」みたいなことを言っているというのだけれど、うーむ、このあたりはどうなのだろう?口承による思想の継承というのは、ちょっと違う次元のものだったのではないのかしら、という気もしなくない(?)。師(というか先達)の思想をいじるということはそもそも、書物による知の伝達においてこそ導かれる、あるいは発想されるという気がするのだけれど……。注解書なんてまさにそういうものだし。でもまあ、確かに写本製作、とりわけ筆写作業などには、一方で口承性の残滓という面もあったのかもしれない……。
今福龍太『身体としての書物』(東京外国語大学出版会、2009)を読んでいるところ。まずこの出版元。ついに外語にも出版会ができたようで(笑)、今後のラインアップも楽しみではある。大学の出版会も全般に懐事情は厳しい、みたいな話も聞こえてくるけれど、頑張ってほしいところ。で、この本。内容は、ボルヘス、ジャベス、ベンヤミンの書物論をきっかけとして、書物の受容というか知的営為との関わりというかを、書物のマテリアルな面との関係性で論じた一連の講義録。活版印刷以後を主に扱っているのだけれど、個人的にとりわけ引き寄せられた(笑)のは「口誦から文字へ」と題された第4章。ボルヘスの講演集を読み進める形で、プラトン以前となる古代の知の伝達の様が取り上げられている。ボルヘスは、口承文化の時代において「師の言葉は弟子を拘束しない、弟子は師の思想を自由に発展させることができた」みたいなことを言っているというのだけれど、うーむ、このあたりはどうなのだろう?口承による思想の継承というのは、ちょっと違う次元のものだったのではないのかしら、という気もしなくない(?)。師(というか先達)の思想をいじるということはそもそも、書物による知の伝達においてこそ導かれる、あるいは発想されるという気がするのだけれど……。注解書なんてまさにそういうものだし。でもまあ、確かに写本製作、とりわけ筆写作業などには、一方で口承性の残滓という面もあったのかもしれない……。
一般論だけれど、書物論が印刷本を主に論じるのは良いとして、やはりそれ以前の写本文化ももっと十全に視野に入れてほしい気はする。注解書が出てくるというのはもちろん文字文化の賜物だけれど、その前段の口承での知的伝達の伝統がどれほどそこに流れ込んでいるのかとか、とても気になってくる。ピエール・アドあたりをもうちょっとちゃんと読んでみるか……?
久々の文学論
 久々に文学ものの本格的論考を読む。ラブレー論。折井穂積『パニュルジュの剣 – ラブレーとルネサンス文学の秘法』(岩波書店、2009)。いわゆる構造分析なのだけれど、従来はせいぜいフォークロア研究などで小さく使うことが多かった手法を、ここでは大胆にラブレーの『パンタグリュエル』から『第三の書』と、それが影響を受けたであろうとされるクレマン・マロの詩、マルグリット・ド・ナヴァールの詩に適用して、結果的にとても面白い問題系が浮かび上がっている。いや、お見事。絵画などにパラレルに見られる作品構造としての対称性に着目して、そこからラブレーの『第三の書』に、地獄めぐりのモチーフを見出し、さらに一種の性表現や、霊的な戦いについての思想が、絵画で言うステガノグラフィー(隠匿記法)として埋め込まれている様を明らかにする……というもの。もちろん、こうした分析は状況証拠の積み重ねの上に成り立っているわけだけれど、このように三種のテキストそれぞれの対称構造が示されると、ある種の迫力・説得力がある。そうした対称構造への当時の「こだわり」は、たとえばルネサンス期の楽譜などにも時に見られるわけで(ルイス・ミランとかね)、文学にそれが持ち込まれない理由は見あたらないように思われる(ま、ラブレーを専門でやっている人が読めばまた違う評価になるのかもしれないけれど)。仮に文学もそうであるなら、思想系のテキストはどうなのかしら、とふと思ったりもする。
久々に文学ものの本格的論考を読む。ラブレー論。折井穂積『パニュルジュの剣 – ラブレーとルネサンス文学の秘法』(岩波書店、2009)。いわゆる構造分析なのだけれど、従来はせいぜいフォークロア研究などで小さく使うことが多かった手法を、ここでは大胆にラブレーの『パンタグリュエル』から『第三の書』と、それが影響を受けたであろうとされるクレマン・マロの詩、マルグリット・ド・ナヴァールの詩に適用して、結果的にとても面白い問題系が浮かび上がっている。いや、お見事。絵画などにパラレルに見られる作品構造としての対称性に着目して、そこからラブレーの『第三の書』に、地獄めぐりのモチーフを見出し、さらに一種の性表現や、霊的な戦いについての思想が、絵画で言うステガノグラフィー(隠匿記法)として埋め込まれている様を明らかにする……というもの。もちろん、こうした分析は状況証拠の積み重ねの上に成り立っているわけだけれど、このように三種のテキストそれぞれの対称構造が示されると、ある種の迫力・説得力がある。そうした対称構造への当時の「こだわり」は、たとえばルネサンス期の楽譜などにも時に見られるわけで(ルイス・ミランとかね)、文学にそれが持ち込まれない理由は見あたらないように思われる(ま、ラブレーを専門でやっている人が読めばまた違う評価になるのかもしれないけれど)。仮に文学もそうであるなら、思想系のテキストはどうなのかしら、とふと思ったりもする。
余談1:ラブレーといえば、白水社からマイケル・A・スクリーチ『ラブレー – 笑いと叡智のルネサンス』(平野隆文訳)というのが出たようなのだけれど、この値段を見てびっくり。1000ページ近いとはいえ、2万円超とは……。これではちょっと手軽に見てみたいとはいかないじゃないの……。とりあえず目次のPDFだけ落として眺めてみると、こりゃかなり細かい注釈書のよう。
余談2:マルグリット・ド・ナヴァールの『牢獄』に、「神とは無限の円である。その中心はいたるところにあり、円周はどこにもない」という定義が出てくるそうで、なにやらクザーヌスを彷彿とさせるこの一節、出典は『24人の哲学者の書』という12世紀の偽ヘルメス文書だという注があるのだけれど、なんと、ちょうどフランスのJ.Vrin社から、羅仏対訳本(“Le livre des vingt-quatre philosophes – Résurgence d’un texte du IVe siècle”)が出たらしい。しかもこれ、マリウス・ヴィクトリヌスの先行テキストを再浮上させたテキストだという新知見が盛り込まれているらしい。こりゃ面白そうだ!
リュートtube 4
久々にリュートtube……ていうか、今回はリュートではなく厳密にはビウエラtube(笑)。アロンソ・ムダーラの名曲、ファンタシア10番を、英国のギター奏者・リュート奏者のジュリアン・ブリームの演奏で。冒頭、クラッシクギターの製作の映像が流れるけれど、いやいやだまされてはいけない。音はビウエラのもの。途中からブリームの演奏の映像になる。右手の斜め上からのアップがいいねえ。それにしてもこの使用しているビウエラ、なにやらやけにデカイんでないの?
悪の問題
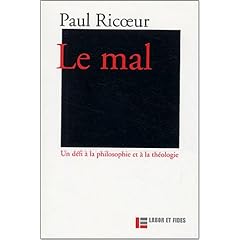 ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
結局リクールによれば、後の時代の弁神論においても、悪についての問いの緊張状態は解かれないという。カントやヘーゲルに至っても、また他のリソース(理性といった)がつぎ込まれて、悪の問題が投げかける問いは再生されていく、と。「凡悲劇論が凡論理主義に回収される世界観にあって、被害者の苦しみにはどんな運命が残されているのか」(p.48)というわけだ。悪というものの現実が神の善性と相反することを認める立場に立ち、従来の弁神論とは「別の仕方で」悪を考えるカール・バルトの神学すら、シェリングがルネサンスの思想家たちに見出したという「神性のダークサイド」を開くことになる可能性を見てとっている。振り出しに戻るかのように……。その上でなお、悪の問題への思考によるアプローチを降伏させてはならない、より緻密な論理をもって臨み、さらに行動と感性をも動員せよ、とリクールは唱える。悪への実践的抵抗、喪の仕事をモデルとした愁訴の変容など、ヒントも示唆しているが、それを受け止めるような議論はその後のフランス思想界(でなくてもよいのだけれど)とかでもなされているのかしら、とちょっと気になる。