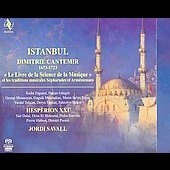イタリアのSISMELが出しているミクロログスライブラリから、『星辰・医学 – 占星術と医学の東西』(”Astro-Medicine – Astrology amd Medicine, East and West”, ed. Charles Burnett and al., Edizioni del Galluzzo, 2008)というのを取り寄せてみる。東西というだけあって、ヘブライやアラビアのほか、インド、チベットの仏教系の「医学占星術」までと、面白そうな論考が並んでいる。西欧はルネサンス以降かと思いきや、中世関連ものも。そんなわけで、まずはヴィヴィアン・ナットンという人の「ギリシアの医療占星術と医学の境界」という一編を読む。これ、基本的にはガレノスの占星術批判を丹念に見直すというもの。ルネサンス期に「再発見」されるまで、西洋では医学占星術は「忘れられ」ていて、人体に影響するのは星辰ではなくむしろ気象現象だというガレノス説が支持されていたということなのだけれど、ガレノス自身はそうした気象現象と星辰との依存関係などを認めていたりして、批判する側(ガレノスを継ぐ医師たち)も、巷でもてはやされていた占星術から案外そう遠い立ち位置ではなかった、という話だ。最後のところでは、ガレノス名義で13〜14世紀に流布したというラテン語訳の『種子について』という文書が取り上げられ(校注がまだ完全には行われていないものらしい)、それについての諸説(実は二冊の別々の書ではないかとか、いろいろ)がまとめられている。うーん、その「再発見前」の医学占星術がいよいよもって気になってくる……。
月別アーカイブ: 2010年4月
「イスタンブール」
ジョルディ・サヴァールによるCDリリースは相変わらず精力的。先の『忘れられた王国』も良かったけれど、最近出たもう一枚が『イスタンブール – ディミトリ・カンテミール「音楽学の書」』(Istanbul – Dimitrie Cantemir: “The Book of Science of Music” and the Sephardic and Armenian Traditions / Jordi Savall, Hesperion XXI)。今度は全編インストゥルメンタルで東方の音楽を満喫できる。サヴァールお得意のアラブ系サウンドだけに、実にメリハリの利いたノれる音楽になっている。ま、ちょっと西方ぽい感じのトーン(?)もなきにしもあらずだけれど……。いや〜、でも全体としてはとても面白い。今回の録音は、18世紀になる直前にイスタンブールに渡ったディミトリエ・カンテミールというモルダビア(ルーマニアの北のほうか)の王子が記した『音楽学の書』という音楽理論書をフィーチャーしたもの。この人物、実に11カ国語を話せたといい、最初は人質として、後には外交官としてイスタンブールに滞在したという話で、「タンブール」という楽器(リュートっぽいものらしいが)の名手でもあったのだという。この書物には多くの曲が独自記譜法により記されているのだそうで、サヴァールはその現代譜版を入手して、時代考証などを踏まえて演奏を試みているらしい(以上ライナーから)。
久々にドゥルーズ論
 久々にドゥルーズ論を読み始めたところ。ピーター・ホルワード『ドゥルーズと創造の哲学 – この世界を抜け出て』(松本潤一郎訳、青土社)。まだ2章めの途中までだけれど、わー、すでにしてこれはなんというか、個人的には読む快楽を味わうことができる一冊。ドゥルーズ哲学の全体像を「創造」をキータームにしてわしづかみにしようという目論み。創造とはつまり生成変化のことで、いわば例のプロセス実在論ということ。ここではそれはある意味それを突き抜けて、むしろプロセス神学的(といっても、ホワイトヘッドのそれとは違うけれど)。まだほんの出だし部分しか読んでいないのでナンだけれども(苦笑)、ドゥルーズが存在の一義性のほか、たとえば神(この場合は創造のプロセスそのものということになるのかしら)の認識が人間主体にもとより可能であるという見解(つまりは神秘主義的な見識だが)でもドゥンス・スコトゥスに重なるらしいことが改めてよくわかる。ドゥルーズってやはりとても「フランシスコ会的」かも(笑)。「われわれが真に思考するとき、神こそがわれわれを通して思考する」(p.35)なんて、反デカルト的にマルブランシュにも通じているし。フランシスコ会系の思想のはるか先にドゥルーズのような思想が待っているとしたら……やはりそのもとの思想を現代において問い直す意義も十分にありそうだ、と改めて。
久々にドゥルーズ論を読み始めたところ。ピーター・ホルワード『ドゥルーズと創造の哲学 – この世界を抜け出て』(松本潤一郎訳、青土社)。まだ2章めの途中までだけれど、わー、すでにしてこれはなんというか、個人的には読む快楽を味わうことができる一冊。ドゥルーズ哲学の全体像を「創造」をキータームにしてわしづかみにしようという目論み。創造とはつまり生成変化のことで、いわば例のプロセス実在論ということ。ここではそれはある意味それを突き抜けて、むしろプロセス神学的(といっても、ホワイトヘッドのそれとは違うけれど)。まだほんの出だし部分しか読んでいないのでナンだけれども(苦笑)、ドゥルーズが存在の一義性のほか、たとえば神(この場合は創造のプロセスそのものということになるのかしら)の認識が人間主体にもとより可能であるという見解(つまりは神秘主義的な見識だが)でもドゥンス・スコトゥスに重なるらしいことが改めてよくわかる。ドゥルーズってやはりとても「フランシスコ会的」かも(笑)。「われわれが真に思考するとき、神こそがわれわれを通して思考する」(p.35)なんて、反デカルト的にマルブランシュにも通じているし。フランシスコ会系の思想のはるか先にドゥルーズのような思想が待っているとしたら……やはりそのもとの思想を現代において問い直す意義も十分にありそうだ、と改めて。
プロクロス「カルデア哲学注解抄」 – 1
Α´
Αὐλαὶ τῶν θείων καὶ οἰκήσεις αἱ ἀΐδιαι τάξεις. Καὶ ἡ ¨πανδεκτική αὐλή¨ τοῦ Πατρὸς ἡ πατρικὴ τάξις ἐστίν, ἡ πάσας ὑποδεχομένη καὶ συνέχουσα τὰς ἀναθείσας ψυχάς · ἡ δὲ τῶν ἀγγέλων μερὶς πῶς ἀνάγει ψυχήν; φέγγουσα φησί, πυρὶ τὴν ψυχήν, τοῦτ᾿ ἔστι περιλάμπουσα αὐτὴν πανταχόθεν, καὶ πλήρη ποιοῦσα τοῦ ἀχράντου πυρὸς ὃ ἐνδίδωσιν αὐτῇ τάξιν ἄκλιτον καὶ δύναμιν δι᾿ ἣν οὐκ ἐκροιζεῖται εἰς τὴν ὑλικὴν ἀταξίαν ἀλλὰ συνάπτεται τῷ φωτὶ τῶν θείων · καὶ συνέχει δὲ αὐτὴν ἐν οἰκείῳ τόπῳ, καὶ ἀμιγῆ ποιεῖ πρὸς τὴν ὕλην, τῷ θερμῷ πνεύματι κουφίζουσα καὶ ποιοῦσα μετέωρον διὰ τῆς ἀναγωγοῦ ζωῆς · τὸ γὰρ πνεῦμα τὸ θερμὸν ζωῆς ἐστι μετάδοσις.
I.
神々の宮および住処とは永遠の秩序である。父の「あらゆるものを受け止める宮」とは父なる秩序であり、高みにある魂をすべて受け止め、留めおくものである。では、天使の階級はどのように魂を押し上げるのだろうか?それは魂を火で輝かせることによってだと(神託は?)言う。つまり、それをあらゆる面から輝かせ、純粋な火で満たすことによってである。その火は魂に、変わることのない秩序のほか、質料の無秩序に音を立てて入り込まずに神々の光に結びついていられる力をも与える。また、魂を固有の場所に留めおき、熱いプネウマで軽くするとともに高みを目指す生命によって上昇をもたらすことで、質料に逆らう純粋なるものとなすのである。というのも、熱いプネウマとは生命の分有のことだからだ。
「グノーシス主義の思想」
 これは少し前にどこぞで話題になっていたと思うのだけれど、大田俊寛『グノーシス主義の思想 – <父>というフィクション』(春秋社、2009)を読み始める。まだ2章目までだけれど、これ、ぐいぐいと引き込む力をもった、なんとも鮮やかな整理が滅法印象的。こんなりすっきり整理されてよいのかしら、と思えるほど。なにやらチャートっぽい感じとか、かつての『構造と力』を思い起こさせたりもするかも、なんて(笑)(古代思想が対象なので文脈などはかなり違うけれど)。いやいや皮肉っているのではありません。世間に出回っているグノーシスについての多くの言説を、ロマン主義的バイアスがかかったままだとして一蹴し、そこから具体的なテキストに即してその思想の核心を取り出していこうとする姿勢には共感を覚えるし、それを「父」の探求という人類学的な視座からアプローチしているところも、スケールを感じさせるものがあるし。これは次回作も期待できそうな予感……って、先走りたくもなる(まずは後半も読み通してからだけれど)。
これは少し前にどこぞで話題になっていたと思うのだけれど、大田俊寛『グノーシス主義の思想 – <父>というフィクション』(春秋社、2009)を読み始める。まだ2章目までだけれど、これ、ぐいぐいと引き込む力をもった、なんとも鮮やかな整理が滅法印象的。こんなりすっきり整理されてよいのかしら、と思えるほど。なにやらチャートっぽい感じとか、かつての『構造と力』を思い起こさせたりもするかも、なんて(笑)(古代思想が対象なので文脈などはかなり違うけれど)。いやいや皮肉っているのではありません。世間に出回っているグノーシスについての多くの言説を、ロマン主義的バイアスがかかったままだとして一蹴し、そこから具体的なテキストに即してその思想の核心を取り出していこうとする姿勢には共感を覚えるし、それを「父」の探求という人類学的な視座からアプローチしているところも、スケールを感じさせるものがあるし。これは次回作も期待できそうな予感……って、先走りたくもなる(まずは後半も読み通してからだけれど)。