 外的事象と心的世界とはどう結びつくのかというのは、中世以来の大問題であり続けてきた。オッカムなどは、スペキエスのような中間的な心的イメージを可能な限り排して、外的事象は直観的(あるいは直接的)に認識されるという論を展開していた。それはつまり、外的事象が認識のトリガーをなすこと(因果関係として)、外的事象と類似の関係にある認識(あるいは概念)がいわば自動的に生成すること(表象として)を示し、これをもって直観的・直接的な認識の成立の説明としていたのだった。メルマガでも取り上げているけれど、でもこれでは概念のような一般的なもの(普遍)が個別の外的事象(個)からどうやって導かれるのかが今一つピンとこない。オッカムはそのあたりを巧みにブラックボックス化して深入りを避けている印象だけれど、そのブラックボックスをあえてこじ開け、再考し、より精緻化しようという試みこそが、その後の長大な認識論の流れを形作っていくことにもなる……と。で、当然ながらそれは現代の哲学や認知科学にまで及んでいく、という次第だ。で、個人的には、まさにそういった問題を正面から扱っている一冊ということで、ゼノン・W・ピリシン『ものと場所:心は世界とどう結びついているか』(小口峰樹訳、勁草書房)を読んでいるところ(やっと前半3章まで)。それによると、さすがにオッカムが考えていたような類似性の関係はすでにあっさりと捨て去られ(笑)、今では心と世界を結ぶものとして指示的関係(意味論的関係)と因果関係のみが取り上げられるようになっているらしい。前者はいわば志向性の問題(狭い意味での)でもあり、いわばトップダウン、後者はアフォーダンスとかを想起させる、いわばボトムアップの関係性とも言える。このボトムアップ型の駆動というのは、個別的なトークンを人はどう追跡するのかという問題を考える場合、認識論的に決して排除できないものなのだという。要は両者が相互に作用しあうようなメカニズムが問題になるということ(らしい)。出現した個物を、人はいかに個物として認識するのか、あるいは、人はいかに個物を個物として出現させるのか。著者はそこに概念的ではない同定メカニズムがあると考える。それは指標付けのメカニズムで、その場合の指標は概念ではとらえられない(つまり表象としてコード化されていない)ものだという。もはやこれはローレベルプログラミングめいた世界で、著者みずから、コンピュータのキーを叩いたときに生じることを譬えとして示している(キーを押したときに生じる割り込みの信号と、そこで呼び出されるサブルーチンによって、どのキーが押されたかが決定されるというプロセスだ。それらは「表象」はされない。また、プログラミングで言うポインタの話もある)。もちろんそういう同定メカニズムそれ自体は依然ブラックボックスであり続けてはいるようだけれど、ずいぶんと縮減されたブラックボックスになっている印象ではある。学問的精緻化というのが、まさにそうした縮減のプロセス(ブラックボックス自体はあるいは完全には開かれることは金輪際ないのかもしれないが)なのだということに、個人的に改めて感じ入るものがある……。
外的事象と心的世界とはどう結びつくのかというのは、中世以来の大問題であり続けてきた。オッカムなどは、スペキエスのような中間的な心的イメージを可能な限り排して、外的事象は直観的(あるいは直接的)に認識されるという論を展開していた。それはつまり、外的事象が認識のトリガーをなすこと(因果関係として)、外的事象と類似の関係にある認識(あるいは概念)がいわば自動的に生成すること(表象として)を示し、これをもって直観的・直接的な認識の成立の説明としていたのだった。メルマガでも取り上げているけれど、でもこれでは概念のような一般的なもの(普遍)が個別の外的事象(個)からどうやって導かれるのかが今一つピンとこない。オッカムはそのあたりを巧みにブラックボックス化して深入りを避けている印象だけれど、そのブラックボックスをあえてこじ開け、再考し、より精緻化しようという試みこそが、その後の長大な認識論の流れを形作っていくことにもなる……と。で、当然ながらそれは現代の哲学や認知科学にまで及んでいく、という次第だ。で、個人的には、まさにそういった問題を正面から扱っている一冊ということで、ゼノン・W・ピリシン『ものと場所:心は世界とどう結びついているか』(小口峰樹訳、勁草書房)を読んでいるところ(やっと前半3章まで)。それによると、さすがにオッカムが考えていたような類似性の関係はすでにあっさりと捨て去られ(笑)、今では心と世界を結ぶものとして指示的関係(意味論的関係)と因果関係のみが取り上げられるようになっているらしい。前者はいわば志向性の問題(狭い意味での)でもあり、いわばトップダウン、後者はアフォーダンスとかを想起させる、いわばボトムアップの関係性とも言える。このボトムアップ型の駆動というのは、個別的なトークンを人はどう追跡するのかという問題を考える場合、認識論的に決して排除できないものなのだという。要は両者が相互に作用しあうようなメカニズムが問題になるということ(らしい)。出現した個物を、人はいかに個物として認識するのか、あるいは、人はいかに個物を個物として出現させるのか。著者はそこに概念的ではない同定メカニズムがあると考える。それは指標付けのメカニズムで、その場合の指標は概念ではとらえられない(つまり表象としてコード化されていない)ものだという。もはやこれはローレベルプログラミングめいた世界で、著者みずから、コンピュータのキーを叩いたときに生じることを譬えとして示している(キーを押したときに生じる割り込みの信号と、そこで呼び出されるサブルーチンによって、どのキーが押されたかが決定されるというプロセスだ。それらは「表象」はされない。また、プログラミングで言うポインタの話もある)。もちろんそういう同定メカニズムそれ自体は依然ブラックボックスであり続けてはいるようだけれど、ずいぶんと縮減されたブラックボックスになっている印象ではある。学問的精緻化というのが、まさにそうした縮減のプロセス(ブラックボックス自体はあるいは完全には開かれることは金輪際ないのかもしれないが)なのだということに、個人的に改めて感じ入るものがある……。
月別アーカイブ: 2012年4月
現前と学知のあいだ
 ディディ=ユベルマン『イメージの前で』(江澤健一郞訳、法政大学出版局)を読み始めたところ。まだ第一章だけなのだけれど(苦笑)、すでにして滅法刺激的だ。かつて『フラ・アンジェリコ:神秘神学と絵画表現』(寺田光徳ほか訳、平凡社)で、ドミニコ会の神学的伝統が絵画表現と一体となり錯綜する様を描き出した著者は、こちらでもまずは同じアンジェリコの絵画でもって、「美術史」という一種の牙城に裂け目を刻みつけていこうとする(おお〜)。アンジェリコの絵画に遍在するという「白」を、著者は絵画を基礎づけている欠如、意味の全体を可能にする根源的な非-知、潜在的ないっさいのものを現前化との二重写しにする空隙、形象化をもたらすための可視性の純化、などと捉えている(それぞれ表現はちょっと違うけど)。なにやらその白は、現象学的な根源性の役割を与えられているかのようだ。で、この空隙はもちろん著者による哲学的な方法(現象学的)によってそのようなものとして見出され、措定されているわけだけれど、ではその同じ方法でもって、「見ているものを知っていると考えている」学知、つまり今の場合なら図像学や美術史などだけれど、そうした学知にアプローチしたらどうなるか、というのがこの第一章の主眼(らしい)。そうした学知の分厚い既知の体系を穿つ特異点は、どうやら「過去」をどう見据えるかという点にあるらしい。
ディディ=ユベルマン『イメージの前で』(江澤健一郞訳、法政大学出版局)を読み始めたところ。まだ第一章だけなのだけれど(苦笑)、すでにして滅法刺激的だ。かつて『フラ・アンジェリコ:神秘神学と絵画表現』(寺田光徳ほか訳、平凡社)で、ドミニコ会の神学的伝統が絵画表現と一体となり錯綜する様を描き出した著者は、こちらでもまずは同じアンジェリコの絵画でもって、「美術史」という一種の牙城に裂け目を刻みつけていこうとする(おお〜)。アンジェリコの絵画に遍在するという「白」を、著者は絵画を基礎づけている欠如、意味の全体を可能にする根源的な非-知、潜在的ないっさいのものを現前化との二重写しにする空隙、形象化をもたらすための可視性の純化、などと捉えている(それぞれ表現はちょっと違うけど)。なにやらその白は、現象学的な根源性の役割を与えられているかのようだ。で、この空隙はもちろん著者による哲学的な方法(現象学的)によってそのようなものとして見出され、措定されているわけだけれど、ではその同じ方法でもって、「見ているものを知っていると考えている」学知、つまり今の場合なら図像学や美術史などだけれど、そうした学知にアプローチしたらどうなるか、というのがこの第一章の主眼(らしい)。そうした学知の分厚い既知の体系を穿つ特異点は、どうやら「過去」をどう見据えるかという点にあるらしい。
歴史家は過去を喪失の対象として見据えつつ、一方でそれを発見の対象、表象の対象として見出すという、ある種の宙吊り状態に置かれる。問題はそのこと自体がなんらかの強制によって見えなくなってしまうこと。歴史家にとっての過去は本来思考不可能なものであり、自身が抱く形象、つまり「想起する現在」の操作を通じてしか存在できない。しかもそれはなんらかの強制力をもってしまう。過去を過去の範疇だけで解釈しようという企て(歴史学ではよく言われることだけれど)は、一見オーセンティックに見えて、近似的な過去の範疇に逆に強制されてしまうという面がある。近似的な過去の範疇はときに、時間的にはわずかなずれにすぎなくとも、意味内容においてはまったく的を外してしまう場合があるのだ、と(著者は、15世紀のクリストフォロ・ランディーノが示し、はるか後にバクサンドールが用いた解釈の範疇が、ランティーノからわずか30年前のフラ・アンジェリコには通用しないことを例として挙げている)。史学がもちいるこうした「過去の現前化」の陥穽は、逆説的にその現前化の「思考されないもの」を徴候として指し示す、というわけだけれど、さらに芸術を扱う学知においては、そうした現前化によって芸術は過去のもの(終わったもの)と規定され、見えるものに属すると括られ、そうして頑強な牙城と化していく……。早い話が、なぜ美術史(に限らないけど(笑))の言説はそんなに偉そうな物言いになるのかという問題に、ディディ=ユベルマンはそういうからくりを説いてみせる……。
アルキノオスの位置づけ
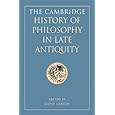 基本文献の一つとなっている『ケンブリッジ古代末期哲学史』(The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, ed. Lloyd P. Gerson, 2 vols, Cambridge Univ. Press, 2010)の第4章「プロティノス以前のプラトン主義」(ハロルド・タラント)が、アルキノオスについていろいろ書いている。それによると、アルキオノスは基本的に、プラトンに「学術的」なイメージを与えようとしていたのだといい、その著書も当時の先行する入門書の類を、ある意味アップデートしようという目論みのもとに書かれていたのではないかという。もとのテキスト(まだ途中だけれど)を見るに、そういう側面は確かにありそうだ。
基本文献の一つとなっている『ケンブリッジ古代末期哲学史』(The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, ed. Lloyd P. Gerson, 2 vols, Cambridge Univ. Press, 2010)の第4章「プロティノス以前のプラトン主義」(ハロルド・タラント)が、アルキノオスについていろいろ書いている。それによると、アルキオノスは基本的に、プラトンに「学術的」なイメージを与えようとしていたのだといい、その著書も当時の先行する入門書の類を、ある意味アップデートしようという目論みのもとに書かれていたのではないかという。もとのテキスト(まだ途中だけれど)を見るに、そういう側面は確かにありそうだ。
タラントの概論で取り上げられているうち、思想史的にとりわけ興味深いのは、たとえば創造神についての考え方など。アルキオノスは、創造神が眠っている世界霊魂を目覚めさせ、創造神が内にもつ知的イデアを見させてその世界霊魂に形相を受け取らせると考えているのだといい、プルタルコスの考える創造(世界を生み出すというよりは、無秩序に秩序を与えるのが創造だとしていた)に近い立場を取る。けれどもプルタルコスのように霊魂にコスモス以前の状態(無秩序の質料と知的ではない魂が存在する状態)があったとは考えず、あくまで世界霊魂は一種の宿酔・酩酊状態から覚醒すると見なしている点が特徴的だという。また、ヌメニオスに見られるような創造神と最高神とを分けるという議論への傾斜が、アルキノオスにも見いだせるらしく、プルタルコスやアッティコス、アプレイオスといった当時のプラトン主義者たちの多く(創造神と最高神を同一視する)とは微妙に立場が異なっているらしい。
さらにまた自然学においても、反アリストテレスの立場に立つアッティコスなどとは違って、アルキノオスはエーテルを第五元素と見なすことに同意しているらしいともいう。同じく自然学の一部に関係するけれど、運命論についてもアルキノオスは、あらゆるものは運命の領域(運命が支配する領域)にあるものの、すべてが運命づけられているわけではないとし、人間の行為や生の選択そのものは自由であるものの、その選択の結果は運命に従って成就するという、いわば調停的な見解を示している(らしい)。……とまあ、各種テーマについてのアルキオノスの立場は、新プラトン主義へと移行する途上という意味合いが強いとの解釈だが、上の創造神の話なども含め、テキストを突き合わせて検証したいところではある。
アルキノオス(プラトン主義の)
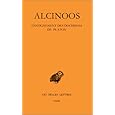 アルキノオスという人物が著したとされる『プラトンの教義の教え(Διδασκαλικὸς τῶν Πλάτωνος δογμάτων)』という書があるのだけれど、これの希仏対訳本(“Enseignement des doctrines de Platon”, éd. John Whittaker, Les Belles Lettres, 2002)を少し前に購入したので、早速読み始めているところ。一種の概説書らしく、文体的にも割と平坦に書かれている印象だ。哲学の区分からその下位区分へというふうに下っていきながら、学知の体系を全体から個別へと見渡して、それぞれについて語っていくという趣向。中期プラトン主義の書とされているのだけれど、同じ中期プラトン主義のほかの概説書と比較してみるのも一興かもしれない。
アルキノオスという人物が著したとされる『プラトンの教義の教え(Διδασκαλικὸς τῶν Πλάτωνος δογμάτων)』という書があるのだけれど、これの希仏対訳本(“Enseignement des doctrines de Platon”, éd. John Whittaker, Les Belles Lettres, 2002)を少し前に購入したので、早速読み始めているところ。一種の概説書らしく、文体的にも割と平坦に書かれている印象だ。哲学の区分からその下位区分へというふうに下っていきながら、学知の体系を全体から個別へと見渡して、それぞれについて語っていくという趣向。中期プラトン主義の書とされているのだけれど、同じ中期プラトン主義のほかの概説書と比較してみるのも一興かもしれない。
ジョン・ウィテカーによる序文によると、著者のアルキノオスの名は長らくアルビノスと同一視されていたのだそうだけれど、この同一視は今では確証はないとされているという。ストア派にアルキノオスという名前の人物がいたという話もあり、ストア派とプラトン主義は紀元前1世紀ごろから相互に接近し、やがてプラトン主義が権勢を誇るようになったという経緯もあることから、それがこの著者ではないかという可能性もあるのだとか。またもう一人、アルキノオスという名の人物が、今度はプラトン主義の陣営内にいたという話もあり、そちらが著者である可能性もあるのだそうだ。うーん、なかなか悩ましい。また、年代的な位置づけも難しい模様。『プラトンの教義の教え』の一部がアリウス・ディディムスからの引き写しで、ディディムスは皇帝アウグストゥスとの親交があったとされることから、同書の成立の下限は1世紀以降だとされるものの、上限は特定が難しいという。同書の中身は新プラトン主義的ではないというものの、中期プラトン主義が新プラトン主義へと道を譲る過程はゆるやかだったことを踏まえると、アルキノオスがプロティノスの同時代人だった可能性すらあるかもしれないとのこと。
強風のもとで
 野暮用で田舎に行かなくてはならず、でもまあ前日の爆弾低気圧の日でなくて良かった良かった、などと思いつつ東北新幹線に乗ったら、低気圧はまだあたりをうろついていて、その影響で新幹線は仙台の手前の白石蔵王駅で3時間以上立ち往生。倒木と架線にビニールが絡まったという説明だった。車内アナウンスの微妙な情報錯綜感が現場の混乱ぶりをうかがわせていた。こちらの予定も大幅に狂った。JR側は結局新幹線のドアを開け、仙台に急ぎの用事がある人たちはそこで降りてタクシーで向かったようだった。けれども、さらに先の場所に用がある人たちは、私も含め、ひたすら待つしかなかった。こういうこともあるから、やはり車内に持ち込む本というのは必要だ。今回はちょうど文庫二冊が入れてあったので、かろうじて退屈をしのいだ(ま、ネットも見たりしていたのだけれども)。
野暮用で田舎に行かなくてはならず、でもまあ前日の爆弾低気圧の日でなくて良かった良かった、などと思いつつ東北新幹線に乗ったら、低気圧はまだあたりをうろついていて、その影響で新幹線は仙台の手前の白石蔵王駅で3時間以上立ち往生。倒木と架線にビニールが絡まったという説明だった。車内アナウンスの微妙な情報錯綜感が現場の混乱ぶりをうかがわせていた。こちらの予定も大幅に狂った。JR側は結局新幹線のドアを開け、仙台に急ぎの用事がある人たちはそこで降りてタクシーで向かったようだった。けれども、さらに先の場所に用がある人たちは、私も含め、ひたすら待つしかなかった。こういうこともあるから、やはり車内に持ち込む本というのは必要だ。今回はちょうど文庫二冊が入れてあったので、かろうじて退屈をしのいだ(ま、ネットも見たりしていたのだけれども)。
 持ち込んでいたのは若桑みどり『イメージの歴史』(ちくま学芸文庫)と伊藤博明『ルネサンスの神秘思想』(講談社学術文庫)。出先なので内容面の具体的な話を記す余裕がないし、まだ通読に至っていないのだけれど、全般的な印象だけ述べておくと、どちらも一種の概説書でありながら、サービス精神あふれる(?)細かな記述と様々な所見が開陳されて、なにやらリッチな読書を味わうことができる。概説書の醍醐味は、扱う分野やテーマについて発展性のあるヒントを与えてくれるところだと思うのだけれど(明示的に与えられる場合もあれば、後から思い起こしてヒントだったと思う場合もあったりと、いろいろなのだけれど)、この二冊はどちらも十二分にそうした期待に応えてくれていそうな気がする。
持ち込んでいたのは若桑みどり『イメージの歴史』(ちくま学芸文庫)と伊藤博明『ルネサンスの神秘思想』(講談社学術文庫)。出先なので内容面の具体的な話を記す余裕がないし、まだ通読に至っていないのだけれど、全般的な印象だけ述べておくと、どちらも一種の概説書でありながら、サービス精神あふれる(?)細かな記述と様々な所見が開陳されて、なにやらリッチな読書を味わうことができる。概説書の醍醐味は、扱う分野やテーマについて発展性のあるヒントを与えてくれるところだと思うのだけれど(明示的に与えられる場合もあれば、後から思い起こしてヒントだったと思う場合もあったりと、いろいろなのだけれど)、この二冊はどちらも十二分にそうした期待に応えてくれていそうな気がする。