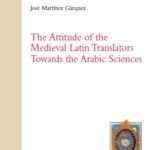 翻訳がらみの話が続いているが、今度はホセ・マルティネス・ガスケス『中世ラテン語翻訳者たちのアラビア化学に対する姿勢』(José Martínez Gázquez, The Attitude of the Medieval Latin Translators Towards the Arabic Sciences, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2016)というのを読んでみた。小著ながら、これは本の作りそのものが興味深い。中世の主要な翻訳者たち(アラビア語からラテン語への)が、とくにそれぞれの訳書に付した序文を読み解いていくというもので、9世紀のアルヴァルス・パウルス・コルドゥベンシスから始まって、14世紀のペドロ4世(アラゴン王)まで、有名どころやそれほど有名でない向きなども含め、扱われている訳者たちは40人以上に上る。それぞれの序文の一部をいわばアンソロジー的に並べ、各人の訳業やスタンス、時代的・文化的背景などを紹介している。
翻訳がらみの話が続いているが、今度はホセ・マルティネス・ガスケス『中世ラテン語翻訳者たちのアラビア化学に対する姿勢』(José Martínez Gázquez, The Attitude of the Medieval Latin Translators Towards the Arabic Sciences, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2016)というのを読んでみた。小著ながら、これは本の作りそのものが興味深い。中世の主要な翻訳者たち(アラビア語からラテン語への)が、とくにそれぞれの訳書に付した序文を読み解いていくというもので、9世紀のアルヴァルス・パウルス・コルドゥベンシスから始まって、14世紀のペドロ4世(アラゴン王)まで、有名どころやそれほど有名でない向きなども含め、扱われている訳者たちは40人以上に上る。それぞれの序文の一部をいわばアンソロジー的に並べ、各人の訳業やスタンス、時代的・文化的背景などを紹介している。
こうして一望してみると、そこからは興味深いスタンスの違いも浮かび上がってくる。12世紀ごろまでは、アラビア科学に強く惹かれた人々が、比較的純粋に(?)その学知を移植しようと熱心に翻訳活動に手を染めている。その後、今度はキリスト教擁護という側面が徐々に強くなり、異教(イスラム教)の改宗を説くための手段、対話の足がかりとしてアラビア語の文献を捉えるようになる。さらに後の14世紀ごろには、定着した学知を補完・完成するためにさらなる文献が求められるようになる。こうした重点の推移は比較的はっきりと現れているが、どの時点でどうシフトしたのかというメルクマールのようなものはなかなか捉えきれない。その意味では、研究の途はまだ開かれたばかりという印象も受ける。