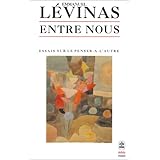続き。祈りの本質が自己の無の認識と、そこからの脱却にあることが示されている。
* * *
(3.4 続き)だがあなたは、「嘆願は、純粋知性に対してなされる呼びかけとは異なる」と述べている。そんなことはまったくない。私たちが能力や純粋さ、その他あらゆる点において神々に劣っているからこそ、それらに究極の嘆願をなすことは、なににも増して時宜に適っているのだ。実際、もし誰かが私たちを神と比べて判断するならば私たちは何者でもないが、自分自身が何者でもないことの認識は、私たちをごく自然に祈りへと向かわせ、その嘆願から、私たちはわずかずつ、嘆願する対象に向かって進んでいくのである。そしてまた、その対象との継続的な対話から、私たちはその対象との類似を得、不完全な状態から神々しき完成へとおだやかに至るのである。もし聖なる嘆願を神々から人間へと贈られたものと考え、またその嘆願が神々のしるしで、神々にしか知りえないものであって、なんらかの形でそれらも神々と同じ力を有していると考えるのであれば、嘆願が感覚的なものであって、神的なもの、知的なものではないなどと、どうすれば正当なこととして受け止められようか?人間の徳ある行いをもってしても簡単には清浄にならないところ[嘆願]に、どのようなパトスがあれば理性的に入り込むことができるというのだろうか?
だが「供物とは感覚と魂をもった対象に捧げられるものである」とも言われる。仮に供物が物体的な効力や複合体のみによって満たされるか、あるいはひたすら感覚器官に仕えるよう従属しているのであれば、それは正しい。だが、供物は非物体的なものにも、なんらかの論理、この上なく質素な基準において与るのである。その点だけでも、供物は適切なものと見なされるし、近くもしくは遠くから見て、なんらかの類縁性、類似性が認められさえすれば、私たちが今述べている当の接触が生じるのである。なぜなら、わずかでも神々に属するとされたものであれば、神々がただちに現れ結びつかないようなものはないからだ。したがって、「感覚や魂をもった対象」のためではなく、まさしく神的な形相のもとでこそ、[供物と]神々とのあたうかぎりの結びつきが生じるのである。この区別についても、以上で私たちは十分に反論した。
Porphyre. Lettre A An‚bon L’égyptien (Collection Des Universit‚s De France S‚rie Grecque) , trad. H.D.Saffrey et A-P.Segonds, Les belles lettres, 2012)
* * *
3.4 これに続いてあなたは、ダイモンに対する神々の別の対抗区分に進んでいる。あなたは「神々は純粋な知性である」と述べている。これをあなたは教義から導かれる仮説、もしくは一部の者がそのことを証言していることとしている。そして「ダイモンは魂をもった存在であるのだから、知性に与る」と説明している。哲学者の多くがそうした見解に導かれていることは私も承知している。だが、あなたに対しては、真理と思えることを隠す必要はないと思う。そうした見解はいずれも混乱をきたしている。一方ではダイモンを魂のほうに含めており−−というのも、魂は知性に与るものだからだが−−、他方では神々を現実態の非物質的な知性へと貶めている。神々はあらゆる点でそれらを凌駕しているとうのにだ。なにゆえにそのような属性を、まったくもってそこに属さないものに割り当てなくてはならないのか?
この区分については−−いずれにせよそれは主たる論点ではない−−以上を記せばそれで十分であると思う。だが、それに対してあなたが問うていることについては、それが聖なる治療に関係する以上、議論の対象にしないわけにいかないだろう[注:λόγου τυγχανέτω:意味の解釈は仏訳注に従う]。「純粋な知性はいっそう魅了に反し、感覚と混在することはない」として、あなたは「それらに対して祈りを捧げるべきなのか」との疑問を掲げている。私からすれば、ほかのものに祈りを捧げるべきですらない。なぜなら、私たちの内なる神、知性、一体性、またもしそう呼びたければ精神は、明らかに祈りにおいて目覚めるのだからである。それは目覚めると、同類のものを超越しようとし、自己の完成に執着する。もしあなたが、「非物体的なものがどうやって音を聞くのかは信じがたい、私たちが祈りにおいて発する言葉には、感覚器官、さらには耳を必要とするのだから」と思うのなら、あなたはあえて第一原因の卓越性を忘却しているのだ。卓越性ゆえにそれら(第一原因)は、おのずと明らかになるすべてのものを認識し内包するのである。というのも、一体性においてこそそれらは、みずからのうちにあらゆるものを包摂するのだからだ。神々がみずからのうちに祈りを取り込むのは、潜在力によるのでも感覚器官によるのでもない。神々はみずからのうちに、正しい者の発する言葉の現実態を内包するのであり、聖なる儀式によって神々に認められ一体となった人々であればなおさらである。その際、神そのものがみずからと一体化し、祈りにおいて示される知的理解をもって、異なるもの同士が交感し合うのである。
* * *
今回の箇所で、「非物体的なものがどうやって……耳を必要とするのだから」というポルフュリオスの問いがあるけれど、上のポルフュリオス本の仏訳注によると、このような「神に耳が必要」といった議論をポルフュリオスがしたとは考えにくいという。プロティノスに同様の議論があり、プロクロスにも「神々とダイモンは祈りを外部から聞き入れるのではなく、人間の意志をあらかじめ受け入れている」という解決策が示されていて、ポルフュリオスは当然それらを知っており、また自著の『節制について』にも「自然はその教えを耳で感じ取れる言葉で発したりはしない」(II. 53.2)という一節がある、と記されている(上記、本文p.12、断片18の注)。
Emmanuel Levinas, Entre nous – Essais sur le penser-à-l’autre , Livre de Poche, Grasset, 1991 邦訳(合田正人ほか訳、法政大学出版局)
冒頭の「存在論は根源的か」という短い論考は1951年初出のもの。当時の「現代的」存在論が、西欧の理論的伝統と断絶する形で実存に身を沈めているとの認識から、他者の問題についても知見の逆転を試みる。他者の理解というのはそもそもが存在の「開かれ」なのだといい、他者を独立した「モノ」のように扱わず、呼びかけ、祈り、語りかける宛先とすることこそが他者の理解なのだ、とレヴィナスは訴える。他者との関わりは突き詰めれば「祈り」に還元され、「理解」がそれに先立つことはない。これをレヴィナスはreligionであるとする。おそらくはreligionの原義である「強い(あらためての)結びつき」「再度の結びつき」ということなのだろうと思うけれど、いずれにしてもディスクールの本質はその「祈り」にある、とレヴィナスは断言する。
さらに他人との「遭遇」(接触)も逆転される。相手をモノのように扱うとは、要するに他人を「所有」するということになり、所有とはこの場合、存在する者としての相手を部分的に否認することになる。他人と「出会う」とは、そうした所有の拡がりの中にあって、相手を所有しないことだ、とレヴィナスは言う。相手を、たとえばレッテルを貼るなどして固定的に捉えることは、相手を抹消(抹殺)することでもあり、「私」は絶えずそういう抹消の望みとともにあるけれど、抹消が成就してしまえば、相手はこちらの手をすり抜けてしまう。このジレンマの中で相手と文字通り顔を突き合わせ対峙すること、それが遭遇(接触)のあからさまな姿にほかならない……ということなのかな(?)。この、境界線がどこかほつれるような、狭間の思考のような文面はたまらない魅力だ。まいど個人的な話で恐縮だが、認知症の親を相手に、理解しにくい奇行の闇と接していると、こうした文面はそこいらの安っぽい癒やしの言葉なんぞよりもよっぽど深い安らぎと残響をもたらしてくれるように思える。というわけで、いまさらながらだけれど、レヴィナスは新たな座右の書候補にすらなってきた(笑)。
あまり頻繁に聞く話ではないけれど、中世の修道僧たちが、自分たちの(というか修道院の、教会の)財産を守るために呪詛を用いていたという話がある。それに関連した論考を読んでみた。ピーター・リーソン「神の呪い:修道院の呪詛の法則と経済」(Peter T. Leeson, God Damn: The Law and Economics of Monastic Malediction, Journal of Law, Economics, and Organization , 2011 )(PDFはこちら
特に取り上げられているのは西フランキア(現在のフランスを含む一帯)。修道僧や司教座聖堂参事会員など、その地の聖職者はとりわけ裕福だったという。主な財産は土地とその付属物。聖職者のコミュニティは最大手の地主だった。カロリング朝では王や役人がその財産権の保護にあたったが、9世紀にはヴァイキングの侵攻があり、10世紀にはカロリング朝の王制自体が揺らいでしまう。地方の豪族が力を増し、こうして追い込まれた聖職者たちは自衛に窮し、こうして彼らは呪詛(神への訴え)への依存を深めていく。つまり、そうした呪詛的な礼拝が執り行われたり、怒号を上げたり(?)、財産の略奪者の眼前で聖遺物を汚したりした(本来崇めるべきものを汚すことで、略奪者の側に不利益が生じるという理屈だったらしい)という。さらには、破門や異端排斥を掲げることもあった。こうした呪詛の脅しは12世紀ごろまで結構功を奏していたようで、計量的データはもちろん存在しないものの、語りものの文献などにその効果が示されているという。当然その背景をなしていたのは、一つには教会の権威や信仰の真摯さが社会の隅々にまで浸透していたことがあるだろうし、呪詛についても教会がその行使を独占してたという事実もある。13世紀にいたるまでに、呪詛が正当とされるのは適切な目的のために適切な人物が行う場合に限られる、といったルールの精緻化も進んでいたというけれど、結局は呪詛そのものの正当化にはやはり無理があり(聖書そのものにも呪詛を禁じるパッセージが多々ある)、さらに13世紀にはフィリップ2世による財産保護制度の復活などもあって、国家の役割が強固になるにつれ、こうした呪詛の活用はそもそも不要になり、やがて廃れていくことになる……。
wikipedia (en)より、1470年ごろのウィーンの祈祷書の細密画
なんとあのビンゲンのヒルデガルトが、アヴィラの聖ヨハネ(16世紀)ともども、法王ベネディクト16世により10月7日に教会博士の称号を与えられたそうだ。教会博士というのは「時代に関係なく意義深くあり続ける神学的な教え」を示した人物に与えられる称号だということだけれど(こちらのサイト Eckehard Simon, Hildegard of Bingen (1098–1179) and Her Music Drama Ordo virtutum: A critical review of the scholarship and some new suggestions , published online, 2011 )というもの。題名通り、音楽劇『オルド・ヴィルトゥートゥム(諸徳の劇)』についての研究動向を多面的にレビューとしてまとめたもの。これはいろいろな意味で勉強になる(笑)。全体としては『中世ヨーロッパの歌』(高田康成訳、水声社)で知られるピーター・ドロンケの研究が下敷きになっている。
アレゴリー的に徳を表す登場人物たちによる、悪魔との戦いを描いた教訓劇のような体裁のこの音楽劇(オルドは当時、一般に音楽劇を指していた)は、ヒルデガルトが開いたルーペルツベルク修道院の聖別に際して上演されたものとも言われ、またそれに類する特別な機会にたびたび上演されたとも考えられるという。ヒルデガルトはこの作品が後世に残ることを望んだらしく、四線のネウマ譜で残しているのが珍しいのだそうだ。つまり、同時代の楽譜が線なしのネウマ譜として記されていたりするのに対し、ヒルデガルトの楽譜は珍しく音の高低や間隔がちゃんと解読できる、というわけだ(もちろんテンポなどは不明なわけだけれど……)。さらに、登場人物たちの心情や、どの人物に向けた歌かといったことも指示されているのだとか。この音楽劇のもとになったビジョンが、ヒルデガルトの有名な幻視を記した初の書『スキヴィアス』の第三巻に記されていて、それぞれの徳(「謙虚」「慈愛」「(神への)畏怖」「(天への)愛」「勝利」)はいずれも独自のきらびやかな衣装をまとって描かれおり、この音楽劇の上演に際してもそれに従ったとするなら、さぞカラフルできらびやかな舞台になっただろうという。実際、ヒルデガルトは修道女が歌う際の衣装の華やかさを皮肉る手紙を受け取っているそうで、それに対する反論の手紙もまた残っているのだとか。ほかにも現存する写本の話とか(リーゼンコデックスという主要な写本のほか、ブリテッシュ・ライブラリー所蔵の写本があり、こちらは16世紀のトリテミウスの手によるとされてきたという)、ヒルデガルトのひょっとしたら着想源だったかもしれないという復活祭の劇『墓への訪問(Visitatio Sepulchri)』の話など、いろいろ興味の尽きない話題が満載だ。
wikipedia (en) より、神からのインスピレーションを受けるヒルデガルトの図。『スキヴィアス』の挿絵
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ