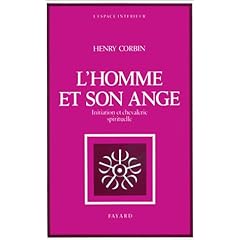メルマガのほうでインペトゥス理論(物体に力が伝わるという中世の運動理論)を復習しているのだけれど、その関係でヨアンネス・ピロポノスの『自然学注解』(Galicaで落とせる)をごく一部分ながら読んでみた。これがなかなか面白そう。ちゃんと最初から読もうかなあ(大変そうだけど)。くだんのインペトゥス理論がらみの話は真空についての論難部分に関連した文脈で出てくるのだけれど、とにかくアリストテレス批判っぽい話が微妙ににじんでいる感じ。ちょっと古い平凡社の『哲学事典』(1971-95)などを引くと、アリストテレスへの批判について「どの程度彼の独創で、どの程度当時までの反アリストテレス思想の伝統に由来しているかは、まだ明確ではない」なんて記してある(p.1171)。うーん、このあたりのことって、その後どのくらい研究が進んでいるのかしら、と関心が沸く。
さらにインペトゥス理論の先駆としての位置づけについても、「この概念が10世紀アラビアの注釈者たちを通じて、ビュリダン、サクソニアのアルベルトゥスら14世紀インペトゥス理論提唱者に伝承された、という説は、そのルートについて完全な確証を得ていない」(同)とある。『自然学注解』は確かシリア語、アラビア語訳はあったはずだが、ということはそこからのラテン語訳がないということなのかしら?でも、おそらく『世界の永遠性について』の話だと思うのだけれど、ボナヴェントゥラとかが影響を受けたという話もあったはず。うーん、ピロポノスの受容とか、基本的なところからちょっと確認せねば(笑)。
おー、これは納得の一枚(笑)。『ヴィヴァルディ:聖母マリアの夕べの祈り』。珍しいヴィヴァルディの宗教曲集。ヴィヴァルディだけに器楽曲重視のミサ曲。これはなかなかご機嫌だ。軽やかさと賛美が入り交じったハイパフォーマンスという感じ。演奏はムジカ・フィアータ、ラ・カペラ・ドゥカーレ。指揮はローランド・ウィルソン。別に新しもの好きというわけでもないのだけれど、2003年と2005年にドレスデン・ザクセン州立図書館で見つかり、ヴィヴァルディのものと特定されたというRV 807 Dixit DominusとRV 803 Nisi Dominusが収録されている(世界初録音というわけではないそうな)のも興味深い。二曲ともなかなかに豪華絢爛。一枚でいろいろな要素が楽しめるお得盤かも(笑)。
『天使の認識と言語』 も少しづつ読んでいるけれど、これまた積ん読になっていたアンリ・コルバン『人間のその天使–霊的イニシエーションと騎士道』(Henry Corbin, “L’Homme et son Ange – Initiation et chevalerie spirituelle”, Fayard, 1983
映画『1408号室』
かつてのジョージ・A・ロメロのゾンビ映画とかは、その出現の唐突さが、たとえ「怖い」というのとは違っても、なにか最低限の不気味さを醸し出していた(びっくりシーンとは別に)。それは、一つにはそういうプロセス理解の不在・否定性を突きつけていたからだと思うのだけれど、翻って最近のゾンビものを見ると、ウィルスとかで異物の出現プロセスをすっかり固めてしまい(たとえば『28週後』『ドーン・オブ・ザ・デッド』(リメイク)、『デイ・オブ・ザ・デッド』(同じくリメイク)、はては『ボディ・スナッチャー』の再リメイク『インヴェイジョン』にいたるまで)、異物の出現はもはや「お決まり」でしかなくて全体につまらんという気がしなくもない。ところが一方で現実にウィルスが問題になれば、それ自体はいまだ十全なプロセス理解を得ておらず(専門家はともかく一般としては)、かくして漠然とした不安感が意味もなく広まってしまったりする。フィクションの中で扱われるプロセス理解は、すでにして現実のプロセス理解よりもはるかに単純で固着的だ。後者はというと、対象となる事物にもよるけれど、場合によりどこか思いっきり開かれていたりする……。
『1408号室』の主人公は、そういうプロセス理解を試みる中で、なんらかのハイテクな方法の可能性すら検討する。実際主人公に突きつけられる現象は、どこかサイコな拷問のようにも見え、主人公を追うわれわれ観客にも、途中で「これって神経系に直接働きかけて個人の妄想を生み出させているとか、そういう話?」みたいな、作品世界へのプロセス理解が促されてきたりもする。でも、観客レベルでのサスペンスフルなそういう仕掛けは、結果的に作品が醸すはずの怖さを大いに薄めているかもしれず、作品的に良いのか悪いのかちょっと微妙だったりもする(笑)。でも、いずれにしてもこの作品は、プロセス理解というものを考える取っかかりとして悪くない映画ではある(かな?)。
最近はアベラールなども、英米系の論者によってどこかそうなっているという話だけれど、原テキストと現代的な論者らによる読み込みとの間になにか乖離というか違和感というかが大きく感じられる中世の思想家の代表といえば、個人的にはやはり13世紀のドゥンス・スコトゥスだ。たとえば往年のジルソンのスコトゥス論などもそう。で、またもファルク本のメモになるけれども、ここでもスコトゥスは哲学史上の転換点を体現する者として描かれている。なにしろスコトゥスにおいては、知性の第一の対象は存在そのものとされ、結果として存在の一義性(あらゆるものの存在の共有)の議論が導かれて被造物から神へとアクセスする途が開かれ、と同時にその一義性の上に個物を個別化する原理、「このもの性」が置かれて、被造物のもつ有限性が哲学史上初めて肯定的に捉えられるのだから。世界を織りなす構造としての偶有性も初めて肯定され、その裏返しだけれど人間のもつ自由も高らかに肯定される。そもそもキリストによる救済というのも、原罪の回復・充足ではなく、栄化という肯定的な動きとして解釈される。普遍を個物より重んじるという古代ギリシア以来の伝統も一挙に転覆される……。ニヒリズムへの対抗原理みたいなものすらほの見えているかのような印象……。
うーん、しかしスコトゥスのテキストをちょこちょこと読み囓る位では、なかなかそういうヴィヴィッドかつ肯定的・称揚的なスコトゥス像には行き着かないのだが……。じっくり腰を据えて取り組めば、そういう解釈へと至るものなのかしら。精妙博士の異名をもつだけに、スコトゥスのテキストは煩雑。細かい議論が延々と続く、みたいな。このギャップをどう埋めればよいのか、あるいは視点を変えて、こうした現代的な議論でのスコトゥス像がどういう過程を経て現れてきたのかとか、なかなかに悩ましい問題ではないかしら(と個人的には思う……)。ファルク本ではハンナ・アーレントのスコトゥス解釈が時折引き合いに出されている。アーレントの『精神の生活』の第二部に出てくるのだという。あるいはそのあたりに、そうしたスコトゥス像成立を振り返る鍵がある?そのうちちょっと覗いてみなければね。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ