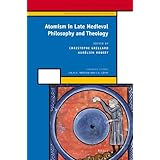 少数派とはいえ、一四世紀にそれなりに議論を展開する例の不可分論の陣営について、その発端はどこにあるのかを知りたいと思い、グルヤール&ロベール篇『中世後期の哲学・神学における原子論』(Grellard & Robert(ed), Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, Brill, 2009)という論集を見始めている。とりあえず最初のマードック「アリストテレスを越えて;中世後期の不可分なもの、および無限の分割性」と、レガ・ウッド「不可分なものと無限:点に関するルフスの議論」の二章を読んだだけなのだけれど、なかなか面白い。まず、マードックのほうは主な不可分論者、アンチ不可分論者をチャートでまとめてくれているほか、いくつかの当時の論点を紹介し、論者たちのスタンスと何が問題だったのかを、アリストテレスからの距離という形で、著者本人言うところの「カタログ」として提示してくれている。ギリシアの原子論にはパルメニデスの一元論への対応や自然現象の説明といった動機があったといい、アラブ世界の原子論(ムタカリムンという学者たち)には連続的創造という教義を通じて、すべての因果関係を神の一手に委ねるという意図があったというが、中世後期の原子論(ないし不可分論)にはそのような大きな、確たる動機が見えてこないらしい。とまあ、いきなり肩すかしを食らう(苦笑)も、気分を取り直して見ていくと、やはり嚆矢とされるのはハークレイのヘンリー(1270 – 1317)だということで、その「無限の不等性」議論などはやはり注目に値するものらしい。これはつまり、連続した線が無限の不可分の点から成るものの、異なった長さの二つの線を比べること、つまり無限同士の比較が可能だという話。ヘンリーは点同士が隣接できるとし、点が互いに接し居並ぶことによって大きさが増えると考えていたという。このあたり、神学も絡んで結構複雑な話が展開しているようだ。
少数派とはいえ、一四世紀にそれなりに議論を展開する例の不可分論の陣営について、その発端はどこにあるのかを知りたいと思い、グルヤール&ロベール篇『中世後期の哲学・神学における原子論』(Grellard & Robert(ed), Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, Brill, 2009)という論集を見始めている。とりあえず最初のマードック「アリストテレスを越えて;中世後期の不可分なもの、および無限の分割性」と、レガ・ウッド「不可分なものと無限:点に関するルフスの議論」の二章を読んだだけなのだけれど、なかなか面白い。まず、マードックのほうは主な不可分論者、アンチ不可分論者をチャートでまとめてくれているほか、いくつかの当時の論点を紹介し、論者たちのスタンスと何が問題だったのかを、アリストテレスからの距離という形で、著者本人言うところの「カタログ」として提示してくれている。ギリシアの原子論にはパルメニデスの一元論への対応や自然現象の説明といった動機があったといい、アラブ世界の原子論(ムタカリムンという学者たち)には連続的創造という教義を通じて、すべての因果関係を神の一手に委ねるという意図があったというが、中世後期の原子論(ないし不可分論)にはそのような大きな、確たる動機が見えてこないらしい。とまあ、いきなり肩すかしを食らう(苦笑)も、気分を取り直して見ていくと、やはり嚆矢とされるのはハークレイのヘンリー(1270 – 1317)だということで、その「無限の不等性」議論などはやはり注目に値するものらしい。これはつまり、連続した線が無限の不可分の点から成るものの、異なった長さの二つの線を比べること、つまり無限同士の比較が可能だという話。ヘンリーは点同士が隣接できるとし、点が互いに接し居並ぶことによって大きさが増えると考えていたという。このあたり、神学も絡んで結構複雑な話が展開しているようだ。
ウッドの論考は、一四世紀の議論の大元のひとつとなったコーンウォールのリチャード・ルフス(1260頃没)の議論を紹介しまとめている。著作から読み取れるその議論は、必ずしも一貫してはいないようで、詳細な説明がない場合もあるようなのだけれど、各著作の摺り合わせを通じて、最適解を作り上げようとしている。それによるとルフスは点を「位置を取る限りで実体のもとにある」と考えているといい(点はもちろん不可分なものとされる)、点が直線の「質料因」(つまり起点をなしているということ)だという言い方をしていることから、唯名論的な概念世界ではなく、外部世界の形而上学的説明を目してることが考えられるという。点は無限に繰り返されて直線をなすのではなく、質料の点的な位置取りが繰り返されて線ができるのであって、点そのものが線を作るのではないとしているという。また球と線が接する場合についても、接するとはそもそも運動であり、接する不可分なものは連続的に移っていくのであって、連続体として(線の流れで?)接するのだと考えているという。このあたりは相変わらず微妙にわかりにくいところではある……。