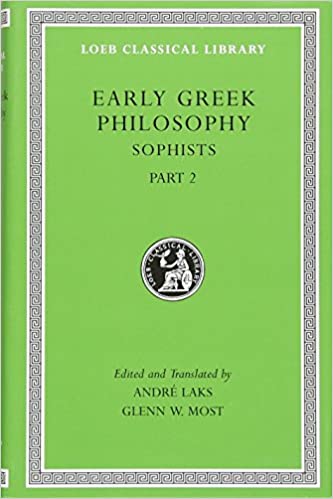偶然・必然から見た世界の階層性
ベルクソンやデュルケムなどの師だったエミール・ブートルー。その博士論文で主要著書でもあった『自然法則の偶然性について』(De la contingence des lois de la Nature, 1874)を、kindleで出ていたデジタル版で読んでみました(途中、飛ばし読み。苦笑)。
https://amzn.to/3EejJ6E
(↑いま手に入りやすいkindle版はこちらです)
全盛だったコント流の実証主義の影響なのか、ブートルーは世界の構造を階層性として捉えています。そして階層の全体を、必然性・偶然性のグラデーションとして解釈します。低い階層ほど(たとえば無機物など)なにがしかの自然法則・数学的法則に支配され、高い階層にいたるほど偶然性に左右されると説くのですね。
で、数学や物理など、諸学が前者の自然法則を扱うとするなら、実証的な学問(実証哲学でしょうか?)こそが、偶然性にかかわる後者を対象に据えうるのである、と考えています。偶然性を扱うその学問は、現象の観察や実験からの推論というかたちの方法論を取ります。推論である限りにおいて、そこには形而上学も含まれ、さらには神についての学知にも到達できるとされています。このあたり、階層性で考えているとはいえ、コントの三段階法則(学知は神学→形而上学→科学と進んでいくといった考え方)とはだいぶ異なっている印象ですね。

最終第9巻はいろいろ寄せ集め
Loeb版『初期ギリシア哲学』シリーズの第9巻は、「ソフィスト、パート2」。アンティフォンを大きく取り上げているほかは、落ち穂拾い的にいろいろな文章を収録しています。この巻はごくざっと目を通しただけなので、取り立ててコメントはありませんが、巻末の「劇中に登場する哲学者たち」のアンソロジーは、存外に面白いコーパスかもしれません。
https://amzn.to/3m3y3IW
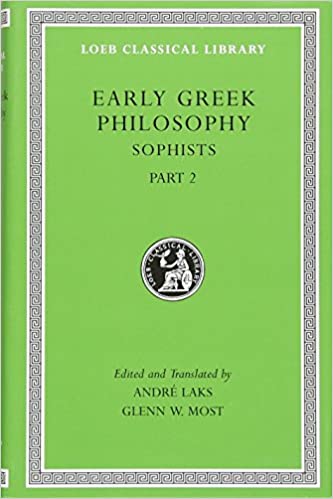
「政治とは対話である」
総選挙のキャンペーン期間に突入しましたね。いわずもがなですが、政治とは対話だという話を久々に見かけたので、転載しておきましょう。ものはkindle unlimitedに入っていた仲正昌樹『悪と全体主義——ハンナ・アーレントから考える』(NHK出版新書、2018)です。アーレントの著作の要約と解説という感じの一冊ですね。
https://amzn.to/3E0GIBQ

そこからの引用です。
アーレントにとって「政治」の本質は、物質的な利害関係の調整、妥協形成ではなく、自立した人格同士が言葉を介して、一緒に多元的なパースペクティブを獲得することなのです。異なった意見を持つ他者と対話することがなく、常に同じ角度から世界を見ることを強いられた人たちは、次第に人間らしさを失っていきます。(ブックマーク – 位置No.1502)
なにやら耳が痛い気もします。
理性主義と自然主義
積ん読の山から、偶然出てきた岩波『思想』2011年12月号(ヒュームの特集号)を、つらつらと読んでみました。
https://amzn.to/3EenwTC
座談会に続く最初の論考、坂本達哉「ヒューム社会科学における「懐疑」と「自然」」がまずもって面白いですね。ヒュームといえば懐疑主義の代名詞、みたいなところがありますが、一方で自然主義の側面も強くあって、両者の兼ね合いをどう解釈するかというのが、ときに問題にもなってきたようです。
懐疑主義は裏を返せば理性主義ということですし、自然主義というのは揺るぎない日々の慣習や実践への信頼ということを意味します。で、この論考では、自然主義こそが、理性主義の行き過ぎへの防波堤になっていると説いています。「人は哲学する前に生きなければならない」というわけです。
自然が許す範囲内で理性を追求すべきだ、というわけなのですが、この論考ではさらに、ヒュームの正義論(社会秩序論)についても、同じ考え方が貫かれていると論じます。ヒュームにとっては、私的所有権と契約にもとづく社会秩序は、外的自然・人間的な自然という条件に適合する唯一の社会秩序だというのですね。自然主義が大きな外枠として、ゆるぎない信頼のもとに設定されていることがわかります。
巻末近くのページに掲載されている、中才敏郎「蓋然性と合理性」という論考は、ヒュームの奇跡論についてまとめていますが、そこでもまた、慣習的なものへの信頼(確証、さらには蓋然性)こそが外枠としてあることがわかります。ヒュームの場合、宗教的な奇跡に類する事象などは、因果関係の推論によってその事象が外枠の確証と矛盾する場合にのみ、どちらの側に与するか判断することになる、としていて、あくまで外枠の頑強さが基本的スタンスであることが窺えます。
現場からの「科学哲学」の声
ザビーネ・ホッセンフェルダー『数学に魅せられて、科学を見失う――物理学と「美しさ」の罠』(吉田三知世訳、みすず書房、2021)を読んでみました。著者も理論物理学の研究者ですが、同書そのものはいわゆる科学哲学・科学社会学の本になっています。
というのも、同書がするどく問うているのは、物理学の最前線が妙に行き詰まっている現状(そのこと自体も、一般向けに取り上げられるのは少ない気がしますが)だからです。著者は、副題にあるように、実験で検証されなていない理論が、数学的な「美しさ」への惑溺のせいで幅を利かせてしまうことに、ある種の危機感を募らせています。
https://amzn.to/3OWhImq
数学的な美というのは、ある種の対称性やシンプルさなどだったりするようです。いずれにしても、なんらかの美的判断が科学者のコミュニティにおいて広く共有され、理論を根底から批判するような目を曇らせるのではないか、というわけですね。著者もコミュニティ内部の人なのですが、どこか覚めた目をもって、そうしたコミュニティから外へと、身をよじって鎖を振りほどこうとする姿勢が見てとれます。
物理学のような高度に精緻化してしまった学問分野では(ほかの分野もそうかもしれませんが)、もはやその内部事情をよく知っていながら、同時にそこから外に向かう開かれたスタンスをもつような人でないと、的確な批判的議論はできないのかもしれません。だとすると、完全に外から眺めるしかない哲学のような学問には、もはやまったく足がかりになれるような部分はないのでしょうか。そうとも限らない、と、同書の著者も少しばかり、そうした批判的言説の一般化の可能性を示唆しているように思われます。
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ