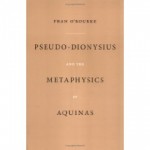τὰ καθ᾿ αὑτὰ ἀσώματα, οὐ τοπικῶς παρόντα τοῖς σώμασι, πάρεστιν αὐτοῖς ὅταν βούληται, προς αὐτὰ ῥέψαντα ᾗ πέφυκε ῥέπειν· καὶ τοπικῶς αὐτοῖς οὐ παρόντα, τῇ σχέσει πάρεστιν αὐτοῖς.
その非物体は、物体に対して場所的に(空間的に?)は現れないが、物体のほうへ下ろうとする潜在性があって、下ろうと望むときには、物体に対して現れる。また、物体に対して場所的には現れないが、物体に見合う形でなら現れる。
旧ブログのほうで取り上げた 土取利行『壁画洞窟の音』(青土社) 。レ・トロワ・フレール洞窟の訪問を軸とし、壁画洞窟そのものが巨大な「楽器」(共鳴装置としてのリトフォン)をなしていたのではないかという仮説を紹介し、その演奏の体験記などが綴られていたのだが、クーニャック洞窟でのその同氏の実演を収めたCD、『瞑響・壁画洞窟–旧石器時代のクロマニョン・サウンズ』(VZCG-687) をようやく聴く。すべてオリジナルの各曲は、石を木や指で叩くとか、骨笛や鼻笛を一定間隔で鳴らすなどの、リズムのみを前面に出したミニマル・ミュージック的なもの。環境音楽的に楽しめる。うーん、でも、音の高低などでの反響の違いとかはどうなんだろうなあ、と思ったりもする。おそらく原始的な音って、もちろん反復動作もあったろうけれど、動物の鳴き声とかを真似て再現しようとするようなものだったりもしたのでは、と思う。そういう声その他の音を取り入れたパフォーマンスも聴いてみたいなあ、と。ま、ともかくうちの再生装置は貧弱なので、洞窟内の雰囲気も再生でいていないほどなのだが(苦笑)、一応これはSHM-CDという、素材的に改良したCDなのだとか。ライナーノーツは土取氏のインタビューで、上の書籍の部分的なエッセンスがまとめられている感じの話になっている。
『神秘と学知』長倉久子訳注、創文社、1996 )。で、そのトマスのソースが気になったのだけれど、何気に目を通したフラン・オローク『偽ディオニュシオスとトマスの形而上学』(Fran O’Rourke, “Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas”, University of Notre-Dame Press, 1992-2005 )に、どうやらそれが偽ディオニュシオス・アレオパギテースであるらしいことが記されている。そっか、やっぱりなという感じ。これまたメルマガに以前書いたけれど、偽ディオニュシオスとトマスの関係性はあんまり研究が多くない印象。その意味ではこれは貴重な一冊。最初の掴みこそいまいちだけれど、論が進むほどに引き込まれる感じ。偽ディオニュシオスのテキストを発出論として読むという視点は、うかつにもスルーしていた……(反省)。アヴィセンナ的な発出論はそれなりに構造として精緻化されていると思うのだけれど、偽ディオニュシオスあたりはもっと素朴というか直接的というか。そのあたりを取り込んで、アリストテレスなどとすり合わせているのがトマス、ということになりそうだ。
*↓深まりゆく晩秋の都内某公園その2
雑誌と思って取り寄せたら、形態は書籍で、しかも新書版サイズで450ページ強……。なかなか力が入っているなあ、と思ったのが『SITE ZERO/ZERO SITE Vol.2 — 情報生態論:いきるためのメディア』(メディア・デザイン研究所) 。残念ながらあまり書店では見かけないのだが、『Intercommunication』誌もなくなった今、こうしたとんがった人文知の雑誌(?)にはぜひ頑張ってほしいところ。面白い体裁で、右から開くと単独論文や連載などが縦組みで掲載され、洋書のように左から開くと特集「情報生態論」の論考や記事が横組みで掲載されている。特集のほうでは、責任編集者らしいドミニク・チェン氏と西垣通氏の対談が面白い。久々に西垣節を聞いたなあ。
単独もののほうでは、冒頭の宮﨑裕助論文「決断主義なき決定の思考」が読ませる。シュミットの決断主義とデリダの決定の思考とを対比させて、主体に回収されてしまわない「決定・決断」のあり方を考えようというもの。でも、デリダ的な根底をさらうような議論は、テキストへの応答というあくまでリアクショナルなものであって、そこから現実的な政治、物象化した形での政治は出てきようがない感じもするのだけれど……。まさにこれは、存在と存在者のいずれに重きを置くのかといった問題にも通じていく。次に掲載されているカトリーヌ・マラブーの論考は、まさにその存在と存在者(有)との狭間の問いを取り上げているのだけれど、これが西欧の哲学的な深い問いであるというのに(中世はまさに、トマスなどによってそれがある意味で先鋭化した時代だ)、どこか妙にあっけらかんとした(失礼)印象を受けてしまう。そうした問題をハイデガーやレヴィナスやナンシーに限定して読み込もうとしているからなのかもしれないけれど、うーん、相変わらず今ひとつ煮え切らない読後感が残る(苦笑)。
余談だけれども、存在と存在者の差異もしくは狭間に垣間見えるものを、「ファンタスティックなもの」(幻想的なもの?)とするのは西欧の底流の一つ。怪物とか異界とか、そういったものはすべてそこに結びつけられる。最近DVDで見たのだけれど、スティーヴン・キング原作、フランク・ダラボン監督作品の映画『ミスト』 とか、あるいは話題になった『クローバーフィールド』 とか、とにかく「外部」のものによって脅かされて、存在者としての人がおのれの存在の根源に向き合わざるをえなくなる、という話になっていて、なるほどこういう基本スタンスからは、たとえば日本版のゴジラのような、怪物がいつしか子供たちのダークヒーローになっていくという話はとうてい出てこないだろうなあ、と納得してしまう。逆に言うと、怪物がそうした根源性をすぐに失ってしまって、あっという間に物象化してしまう風土というのは何だろう、という問題もあるのだけれど(笑)。
*↓深まる晩秋の都内某公園
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 ポルピュリオスの『命題集』こと「知の起源」(ΑΦΟΡΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΗΜΑ)をなんとはなしに見ていくシリーズ(笑)。
ポルピュリオスの『命題集』こと「知の起源」(ΑΦΟΡΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΗΜΑ)をなんとはなしに見ていくシリーズ(笑)。 少し前に
少し前に