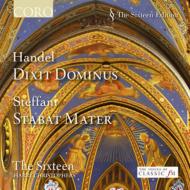ウンベルト・エーコ『バウドリーノ(上・下)』(堤康徳訳、岩波書店、2010) 。少し前に読了していたのだけれど、改めて。まず冒頭のたどたどしい言葉で綴られる主人公の文章から引き込まれる。てっきり、しばらくはこの文章が精緻なものになっていくプロセスを段階的に読まされるのかなと期待したのだけれど……それはなかった(苦笑)。でも、その後の物語は主人公バウドリーノがニケタス・コニアテス(ビザンツの実在の歴史家)に聴かせる語りとして進行する。前半の舞台はフリードリヒ1世の宮廷。物語を引っ張るのは司祭ヨハネ(プレスター・ジョン)の王国の伝説。12世紀に出回ったという司祭ヨハネの手紙
バウドリーノの師匠とされた実在のフライジングのオットー(Otto Frisingensis)が司祭ヨハネについて記したという「二つの国の年代記(Chronica sive Historia de duabus civitatibus)」がネットにないかと思ってざっと調べたのだけれど、どうも見あたらない。残念。書籍を入手するしかないかなあ。一方、教皇アレクサンデル3世が1177年に司祭ヨハネに送った書簡もあるといい、これはネットで手に入る「書簡・勅令集」
長谷川三千子『日本語の哲学へ』(ちくま新書、2010)
クリスマスから新年のこの時期は、やはり宗教曲がよく合う。というわけで今年の一枚は、ザ・シクスティーンによる『ヘンデル:ディクシット・ドミヌス、ステファーニ:スターバト・マーテル』(Handel : Dixit Dominus: Christophers / The Sixteen steffani: Stabat Mater
佐々木中『切りとれ、あの祈る手を』(河出書房新社、2010)
一般的に、先鋭的な思想や批評はその華々しさもあって断絶に重きを置くのに対し、実直な史学などは連続のほうに重きを置く(かな?)。多くの場合、断絶を喝破してみせる刺激的な言説のあとには、そうした連続的な視座による事象の検証が続く……。そういう観点から眺めると、同書の要になっている「中世解釈者革命」というものの実情はどうなのか、という部分が若干気になってくる。これはルジャンドルがもとだそうだけれど、ルジャンドル自身がフランス思想的な物言い(あるいはフランス的放言?)を駆使する人物という印象もあり、個人的には、その文章も慎重に見ていく必要がありそうな気がしている。グラティアヌス教令集に結実する教会法の鍛え上げが、ユスティニアヌス法典の「再発見」によると果たして言い切れるのかどうかとか、微妙な気がする。ローマ法自体はある意味早い段階から教会法に取り込まれる形で細々と伝えられていたとも言われるし。
うむ、いずれにしてもグラティアヌス教令集もある程度ちゃんと読まないとなあ、と改めて思う。ちなみにこのグラティアヌス教令集(Decretum Gratiani) 、ネットでならたとえばこのサイトでダウンロード可 ユスティニアス法典(Codex Justinianus) はたとえばこちらScribdのサイト
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ

 もう大晦日。今年を締めくくる一冊はウンベルト・エーコ『バウドリーノ(上・下)』(堤康徳訳、岩波書店、2010)。少し前に読了していたのだけれど、改めて。まず冒頭のたどたどしい言葉で綴られる主人公の文章から引き込まれる。てっきり、しばらくはこの文章が精緻なものになっていくプロセスを段階的に読まされるのかなと期待したのだけれど……それはなかった(苦笑)。でも、その後の物語は主人公バウドリーノがニケタス・コニアテス(ビザンツの実在の歴史家)に聴かせる語りとして進行する。前半の舞台はフリードリヒ1世の宮廷。物語を引っ張るのは司祭ヨハネ(プレスター・ジョン)の王国の伝説。12世紀に出回ったという司祭ヨハネの手紙のいきさつとかのほか、アレッサンドリア(ってエーコの生まれた町)の来歴とか、宿敵登場とかいろいろなエピソードが満載して飽きさせない。ところどころに、やや時代を無視して挿入されているエピソード(真空の存在とかインペトゥス理論めいた議論など)も、とても自然に溶け込んでいる。後半にいたると、聖杯話から一挙に司祭ヨハネの王国探しに話がなだれ込み、夢想譚の趣きに。東方の異世界の描写がやや饒舌だけれど、終盤は加速していって最後はオチ(エーコはやはりこういうのがお得意)も控えている。うーむ、お見事。個人的には前半の歴史もの的な部分のほうが気に入っているけれど……。
もう大晦日。今年を締めくくる一冊はウンベルト・エーコ『バウドリーノ(上・下)』(堤康徳訳、岩波書店、2010)。少し前に読了していたのだけれど、改めて。まず冒頭のたどたどしい言葉で綴られる主人公の文章から引き込まれる。てっきり、しばらくはこの文章が精緻なものになっていくプロセスを段階的に読まされるのかなと期待したのだけれど……それはなかった(苦笑)。でも、その後の物語は主人公バウドリーノがニケタス・コニアテス(ビザンツの実在の歴史家)に聴かせる語りとして進行する。前半の舞台はフリードリヒ1世の宮廷。物語を引っ張るのは司祭ヨハネ(プレスター・ジョン)の王国の伝説。12世紀に出回ったという司祭ヨハネの手紙のいきさつとかのほか、アレッサンドリア(ってエーコの生まれた町)の来歴とか、宿敵登場とかいろいろなエピソードが満載して飽きさせない。ところどころに、やや時代を無視して挿入されているエピソード(真空の存在とかインペトゥス理論めいた議論など)も、とても自然に溶け込んでいる。後半にいたると、聖杯話から一挙に司祭ヨハネの王国探しに話がなだれ込み、夢想譚の趣きに。東方の異世界の描写がやや饒舌だけれど、終盤は加速していって最後はオチ(エーコはやはりこういうのがお得意)も控えている。うーむ、お見事。個人的には前半の歴史もの的な部分のほうが気に入っているけれど……。