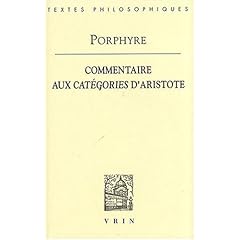『ラテン詩人水野有庸の軌跡』(大阪公立大学共同出版会、2009)
その水野氏の『古典ラテン詩の精』は現在は入手不可のようだけれど、機会があればぜひ見てみたいところ。ちなみに、「Nux mea uoluitur; en nucula / in stagnum incidit: hac quid fit?」と始まる「どんぐりころころ」ほかいくつかのラテン語訳は同文集に収録されている。ちゃんと歌として歌えてしまうこの見事さ!
ポルピュリオス話が続くけれど、ブログ『ヘルモゲネスを探して』
“Commentaire aux Catégories d’Aristote”, trad. Richard Bodéüs, Vrin, 2008
Ἄλλο τὸ πάσχειν τῶν σωμάτων, ἄλλο τὸ τῶν ἀσωμάτων· τῶν μὲν γὰρ σωμάτων σὺν τροπῆ τὸ πάσχειν, τῆς δὲ ψυχῆς αἱ οἰκειώσεις καὶ τὰ πάθη ἐνέργειαι, οὐδὲν ἐοικυῖαι θερμάνσεσι, καὶ ψύξεσι σωμάτων. διὸ εἴπερ τὸ πάσχειν πἄτως σὺν τρόπη, ἀπαθῆ ῥητέον πάντα τὰ ἀσώματα· τὰ μὲν γὰρ ὕλης κεχωρισμένα καὶ σωμάτων ἐνεργείᾳ ἦν τὰ αὐτὰ, τὰ δὲ ὕλῃ πλησιάζοντα καὶ σώμασιν αὑτὰ μὲν ἀπαθῆ, τὰ δὲ ἐφ᾿ ὧν θεωρεῖται πάσχει. ὅταν γὰρ τὸ ζῷον αἰσθανηται, ἔοικεν ἡ μὲν ψυχὴ ἁρμονίᾳ χωριστῇ ἐξ ἑαυτῆς τὰς χορδὰς κινούσῃ ἡρμοσμένας ἁρμονίᾳ ἀχωρίστῳ. τὸ δὲ αἴτιον τοῦ κινῆσαι, τὸ ζῷον, διὰ τὸ εἶναι ἔμψυχον ἀνάλογον τῷ μουσικῷ διὰ τὸ εἶναι ἐναρμόνιον, τὰ δὲ πληγέντα σώματα διὰ πάθος αἰσθητικὸν ταῖς ἡρμοσμέναις χορδαῖς· καὶ γὰρ ἐκεῖ οὐχ ἡ ἁρμονία πέπονθεν ἡ χωριστή, ἀλλ᾿ ἡ χορδή. καί κινεῖ μὲν ὁ μουσικὸς κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ἁρμονίαν, οὐ μὴν ἐκινήθη ἄν ἡ χορδὴ μουσικῶς, εἰ καὶ ὁ μουσικὸς ἐβούλετο, μὴ τῆς ἁρμονίας τοῦτο λεγοῦσης.
物体を受け取るのと、非物体を受け取るのは異なる。物体を受け取る場合は変化を伴うが、魂の内在化やその受け止めは、物体を暖めたり冷やしたりするのと少しも似るところのない所為である。ゆえに、あらゆる物体を受け取る際には変化を伴うが、非物体の場合にはいっさい変化を被らないと言わなくてはならない。というのも、質料や物体から離れたものは所為において同一であるし、質料や物体に近いものは、それ自身では変化を被らないとしても、見られる部分については変化しうるからだ。生物が感覚をもつときには、魂は別個の調和に似通い、分かちがたく結びついた調和にそって調律された弦をおのずと振動させる。魂をもつがゆえに振動の原因となる生物は、調和にあるがゆえに音楽家にたとえられ、それに打たれる身体は、感覚を被るがゆえにその調律された弦にたとえられる。というのも、ここで変化を被るのは別個の調和ではなく、弦のほうであるからだ。また、音楽家はみずからの調和のもとで振動を与えるが、調和がかくあるべしと告げず、なおかつ音楽家が望むのであれば、弦は音楽的に振動しない。
先のジルジェンティの『ポリュピュリオスの特徴的思想』 も中盤を超えて佳境(?)にさしかかったところ。中盤では、「パルメニデス注解」の現存する断章をポルピュリオスのものと特定したピエール・アドの議論をベースに、思想内容からその確認をし、ここから「一と存在」「存在と存在者」「知性」「三幅対」などのテーマの詳述に入っていく。ちょっと面白いのは、「ポルピュリオスが西洋思想史の流れの分岐点に位置づけられる。というのも、哲学史上初めて、存在する(essere)という動詞が行為として概念化され、その純粋な行為が第一原因と同一視され、と同時にそれが一者と存在の漸進的同化を準備したのだ」というくだり(p.219)。actus essendiというときのactusを単純に「現実態」と訳すことへの違和感は以前にも記したことがあったけれど、やはりそこには行為というか働きというか、そういう動的な意味合いが入っていることを確認させてくれる一節。うーむ、現実態=行為としての存在論は、先日のマクシモスの存在論なども含め、はるか後裔にまで連綿と継承されていくようだけれど、その嚆矢はポルピュリオスにありということなのか?けれどもちょっとこのあたり、テキストでの検証が物足りない感じもするのだが……。
新緑の季節はゆっくりと本を読みたい。というわけで、またまた新刊の備忘録。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ
 普通なら関係者だけで共有される本という感じだけれど、一般販売されているのがとても嬉しい『ラテン詩人水野有庸の軌跡』(大阪公立大学共同出版会、2009)。昨年春に鬼籍に入った日本随一の「ラテン詩人」。大学でのそのラテン語授業も超弩級の激しいものだったといい、その学恩に与った人々を中心に、様々な思い出を綴っているなんとも刺激に満ちた追悼文集だ。そこから浮かび上がる「ラテン語一代記」。そして弟子の方々の分厚い層。うーん、圧倒される。古典学の学会で、水野氏があたりの人にラテン語で話しかけまくり、皆が逃げたなんていうエピソードも。奇矯さ(というかある種の狂気というか)は偉大さの裏返しみたいなものなのだろうけれど、でも、ラテン語会話を受け止める人がいなかった(らしい)というのもちょっと問題よね(笑)。どの古典語だろうと言葉なのだから、文献を読む(黙読的に)だけでなく、音読し書けて話せて聞けるというのはやはり基本……だよなあ。学問としてはそこまでしなくても、というコメントも誰か寄せているけれど、でも自由に使いこなすというのは無上の楽しみなはず。というわけで、まあ、あまり激しくはできないけれど(苦笑)、自分も「エウパリノス・プロジェクト」に向けて少しづつ前進しようと改めて思ったりする。
普通なら関係者だけで共有される本という感じだけれど、一般販売されているのがとても嬉しい『ラテン詩人水野有庸の軌跡』(大阪公立大学共同出版会、2009)。昨年春に鬼籍に入った日本随一の「ラテン詩人」。大学でのそのラテン語授業も超弩級の激しいものだったといい、その学恩に与った人々を中心に、様々な思い出を綴っているなんとも刺激に満ちた追悼文集だ。そこから浮かび上がる「ラテン語一代記」。そして弟子の方々の分厚い層。うーん、圧倒される。古典学の学会で、水野氏があたりの人にラテン語で話しかけまくり、皆が逃げたなんていうエピソードも。奇矯さ(というかある種の狂気というか)は偉大さの裏返しみたいなものなのだろうけれど、でも、ラテン語会話を受け止める人がいなかった(らしい)というのもちょっと問題よね(笑)。どの古典語だろうと言葉なのだから、文献を読む(黙読的に)だけでなく、音読し書けて話せて聞けるというのはやはり基本……だよなあ。学問としてはそこまでしなくても、というコメントも誰か寄せているけれど、でも自由に使いこなすというのは無上の楽しみなはず。というわけで、まあ、あまり激しくはできないけれど(苦笑)、自分も「エウパリノス・プロジェクト」に向けて少しづつ前進しようと改めて思ったりする。