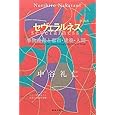14世紀後半に活躍した唯名論者、インヘンのマルシリウスについての論考を読む。マールテン・フネン「<言葉の力>と三位一体:インヘンのマルシリウスと14世紀後半の神学の意味論」というもの(Maarten J.F.M. Hoenen, ‘Virtus sermonis and the Trinity: Marsilius of Inghen and the Semantics of Late Fourteenth-Century Theology’ in “Medieval Philosophy and Theology 10”, 2001)(PDFはこちら ) 。14世紀後半の神学思想の特徴は、なんといっても伝統への回帰にあるのだそうだが、その一方で論理学、数学、自然学といった諸学の方法論の影響から、神学にも新しい方法が持ち込まれるという動きもあり、そのあたりの摺り合わせが問題になっていたと著者は言う。パリ大学で活躍したインヘンのマルシリウスなどはまさにその「渦中」にあったらしい。というわけで、著者は三位一体をめぐる思惟についてマルシリウスの方法を追いかける。そこに見られるのは、論理学と伝統との対立で、その鍵となるのが「virtus sermonis(語法の効力?)」という概念だ。
神の三位一体を「本質は同一ながら、そこに加わる属性によって位格が異なる」とするのが伝統的な立場。属性と本質が違うとなれば、たとえば父とその属性である父性は別物といった議論が成り立つ。「父は子をもうけるが、父性は子をもうけない」と言うことができるからだ。これに対しマルシリウスは、父と父性(つまりこの場合は具象と抽象)との違いはそれぞれの項が指し示すものの違いではなく、むしろ項が意味するところの様態が違うことに起因する、とする。抽象は形相そのものを意味し、具象は全体としての個体を意味するという違いがあるだけで、内実は同じなのだとし、ゆえに父(という本質)と父性(という属性)は同一であると論じる。
著者によれば、これは普通の語法にもとづく分析だという。これに対立するものとして、マルシリウスは「語法の効力」をもとにした分析をも展開するという。上の例の「父は子をもうける」と「父性は子をもうける」は、主語の「代示」としては同一であり、父も父性も同じ事態を指示しているがゆえに、同一の述語を取ることができるはずだ、というもの。要するにそれは、言葉を普通の語法で考えるのではなく、命題として、別様の語法で考えるという、論理学寄りの方法論ということらしい。14世紀後半の伝統への回帰というのは、つまりはこの「語法の効力」ではない、普通の語法の分析に戻るという動きにも重なるようで、そこにはパリ大学が権威として果たすようになった正統教義の守護者としての役割などが絡んでくるようだ。マルシリウスはまさにそうした動きを体現していたといい、通常語法の方に重きを置いていくのだという。
↓アンドレイ・ルブリョフによる三位一体のイコン
震災と原発事故で改めて明らかになったことの一つに、避難を余儀なくされた人々が郷里から遠く離れようとはしないという全体的な動向がある。震災後に、被災地から遠い各県がいろいろな施設を用意したと聞くが、中にはほとんど入所希望が出なかったようなところもあったらしいし、退避勧告が出た原発近くの住民には、それでもなお地元で暮らし続けようとしている人もいるという。もちろん直接的理由は様々だろうけれど(世話をしている家畜を見捨てていけない、よそに行っては仕事がない、などなど)、大きな括りとしてはどこか漠然とした「離郷に対する抵抗感」があるように見える。これは一体どういうものなのか。これを郷里への執着として理解しようとすると、なにやら感情論や審美的判断のように見えてしまうのだが、そう考えることにどこか違和感を伴うのもまた事実だ。疎開論もどこか違うという感覚を覚える。これはどういうことなのか。
なにも罹災者に限ったことではない。田舎に暮らす老親を都会に住む子ども世代が引き取ろうとするような場合でも、同じような抵抗に遭う場合がある。たいていは一般論として、老人特有の頑固さのせいで地元への執着が高まる、みたいな話に帰着させてしまうのだろうが、これもそれだけではないような気もする。問題はもっと細やかな理にあるようにも思われる。つまり、土地勘という名称で呼ばれているある種の認識形態・認識プロセスが、そこに大きく影響している可能性があるのではないか、と。それはおそらく情動的なものと、なにがしかの記憶、隠微な合理性などが入り組んだプロセスで(ある種のアフォーダンス?)、だからこそ見知らぬ土地に放り込まれてしまうと、そうしたプロセスの不全が反動的な不安となって襲ってくるのではないか……。この「土地勘」みたいなものは、詳細に分析する必要がありそうだ。震災後の復興において、それは一つの鍵になるかもしれないからだ。首相が提唱しているらしい沿岸都市のあり方とかエコタウン構想などが、どこか机上の空論に終わりそうな、微妙な「よるべなさ」を醸し出しているのも、そのあたりに理由を見いだせそうな気がするのだが……。
中谷礼仁『セヴェラルネスPLUS – 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)
久々に天使の意思疎通論を読む。ハーム・ゴリス「天使的博士と天使的発話」という論考(Harm Goris, ‘The Angelic Doctor and Angelic Speech: The Development of Thomas Aquinas’s Thought on How Angels Communicate’, Medieval Philosophy and Theology 11 (2003))(→PDFはこちら ) 。13世紀半ばにもてはやされた「天使はどんな言葉を交わすか」という問題をトマス・アクィナスはどう考えていたかについて、その経年別の思想的変遷を中心に手堅くまとめたもので、とても参考になった。ここで考えられている天使のコミュニケーションとは天使同士の意思疎通の場合。コリント書13.1の「もし私が人間や天使の言葉で話しても……」というのが、聖書での「天使の言語」に関する唯一の出典なのだそうだけれど、これをめぐって、すでにヘイルズのアレクサンダーの『神学大全』、ボナヴェントゥラ、アルベルトゥス・マグヌスなどが議論していたという。彼らはいずれも、天使の言語を人間の言語とパラレルなものと見なしていて、知的スペキエス(像、形象)のあり方として、理解(概念化)、獲得(定着)、伝える意志および表出といった段階があると考えていた(これはアレクサンダー、ボナヴェントゥラ、アルベルトゥスでそれぞれ用語が異なる)。トマスも初期には、アウグスティヌスを踏まえて心的概念、内的言語、知解可能な徴という区別(もしくは段階)を考えていた。アウグスティヌスを踏まえてとはつまり、思惟というのは内的言語だという考え方を前面に出すということ。しかしトマスはやがて、今度はアリストテレス的な可能的・常態的(獲得された)・現勢的知識という区別を適用して、天使における知性内の知解対象のあり方を、常態(獲得)、当人にとって現実態(理解)、他者にとって現実態(表出)という三区分とするようになる。理解(概念化)と内的言語を切り離し、三つめの外的な表出においてのみ言語が関与するという立場に転じたらしい。
けれどもこれで終わらず、トマスはアウグスティヌスとアリストテレスの摺り合わせへと進んでいき、やがて二つめの「当人にとって現実態」という段階が、アウグスティヌス的な内的言語で説明されることになる。現実態としての理解が内的言語とイコールだと見なされるというのだ。で、さらにその思想の「成熟期」においては、いつしか再びアウグスティヌスへと舞い戻っていくという。外的な表出すら区分として薄らいでいき、天使においては、伝える意志が向かえばそれで他の天使に概念が伝わるという考え方になり、ここへきて、人間と天使のコミュニケーションはパラレルなものとは捉えられなくなる。もとより言葉の徴とは感覚的・物体的なものである(だから非物体的な天使には必要ない)というアウグスティヌス主義の伝統へと、すっかり回帰していくというのだ(もっとも、多少の留保はとどめているらしいのだが)。なるほど、このあたり、タンピエの糾弾などが絡んでいそうで、なにやら反動的保守化という感じも……。うーむ、ま、性急にそういう括りにしてしまうのはよしておこう。とはいえ、とても興味深い変遷の過程だ。
↓フラ・アンジェリコの「受胎告知」
ドナルド・デイヴィドソン『真理・言語・歴史』(柏端達也ほか訳、春秋社)
これはつまり、エノンセ(言表)だけがあるとして、ラング(コードとしての「言語」)というものの先行性を否定する立場か。つまりは「類」概念の否定ということなのだけれど、これだとたとえば言語的規範に従おうとするような意志の拘束力が説明できないことになってしまう。デイヴィドソンはそれに、修正する義務感が生じる場面の分析で対応している。誤用に気がついて修正しようとするような場合、先に合わせるべき言語的規範があるのではなく、あくまで理解されたいという欲求があるのみで、そうした欲求によって、相手に意図を伝えられるような仕方で話すという唯一の義務が、いわば欲求と同時的(事後的?)に生じるだけなのだ、というのである。共同体的な規範に従うように見えるのは、偶然の産物でしかないというのだ。なるほど、きわめて唯名論的な議論ではある。とはいえこれは、一方において、話し手のうちに「当座理論」の成功体験という形である種の蓄積ができることは想定されているようにも読める。もちろん、そういうふうな理解でいいのかどうかはまだ不明だが……(苦笑)。言語という名で考えられているような確固たるコードの束ではないかもしれないけれど、当座理論が運用されるプロセス自体は名辞で名指しうるものとして実在しうる(プロセス自体がそれを可能にする)としたら、これはある種のプロセス実在論(きわめて限定的・狭義の)だと言うこともできるかもしれないなあ、と。そのプロセスがコミュニケーションの成功という共有の実践、ひいては意味を産出することからして、それが種に類するものとされうることは明らかだ。
フランスのサルコジ大統領は3月末の来日会見で、「原発は地震は耐えたが津波にやられた。津波が問題だったのだ」と述べていた。おそらく日本側からの説明がそういうものだったのだろう。けれども、先日7日の夜の大きな余震後、この余震の影響を受けた福島以外の原発が軒並み綱渡り的な状況になったことで、問題が津波だったとは断定できなくなった。少なくとも疑問符が付いた……そう、原発はそもそも地震に耐えたのかという問いが浮上した。
原発には耐震処理がなされているという話は以前からあったように思う。問題なのは「耐震」が何を意味するかだ。なるほど、確かに建物自体が崩壊するような事態はなかった。単に家屋ならばそれで「耐震」ということで問題はないだろう。けれども、原発などなんらかの生産設備は、そもそも地震によって機能が損なわれてしまわないことを「耐震」と呼んでしかるべきなのではないか、と思われる。電源が簡単に落ちてしまうような設備を「耐震」とは言えない。そういう意味での「耐震」を基準にするなら、現時点での原発は必ずしも合格点とは言えない。構造体としてのみ捉えてしまい、機能面を加味した全体的な生産設備(それもクリティカルな)として「耐震」を考えていなかった可能性は否定できない。少し前のポストとも重なるけれど、構造体として捉えるとは、いわば一面(一点)だけをピックアップして考慮するということであり、生産設備を全体として捉えることができていないということ。リスク管理としては、もはやそうした点的な対応では不十分で、全体的・包括的な捉え方が求められる……。今の場合でいえば、「電源込み」で耐震設計をするとか、電源の取り込み口を複数化しておくとか、システム全体で「耐震」ないし「免震」を実現する……。
アンドリュー・フィーンバーグ『技術への問い』(直江清隆訳、岩波書店) 「技術プロセスから製品や人に、事前の防止から事後的な後始末に、批判の目をそらせようとする傾向が見られる」 (p.137)という(なぜそうなるのかは触れていないようだが……)。一方の運営する側はこれを受けて「トレードオフを含むコストとして認識」(この技術を使わないと、その先に待ち構えているのは貧困だぞ、と)し、相手を追い詰めていく。
著者によれば、このトレードオフモデルは一種の偏向(バイアス)であり、そこで突きつけられるジレンマ(「環境的に健全な技術VS繁栄」など)の統合こそが重要だという。それが政治的なイデオロギーの対立に見えるというのは本質的問題ではなく、技術の本質からすると(シモンドンが引き合いに出されているが)、そもそも技術的発展の目標とはそうしたジレンマを避けることにあるはず、と。その上で、こうしたトレードオフではない別の価値観へのシフトを模索することが求められる、ということを著者は論じている。一例として、アメリカ政府が汽船のボイラーに課した安全規則が挙げられている。それは「人間の生命の価値と政府の責任についての非経済的な決定」(p.143)だったという。話を目下の問題に戻すならば、おそらくはもう一度、上の技術プロセスと事前の防止 の方へ立ち戻ることが肝心だということになるだろう。この著者が示すようなバイアスを生む土壌すらをも見据えて……。それは当該技術を全体(関連技術や組織論も含めたまさにマクロな体制)から捉え直すというスタンスと切り離すことはできないはずだ。
投稿ナビゲーション
δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ