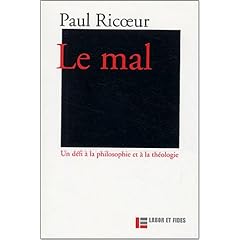 ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
ちょっと思うところあって、ポール・リクールの小著『悪 – 哲学と神学への挑戦』(Paul Ricoeur, “Le mal : Un défi à la philosophie et à la théologi”, Labor et Fides, 2004)を読んでみる。ローザンヌ大学での1985年の講演テキストだそうだ。リクールはここで、悪の存在という問題が、それと表裏をなす罪の問題とともに、弁神論(悪の存在が神の全能と矛盾しないという説)の系譜の中で、いかに始原的な問題をなしてきたを振り返っている。それは神学の体系・全体を脅かすものなのだという。まずは神話、グノーシス思想、そしてアウグスティヌスによる悪の扱いを概観するリクール。特にアウグスティヌスにおいて、「unde malum ?(悪はどこから来るのか)」という問いが存在論的な意味を失い、「unde malum faciamus(私たちはなにゆえに悪をなすのか)」という問いが掲げられて、グノーシスのディスクールが中身こそ破棄されるものの、形式は再構築されるのだという。この指摘は面白い。もっとテキストに即した検討を見てみたいところ。リクールのこれまでの著書に何かあったような気もする。後で確認しよう。
結局リクールによれば、後の時代の弁神論においても、悪についての問いの緊張状態は解かれないという。カントやヘーゲルに至っても、また他のリソース(理性といった)がつぎ込まれて、悪の問題が投げかける問いは再生されていく、と。「凡悲劇論が凡論理主義に回収される世界観にあって、被害者の苦しみにはどんな運命が残されているのか」(p.48)というわけだ。悪というものの現実が神の善性と相反することを認める立場に立ち、従来の弁神論とは「別の仕方で」悪を考えるカール・バルトの神学すら、シェリングがルネサンスの思想家たちに見出したという「神性のダークサイド」を開くことになる可能性を見てとっている。振り出しに戻るかのように……。その上でなお、悪の問題への思考によるアプローチを降伏させてはならない、より緻密な論理をもって臨み、さらに行動と感性をも動員せよ、とリクールは唱える。悪への実践的抵抗、喪の仕事をモデルとした愁訴の変容など、ヒントも示唆しているが、それを受け止めるような議論はその後のフランス思想界(でなくてもよいのだけれど)とかでもなされているのかしら、とちょっと気になる。